野球では強打が称賛されがちですが、実は「バットを振らずに見送る」勇気こそが勝負を分ける場面もあります。
日本の新潟医療福祉大学(NUHW)と大阪経済大学(OUE)の研究グループは、そんな「選ばない勇気」の重要性を、最新の研究がVR(バーチャルリアリティ)技術によって科学的な関連が示されました。
研究グループはVRを用いて打者の選球能力(ストライク・ボールを見極める力)を測定し、そのスコアは実際の出塁率や四球率(フォアボールで出塁する割合)と中〜強く相関し、打者の成績と関連する指標の一つであることが示されました。
さらに、空間的な認知能力(空間認知の実行機能)が高い選手ほど、ストライクの見極めも正確であり、選球能力と空間認知の実行機能がそれぞれ独立して特に四球率に対して打者の成績に関連していることも明らかになりました。
VR技術により打者の秘密が明らかにされようとしています。
研究内容の詳細は2025年10月17日に『Sports』にて発表されました。
目次
- 最強のバッターは『見極めの達人』?―選球眼を科学で解明する
- 『見る力』と『頭の速さ』が打者を決める?VRが明かす新事実
- 『振らない勇気』を科学する―打者の本当の才能とは
最強のバッターは『見極めの達人』?―選球眼を科学で解明する

最高の打者は、もしかしたら最高に「見逃し上手」な選手なのかもしれません。
野球といえば豪快なホームランや華麗なヒットが注目されますが、実はバットを振らずに球を見送るという一見地味な動作にも重要な価値があります。
プロの世界では、打者が投手の投げたボールを見極めて「ストライクゾーンを通るか」「ボールになるか」を瞬時に判断しなければなりません。
この「ストライクかボールか」を正しく判断する能力は専門用語で「選球眼(せんきゅうがん)」と呼ばれています。
選球眼が優れている打者は、難しい球を無理に打つことが減り、結果としてフォアボール(四球)で出塁できる可能性が高まります。
また、ストライクゾーンをしっかり見極めることで、自分にとって打ちやすいコースの球を選んで打つことが可能になるため、ヒットを打つ確率も上がると考えられてきました。
ところが、これまで選球眼という能力を科学的に定量化して正確に測定する方法は十分に確立されていませんでした。
言い換えると、選球眼の良し悪しは選手やコーチの「感覚」や「経験」によって判断されてきたのです。
また、どうすれば選球眼を鍛えられるのかというトレーニング方法についても、ほとんどわかっていませんでした。
なぜ、選球眼を科学的に評価することが難しかったのでしょうか?
その理由の一つは、野球というスポーツが非常に短い時間の中で判断と行動が求められる競技だからです。
たとえば、プロ野球のピッチャーが投げる速球は時速150キロメートル(約94マイル)にも達します。
これはピッチャーが球を投げてから、わずか0.44秒という短い時間で打者のいるホームベースに到達する速さです。
さらに打者はバットを振る動作に約0.18秒ほどかかるため、打つか打たないかの判断を下すために与えられる時間は、実質的にはたったの0.26秒しかありません。
一瞬の間にボールの軌道や速さを見極めるには、極めて高度な脳の処理能力(認知能力)が求められますが、従来の研究では、このわずか0.26秒の中で打者がどのように判断しているかを具体的に測る方法はありませんでした。
これまでにも、パソコン画面上でシンプルな反応速度を測ったり、動画で投球シーンを再生して打者に見せたりする方法が試されましたが、こうした簡単な実験と実際の試合での打撃成績との間には、明確な関連がなかなか見つかりませんでした。
そこで今回、日本の新潟医療福祉大学(NUHW)と大阪経済大学(OUE)の研究グループは、この選球眼という見えにくい能力を「VR技術(仮想現実の技術)」を使ってリアルに再現し、数値化するという新しい方法を考え出しました。
この研究では、実際に投手が投げた球を360度カメラで撮影してVRの中に投影し、実戦に近い状況を再現して、選手の選球眼を測定しています。
さらに研究者たちは、選球眼を支える脳の認知能力(実行機能と呼ばれ、状況に応じて考えたり判断したりする能力)についても詳しく調査しました。
果たして、打者が球を「振らずに見送る勇気」を発揮するためには、どんな能力が必要なのでしょうか?
また、それらの能力を科学的に明らかにすることは可能なのでしょうか?
『見る力』と『頭の速さ』が打者を決める?VRが明かす新事実

「選球眼は大事だ」と言っても、実際にどんな能力を持つ選手が選球眼が良いのかを具体的に示した研究は、これまでほとんどありませんでした。
そこで今回の研究チームは、野球選手がボールを見極める能力を、VR(バーチャルリアリティ)という最新の技術を使って客観的に測定する方法を考え出しました。
研究対象となったのは、日本の北信越地区大学野球連盟1部リーグでプレーする男子大学生の野球選手14人です。
彼らにはVRヘッドセットを装着してもらい、実際の投手が投げた80球の投球映像を360度カメラで撮影したものを見せました。
選手たちは、そのリアルなVR空間の中で「ストライクかボールか」を瞬時に判断しなければなりませんでした。
研究者は、これら80球の判定がどの程度正確に行われたか(正答率)を測定しました。
また、選球眼に関連すると考えられるもう一つの能力として、選手たちの「空間的な認知能力」も同時に調べました。
これは専門的には「空間ストループ課題」と呼ばれるテストで、画面上に現れる矢印がどの方向を指しているのかを素早く答えるというものです。
ただし、このテストはちょっと意地悪で、矢印が表示される位置と指す方向が一致していないケースがあり、頭の中で素早く「混乱」を解消する能力(脳の処理速度や柔軟性)を測ることが狙いです。
この実験がなぜ重要かというと、打者は実際の打席で投球を見極めるときも、素早く正確に情報を処理する力が求められるからです。
さらに、選手たちが過去3年間(2020年秋季~2023年秋季)の公式試合でどのような成績を出していたのか、という実際のデータも集められました。
このデータには、打率(ヒットを打つ割合)や出塁率(ヒットやフォアボールなどで塁に出る割合)、四球率(フォアボールを選ぶ割合)などの重要な打撃成績が含まれています。
研究者はこれらのデータとVR課題・空間ストループ課題の結果を統計的に分析し、どのような関連があるのかを調べました。
結果は非常に興味深いものでした。
まず、VR課題でボールとストライクを正しく判定できた選手ほど、実際の試合での出塁率(r=0.57)や四球率(r=0.82)が高い傾向にあることが分かりました。
特に、四球率との相関は非常に強く、選球能力が高い選手ほどフォアボールを多く選び、出塁することが多いという明確な関連が数字で示されました。
また、もう一つの課題である空間ストループ課題の結果も重要な示唆を与えました。
この課題で反応が速かった選手ほど、VR課題でストライクを正しく判定する精度が高く、負の相関(r=-0.67)が確認されました。
つまり、素早く混乱を解消して判断するという脳の能力が高い選手ほど、実際の打席でも冷静にボールを見極める力が高い可能性が示唆されました。
では、この「選球眼」と「脳の処理能力」、この2つは打撃成績にどのように関わっているのでしょうか?
研究者は統計学の手法を用いて、この2つの能力が選手の成績にどのように影響しているのかを詳しく分析しました。
その結果、選球能力と空間的な認知能力は、どちらかがもう一方を通じて影響しているわけではなく、それぞれが独立して、特に四球率に対して成績と関連していることが分かりました。
分かりやすく言えば、野球選手の打撃成績というのは、「ボールを正確に見る力(選球能力)」と「脳の素早い情報処理能力」という2つの異なる能力が、それぞれ別々に貢献しているということです。
この結果は重要で、単に目が良いだけでも、頭が切れるだけでもなく、その両方が高いレベルで備わっていることが、より良い打撃パフォーマンスにつながっていることを示唆しています。
つまり、打者の優秀さというものは、まさに「目」と「脳」という2つの異なる「ギア(歯車)」が組み合わさって生まれている可能性があるのです。
『振らない勇気』を科学する―打者の本当の才能とは
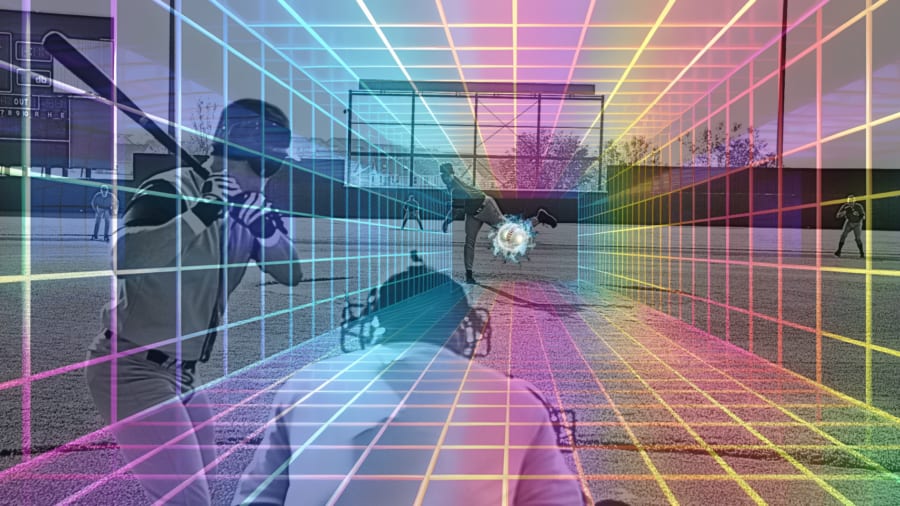
今回の研究から得られたもっとも大きなポイントは、「振らない勇気」つまり選球眼が、打者の成績にとって意外なほど重要だということが科学的に関連づけて示された点です。
一見、野球というスポーツではホームランやヒットを打つことが最も評価されやすいです。
ところが、研究チームは今回、VR技術という新しい手法を使って、打者が投球を見極める能力を具体的な数値で評価しました。
その結果、選球眼の優れた選手ほど、実際の試合で塁に出る割合(出塁率)やフォアボールを獲得する割合(四球率)が高い傾向を示しました。
ただし、ここで興味深いのは、選球眼が優れていても打率(ヒットを打つ割合)や長打率(塁打を多く獲得する割合)といった他の成績指標には明確な関係は見られませんでした。
これは一体何を意味するのでしょうか?
簡単にいえば、「ボールを見る力」と「ボールを打つ力」は必ずしも一致しないということです。
選球眼が優れているからといって、それだけでどんなボールでもヒットにできるわけではありません。
実際にヒットを打つには、見極めたボールを正しく打ち返すバットコントロールやスイングスピードなど、別の技術が必要になります。
つまり、選球能力というのは、野球のパフォーマンスを支える複数の能力のうちの「1つの歯車」に過ぎないということです。
そして、今回の研究はさらに重要な発見を示しました。
それは選球能力だけでなく、「脳の処理能力(空間的な認知能力)」も打者の成績に関係していることです。
しかも、この2つの能力は互いに直接影響を与えているわけではなく、それぞれが独立して、特に四球率に対して打者の成績に関連していることが分かりました。
わかりやすくいえば、投球を見極める「目の力」と、状況を瞬時に判断して対応する「頭の力」は、車の両輪のように、別々に機能しながら打者を支えている可能性があるのです。
これは、野球の世界で指導者や選手が感じてきた「見極める力」と「反応の速さ」の重要性を、科学が改めて裏づけた形ともいえるでしょう。
こうした成果は、今後の野球指導やトレーニング法を大きく変える可能性を持っています。
従来は、選球眼というのは「経験」や「感覚」によるものと考えられ、科学的なトレーニング方法も確立していませんでした。
しかし、今回のVR技術を活用した研究成果を応用すれば、選球眼をより科学的に評価し、効率的に鍛える方法を開発できる可能性があると考えられます。
たとえば、選手が試合のない日にも、VRでリアルな投球シーンを繰り返し経験し、ボールの見極めを練習できるようになるなど、将来的な展開も期待されます。
一方で、この研究には明確な限界もあります。
対象となった選手は14人と少数で、全員が大学野球の男子選手でした。
そのため、プロの選手や高校生、女性の選手にも同じ結果が当てはまるかは、まだ分かりません。
今後は、より多くの選手を対象にした研究や、実際にVRを使ったトレーニング効果を直接調べる研究が求められます。
それでも今回の研究が持つ意義は大きいです。
これまで「経験」や「感覚」の世界だった選球眼が、VRを使うことでより客観的な数値として可視化されたことは、野球科学の新しい一歩です。
今後、VR技術が野球の現場で積極的に活用され、選球眼というこれまで見えなかった能力が、誰でも理解できる科学的なスキルとして定着する日が来るかもしれません。
参考文献
【新潟医療福祉大学】VR技術により野球の「選球眼」を科学的に解明!選球能力と実行機能が打撃成績に独立して貢献することを発見
https://www.nsg.gr.jp/blog/nuhw-yr_baseball-202510/
元論文
Pitch Selection Ability and Spatial Executive Function Independently Predict Baseball Batting Performance
https://doi.org/10.3390/sports13100367
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


