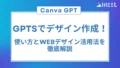トルコのアンカラ大学(Ankara University)などで行われた研究によって、飼い猫が「おかえり」のときにどれくらい鳴いて挨拶するのかを計算してみると、女性の飼い主には100秒のあいだにだいたい2〜3回しか鳴かないのに、男性の飼い主には5回くらい鳴いていて、回数にするとほぼ2倍ちかい差が出ていました。
さらに、猫の性別や年齢、血統、多頭飼いかどうかといった条件を考慮に入れても、この違いはほとんど変わらず、「帰ってきた人が男性か女性か」という点だけが鳴き声の多さと有意な関係を示したのです。
いったいなぜ猫たちは男性へより多く鳴き声をあげているのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年11月14日に『Ethology』にて発表されました。
目次
- 猫の投げかける「ニャー」に男女差はあるのか?
- 猫の「おかえりニャー」、男性へは2倍賑やかだった
- なぜ猫は男性飼い主に対して鳴き声頻度が上がるのか?
猫の投げかける「ニャー」に男女差はあるのか?

「なぜかこの人にだけ、うちの猫はよく鳴く気がする」
そう感じたことがある方もいるのではないでしょうか?
呼んでも来ないのに、玄関の音がした瞬間だけは、しっぽを立てて走ってきて「ニャー」と挨拶する――そんな“猫あるある”の裏側に、猫なりの細かい駆け引きが隠れているかもしれません。
動物の世界では、「挨拶行動」が、仲直りや仲良し確認のために大きな役割を果たすことが知られています。
ハイエナやゾウでは、特徴的な挨拶のしかたを通して、社会の秩序や協力関係が保たれています。
猫はもともと単独で狩りをするハンターですが、エサが豊富な場所では集まって暮らし、お互いに毛づくろいをしたり、体をこすりつけ合ったりして関係を作る「社会的に柔軟な動物」だと考えられています。
人と猫のコミュニケーションは、さらに複雑です。
目線やまばたき、指差しといった視覚のサインに加えて、「猫向けの高い声」(cat-directed speech:赤ちゃん言葉のような話し方)や、ミャー、トリル、ゴロゴロといった鳴き声を組み合わせた、マルチモーダル(複数の手段を同時に使う)なやりとりになっています。
別の研究では、猫が飼い主の声と他人の声を聞き分けていることも示されていますが、主な反応は頭や耳を向けるといった姿勢の変化で、鳴き返す個体ばかりではありませんでした。
ここまで分かってきたのは、「猫は人の声を聞き分けられるし、いろいろな手段で挨拶しているらしい」ということです。
しかし飼い主の性別や年齢、猫の性別や血統といった条件が、それらの挨拶パターンにどう影響しているのか――ここはまだ十分には調べられていませんでした。
そこで今回の研究は、「日常のごく短い瞬間」に焦点を絞りました。
帰ってきた飼い主を見つけた猫が最初の100秒でどんな挨拶をするのかを調べることにしたのです。
もし猫が「男性の飼い主にはこう鳴く」「女性にはこう振る舞う」といった具合に、相手別に挨拶を使い分けていたとしたら、それはかなり興味深い発見になります。
猫の「おかえりニャー」、男性へは2倍賑やかだった

研究チームは、トルコに住む猫の飼い主40名を募集し、そのうち条件を満たす31名とその猫を最終的な対象としました。
猫はすべて生後8か月以上で、飼い主と少なくとも半年以上一緒に暮らしていました。
飼い主には、外出から自宅に戻るときに、胸に小型カメラを装着してもらいました。
玄関を開けてから5分間、できるだけいつも通りに振る舞ってもらい、その映像のうち「最初の100秒」だけを切り出して分析しています。
映像は、行動解析ソフトを使って、猫のしっぽ、体の向き、歩き方、接近、飼い主へのスリスリ、あくび、身震い、自分を舐めるセルフグルーミング(自分みがき)、そして鳴き声など22種類の挨拶行動に細かく分解されました。
この22項目について、「何回出たか(頻度)」と「どれくらい続いたか(時間)」を数え、行動同士の相関関係(どれとどれが一緒に出やすいか)と、その結果をもとに飼い主や猫の属性との関係を統計的に調べています。
まず、挨拶行動の全体像を見ると、しっぽをピンと立てる行動、飼い主に向かって近づく行動、体をこすりつける行動はお互いに強く結びついていました。
これは、典型的な「うれしい挨拶セット」と解釈できます。
一方で、あくびや身震い、自分を掻く、自分をやたら舐めるといった行動同士もまとまっていて、こちらは「ディスプレイスメント行動(緊張や葛藤をごまかすしぐさ)」のクラスターとして説明されています。
注目すべきなのは、「鳴き声」です。
鳴き声の頻度は、これらどちらのクラスターとも相関せず、他のどの行動ともはっきりした関係を示しませんでした。
つまり、鳴き声は「うれしさ」や「緊張」といった単一の感情に縛られたサインではなく、別レイヤーのコミュニケーション手段として機能している可能性があります。
そこで研究チームは、鳴き声の頻度と、飼い主・猫の属性との関係を詳しく調べました。
具体的には飼い主の性別、猫の性別、猫の年齢、血統(雑種か純血種か)、多頭飼いかどうかなどをすべての条件を換算にいれて分析したのです。
結果「飼い主が男性のときは、女性のときより平均約2倍ほど多く鳴く」という傾向がみえてきました。
帰宅から100秒余りの僅かな期間とは言え、これほどの差がついたのは驚きと言えます。
次のページではいよいよ、その原因を探っていきます。
なぜ猫は男性飼い主に対して鳴き声頻度が上がるのか?

では、なぜ猫は男性の飼い主にだけ、鳴き声の頻度が上がるのでしょうか?
単純に考えれば、猫たちは男性に対してより強くアピールする必要があると感じていると言えるでしょう。
問題はその理由です。
論文の著者たちは、先行研究をもとに「男性のほうが、猫のささやかなサインを読み取りにくいのではないか」と推測しています。
女性の飼い主は、日頃から猫に話しかけ、鳴き声の意味を読み取ることに慣れているため、小さな声やしぐさでも気付いてくれます。
一方で、男性はそうとは限らず、「はっきり鳴かなければ反応してくれない」と猫が学習しているのかもしれない、というわけです。
さらに著者らは、トルコという文化の影響も指摘しています。
トルコでは、男性が感情をあまり言葉で表さない傾向があるとする研究があり、そのため猫が「言葉少なめの男性」のかわりに、自分の鳴き声でコミュニケーションのギャップを埋めている可能性があると述べています。
猫たちは日常の経験を通して、「この人には小さく鳴いても伝わりにくい」「この人には一声で十分」といった、相手ごとの“反応パターン”を学んでいる可能性は十分にあります。
これら論文著者の予測が正しければ、男性に対してお帰りの「ニャー」が多いのは「愛ゆえ」というより猫目線では男性のほうがが「鈍くみえるから」となるでしょう。
さらに今回の研究は「鳴き声は他の挨拶行動と独立したレイヤーかもしれない」「猫は人の性別や文化的な話し方の違いに応じて鳴き方を変えているかもしれない」という、新しい問いを投げかけました。
著者たちは今後、多様な国や文化で同様の調査を行うこと、飼い主の話しかけ方や猫の性格なども同時に測ることを、次のステップとして提案しています。
もしあなたの家で、猫が特定の人にだけよく鳴くなら、それはもしかすると「この人には、これくらい声を張らないと気付いてもらえない」という、猫からの鈍感度の評価なのかもしれません。
元論文
Greeting Vocalizations in Domestic Cats Are More Frequent With Male Caregivers
https://doi.org/10.1111/eth.70033
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部