スウェーデンのカロリンスカ研究所(Karolinska Institutet)の研究によって、マウスの脳内に「やめたいのに続けてしまう」ような反復行動を生み出す、スイッチのように働く神経回路があることが明らかにされたと報告されました。
この回路が働き始めると、動物は実験条件下で、空腹や社会的な関わりといった生きるために重要な欲求よりも、「穴を掘る」「床を嗅ぐ」といった意味のないように見える反復行動を延々と続けてしまいます。
研究では脳のごほうびを感じる部分(側坐核)から来た信号が、嫌な感情を生み出す部分(外側手綱核)へつながることで「やめられない反復モード」が起こる様子も示されています。
一体なぜ、脳にはこのような「理不尽な行動」を生み出す回路が備わっているのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年11月21日に『Science Advances』にて発表されました。
目次
- なぜ私たちは意味のない繰り返しにハマってしまうのか?
- どうでもいい行動が食欲や友情すら上書きする
- 理不尽な反復行動は、生き残り戦略の“副作用”か
なぜ私たちは意味のない繰り返しにハマってしまうのか?

「いや、別に楽しいわけじゃないんだけどなあ」。
そんな気分で、つい同じ行動を繰り返してしまうことはありませんか?
スマホを開いては閉じ、また開いて、たいして新しい情報があるわけでもないのに指だけが勝手に動いてしまう。
ドアの鍵を閉めた記憶があるのに、なぜか戻って確認してしまう。
そこにあるのは快感というより、「よく分からない引き戻し力」のようなものです。
脳の中では、たえず多くの欲求が同時に動いています。
「お腹がすいた」「誰かと遊びたい」「危険だから離れたい」。
こうした欲求は同じ舞台の上で押したり引いたりしながら、その瞬間に一番必要な行動を決めています。
ふつうなら、空腹のときは食べ物へ、刺激的なものがあればそちらへ向かうはずです。
しかし不思議なことに、やめられない反復行動では、この“優先順位づけ”がひっくり返ります。
周りから見ると特に目的があるようには見えない行動が、食事や探索よりなぜか勝ってしまうのです。
この「意味のないくり返し」が起きるのは、人間だけではありません。
動物の世界でも、ときに似た現象が見られます。
ネコが壁を執拗に引っかき続けたり、鳥が何度も同じ羽をいじり続けて羽根が薄くなったり、といった例はよく知られています。
動物本人は“楽しんでいるわけではない”のに、身体だけが同じ動きを続けてしまうのです。
人も動物も、「本心ではもう十分なはずなのに、行動が止まらない」という点では似ています。
とはいえ、この“止まらなさ”がどの脳回路で作られているのかは、長く分からないままでした。
繰り返し行動の研究はこれまで、主にごほうびを感じる領域を中心に行われてきました。
それは、「何かが強く快く感じられるから、くり返してしまうのでは」という発想があったからです。
ところが、この考え方では説明できない場面がたくさんあります。
実際には「快いどころか、特に意味もない行動」の方が勝ってしまうのです。
そこで研究者たちは、大胆に視点を変えました。
あえて“嫌な感じ”を生み出す領域も含めて、脳の回路を調べ直すことにしたのです。
本来、嫌悪感に関わる脳領域は「不快な行動を止めるためのブレーキの一部として働くしくみ」と考えられてきました。
しかしもし、ここに“止める”どころか、むしろ「やめたくてもやめられない」状態へ押し込んでしまう何かがあるとしたらどうでしょうか。
研究チームは、この疑問こそ強迫的な反復行動の核心に近づく手がかりになると考えました。
そして、「ごほうび」と「嫌な感じ」という、一見すると正反対に思える二つの感情をつなぐ回路にこそ、秘密が隠れているのではないかという仮説を立てたのです。
もしそこに“行動の優先順位をひっくり返すスイッチ”が潜んでいるのだとしたら──そしてそれが嫌な感じと結び付いているなら、そもそもなぜそのような仕組みが存在するのでしょうか?
どうでもいい行動が食欲や友情すら上書きする

「やめたくてもやめられない」「本心は嫌なのに続けてしまう」という行動はどのような脳回路が制御しているのか?
答えを得るため研究者たちは、マウスの頭蓋骨に穴をあけて光ファイバーを差し込み特定の神経経路を光で活性化できるようにしました。
そして脳の報酬系の中心にある領域(側坐核)から食欲などを司る領域(外側視床下部)を介してその先にある嫌な感じを司る領域(外側手綱核)を繋ぐ脳回路を人工的に活性化したりすることにしました。
私たちやマウスの脳内は複雑な脳回路が構成されており、ご褒美をもたらす報酬系と嫌な感じをもたらす領域も相互に連結しています。
コラム:なぜごほうびと嫌な気持ちが繋がっているのか?
「ごほうび」と「嫌な気持ち」が同じネットワークでつながっていると聞くと意外に思うかもしれませんが、実はそのほうが動物にとっては都合がいいのです。たとえば、ある食べ物が「おいしいけれど、たくさん食べるとお腹をこわしやすい」とします。このとき脳は、「おいしいからやりたい」と「お腹が痛くなるからやめたい」という二つの評価を同時に扱わなければなりません。もし、ごほうび系の回路と嫌悪系の回路が完全にバラバラで、お互いに会話もしていなかったら、ごほうび側は「おいしい!もっと!」とアクセルを踏み続け、嫌悪側は「お腹が痛い!やめて!」と別の場所でブレーキを踏むだけで、最終的な判断がいつまでもまとまりません。そのため私たちの脳では報酬を扱う領域から嫌悪を扱う領域へ信号が流れ込むように配線されていると考えられています。
そして実験の結果、この回路を繰り返し光刺激すると、マウスに徐々に「嫌な感じのする状態」(ネガティブな行動状態)が誘発されました。
刺激を受けたマウスは、自分が置かれた場所を「嫌だ」と感じているかのように隅に避けるようになり(回避行動)、同時に、地面をひっかく穴掘り行動や床の匂いを嗅ぐ行動を延々と繰り返し始めたのです。
驚くべきことに、たとえ目の前にエサがあって空腹でも、刺激中のマウスはエサをほとんど食べようとせず、食事に使っていた時間が大きく減り、その分ずっと地面を掘り続けていました。
さらに、同じ空間に他のマウスがいても、社会的な関わりより掘る行動を優先しました。
そして光刺激を止めると、マウスはエサを食べたり仲間に近づいたりする行動に戻ります。
つまり、この回路が作動している間は、自然な報酬(食欲や社会欲求)ですら後回しになるほど、無意味に見える反復行動が優先されてしまったのです。
では、この「掘り続けモード」は一体なぜ起きるのでしょうか?
鍵は回路の途中にある食欲などを司る領域(外側視床下部)と、嫌な感じを司る領域(外側手綱核)を繋ぐ回路にありました。
研究者たちがこの部分の神経活動を人工的に遮断してみたところ、繰り返しの刺激で生じていた「その場所を避ける」行動はほとんど見られなくなり、場所の好み方も元の状態に近づきました。
つまり「ごほうび領域➔食欲などの中枢領域➔いやな気持ちの領域」という一連の繋がり全体が、行動の優先順位の変化に深く関わっていると考えられます。
つまり、このやめられない行動はある意味で、快感だけではなく「嫌な気持ち」をも原動力にしていたのです。
しかしなぜ脳には「報酬に関係なく起こる反復行動」を起こすような理不尽な回路が存在するのでしょうか?
理不尽な反復行動は、生き残り戦略の“副作用”か
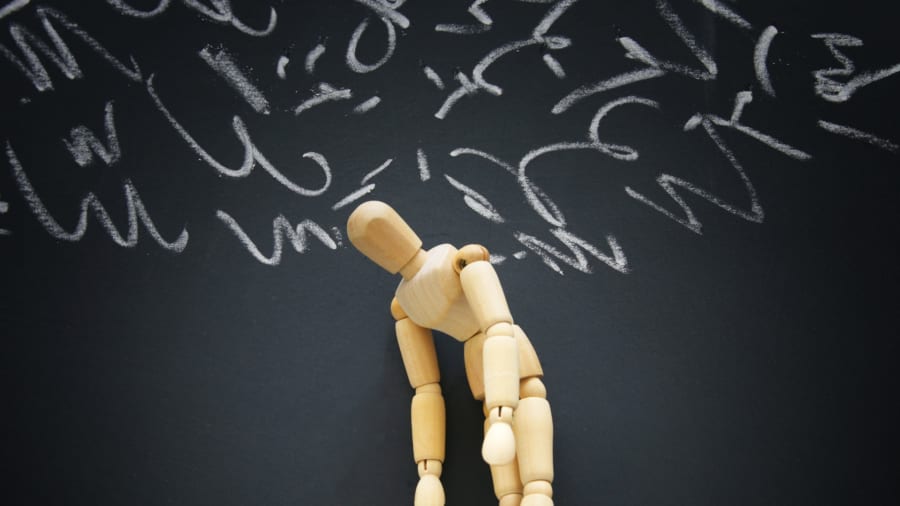
本研究により、マウスの脳内に、比喩的に言えば「行動を乗っ取るスイッチ」ともたとえられる回路が存在することが示唆されました。
この回路が光刺激によってオンになると、まるで自動操縦に入ったように行動が反復モードへシフトし、目的のない行動が延々と続いてしまいます。
本来であれば「嫌な感じ」がストッパーとなって行動を抑制するはずが、その嫌悪回路とほかの回路とのバランスが崩れるとかえって行動をやめられなくなる──比喩的に言えば、まるで自動車のブレーキが故障してアクセルになってしまったかのようです。
研究を主導したコンスタンティノス・メレティス教授は「この回路が行動を反復モードにシフトすることが分かった」と述べており、この発見が強迫行為や依存症など人間の神経精神疾患の理解につながる可能性に言及しています。
コラム:なぜそもそも報酬に関係ない反復行動を起こす脳回路が存在するのか?
しかしそもそもなぜ脳内に、報酬に関係ない反復行動を起こすような脳回路が存在するのでしょうか?お腹がすいていても、目の前に仲間がいても、エサや交流を後回しにして床を掘り続けさせる回路に、実用性があるとは思えません。
ですがここで少し視点を変えてみます。マウスにとって「掘る」「床を嗅ぐ」「穴を鼻でつつく」といった行動は、本来は意味のある行動です。巣穴を整えたり、土の中の情報を集めたり、捕食者や他個体のにおいをチェックしたりと、環境を“スキャン”する役割があります。野生の環境では、危ない場所に出てしまったときや、周囲の状況がよく分からないときに、いったんエサ探しや遊びをやめて「足元の安全確認モード」に入ることは、むしろ合理的です。今回問題になっている回路は、本来そのような「いったん他の行動を止めて、安全確認や環境チェックに集中する」ためのスイッチとして進化してきた可能性があります。
ところが、光遺伝学のような強い人工刺激でこのスイッチを押し続けると、本来は一時的な“保留モード”が、延々と続く「掘り続けモード」に変質してしまいます。非常ブレーキは、一瞬だけ踏むから役に立ちますが、ペダルをガムテープで固定したら車は前にも後ろにも動けなくなります。
それと同じように、もともとは「危ないときに役立つ」仕組みが、過剰に働いたときにだけ“理不尽な反復行動”という顔を見せているのかもしれません。もう一つ、大きな枠組みとして「習慣(ルーティン)」の問題もあります。私たちの脳は、なんでもかんでも一から考えていたらエネルギーが足りません。そのため、よく使う行動は徐々に“自動運転モード”に移し替えます。毎回ルールを検討するのではなく、「この状況ではとりあえずこのパターン」という形で、思考コストを節約しているのです。
今回の回路は、もともとそうした「行動パターンの選び直し」や「習慣モードへの切り替え」に関わっていて、上手く働いているときには、環境に合わせて効率よく行動を切り替える役に立っていると考えられます。ただし、スイッチの感度が高すぎたり、慢性的なストレス状態で誤作動したりすると、「本来は役に立つ行動パターン」が過剰に固定されてしまい、報酬に関係なく反復される“クセ”や“こだわり”として表に出てくることがあるのでしょう。
進化は、「人間から見て気持ちのいい行動だけ」を選んでくれるわけではありません。多少の副作用があっても、全体として生き残りにプラスなら、その仕組みは残ります。「報酬に関係ない反復行動」を引き起こすように見える回路も、もともとは危険回避や学習、エネルギー節約のために組み込まれていて、強い人工刺激や特殊な環境のもとで、その“影の側面”だけがあぶり出されていると考えると、少し納得しやすくなるのではないでしょうか。理不尽に見える行動を生む回路も、視点を引いてみれば、「生き延びるためのざっくりした戦略」がむき出しになった姿の一つなのかもしれません。
今回の発見は、マウスにおける「不適応な強迫的行動」の神経基盤を探る上で、一種の実験モデルケースになり得るでしょう。言い換えれば、報酬系・嫌悪系・本能系が三つ巴で暴走するこの回路は、強迫的行動を引き起こす脳内スイッチの一つなのかもしれません。
マウスにおける「やめたいのにやめられない」状態に対応する反復行動に脳内メカニズムの側面から光を当てた本研究の成果は、強迫症や依存症を神経回路レベルで理解していくための大きな一歩と考えられます。
原因不明だった“悪循環”の謎が、少しずつ解き明かされつつあります。
「やめられない」は意思の問題だけでなく、脳回路の働きも深く関わっている可能性があるのかもしれません。
参考文献
Brain circuit controlling compulsive behavior mapped
https://www.eurekalert.org/news-releases/1106715
元論文
A striosomal accumbens pathway drives stereotyped behavior through an aversive Esr1+ hypothalamic-habenula circuit
https://doi.org/10.1126/sciadv.adx9450
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


