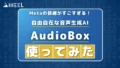誰かに助けられて“ありがとう”と思った瞬間、急にその人と気持ちが通じやすくなったように感じたことはありませんか。
この日常的な感覚に、じつは神経科学的な裏付けがあるようです。
中国・上海師範大学(SHNU)の研究チームは、感謝の気持ちが人と人の協力を促進しており、その背景で脳同士の活動が同期する現象が生じることを明らかにしました。
研究成果は2025年3月17日付の『Social Cognitive and Affective Neuroscience』誌で公開されました。
目次
- 「感謝」が二人の脳を同期させ、チームプレイの力を高める
- 感謝が引き出す「見えない力」とは?
「感謝」が二人の脳を同期させ、チームプレイの力を高める
「感謝」は、人間関係を良くする感情として知られていますが、その効果が実際の協力行動にどのような影響を与えるのかについては、これまで十分に検証されていませんでした。
研究チームはこの点に注目し、まず186人(93組)の女性ペアを募集し、感謝が協力行動をどのように変えるのかを調べました。
(実験の途中で手順の誤解や測定の不備があった参加者は除外され、最終的には83組のペアのデータが分析に使われています)
ある参加者たち(感謝グループ)にはまず、「相手から思いやりのメッセージを受け取る」「金銭分配で相手が自分に多く分けてくれる」などの小さなやり取りが用意され、自然に感謝の感情が生じるよう工夫されています。
一方で、同じ金額をコンピュータから受け取るだけで気分だけが良くなる条件(喜びグループ)や、特に感情が動きにくい中立グループも用意され、感謝そのものの効果が検証できるように設計されていました。
その後、相手を信じるか裏切るかで自分の利益が大きく変わる“かけひき型の協力ゲーム(プリズナーズ・ジレンマ)”と、2人でタイミングを合わせる“息合わせ型の協力ゲーム(同時ボタン押し)”の2種類を体験してもらいました。
プリズナーズ・ジレンマでは、協力すれば2人とも得をしますが、一方が裏切るとその人だけが大きく得をするようになっており、現実の「ちょっとずるい選択」を連想させる状況が再現されています。
同時ボタン押しのゲームでは、合図のあとに2人がほぼ同時にボタンを押せたときだけ得点が入る仕組みで、裏切る余地はなく、単純に息を合わせられるかどうかが問われました。
さらに、2人の脳活動がどれだけ同じリズムで変化しているかを測定するため、fNIRSを用いて、前頭前野や感覚運動野などの領域で脳の同期の有無が調べられました。
そして実験の結果、感謝グループは、どちらの協力ゲームでも、喜びグループや中立グループに比べていちばん協力的な行動を示しました。
相手がやや利己的に見える状況でも協力行動を続けやすく、2人で行うボタン押しのゲームでは、相手に合わせる動きが時間とともに上達しやすい傾向が見られました。
加えて、感謝グループでは、中前頭回や感覚運動野といった領域で脳同士の活動がより強く同期することも確認されました。
この脳同期が高いペアでは、実際の行動の調整もうまくいっており、感謝が協力行動を支える神経的な基盤となっていることが示唆されました。
では、なぜ“ありがとう”の気持ちががそこまで強い力を発揮するのでしょうか。
感謝が引き出す「見えない力」とは?
感謝グループだけが協力を維持できた背景には、感謝の感情が相手への信頼を高め、「この関係を続けたい」という気持ちを強くする作用があると考えられます。
その結果、多少の利己的な行動が見えても、すぐに関係を切らずに協力を続けやすくなるのです。
こうした心理的な働きは、脳活動の同期というかたちで可視化されました。
前頭前野は相手の意図や視点を読み取り、自分の行動を調整する役割を担う領域ですが、感謝を感じているペアではこの領域の活動が特に強く同期していました。
これは、相手の考えや動きを読み取るための準備が整い、2人が同じ方向へ向きやすい、いわば“協力しやすいモード”が脳レベルで生じている可能性を示しています。
さらに、同時ボタン押しの課題では、協力がうまくいっているペアほど脳の同期も高いという関係が見られ、行動と脳の状態が歩調を合わせながら協力を支えていることが示唆されました。
つまり、感謝は相手への信頼感を高め、その信頼感が「一緒にがんばろう」という姿勢と、相手に合わせて自分の行動を微調整する力を引き出し、その結果として脳のリズムまでそろっていく、と考えられるのです。
ただし、この研究にはいくつかの注意点があります。
参加者は若い女性のみであり、男性や年齢の異なるペアで同じ結果が得られるかはまだ明らかではありません。
また、協力ゲームは単純化された実験課題であり、現実の友人関係や職場のような複雑な状況と同じとは限りません。
文化的背景も限定されているため、感謝の影響が文化間でどのように変化するかについても検証が必要でしょう。
研究者たちは、今後は男女混合や年齢差のあるペア、複数人のグループを対象とした研究によって、感謝が協力行動に与える影響をより広い文脈で調べられると期待しています。
また、感謝が欠如している状況が協力関係をどのように損なうのかという逆方向の研究も、社会的な応用に向けて重要なテーマになるはずです。
“ありがとう”という一言が、人間同士を結びつける見えないリズムを生み出しているのだとすれば、感謝の力は私たちが思っている以上に大きな意味を持っているのかもしれません。
参考文献
Feeling grateful fosters cooperation by synchronizing brain activity between partners
https://www.psypost.org/feeling-grateful-fosters-cooperation-by-synchronizing-brain-activity-between-partners/
元論文
Gratitude enhances widespread dynamic cooperation and inter-brain synchronization in females
https://doi.org/10.1093/scan/nsaf023
ライター
矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。
編集者
ナゾロジー 編集部