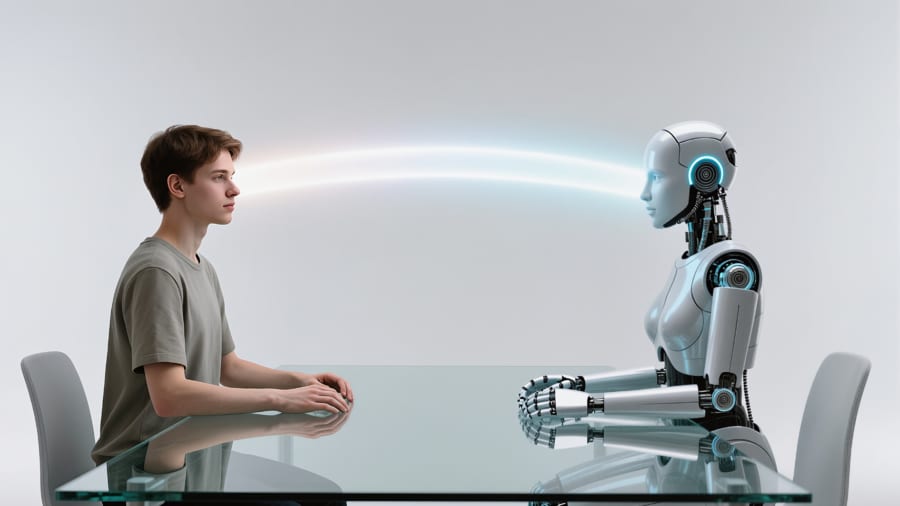アメリカのアマゾン研究所(Amazon)で行われた最新の研究によって、人は相手がAIだと分かると、言葉遣いの丁寧さのレベルは人間同士の会話と比べて約14.5%も低下することが明らかになりました。
さらに、このような人間の「ぶっきらぼう」な話し方が、AIアシスタントのユーザー意図理解能力をわずかに低下させる可能性が示唆されました。
しかし研究チームは、AIにあらかじめ様々な話し方を学ばせておくことで、人間がAIに対して使う自然な雑さや短い言い回しにも対応できるようになり、その認識精度が約2.9%改善することも実証しました。
果たして、人間の自然な話し方にAIが上手く合わせる未来は、本当にやってくるのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年10月3日に『arXiv』にて公開されました。
目次
- 人がAIに「礼儀正しくない」理由とは?
- 「丁寧に話せばAIは賢くなる」は幻想か?
- AIが人間の「雑な話し方」に適応する未来
人がAIに「礼儀正しくない」理由とは?
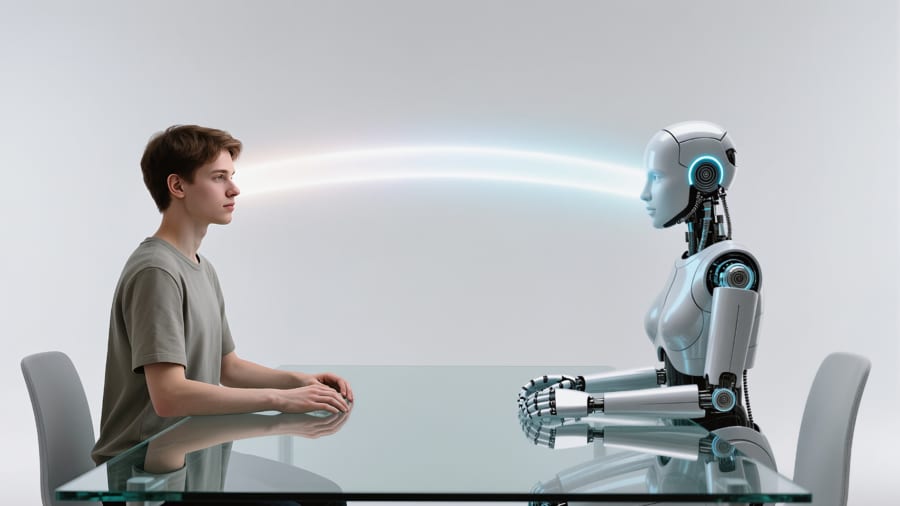
「相手がAIだと分かると、ついつい丁寧な言葉を使わなくなってしまう──」そんな感覚を持ったことがある人も多いのではないでしょうか。
例えば、スマホやスマートスピーカーの音声アシスタントに対して、「ちょっと天気教えて」と気軽に呼びかけることがありますよね。
これがもし本物の人間相手なら、「恐れ入りますが、今日の天気を教えていただけますか?」というように、もう少し丁寧に言い直すことがほとんどでしょう。
こうした違いは、私たちの日常の中で「あるある」な現象として自然に起きているかもしれません。
実際、人間は相手や状況によって自然に言葉遣いを変える生き物です。
心理学の世界では、この現象を「コミュニケーション順応理論」と呼んでいます。
これは少し難しそうな名前ですが、要は「相手に合わせて話し方や表現を自然と変える」という、人間なら誰しもが持っているコミュニケーションのクセを説明する考え方です。
例えば、小さな子どもにはゆっくりと簡単な言葉を使い、先生や職場の上司には敬語で丁寧に話す、親しい友達にはくだけた口調を使う、といった具合です。
話す相手や場面に応じて、自動的に言葉遣いを調整しているというわけですね。
さて、ここで問題となるのが、相手が人工知能(AI)の場合です。
相手がAIだと私たちは、「機械だし、感情なんてないだろうから丁寧に話す必要もないだろう」と無意識に感じてしまう可能性があります。
言い換えれば、私たちはAIを「気を遣わなくてもいい相手」として認識してしまっているのかもしれません。
ところが、ここで意外な盲点が生じるのです。
というのも、AIチャットボットや音声アシスタントを開発している技術者たちは、AIが人間とのコミュニケーションを円滑にできるようにするために開発を進めています。
そのため、人間同士の対話データを使ってAIを学習させています。
例えば、企業のカスタマーサポート担当者とお客さんのやりとりを大量に記録し、AIに読み込ませています。
こうすることでAIは、人間同士の自然な会話パターンや丁寧な表現方法を覚えるわけですね。
しかしここで重大な疑問が浮かび上がります。
もし実際のユーザーが、人間相手ではなくAI相手にだけ、大きく異なる話し方をしているとしたらどうなるでしょう。
AIは人間同士の丁寧な言葉遣いや文章を「普通の話し方」として学習しています。
ところが実際にやってくるユーザーからのメッセージは、AIが慣れているはずの丁寧なものではなく、いきなりフランクでぶっきらぼうな言葉遣いになるかもしれないのです。
そうなれば、AIは「想定外の言葉遣い」が急に飛んできたことで混乱し、本来の性能を十分に発揮できなくなってしまう可能性があります。
研究チームは、まさにこの盲点を突き止めることを目指しました。
まず1つ目の基本的な問いとして、「人は本当にAI相手だと話し方が変わってしまうのか?」という点を調べようとしたのです。
もしそれが事実であれば、AIの学習方法やコミュニケーション設計にも新しい工夫が必要になります。
また2つ目の問いとして、「話し方が違うことで本当にAIの理解力に影響が出るのか?」という点を詳しく検証しました。
そしてこの2つ目の問いの中には、よく耳にする「AIが理解できるようにユーザー側の言葉遣いを丁寧に直せばいい」という通説も含まれています。
本当にそれで解決できるのでしょうか。
単純にユーザーが丁寧に話せば、それだけでAIの理解力は改善するのでしょうか。
それとも問題はもっと複雑で、AIの学習そのものに大きな改善が必要なのでしょうか。
研究チームは、この誰もが気づかなかった「言葉遣いの盲点」を深掘りし、真相を明らかにするために正面からこの研究に挑みました。
「丁寧に話せばAIは賢くなる」は幻想か?
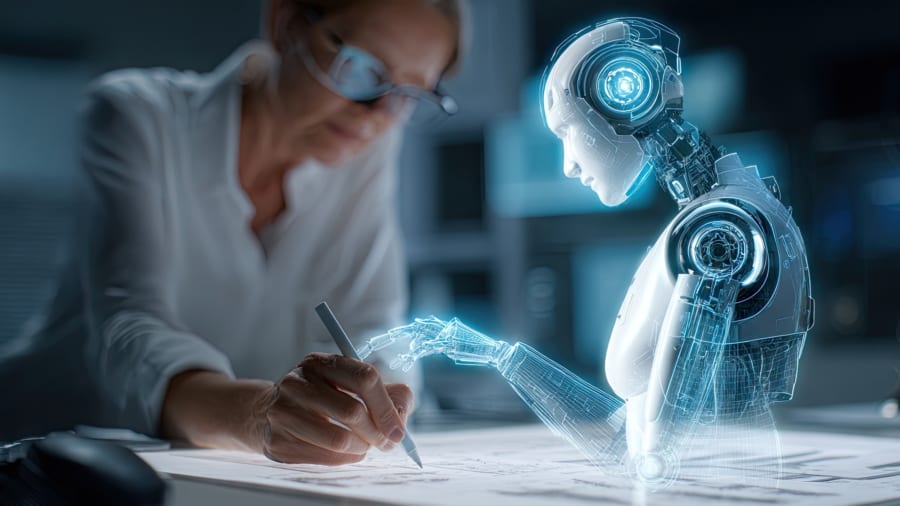
今回の研究を進めるにあたって、研究チームはまず、ある大手企業(Amazon)の実際のチャット対話のデータを詳しく分析することにしました。
つまり、本当にユーザーは人間相手とAI相手で言葉遣いが違うのかを調べるために、普段どのような言葉が使われているか、現実のデータを覗いてみたわけです。
用意したのは、人間のカスタマーサポート担当者とユーザーが実際に交わした「人対人」の会話データと、AIのチャットボット(対話型AI)とユーザーが交わした「人対AI」の会話データです。
こうした対話データはそれぞれ大量に集められましたが、今回使われたデータは、学習用として「人間同士のやり取りが13,000件」、AIの性能をテストする評価用として「AI相手のやり取りが1,357件」です。
こうして用意したデータから、個人情報などを削除した上で、「人対人」と「人対AI」でユーザーの話し方がどう変わるかをじっくりと分析しました。
では実際にどんなポイントをチェックしたかというと、次の6つの基準でそれぞれのメッセージを採点しています。
具体的には、
①文法が正しく使われているか、
②言葉遣いが丁寧かどうか(敬語が使われているか)、
③使われている言葉の種類が多いか(語彙が豊富か)、
④情報が具体的にきちんと伝わっているか(情報の具体性)、
⑤表現が明確でわかりやすいか、
⑥気持ちや感情がどれくらい表現されているか、
という6つの観点から、AIモデル(チェーン・オブ・シンキング法=chain-of-thought、AIに段階的に考えさせて判断させる方法)を使って、丁寧にスコアリング(採点)しました。
さて、気になる結果ですが、これが実に明確なものでした。
AI相手の会話と人間相手の会話を比べると、はっきりとした違いが現れたのです。
AI相手のメッセージでは、人間相手のときよりも文章が短くなり、言葉遣いがぶっきらぼうになりやすく、敬語もあまり使われませんでした。
人間のカスタマーサポートに対しては「お願いします」や「ありがとうございます」などの丁寧で礼儀正しい表現がよく使われましたが、AIのボットにはそれらがぐっと減ったのです。
実際のスコアを比べると、「丁寧さ・形式的な表現」のスコアは、AI宛てのメッセージのほうが人間宛てよりも14.5%も低くなっていました。
また、文法の正確さもAI相手のほうが5.3%低下しており、使われる言葉の種類も少し少ない傾向がありました。
つまりAIに対して人は、敬語や細かな表現をかなり省略し、言葉遣いが雑でタメ口に近づいてしまう傾向が明らかになったわけです。
しかし、ここで興味深いのは、言葉遣いが丁寧ではなくても、メッセージの内容そのもの(情報の具体性や明確さ、気持ちの表現)にはほぼ差がなかったことです。
つまりユーザーはAIに対しても、自分が伝えたい用件自体はきちんと伝えていました。
例えば、「これを教えていただけますか?」と丁寧に聞くかわりに、「これ教えてよ」と短くぶっきらぼうに聞いているだけで、伝えている情報自体は変わらなかったのです。
言い換えれば、「礼儀や丁寧な言い回しは省くけれども、本当に伝えたいことはそのまま伝えている」という状態ですね。
それでは、人がAIに対してだけ、このように言葉遣いを崩してしまうのはなぜでしょうか。
研究チームは、この理由を「私たちユーザーが持っているAIへのイメージ」と関係があるのではないかと考えました。
つまりユーザーが「AIは感情がなく、言葉遣いが雑でも特に問題ない」と無意識に感じているからこそ、丁寧に話す必要を感じないのかもしれません。
実験からも、「AIは社会的に鈍感で、丁寧に話さなくても理解してくれるだろう」というユーザーの考え方が、言葉遣いに影響を与えている可能性が示唆されています。
あえて比喩を使えば、ユーザーはAIを「機械なんだし、多少雑に話しても平気だろう」と無意識に判断しているようなものかもしれません。
しかし、先にも触れたように、ここに大きな問題が隠れていました。
AIはこれまで、人間同士の丁寧な会話を学習して、そのスタイルに慣れ親しんでいます。
そのためユーザーが急にフランクでぶっきらぼうな話し方をすると、学習時の丁寧な会話スタイルとのギャップに戸惑ってしまい、本来の性能を発揮できなくなってしまう可能性があります。
研究チームはこのギャップによってAIの理解力が低下する可能性を指摘しました。
そこで研究チームは、このギャップを解決するために2つの方法を試してみました。
1つ目は、AI側の訓練データにあらかじめ多様な話し方の例を混ぜる方法です。
これは丁寧な言葉遣いだけではなく、「ちょっと雑な口調」や「短くてぶっきらぼうな言葉遣い」も最初から学ばせておくという方法です。
言ってみれば、AIに「色々な方言」を最初から学習させるイメージですね。
2つ目の方法は、ユーザーがAIに入力する言葉を、AIに届ける前に自動で丁寧な言葉に書き換えるという方法です。
例えばユーザーが「これ教えてよ」と短く入力しても、AIが受け取る前に「これを教えていただけますか?」というふうに自動で丁寧に変換してしまうという方法です。
要するに、AIが理解しやすいように人間に対するような「礼儀正しい言葉遣い」に変えてしまおうという試みですね。
では、その結果はどうだったのでしょうか。
まず訓練データを多様化する方法では、AIの性能が実際に向上しました。
ぶっきらぼうな表現や丁寧すぎる言葉遣いなど、いろいろな話し方を最初から学習したAIは、実際のユーザーからの雑な言葉遣いに対しても理解力が向上しました。
具体的には、ユーザーが何を求めているかをAIが正しく理解できる割合が、従来の方法より約2.9%(相対)高くなったのです。
数字だけ見ると小さいようですが、実際には多くのユーザーとのやり取りでの誤解が減ることを意味しています。
しかし、意外なことにもう一つの方法、ユーザーの言葉を丁寧に書き換える方法はうまくいきませんでした。
それどころか逆効果で、AIの理解力は約1.9%(相対)ほど低下してしまいました。
研究チームによれば、この原因は、丁寧に書き換える過程で、元の短く雑な言葉に含まれていた「微妙なニュアンスや手がかり」が失われたり、文章が不自然になるためではないかと考えています。
つまり、言葉遣いを丁寧に整えればAIの理解力が上がるという「言い換え神話」は、残念ながら普遍的現象ではなかったということです。
AIが人間の「雑な話し方」に適応する未来
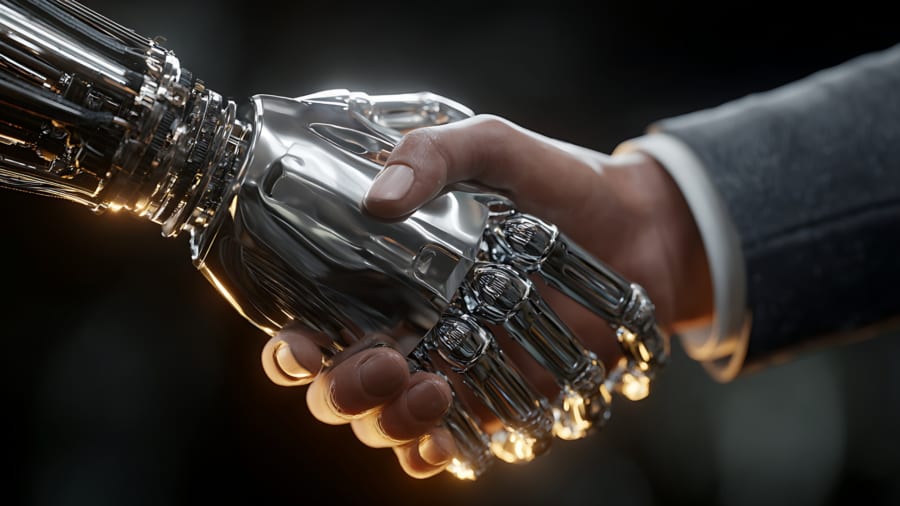
今回の研究を振り返ってみると、人がAI相手だと自然とぶっきらぼうになってしまうという現象が示されました。
これは人間相手の会話では当たり前のように使っている丁寧な言葉遣いを、AI相手だと無意識に省いてしまうということです。
単純に言えば、「AIには丁寧に話さなくても問題ないだろう」と人が感じているためですが、このちょっとした気の緩みが、実はAIにとっては小さな壁になっていることが明らかになったわけです。
この発見は、AIを開発する側にとって非常に大事な意味を持っています。
従来のAI開発では、人間同士の丁寧な対話を基準にAIが訓練されているため、ユーザーがAIに対して突然フランクな口調を使うと、AIがうまく理解できないことがありました。
その意味で今回の研究成果は、これまでのAI開発に見落とされてきた重要なポイントを照らし出したことになります。
研究チームは、この新たな視点をもとに、多様な話し方に対応できる強力な対話型AIを開発する道筋ができたと示唆しています。
AIをさらに賢く、そしてよりユーザーフレンドリーな存在にしていくためには、丁寧な言葉遣いだけでなく、ユーザーが実際に使うような少し雑な言葉遣いやフランクな表現までAIが理解できるように鍛える必要があります。
例えば、カスタマーサービスのチャットボットに対してユーザーが多少ぶっきらぼうな質問をしても、AIがその意図を正確に理解できるようになれば、ユーザーはイライラせずにすぐに知りたい情報が得られ、企業側も顧客対応がスムーズになるでしょう。
つまり、AIがユーザーの自然な話し方を理解できれば、みんなが気持ちよく使えるシステムになり、社会的にも大きなメリットになるはずです。
ただし、研究にはいくつかの限界もあります。
今回の研究は、主にテキストを使ったチャット形式の対話を対象にしています。
また、調べたのは会話の初期段階(特にユーザーの最初の発話)に限定されており、やり取り全体を通した分析ではありません。
実際の生活では、やり取りが長くなるにつれてユーザーの態度や口調が変化する可能性もあるので、今後はこうした長期的な対話での礼儀や言葉遣いの変化を詳しく調べていく必要があります。
さらに、今回使ったデータは英語圏の特定のサービスに限定されており、他の言語や異なる文化圏では同じような結果になるとは限りません。
加えて、企業の内部で扱われる匿名データを使っているため、誰もが同じ方法で検証するのは少し難しい状況です。
こうした制約があることを念頭に置きつつも、人間がAIに対して丁寧さを省略してしまう現象自体は、多くの人が共感できる傾向だと考えてよいでしょう。
それでも、今回の研究結果はとても重要です。
これまでの「ユーザーが丁寧に話せばAIは正しく理解できるはず」という単純な考え方は再検討が必要だと示唆されました。
むしろ、ユーザーがAIに対して自然に使ってしまう雑な言葉遣いを前提として、それに適応できるAIを作るべきだという方向性が見えてきたと言えるでしょう。
研究チームは今後、この考えを生かしてAIのさらなる改善を進めていきたいと述べています。
具体的には、ユーザーの言葉遣いを自動的に判別して、それに合わせた対応ができるAIシステムや、さまざまなスタイルの言葉遣いを理解できる「次世代のAIチャットボット」の開発などが考えられます。
「歩み寄るべきはAIの側」ということになりそうです。
元論文
Mind the Gap: Linguistic Divergence and Adaptation Strategies in Human-LLM Assistant vs. Human-Human Interactions
https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.02645
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部