人間の記憶に「五感を超える最適な次元」があるのかもしれません。
ロシアのスコルコボ科学技術研究所(Skoltech)を含む国際共同研究チームによって行われた理論研究によって「記憶がどのように作られ、また忘れられていくのか」というメカニズムが再現されました。
その結果、感覚の種類(次元)が五感ではなく七感あるときに、記憶容量(脳が区別して覚えられる情報の数)が最大になることを発見しました。
さらに驚いたことに、次元の数がこれを超えて増えすぎると、逆に記憶できる情報が減ってしまうことも分かりました。
これは、「情報が多いほど記憶力が良くなる」という常識に反する、ちょっと不思議な発見です。
では、なぜ「7次元」なのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年8月15日に『Scientific Reports』にて発表されました。
目次
- 感覚を増やしたら記憶はどうなるか
- 記憶は7次元で最大容量になる
- なぜ「7」が最適なのか?
感覚を増やしたら記憶はどうなるか

誰しも一度は「第六感」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
映画やマンガでも、「なんか嫌な予感がする!」と主人公が第六感を働かせるシーンはよくあります。
ただ、私たち人間は基本的に五感、つまり「視覚(目で見る)」、「聴覚(耳で聞く)」、「嗅覚(鼻で匂いを嗅ぐ)」、「味覚(舌で味わう)」、「触覚(肌で触れる)」で世界を記憶しています。
たとえば、リンゴについて考えてみましょう。
「赤くて丸い」という視覚的な情報、「シャリッとした歯ごたえ」という触覚や聴覚、「甘酸っぱい味」といった味覚。
こうした複数の感覚が組み合わさることで、リンゴという記憶は私たちの脳に強く鮮明に刻まれます。
では、もし「第六感」やさらにその上を行く「第七感」など、これまでの五感にはない全く新しい感覚が加わったらどうでしょうか。
たとえば、「磁場を感じることができる」「放射線を感知する」など、新しい感覚を人類が将来的に獲得したら、記憶力や学習能力が飛躍的にアップするのでしょうか。
一見すると「感覚が多いほど記憶は良くなる」と思いがちです。
ですが、ちょっと待ってください。
もし仮に感覚の種類が数十、数百、あるいは数千にもなったとしたらどうなるでしょうか。
たとえば、たった一つのリンゴという記憶にも、「重力の揺らぎ」や「紫外線の微妙な変化」といった、今はまったく感じ取れない情報が大量に付け加わるかもしれません。
そうなると、脳はそれだけの膨大な情報量を整理して記憶できるのでしょうか。
まるで片付けが苦手な人が、一気に大量の荷物を抱えてパニックになるように、脳も情報過多に耐えられなくなるかもしれません。
空想じみた話に聞こえるかもしれませんが、実はこうした「記憶に最適な感覚の数」は、科学の世界でも真剣に議論されています。
これまで、「記憶には多様な情報が含まれたほうが良い」という常識的な考え方がありましたが、それは本当に正しいのでしょうか。
もしかすると、記憶のシステムには最適な「ちょうど良い」感覚の数、つまり「臨界次元」が存在するのかもしれません。
これこそが、今回研究者が取り組んだテーマなのです。
ここで鍵になるのが、「エングラム(記憶の痕跡)」という、少し難しそうな言葉です。
エングラムとは、簡単に言えば「記憶が脳に刻まれる仕組み」のことを指します。
もう少し具体的に説明すると、「ある記憶に対応した特定のニューロンの集まり」です。
たとえばマンガのセリフを覚えている場合、そのセリフを記憶したときに活動したニューロンの集団が、あなたの脳に「エングラム」として残っているというイメージです。
実はこのエングラムという考え方は、最近出てきたものではありません。
なんと100年以上前から研究者たちが提唱してきた、歴史ある概念なのです。
とはいえ、私たちが普段エングラムという言葉を耳にすることはほとんどありません。
でも、「あのセリフを言っていたキャラ、なんて名前だっけ?」と思い出そうとするとき、私たちの脳ではこのエングラムがしっかり働いているのです。
さて、今回の研究チームは、このエングラムがどのように形成され、変化し、そして消えていくのかを詳しく調べることにしました。
といっても、人間の頭を割って中を調べることはできません。
そこで、研究者たちは脳内で起きているエングラムの働きをコンピュータ上のシミュレーション、いわば「仮想の脳」で再現することにしました。
具体的には、感覚の数(視覚や聴覚など)を「次元」という数学的な考え方で表現し、それを「概念空間」と呼ばれる記憶の世界に落とし込みました。
言い換えれば、「感覚が3つの世界」「5つの世界」「7つの世界」といった仮想空間をコンピューター上で作り、それぞれの世界で記憶の働き方を観察したのです。
この研究で明らかにしたかったのは、「感覚の数が増えると記憶できる概念(つまり脳内で区別できる記憶)は無限に増えていくのか?」という疑問でした。
それとも、「どこかに上限があり、それ以上は記憶能力が下がるのか?」という問いも重要でした。
こうして研究チームは、「記憶にとって最適な感覚の数=臨界次元」を求める冒険の旅に出たのです。
記憶は7次元で最大容量になる
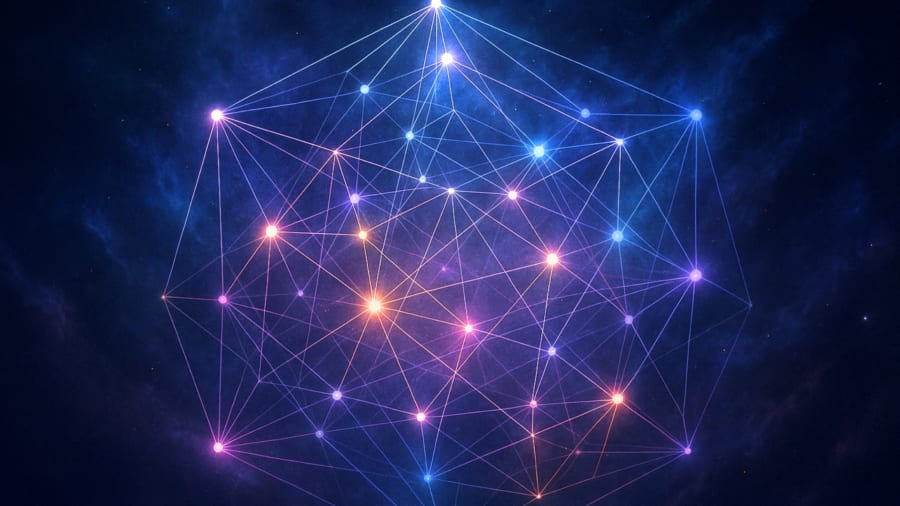
この疑問に答えるため、研究チームは記憶の形成や忘却のプロセスを「仮想の脳」で再現することにしました。
とはいえ、培養液の中で脳を作るわけではありません。
実際には、私たちの脳や人工知能が「外から入ってくる情報」をどう記憶し、どのように忘れていくかを、数式で表現したモデルに置き換えて調べたのです。
まず研究チームが取り組んだのは、「感覚の数=次元の数」という発想をもとにしたシンプルなモデル作りでした。
たとえば私たちは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という五感を使って世界を感じています。
この五感があるからこそ、リンゴの色や香り、味や手触りといった情報を組み合わせて、「リンゴ」という一つの概念として記憶できるのです。
もし視覚と嗅覚と聴覚しかない、三次元の世界だったらどうでしょうか。
リンゴは見た目と匂いと噛んだときの音だけで表され、味や手触りの記憶は抜け落ちてしまいます。
一方で、もし味覚や触覚に加えて、第六、第七の感覚があったとしたらどうでしょう。
「リンゴの磁場の揺らぎ」や「リンゴから発せられるわずかな放射線」といった、今は感じられない新しい情報も、脳に入力できる世界です。
研究者たちは、こうした「感覚の数」を数学的な「次元」として表現した「概念空間」という仮想世界をつくり、その中で記憶がどのように生まれたり消えたりするのかをシミュレーションしました。
ここでカギになるのが、先ほども登場した「エングラム」というキーワードです。
エングラムは「記憶の痕跡」という意味ですが、簡単に言えば、脳の中で「特定の記憶を担当するニューロンのチーム」です。
リンゴの記憶なら、「赤い色の情報」「甘酸っぱい味の情報」「噛んだときのシャキッという音の情報」など、それぞれの感覚を担当するニューロンが集まり、1つのまとまった記憶を作っています。
こうしたエングラムは、一度記憶が作られたらそのまま残るわけではありません。
新しく入ってくる情報や刺激(たとえば再びリンゴを食べる、見るなど)によって、エングラムは「シャープさ(鮮明さ)」を取り戻します。
一方、何もしないままでいるとエングラムは徐々にぼんやりと拡散し、記憶は薄れていきます。
よく使う知識は覚えているのに、使わない知識を忘れてしまうのは、こうした仕組みが脳内で働いているからなのです。
研究チームは、この仕組みをコンピューター上の仮想空間で詳しく再現しました。
その中で「感覚(次元)が増えると、覚えられる概念(記憶)の数はどう変化するか?」という実験を行いました。
予想通り、感覚の種類を増やすほど最初のうちは記憶できる概念の数も増えていきました。
これは料理に例えるなら、材料(感覚)が増えるほど料理(記憶)のバリエーションが増えるようなものです。
視覚だけよりも、視覚+嗅覚+触覚の方が記憶は豊かになるという感覚です。
しかし驚いたことに、この増加には限界がありました。
感覚(次元)が7種類を超えると、脳内に覚えられる記憶の数は逆に減り始めたのです。
これが、研究者が見つけた「臨界次元」、つまり記憶にとってちょうど良い感覚の数です。
ではなぜ7という数字が最適なのでしょうか。
研究チームによれば、感覚の数が多すぎると、脳が新しい記憶を作る際に、それぞれの記憶が重なりやすくなってしまうためだといいます。
簡単に言えば、情報が多すぎて脳が混乱し、「どこかで見たような似た記憶」ばかりが増えてしまうのです。
逆に、感覚の数が少なすぎると、新しい刺激を区別するための情報が足りず、異なる刺激もひとまとめにしてしまうため、新しい記憶のカテゴリーが生まれにくくなります。
こうした「感覚が多すぎても少なすぎてもダメ」という現象は、「バイアスとバリアンスのトレードオフ」と呼ばれる、機械学習の分野でも知られる考え方に似ています。
つまり、情報量が多すぎても少なすぎても、脳はうまく記憶を整理できないというわけです。
この“7”という最適次元は、モデルの詳細仕様(刺激の分布、概念空間性質、刺激発生確率など)にあまり依存しない頑健な性質として現れると主張しており、「モデルの設定を変えても最適次元は7前後で飽和する」傾向が観察されたと述べています。
研究者たちも「7という数字がエングラム(記憶の痕跡)の基本的な性質から自然に導かれた」と驚きを語っています。
まさに、記憶にとっての「ちょうど良さ」を科学が初めて数字で示した瞬間でした。
なぜ「7」が最適なのか?
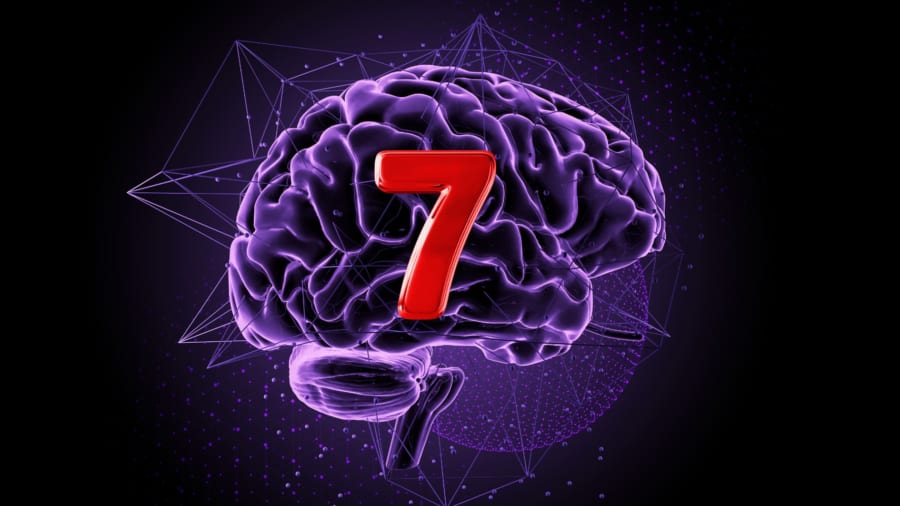
今回の研究が示した最大の発見は、「記憶には最適な情報量、つまり“臨界次元”が存在するかもしれない」ということです。
これまで、私たちは五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)をベースにして記憶を形成してきました。
しかし研究チームが示した数学モデルでは、感覚の種類が7つになったときに「記憶容量」、つまり区別して覚えられる記憶の数が最も多くなるという結果が出ました。
単純に「感覚が多いほど記憶力が良くなる」と思われがちですが、実際には増えすぎるとかえって逆効果になるという、ちょっと意外な結果です。
これは脳が「多すぎる情報」に振り回されず、「ちょうどよい複雑さ」を求めていることを示唆しているのかもしれません。
現実には、私たち人間がすぐに第六感や第七感といった新しい感覚を持つようになるわけではありません。
ただし、この研究の結果は「人工システム」や「ロボット」にとって大きなヒントになる可能性があります。
どういうことでしょうか?
例えばAIロボットにさまざまなセンサーを搭載する場合、「情報をたくさん取り入れれば賢くなる」と考えがちです。
ところがこの研究によると、情報を増やしすぎると逆に情報が混乱し、かえって頭が悪くなってしまう可能性があるというのです。
簡単に言うなら、「情報が多すぎて整理整頓が間に合わず、記憶がゴチャゴチャになる」というイメージです。
だからこそ、ロボットやAIを設計する人にとっては、「7種類くらいのセンサーで情報を集めるのが、実は最も効率が良い」と考えられるわけです。
研究者たちはこの「7」という数字が出現する背景として、エングラムの幾何的構造や空間詰めの問題など数学的な部分要因としています。
記憶をエングラムに頼るシステムを採用していると、7という数字がモデルの数式から自然に導かれるのかもしれません。
また、研究者たちはあくまで慎重に述べていますが、人間の感覚そのものが今後どう変わっていくのかにも、この研究は示唆を与えています。
つまり「未来の人類が磁場や放射線のような新しい感覚を身につける可能性もゼロではない」と考えられます。
この研究結果は、脳の仕組みをより深く理解するための今後の研究にもつながるでしょう。
脳が扱える情報の限界や「最適な複雑さ」を明らかにすることで、記憶を効率よくするヒントが得られるかもしれません。
例えば、異なる動物で「記憶できる情報量」を比較する研究や、人間が新しい感覚を学習したとき認知能力がどう変わるかを調べる新しいテーマも生まれそうです。
もちろん、この研究にも限界はあります。
最大の限界は、この結果が「数理モデル(コンピュータ上の仮想世界)」に基づいている点です。
現実の人間の脳が本当に同じように働くかどうかは、まだ証明されていません。
それでも、異なる条件でも一貫して同じ結果が得られている点は十分に価値があります。
また、今後の実験で検証されるべき大事な仮説を示したことにも意味があります。
最後に、この研究が投げかける意外な教訓をまとめてみましょう。
「感覚や情報は増やせば増やすほど良い」というのは思い込みで、むしろ「適度な複雑さと適切な情報量を効率よく整理すること」こそが大切かもしれません。
料理で材料を入れすぎると美味しくならないように、記憶や学習にも“ちょうどいい材料の数”がある、というイメージです。
この「ちょうどよい情報量」の追求が、今後の脳科学やAI研究の新しい目標となっていくでしょう。
元論文
The critical dimension of memory engrams and an optimal number of senses
https://doi.org/10.1038/s41598-025-11244-y
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


