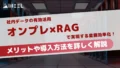私たち人類の祖先は、果たして“狩る者”だったのか、それとも“狩られる者”だったのか。
東アフリカ・タンザニアのオルドヴァイ峡谷で発見された約200万年前の絶滅人類「ホモ・ハビリス(Homo habilis)」の化石。
スペイン・アルカラ大学(Universidad de Alcalá)はこれを最新の人工知能(AI)で解析した結果、初期人類は狩る側ではなく、狩られる側だった可能性が示されました。
これまで「最初の石器製作者」「肉食への転換者」として語られてきたホモ・ハビリスですが、実際には、現代のヒョウなど大型肉食獣にとって格好の“獲物”だったのかもしれません。
研究の詳細は2025年9月16日付で科学雑誌『Annals of the New York Academy of Sciences』に掲載されています。
目次
- AIが暴いた「人類は獲物だった」証拠
- 「人類が頂点に立つ」のはもっと後の時代だった?
AIが暴いた「人類は獲物だった」証拠
研究チームが着目したのは、タンザニア・オルドヴァイ峡谷で見つかった2体のホモ・ハビリス化石です。
一つは約185万年前の幼い子供「OH 7」で、もう一つは約180万年前の成人個体「OH 65」でした。
この2体の骨には、目視でも分かる“歯型”が残っていましたが、「どの動物によるものか」は、これまで長年はっきりしませんでした。
チームは、現代のヒョウ、ライオン、ワニ、ハイエナ、オオカミといった肉食獣が残す歯型の写真を1,496枚も集め、それをAI(ディープラーニング)で学習させました。
そして最新のAIモデル(ResNet-50やDenseNet-201など)に、ホモ・ハビリス化石の歯型画像を読み込ませて分析。
すると2つのモデルがともに「骨に残された歯型は、90%以上の高確率でヒョウによるもの」と判定したのです。
特に、骨に残る歯型が三角形のくぼみで、現生ヒョウのサンプルと一致していた点が決め手となりました。
もしハイエナのような骨を噛み砕く動物が咬んでいたなら、化石骨はもっとバラバラになっていたはずです。
しかし、損傷は比較的軽微で、ヒョウが肉を食べる際に残す特徴と完全に合致していました。
このことは、当時のホモ・ハビリスが「捕食者として頂点に立っていた」のではなく、むしろヒョウなどに狙われる“弱い立場”だった可能性を示唆しています。
「人類が頂点に立つ」のはもっと後の時代だった?
これまで多くの研究者は、約240万〜140万年前にたいホモ・ハビリスを「最初の石器を使い、肉食獣と対等に渡り合い始めた存在」と位置づけてきました。
しかし実際には、オルドヴァイ峡谷の当時の環境において、ヒョウのような中型~大型肉食獣が食物連鎖で優位にあり、人類はその「獲物」として日々を過ごしていた可能性が高いといえます。
特に、ホモ・ハビリスの身体には樹上生活の名残(木登り適応の証拠)が多く残っており、地上での生存戦略がまだ未発達だったと考えられています。
実際、樹上に逃れることで、ヒョウやライオンの脅威を避けていたとも推測できます。
この事実は「初期人類が食物連鎖の頂点に立つ」というストーリーが、やや“先走り”だったことを示しています。
また、当時のオルドヴァイ峡谷の発掘現場では、ホモ・ハビリス以外のホモ属(ホモ・エレクトス=原人)やパラントロプス属も同時期に存在していたことが分かっています。
今回の結果は、「石器を使った肉食」という進化的転換が、ホモ・ハビリスだけでなく、より進化したホモ・エレクトスのような種で本格化した可能性を示唆しています。
参考文献
The hunted, not the hunters: AI reveals early humans were prey for leopards
https://phys.org/news/2025-09-hunters-ai-reveals-early-humans.html
Leopards may have feasted on our earliest ancestors
https://www.popsci.com/science/leopards-ate-early-humans/
元論文
Early humans and the balance of power: Homo habilis as prey
https://doi.org/10.1111/nyas.15321
ライター
千野 真吾: 生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。
編集者
ナゾロジー 編集部