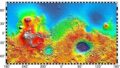台湾の国立陽明交通大学(NYCU)で行われた研究によって、電気の力で焦点距離(ピント)を切り替える液晶レンズが開発されました。
従来の遠近両用メガネではレンズの上半分と下半分で見るべき距離が異なり、利用者は視線を上下にずらす必要がありました。
しかし新しい液晶レンズではフォーカスを自在に切り替えられるため、視線の移動が大幅に減ると期待されています。
果たして、液晶で作られたメガネレンズは私たちの視生活を根本から変えることができるのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年8月29日に『Physical Review Applied』にて発表されました。
目次
- ピントを自由自在に切り替える液晶レンズの可能性
- 「電気で動くレンズ」――液晶レンズのしくみを解説
- 液晶レンズはメガネに革命を起こす
ピントを自由自在に切り替える液晶レンズの可能性

多くの人にとってメガネは生活になくてはならない道具ですが、その必要性は近年ますます高まっています。
日本をはじめ先進国の多くでは高齢化が急速に進み、それに伴って老眼に悩む人も増加しています。
老眼とは、年を取るにつれて目の中のレンズ(水晶体)が硬くなり、近くのものにピントが合いにくくなる現象です。
スマートフォンやパソコンが普及した現代では、若い人の間でも近視が増えています。
この両方の問題に対応するために古くから使われているのが遠近両用メガネです。
これは1つのレンズの中で遠くを見る部分と近くを見る部分が分かれているもので、代表的なものには「バイフォーカル(二重焦点)レンズ」と呼ばれるものがあります。
しかし、このバイフォーカルレンズには特有の問題があります。
レンズの上側で遠くを見て、下側で近くを見るという構造になっているため、見る距離が変わるたびに視線や顔を上下に動かす必要があります。
またレンズの中央には度数の境目があるため、この境目を通して見ると像が突然ジャンプしたように感じることもあります。
一方で、境目がないように作られた「累進多焦点レンズ」というものもあります。
これは境目が無いために滑らかに遠くから近くまで焦点を合わせられるのが特徴ですが、レンズの周辺部分では像がゆがんでしまうことがあります。
そのため、視界が狭く感じたり、ピントが合う範囲が限られてしまったりして、慣れるまで違和感があるというデメリットもあります。
こうしたレンズ特有の不便さから、階段でつまずいてしまうなどの転倒事故につながったケースも報告されています。
そのため、多くの人は結局、遠くを見るためのメガネと近くを見るためのメガネをそれぞれ別々に用意して、状況によって使い分けています。
これにはメガネを掛け替える手間や、複数のメガネを買うコストの問題が生じてしまいます。
こうした問題を解決するため、理想的なのは「1つのメガネで必要に応じてピントを自由に調節できる」ような技術を実現することです。
実はこうした可変焦点レンズ(焦点を自在に変えられるレンズ)のアイデア自体は古くからあり、カメラの「オートフォーカス機能(自動でピントを合わせる仕組み)」のように、自動で焦点距離を変えるメガネも研究されてきました。
例えば過去には、液体を封入した柔らかいレンズの厚みを機械的に変えるタイプや、特殊なプラスチックレンズを物理的に変形させて焦点を調整する方法も考案されました。
しかし、これらの方式ではレンズが厚く重たくなったり、メガネの構造が複雑になったりするため、日常的に身につけるメガネとして使うのは難しいとされてきました。
そこで今回の研究チームは、これまでとは全く違う新しい発想をしました。
「レンズの形状や物理的な厚みを変えるのではなく、レンズの中身自体の屈折力(光を曲げる力)を電気の力だけで自由に変えられるのではないか」と考えたのです。
研究チームが注目したのが、液晶テレビやスマートフォンなどに使われている「液晶」の技術でした。
液晶は、液体のように流動的でありながら結晶のように分子がきれいに並ぶ特殊な性質をもっています。
この液晶の分子は、電気をかけると並び方が変わるため、これを利用してレンズの屈折力を電気信号で変えることができると考えました。
これが実現すれば、ボタン一つ押すだけで、遠くでも近くでも好きなときに焦点距離を調整できるメガネが可能になるかもしれません。
しかし、はたして液晶を本当に実用的なメガネのレンズとして利用することができるのでしょうか?
「電気で動くレンズ」――液晶レンズのしくみを解説

新型液晶レンズは、どのような仕組みでピントの調整をしているのでしょうか。
その鍵を握るのが、「液晶」という物質が持つユニークな性質です。
液晶は液体のように自由に流れる一方で、分子が一定の方向に規則的に並ぶという、固体の結晶のような特徴も持っています。
そして、この液晶分子の並び方は、電気をかけることで自由に変化させることが可能です。
通常のメガネレンズでは、表面の形状(凸レンズや凹レンズのような曲がった形)によって光を曲げ、ピントを合わせます。
しかし、液晶レンズの場合、レンズの表面形状は変えずに、内部の液晶分子の並び方だけを変化させることで、光を曲げる力(屈折力)を調整できるのです。
具体的には、透明なレンズ基板(レンズを形づくる土台)の内部に液晶を入れ、その液晶に電圧を加えると、液晶分子の並ぶ方向が揃ったり変わったりします。
この液晶分子の並ぶ方向によって、光がどれくらい強く曲がるかが変わるので、レンズの焦点位置(ピントが合う位置)も変えることができるという仕組みです。
この方式が画期的なのは、レンズの表面を物理的に動かさなくても、電気信号ひとつで自在にピント調整ができる点です。
これまでのようにモーターや機械的な仕掛けを使わないため、故障が少なく、消費する電力も非常に小さいことが期待されています。
とはいえ、これまでの液晶レンズにも大きな課題がありました。
従来の液晶レンズは、小さく、厚みがあり、実際にメガネとして使うには視野(はっきり見える範囲)も狭かったのです。
そのため、実用的なメガネとして日常的に使うには難しいという問題が指摘されていました。
今回の研究チームは、こうした従来の液晶レンズの弱点を克服するために、レンズを薄く、大きく、そして実用的な焦点調整ができるような設計を目指しました。
その結果、直径約10mm程度の範囲内でピント調節が可能な試作レンズを作ることに成功しました。
また新たな液晶レンズは従来のような分厚いガラス基板(0.3 mm)を用いた場合と比較して、動作に必要な電圧を約15分の1に大きく減らすことができました(40 Vrmsで約8.1πの位相変化を達成)。
次に研究チームは、この試作レンズを実際にメガネフレームに組み込み、日常的に使えるかどうか性能をテストしました。
メガネフレームには小型の電池と電子回路が組み込まれていて、ボタンを押すとレンズに電圧がかかり、液晶の分子の向きを変えてピントを切り替えます。
この実験の結果、ボタンを押してから焦点が切り替わるまでの時間は約5秒ほどでした。
切り替わった後、約10mmの作動範囲内では遠くも近くもはっきり見えることが確認できました。
従来の遠近両用レンズでは、視線を動かして見る位置を変えなければならないため、これは大きなメリットです。
もちろん、現段階ではまだ課題も残っています。
現在の試作レンズは焦点を切り替えられる範囲が約10mm程度と狭いため、今後さらに実用的にするには、レンズの作動範囲を広げる必要があります。
また、ピントが合うまでの約5秒という時間も、実際に使う上ではもう少し短縮する必要があるでしょう。
研究チームはこれらの課題に取り組み、将来的にはレンズのサイズを大きくし、より広い視野を持ち、焦点調整の速度も速くした液晶レンズの開発を目指しています。
もしこれが実現すれば、他の競合する技術に比べても、より快適で実用的なメガネが誕生する可能性があります。
液晶レンズはメガネに革命を起こす

電気で自在に焦点を操れる液晶メガネは、私たちの視生活に大きな変化をもたらす可能性があります。
最大の利点は、メガネ使用者がこれまで感じていた不便を解消できる点です。
遠近両用メガネ利用者は、「手元を見るたびに顔を下げる」「遠くを見るときはレンズの上端から覗く」といった動作を無意識に行っています。
新技術により、こうした負担から解放され、自然な姿勢のまま視界の遠近をシームレスに切り替えられるでしょう。
また、老眼の進行や視力の変化に合わせてメガネの方が順応してくれるため、度数が合わなくなるたびにメガネを買い替える必要も減るかもしれません。
視力に不自由を抱える高齢者だけでなく、小さな子どもや障がいで意思疎通が難しい人にも恩恵があります。
自分で「よく見えない」と伝えられない場合でも、オートフォーカス機能付きのメガネが自動でピントを合わせてくれれば、適切な視力補正が可能になるからです。
さらに、この技術はメガネ以外の分野にも波及効果をもたらします。
たとえばバーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)のヘッドセットでは、映像表示の焦点距離を動的に変えることで目の負担を減らす研究が進んでいます。
液晶レンズは小型・薄型で電気制御が可能なため、こうした次世代のディスプレイデバイスにも応用が期待できます。
また、液晶を使うことでメガネに情報を表示させるといった新たな機能も考えられます。
とはいえ、実用化に向けて乗り越えるべき課題も残っています。
たとえば、レンズのさらなる大口径化(視野の拡大)や度数制御の高速化・高精度化は、引き続き研究開発が必要です。
ピント切替の速さについても、快適な使用感のためには重要なポイントです。
将来的に自動焦点検出センサーや目の動きの追跡と組み合わせて常時オートフォーカス化するには、より洗練された制御技術が求められます。
それでも液晶レンズを用いた遠近両用メガネは、メガネやレンズの歴史を書き換えるポテンシャルを秘めています。
もしオートフォーカスを備え、PCと連動した情報表示システムや通信システムと連動させることができれば、メガネは望遠鏡にも虫メガネにも、スマホにもなれる万能デバイスに進化するでしょう。
もしかしたら未来の人々は、今のメガネを見て「昔の人はオートフォーカスもない、ただのガラスやプラスチックだけで必死に板(スマホ)を覗き込んでいたんだなぁ」と感じるかもしれません。
元論文
Polarization-independent electronically tunable liquid-crystal spectacles
https://doi.org/10.1103/3m2d-k24l
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部