アメリカのコロンビア大学(Columbia University)で行われた研究によって、「ほぼどんなウイルスにも広く効く可能性をもつ新しいmRNA薬」の開発に大きな進展がありました。
研究ではウイルス感染に強い耐性を持つ人々の免疫の仕組みをヒントに、10種類の防御たんぱく質を一時的に体内で作らせることで、インフルエンザや新型コロナウイルス、さらには未知のウイルスにまで対応できる「広域抗ウイルス薬」の実現が目指されています。
実際のテストでは、mRNA薬の投与で細胞では複数のウイルスで増殖が抑えられ、動物では病状の悪化が抑えられるといった効果が示されています。
いったいどのようにして、この“ウイルスに強い体”を人工的につくり出す薬が生まれたのでしょうか?
研究内容の詳細は2024年8月13日に『Science Translational Medicine』にて発表されました。
目次
- なぜ「広く効く」ウイルス薬は難しいのか?
- 万能ウイルス防御を細胞と動物でテスト
- パンデミックに備える“体内防衛薬”
なぜ「広く効く」ウイルス薬は難しいのか?

私たち人間は、ウイルスに感染しないようにさまざまな工夫を重ねてきました。
インフルエンザや新型コロナ、エボラ出血熱などのウイルスはそれぞれ異なる「姿かたち」や「攻撃の方法」を持つため、ふつうは種類ごとに別々のワクチンや治療薬を開発する必要があります。
これは、たとえるなら「鍵の形が違うドアに、それぞれ専用の鍵を用意する」ようなものです。
一方で、細菌(バクテリア)に対しては抗生物質という「広く効く鍵」があります。
細菌の種類が異なっていても、同じ薬で一度に退治できることも多く、医療現場では大きな助けになっています。
しかしウイルスは細胞の中に入り込んで姿を隠してしまうため、このような“万能薬”はなかなか作れませんでした。
(※他にもウイルス自身は生命活動をしていないので細菌のように毒で殺すという手も使いにくくなっています)
抗生物質のようなオールラウンドな薬が効かない点こそが、ウイルスという相手のやっかいなところなのです。
そうした中で、世界にはごく少数ですが「めったに風邪やインフルエンザで重い症状が出ない」という不思議な体質の人たちがいることが、医学研究によって明らかになってきました。
この人たちは「ISG15(アイエスジー・フィフティーン)」という免疫に関わる重要な遺伝子を生まれつき持っていません。
本来この遺伝子は、ウイルスと戦うときに暴走しがちな免疫の働きにブレーキをかける役割を果たします。
たとえばウイルスが体に入ると免疫は一気にスイッチを入れて攻撃を始めますが、やりすぎると自分の細胞まで傷つけてしまいます。
ISG15は、こうした“やりすぎ”を防ぐためのブレーキのような存在です。
ところが、このISG15が欠けている人ではブレーキがうまく働かないため、免疫は常に「ゆるやかな戦闘モード」を続けています。
ふつうなら微弱な炎症が体に負担をかけそうですが、実際にはこの人たちはインフルエンザやはしか、水ぼうそうなど多くのウイルスにかかっても重い症状が出にくいという傾向を示します。
体の中で常に低レベルの“ウイルス警戒モード”が作動しているイメージです。
この珍しい現象にヒントを得た研究チームは、「もしこの体質の特徴的な部分だけを薬の力で一時的に再現できたら、ウイルスに対してより強い備えを持てるのではないか」と考えました。
つまり、遺伝子がないことによって生まれる特別な状態を、ふつうの人にも薬で短時間だけ再現できる方法がないか――それが今回の研究の出発点です。
たとえるなら、ウイルスがやってくる前に体の中に強力な“防御の結界”を短時間張っておくようなものです。
この新しい発想こそが研究の目的となりました。
万能ウイルス防御を細胞と動物でテスト

まず研究チームは、「ISG15」という遺伝子が欠けている人の細胞が、なぜ多くのウイルスに対して重い症状が出にくいのかというしくみを調べました。
ISG15が働かないと、体内で免疫の“警報装置”が小さく鳴り続ける状態が保たれ、ウイルスが侵入してもすぐに反応できる体勢が整うと考えられます。
このような警戒状態には「ISG」と呼ばれる遺伝子群が関係しており、それぞれが「防御たんぱく質」を作る設計図になっています。
実際、ISG15が失われると60種類を超えるISGが活性化しますが、研究者たちはその中でもウイルスの増殖を広く抑えられそうな10種類に絞り込みました。
これらはウイルスが細胞に入る前・増える途中・外に出ようとする段階などで働き、さまざまなタイミングでウイルスの活動を妨げると考えられています。
次に、これら10種類の防御たんぱく質を一斉に細胞内で作らせるため、研究チームはmRNA薬という最新の技術を活用しました。
mRNAは細胞に「このたんぱく質を作ってください」と命令を伝える分子で、新型コロナのワクチンにも使われています。
チームは10種類の遺伝子ごとにmRNAを合成し、それらをまとめて「脂質ナノ粒子(LNP)」というナノサイズのカプセルに封入しました。
こうして作られた「10-ISGカクテル」は、ウイルス退治の専門家チームへ一斉に出動命令を送るような仕組みです。
このmRNA薬を使った最初の実験では、ヒトの培養細胞に薬を導入し、ベシキュロウイルス(VSV)、インフルエンザウイルスA型、ジカウイルス、ウエストナイルウイルス、そして新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)などを感染させました。
10種類すべてを同時に作らせたときに最も強い効果が見られ、複数のウイルスの増殖が大きく抑えられました。
一方で、1種類ずつ使った場合には、たとえばMX1はVSVやインフルエンザに、IFI6はジカに部分的な効果を示しましたが、広い範囲には十分ではありませんでした。
つまり、10種類を組み合わせることで互いの力が補い合い、相乗効果が生まれたのです。
この戦略は複数の薬でウイルスの逃げ道をふさぐ「カクテル療法」に似た、遺伝子版の新しいアプローチと言えます。
副作用についても細胞実験の範囲で慎重に確認されました。
10-ISGカクテルを導入した細胞では、インターフェロンを直接加えたときのような強い炎症反応は見られず、細胞の生存率も通常と変わりませんでした。
つまり、余計な“警報”を鳴らさずに必要な防御だけを静かに働かせることができたのです。
この技術が生きた体でも通用するかを確かめるため、次にマウスとハムスターで動物実験が行われました。
まずマウスには致死量のインフルエンザウイルスA型を感染させ、感染の1日前に10-ISGカクテルを投与しました。
3日後には肺内のウイルス量が大きく低下しましたが、生存率の大幅な改善までは達成できませんでした。
今後は投与タイミングや量、遺伝子の組み合わせの改良でさらなる効果向上が期待されています。
ハムスターの実験では強毒株のSARS-CoV-2を用い、感染の1日前に同じmRNA薬を鼻から投与しました。
薬を受けたハムスターは体重の減少がほとんどなく、肺内ウイルス量も少なく、肺の組織ダメージも軽減されました。
この結果は、事前にmRNA薬を使うことで感染後の重症化を抑えられる可能性を示唆しています。
以上のように、10種類の防御遺伝子を一時的に働かせる方法は、ヒト細胞実験と動物実験の両方で多くのウイルスに効果を示し、広域防御戦略の第一歩となると期待されています。
パンデミックに備える“体内防衛薬”
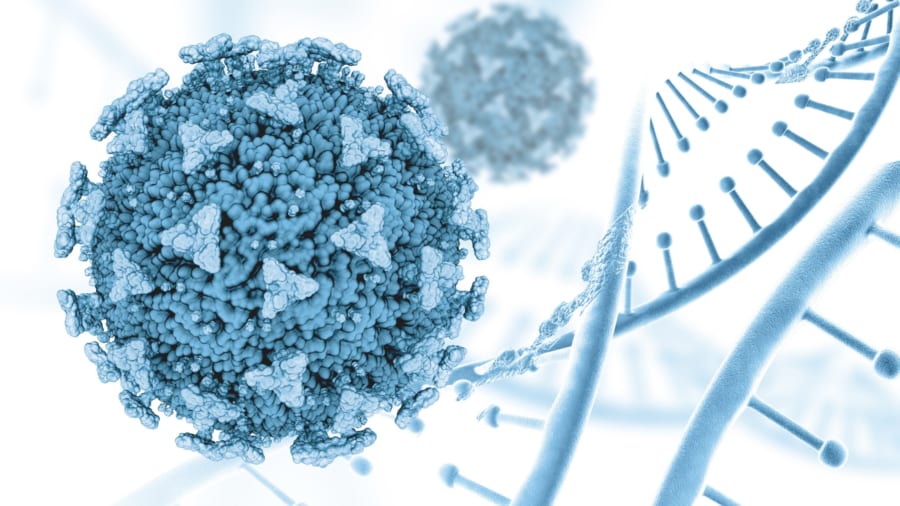
今回の研究で開発されたmRNA薬は、これまで困難とされてきた「広く効く抗ウイルス薬」の実現に向けた新しい可能性を示しています。
これまでの医療では、インフルエンザにはインフルエンザ薬、コロナにはコロナ治療薬というように、ウイルスの種類ごとに個別の薬を用意する必要がありました。
一方で、細菌に対しては抗生物質という“万能型の薬”が使えることが多く、医療の現場で長年活躍してきました。
しかし、ウイルスはその姿形も仕組みも多様で、共通して効く薬を作るのは難しいと考えられてきたのです。
そこで今回のmRNA薬は、ウイルスの種類を問わず働く可能性をもつ「防御たんぱく質」を10種類組み合わせ、それらを短時間だけ細胞の中で作らせるという仕組みをとっています。
これにより、ウイルスが体に入ってくる前に“防御の態勢”を整え、一時的にでも広い範囲のウイルスに備えることができるのです。
この方法は、今後登場する可能性のある未知のウイルスや変異ウイルスに対しても応用できる柔軟な基盤(プラットフォーム)となるかもしれません。
特に注目すべき点は、このアプローチが「自然免疫(生まれつき体に備わっている防御機能)」の仕組みからヒントを得ているところです。
たとえば、インターフェロン(体内でウイルス感染に反応して出る警報物質)をそのまま投与すると副作用が出やすいとされていますが、このmRNA薬では、必要な防御たんぱく質だけを短時間・少量作らせることで、副作用のリスクを抑える設計になっています。
実際、細胞を使った実験では、強い炎症のサインや細胞死といった悪い反応は見られませんでした。
つまり指標上、余計な反応を増やさずにウイルスの増殖を抑える挙動が示されました。さらに、mRNAという技術はカスタマイズしやすい特長を持っています。
この研究で使われた「10種類の遺伝子」はまるでパーツのように入れ替えが可能で、将来的には流行しているウイルスの種類や狙いたい臓器(肺や腸など)に合わせて中身を調整できる可能性があります。
つまり、ISGカクテル(防御たんぱく質のセット)をそのときの状況に応じて最適化することで、オーダーメイドのようなウイルス対策ができるかもしれないのです。
もっとも、この技術はいまのところまだ研究段階にあり、人に使うには多くの課題が残されています。
たとえば、この薬の効果がどれくらい長く続くのかや、どれくらいの頻度で投与すればよいのかは、今後さらに詳しい検証が必要です。
また、今回のマウス実験では肺のウイルス増殖は大きく減らせましたが、厳しい条件下では生存率の改善までは確認されていません。
こうした課題を乗り越えるためには、投与タイミングや量の調整、最小限の遺伝子組み合わせを見極める研究、そして体の中で薬を確実に届けるデリバリー技術の改良が必要になります。
研究チームもこうした技術面の進化に向けて今後の開発を進めていく予定です。
今回の成果は、「未知のウイルスにどう備えるか」という世界共通の課題に対し、新しい道筋を示したといえます。
もしこのmRNA薬が実用化されれば、ウイルスの流行が始まったばかりの段階で、ワクチンや特効薬ができるまでの“つなぎ”として人々を一時的に守る方法になるかもしれません。
実際の使い方については今後の臨床研究や追加データが必要ですが、「体の中に広域防衛チームを一時的に派遣する」という発想は、将来のパンデミック対策にとって非常に有望な手段になり得ます。
そして、この防御戦略の有効性と安全性が今後の研究によってより明確になっていくことが大きく期待されています。
元論文
An mRNA-based broad-spectrum antiviral inspired by ISG15 deficiency protects against viral infections in vitro and in vivo
https://doi.org/10.1126/scitranslmed.adx5758
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


