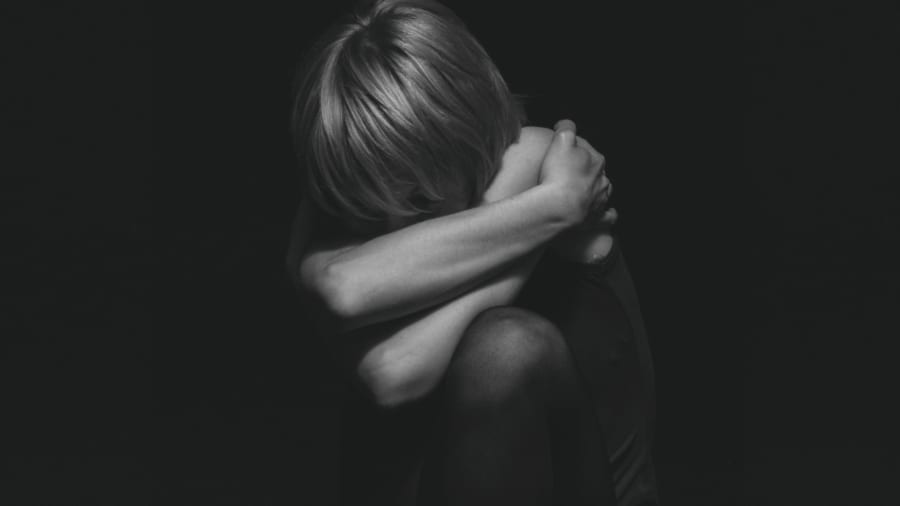「いちばん許しがたい相手は誰ですか?」——そんな問いに、多くの人が実は「自分自身」と心の中で答えるのかもしれません。
誰でも過去の失敗や後悔を抱えながら生きていますが、ときに私たちは、その出来事を何度も頭の中で再生し、自分を責め続け、なかなか前に進めなくなります。
では、なぜ「自分を許す」ことはこれほど難しいのでしょうか。
オーストラリアのフリンダース大学(Flinders University)で行われた研究によって、自己非難のループから抜け出せない人たちの心の内には4つの心理に関わる複雑なメカニズムがあることが明らかになりました。
“過去の自分”とどう向き合い、どうすれば「前を向いて歩き出す」ことができるのでしょうか。
研究内容の詳細は2025年6月3日に『Self and Identity』にて発表されました。
目次
- なぜ「自分を許す」のは難しい?
- 自分を許せた人と許せない人の4つの違い
- 自分責めからの回復に必要なこと
なぜ「自分を許す」のは難しい?
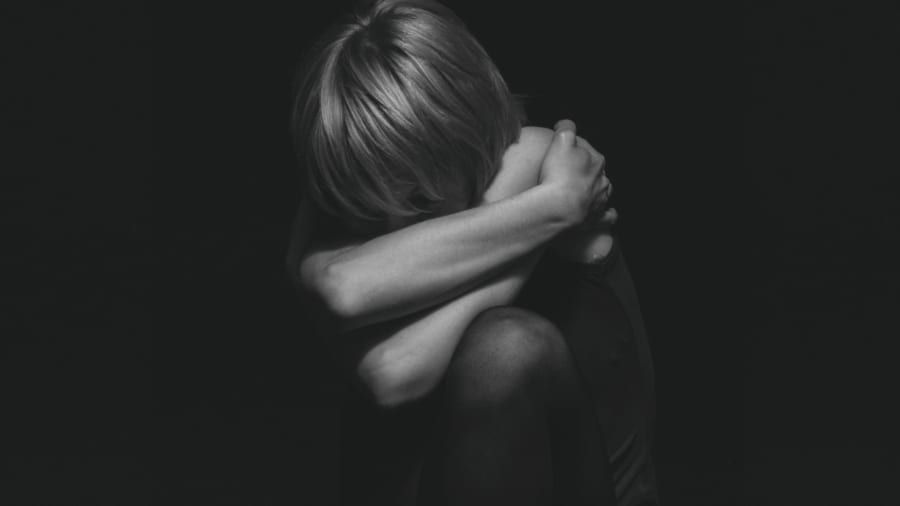
人生では誰でも失敗や過ちを犯します。
周囲から「自分を許して前に進むことが大事だ」とよく言われますが、それが頭で分かっていても、実際には自分を許せず何年も罪悪感や恥の念に苦しみ続ける人も少なくありません。
こうした罪悪感や自己非難の感情が長引くことは、先行研究でも心の健康に悪影響を及ぼし、うつ病や不安障害など様々な心の病の一因になると報告されています。
しかし、「なぜ自分だけは許せないのか?」という問いに対して、心理学はまだ完全な答えを出せていませんでした。
なぜなら、自己許しに関する従来の研究は、アンケート調査などの数量的(量的)な手法に偏っており、人々の内面にある複雑で揺れ動く心のプロセスを十分に捉えきれていなかったからです。
そこで今回、オーストラリア・フリンダース大学を中心とする研究チームはアプローチを変えました。
自分を許せずにいる人々と、自分を許すことができた人々、それぞれの生の体験談を自由記述で集め、質的手法であるテーマ分析(共通パターンを見つけ出す方法)を行い、「自分を許すことが難しい理由」を探ったのです。
自分を許せた人と許せない人の4つの違い

研究では、米国の一般成人80名(オンラインプラットフォームMTurk経由)に、自分自身を許せなかった経験または許せた経験について自由記述で語ってもらいました。
その中には、長年にわたり罪悪感にとらわれ「今も自分を許せていない」と語る人(41名)と、苦しみながらも最終的に「自分を許すことができた」と振り返る人(39名)が含まれていました。
研究チームはこの80件におよぶ体験談を詳細に読み込み、反射的テーマ分析(体験談の中から意味のあるパターンやテーマを抽出する質的分析手法)を行いました。
その結果、両者の心のあり方には、以下の4つの大きな違い(テーマ)が浮かび上がりました。
① 過去が現在のように感じられる:昨日のことのように生々しい
自分を許せない人たちは、過去の出来事をまるで現在進行形のように感じていました。
失敗から長い年月が経っても、その記憶が「昨日のことのように生々しい」と感じられ、頭の中で何度も反芻(同じことを繰り返し思い返すこと)してしまうと述べています。
ある参加者は、出来事から20年たっても「今もすぐそばで起きているように感じる」と語ったといいます。
後悔や罪悪感から抜け出せず、「前に進めない」と嘆く声もありました。
一方、自分を許せた人たちは、過去を「過去のもの」として受け止め、人生を支配されないように心理的距離を取っていました。
感情の激しさは時間とともに和らぎ、「過去は変えられない」と割り切ったうえで、「これから何を学び、どう生きるか」に意識を向けていたのです。
② 責任の捉え方:「もっと〇〇できたはず」
自分を許せない人の語りには、「本当は自分が悪いのでは」という自己非難と、「いや、自分だけのせいじゃない」という自己弁護の間を行き来する揺れが見られました。
これにより罪悪感が整理されず、長く残ってしまいます。
また「もっと〇〇できたはず」という強い後悔や、「結果を防げると知っていれば別の行動をとれた」という後知恵バイアス(出来事の後でなら結果が予測できたと思い込む傾向)に苦しむ人も多くいました。
特に親や保護者、先輩など守る立場にあった場合、「自分がもっと注意深ければ防げた」という過剰な責任感を抱き、深い自己嫌悪に陥ることが多かったのです。
一方、自分を許せた人は「責任は果たすが、当時の自分の限界も認める」という両立思考(矛盾する二つの考えを同時に受け入れる姿勢)ができていました。
「完璧にはできなかったが精一杯やった」「物事は思い通りにならないこともあると悟った」と語る人も多く、この受容が自己許しへの大きな一歩になっていました。
③ 理想と現実の自分とのギャップ:2度と〇〇する資格はない
自分を許せない人は、自分の行為が「本来あるべき自分」や「理想の自分」から大きく外れてしまったと感じていました。
道徳的アイデンティティ(=“良い人間”でありたいという自己像)が揺らぎ、「こんなことをする自分は善い人間ではないのでは」という深い恥や自己否定に陥ります。
中には「2度と〇〇する資格はない」と自ら罰することで、同じ過ちを防ごうとする人もいました。
例えば「ペットを死なせてしまった自分は、もう新しいペットを飼う資格がない。許せばまた同じことを繰り返すかもしれない」と考えるケースです。
長年やめられない悪習慣に悩み、「意志が弱くダメな人間だ」と自己嫌悪に陥る事例もありました。
一方、自分を許せた人は「過ちは犯すけれど、自分は大切な価値観を持っている」と不完全な自分を受け入れていました。
過去の自分も含めて自分だと認め、現在の自分と和解し、「本当に大事にしたい価値」に立ち戻っていました。
研究チームは、こうした価値の再確認(価値アファメーション)が道徳的アイデンティティを回復させると述べています。
ある参加者は「最良の親であるために自分を許し前を向こうと思った。娘のうつには様々な要因があり、自分だけが悪いわけではないと理解し直した」と語りました。
④ 感情対処の違い:押し殺そうとすると余計に頭から離れなくなる
自分を許せない人は、辛い感情に直面することを避け、「考えないようにする」「仕事やゲームで気を紛らわせる」といった回避的対処を取っていました。
一時的には楽になりますが、根本的な解決にはならず、罪悪感が残り続けます。
「押し殺そうとすると余計に頭から離れなくなる」と自覚する声や、「罪悪感に耐えられず危険な作業に没頭する」という自己罰的な例もありました。
一方、自分を許せた人は、辛い感情や過去の出来事に正面から向き合い、時間をかけて深く掘り下げる「ワーキング・スルー(working through)」を行っていました。
これは感情を押し殺さず、あえて再体験しながら、責任・価値観・自己像の矛盾を少しずつ統合していくプロセスです。
ある参加者は「何ヶ月も自分と向き合い、納得できたことで解放された」と振り返りました。
また、多くの人が信頼できる他者に打ち明け、対話を通じて客観的な視点を得たことで「自分だけが極悪人ではない」と気づく助けになったと述べています。
自分責めからの回復に必要なこと

以上の結果から、「自分を許せない」心理には過去への強い囚われ、過剰な責任感、理想の自分とのギャップ、そして感情を避けようとする対処癖が複雑に絡み合っていることがわかりました。
一方で「自分を許せた」人たちは、過去を受け入れつつ未来に目を向け、自分の責任は認めながらも限界も理解し、そして自分の大事な価値観に立ち返って行動することで前に進めていました。
あえて比喩で言えば、どうしても自分を許せず苦しんでいる人は、自分の心の車にブレーキ(罪悪感)をかけっぱなしにして止まってしまっている状態です。
論文は、こうした状態では過去の出来事が何度も頭に浮かび、行動の前進を妨げることを示唆しています。
ここから抜け出すには、ブレーキとアクセル、そしてハンドルをバランスよく使う必要があります。
具体的には、責任をきちんと認める(むやみに言い訳しない)と同時に、自分にも限界があったことを理解するという両立思考を持ち、さらに価値アファメーション(自分の大切な価値を再確認し、それに沿って行動すること)を行うことです。
これこそが「ワーキング・スルー(向き合って考え抜く)」のプロセスであり、痛みから逃げずにこの作業を続けることで、心のハンドル(価値観)が効き始め、少しずつ前進できるようになります。
時間はかかりますが、ブレーキを少しずつ緩めることが「自分を許す」ことにつながります。
今回の研究は、従来の量的データだけでは捉えにくかった「本人の語り」を用いた質的研究であり、自己許しの心理的プロセスをより立体的に示した点で意義があります。
特に、自己許しが単なる“一度きりの決断”ではなく、状況や心境の変化によって揺れ動きながら続くプロセスであることは重要です。
研究では、自分を許せた人であっても、罪悪感が再び顔を出すことがあると記されていますが、それでも価値観に沿って未来へ舵を切り直せることがわかりました。
また、「自己許しができる人とできない人が明確に二分されているわけではなく、多くの人にとって自己許しは継続的な揺らぎを伴う」とも示されています。
つまり、自己許しとは一瞬で完了するものではなく、試行錯誤を重ねながら少しずつ心を修復していく営みなのです。
では、この知見は私たちの日常や周囲の支援にどう役立つのでしょうか。
自分自身の場合、もし過去の失敗にとらわれて苦しんでいるなら、「時間が解決する」と放置せず、勇気を出して自分の感情や過去と向き合うことが大切です。
それは簡単ではありませんが、研究が示すように、それこそが前進するための有効なプロセスだからです。
同時に、「自分が完全に悪いわけではない」「人は誰しも限界や過ちがある」という自己への優しさや理解も忘れないでください。
この自己への共感と教訓の両方から学ぶ姿勢が、次の一歩への原動力になります。
周囲の人を支援する場合も、この研究はヒントを与えます。
研究チームは、自己嫌悪に苦しむ人を支えるとき、安易に「あなたは悪くない」と否定するのではなく、その人が抱える罪悪感や恥の背景を一緒に探り、現実的かつ適切な責任の捉え方を支援する重要性を示唆しています。
それによって本人は自分の中のモラルの傷(moral injury)を癒し、再び自分の価値観に沿った生き方(モラルの回復)を取り戻せる可能性が高まります。
言い換えれば、「自分を許す」ことは過ちをなかったことにするのではなく、本当に大切なものを見失わずに生きるためのプロセスなのです。
「自分を許すのが難しい理由」は、人間の心の複雑さを映す鏡でもあります。
しかし今回の研究は、その複雑さの中にも共通する心理的パターンや道筋があることを示しました。
たとえ心のブレーキを長く踏み続けてきたとしても、責任を認め、限界を理解し、価値観というハンドルを取り戻せば、少しずつでも前へ進めます。
自分を許すことは容易ではありませんが、過去から目を逸らさず向き合い、そこから学んだ教訓を胸に、自分の大切なものに向かって舵を切り直すことで、長い停滞から抜け出せるかもしれません。
今回の研究は、その希望のシナリオを裏付けています。
元論文
What makes self-forgiveness so difficult (for some)? Understanding the lived experience of those stuck in self-condemnation
https://doi.org/10.1080/15298868.2025.2513878
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部