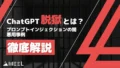私たちは健康のために「大人になってからの食生活」を意識しがちですが、実は人生最初の数年間に口にするものが、将来の健康の運命を大きく左右しているかもしれません。
香港科技大学(HKUST)や豪モナシュ大学(Monash University)らの最新研究から、幼少期の糖分制限が、将来の心疾患リスクを大幅に減少させることが明らかになりました。
「赤ちゃん時代の食卓」が、思った以上に“未来の心臓”を守っていたのです。
研究の詳細は2025年10月22日付で医学雑誌『The BMJ』に掲載されています。
目次
- 幼少期の糖分制限による健康効果
- なぜ「最初の1000日」が重要なのか?
幼少期の糖分制限による健康効果
第二次世界大戦後のイギリスでは、物資不足を背景に食品ごとに配給制度が敷かれていました。
砂糖も例外ではなく、1953年まで大人も子どもも、1日あたり40グラム以下に制限されていました。
2歳未満の乳児には、添加糖が一切与えられませんでした。
これは偶然にも、現代の食事ガイドラインが推奨する「幼少期の砂糖制限」とほぼ同じレベルの厳格なルールです。
今回の研究では、配給制度の終了(1953年9月)を「自然実験」として活用しました。
イギリス国内で1951年10月~1956年3月に生まれた約6万人を対象に、心疾患の発症率や発症年齢を追跡調査。
生まれた時期によって「母親の胎内~2歳頃まで砂糖制限を受けていたグループ」と「配給解除後に生まれ、制限を受けていないグループ」を比較しました。
結果、幼少期に砂糖制限があった人ほど、成人後の心疾患リスクが大幅に低下することが判明しました。
特に「胎内~2歳まで」制限を受けていたグループでは、心筋梗塞(心臓発作)や心不全、脳卒中、心房細動(不整脈)、心血管死亡といったリスクが20~30%も低くなっていました。
また、これらの疾患の発症時期も、最大で2年半ほど遅くなる傾向が見られたのです。
研究者らは、配給制度の影響を受けていない他国生まれの人々とも比較し、生活環境や遺伝的な要因、生活習慣なども調整した上でデータを解析しました。
その結果、幼少期の糖分制限と将来の心臓の健康との関連が、非常に高い信頼性で裏付けられました。
なぜ「最初の1000日」が重要なのか?
この研究が特に注目しているのは「人生最初の1000日」(受胎から約2歳まで)という期間です。
この時期は心臓や血管、代謝をコントロールする仕組みが作られる決定的なタイミングであり、摂取する栄養が体の“設計図”に大きく影響します。
現代の栄養学でも、この期間に過剰な糖分や超加工食品(多くの砂糖を含む)が加わることで、将来の生活習慣病リスクが高まることが示唆されています。
今回の研究は「国全体で強制的に砂糖が制限された」という特殊な状況を利用したことで、一般的な観察研究よりも「因果関係」に近い形で健康への影響を明らかにできた点が大きな特徴です。
もちろん、観察研究である以上「絶対的な因果関係」とまでは言えません。
しかし、心疾患リスクの低下だけでなく、発症年齢の遅延や心臓機能の向上といった“複数の健康指標”で一貫したメリットが見られたことは注目に値します。
研究チームは「大人になってからの食生活だけでなく、幼少期の政策的な食事管理が、社会全体の心臓の健康にとって非常に重要」と結論づけています。
参考文献
Early life sugar restriction linked to lasting heart benefits in adulthood
https://medicalxpress.com/news/2025-10-early-life-sugar-restriction-linked.html
元論文
Exposure to sugar rationing in first 1000 days after conception and long term cardiovascular outcomes: natural experiment study
https://doi.org/10.1136/bmj-2024-083890
ライター
千野 真吾: 生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。
編集者
ナゾロジー 編集部