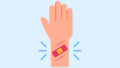仕事終わりに同僚から「今夜、一杯どう?」と声をかけられたとき、あなたはどんな気持ちになるでしょうか。
日本では職場の飲み会については「飲みニケーション」という言葉で仕事を円滑に進める交流のとして重要という意見がある一方、非常に気の重いイベントと捉える人も大勢います。
「飲みニケーション」は日本特有の文化という人もいますが、実際は海外でも同僚からの仕事終わりの食事の誘いや、休日のパーティーの誘いは気が重いという人が大勢いると言われています。
こうした職場の誘いが問題にされやすいのは、職場の飲み会が大嫌いという人いる一方で、これが好きな人や必要と感じる人も多くいるためです。
では、同じ“誘い”なのに、ある人には楽しみとなり、別の人には負担になるのはなぜでしょう。
米国・ジョージア大学(University of Georgia)のスー・ハン(ジョアナ)・リン(Szu-Han “Joanna” Lin)准教授らの研究チームは、この疑問について調査を行いました。
そして誘いが「自分を大切にしてくれた」と感じる感謝(gratitude)を生む場合と、「断れない」「気を使う」といったストレス(stress)につながる場合のどちらに傾くかを決める鍵は、対人自己効力感(interpersonal self-efficacy)――つまり「人づきあいにどれだけ自信があるか」という心理的要因にあることを明らかにしました。
この研究の詳細は、2025年10月付けで科学雑誌『Personnel Psychology』に掲載されています。
目次
- 心は有限の資源を消耗しているという考え方
- 職場の誘いが「嬉しい人」と「負担な人」の分かれ目
心は有限の資源を消耗しているという考え方
仕事のあとに同僚から「今夜どう?」と誘われたとき、うれしく感じる人もいれば、気を使って少し疲れる人もいます。
今回、ジョージア大学(University of Georgia)の研究チームが注目したのは、そうした誘いに「どう反応するか」ではなく、誘われた瞬間に心の中で何が起きるのかという点です。
これまでの研究では、飲み会やレクリエーションなど、実際に参加したあとの満足感や生産性への影響が中心でした。
しかしこの研究では、誘いを受けたその瞬間に生まれる小さな感情の変化が、後の行動や疲労感にまで影響するのではないかと考えたのです。
研究の土台となったのは、心理学の資源保存理論(Conservation of Resources Theory)という考え方です。
この理論では、人は日常生活の中で「資源」と呼ばれる心の余裕や時間、体力、他人からの承認などをやりくりしながら暮らしているとされます。
そして、これらの資源が増えると気持ちに余裕が生まれ、逆に減るとストレスや疲労を感じやすくなるという仕組みです。
同僚からの誘いは、この資源に対して二つの正反対の働きを持ちます。
「自分を気にかけてくれた」と感じるときには、安心感や感謝の気持ちが生まれ、協力的な行動を取りやすくなります。
一方で、「断りづらい」「場の空気を壊したくない」と感じると、心の余裕が削られ、ストレスや疲れがたまりやすくなります。
研究チームは、このように一つの誘いが“感謝の連鎖”にも“ストレスの連鎖”にもなり得ることを実証的に確かめようとしました。
調査は、米国と台湾の2つの国の職場でそれぞれ独立して行われました。
まずアメリカの社会人を対象に三つのオンライン実験を実施し、同僚から「映画に行かない?」と誘われた場面を想定させ、誘いを受けた直後に感じる感情(感謝やストレス)を測定しました。
台湾の企業における調査では、156組の同僚ペア(計312人)を対象に、数週間にわたる追跡調査を行いました。この調査では、自分の感じ方だけでなく、相手がどう受け止めていたかという評価も集め、誘いが人間関係に与える影響をより多面的に検証しました。
さらに、研究チームは「イベント日誌(event diary)」という心理学の手法も取り入れました。これは、ある出来事――この場合は同僚から誘いを受けたこと――が起きた当日に、そのときの気持ちや反応を記録してもらう方法です。
こうした複数の手法を組み合わせることで、研究チームは、職場での「誘い」というささいな出来事が、人の心理と行動にどのような影響を及ぼすかを調査したのです。
職場の誘いが「嬉しい人」と「負担な人」の分かれ目
同僚からの誘いは、一律に良い影響をもたらすわけではありません。
多くの人は「自分を気にかけてくれた」「仲間に入れてもらえた」と感じ、感謝が高まり、誘ってくれた同僚に向けた組織市民行動(organizational citizenship behavior:OCBI)が増える傾向が見られました。
一方で、「断りづらい」「自分の時間が減る」と感じる場合は、心理的資源が消耗し、感情的疲労が高まりやすくなりました。
その結果、その日や、翌日以降にかけて意欲の低下や離脱行動につながる傾向が確認されました。
つまり、誘われるという出来事そのものが、感謝を生む“資源の連鎖”にも、ストレスを生む“消耗の連鎖”にもなりうるのです。
明暗を分けたのは、対人自己効力感(interpersonal self-efficacy)、すなわち「人づきあいをうまくこなせる」という自信でした。
この自信が高い人は、誘いを「信頼のサイン」と捉えやすく、感謝や帰属意識が強まり、協力行動が自然に増えます。
一方で、この自信が低い人は、「うまく対応できるか不安」「場を盛り上げねばならない」と感じやすく、ストレスや疲労につながります。
つまりこの問題においては、その人の性格特性よりも、社交の場でうまくやれるという“自信”が鍵だったのです。
日本では、飲み会が親睦の場として定着してきましたが、近年は「気を使って疲れる」「断りづらい」と感じる人も増えています。
今回の結果は、こうした感覚の差が性格の違いだけではなく、心理的資源や自己効力感の差で説明できることを示します。
誘う側は、相手の状況や心の余裕を尊重し、「断っても関係が悪化しない」「自由に選べる」雰囲気づくりを意識することが大切です。
ただ、本研究はアメリカと台湾で実施されたため、文化的背景の影響をさらに検証する必要があります。
また、飲み会やバーベキューなど、活動の内容や頻度による違いも十分には解明されていません。
職場の誘いを“交流のチャンス”と感じるか、“負担”と感じるかは、あなたの社交への自信に左右されます。
同時に、誘う側の小さな配慮が、相手の心の資源を守り、チーム全体の余裕を生み出します。
「飲みニケーション」の成立には、互いの心に余裕を残せるかどうかにかかっているのです。
参考文献
Happy hour with co-workers can be a double-edged sword
Happy hour with co-workers can be a double-edged sword
https://news.uga.edu/happy-hour-with-co-workers/
元論文
Do You Want to Hang Out? Understanding the Positive and Negative Consequences of Receiving Social Activity Invitations at Work
https://doi.org/10.1111/peps.70009
ライター
相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。
編集者
ナゾロジー 編集部