圧倒的な証拠があるにもかかわらず、それを認めない頑固者があなたの近くにいるかもしれません。
地球温暖化はでっち上げだと信じている友人、明らかに非効率なやり方に固執する上司、健康に悪いと何度も伝えているのに生活習慣を変えようとしない家族がいるかもしれません。
では、そんな頑固な人たちをどうやって変えることができるのでしょうか。
この疑問に答えるのが、アメリカ・セントラルフロリダ大学(University of Central Florida)のボビー・ホフマン博士です。
博士は、私たちが一般的に使っている説得法が、脳の働きに反しているため、逆効果になることすらあると警告しています。
本記事では、「なぜ人は変わらないのか」「どうすれば変わるのか」という科学的なメカニズムを紹介していきます。
目次
- なぜ説得はうまくいかないのか?脳の2つのメカニズム
- 「失敗する説得」と「成功する説得」の違いは?
- 脳にやさしい4つの説得テクニック
- あなたも説得テクニックを上手に活用できる
なぜ説得はうまくいかないのか?脳の2つのメカニズム
まず最初に理解すべきなのは、説得がうまくいかない理由は、その人が愚かだからでも意地悪だからでもないということです。
問題はもっと根深く、人間の脳の仕組みに起因しています。
ホフマン博士が紹介する重要な神経メカニズムは、報酬予測誤差と情報の主観的価値という2つの概念です。

報酬予測誤差(Reward Prediction Error:RPE)とは、期待した結果と実際の結果のズレに対する脳の反応のことです。
期待より良い結果が起これば、脳はドーパミンを放出して「これは学ぶ価値がある」と判断します。
一方で、期待より悪い結果だとドーパミンの分泌は抑えられ、「これは避けるべきだ」と判断されます。
この反応は主に線条体や前頭前野といった脳の部位で起こり、学習や意思決定に関わっています。
つまり、意外なほど良い体験、すなわちポジティブな驚きが相手の脳に学習と行動変容を促すのです。

もう一つの重要な仕組みは、主観的な情報価値(Subjective Value of Information:SVOI)です。
これは、どれだけ正しい情報でも「自分と関係ない」と感じると、脳がその情報に価値を認識しなくなるというものです。
自分の目標やアイデンティティに合う情報であれば、脳はそれを高く評価します。
逆に、自分に無関係だと感じる情報は、脳にとって無意味なものとして処理されてしまいます。
SharotとGarrettの2016年の研究によれば、主観的価値が高い情報は脳の報酬系が強く反応することが明らかになっています。
つまり、ただ正しい情報を提示するだけでなく、それが相手にとって意味のあるものであることが重要なのです。
この2つの仕組みを理解することで、よくある論破や否定、恐怖喚起といった説得法が、なぜ逆効果になるのかがわかってきます。
「失敗する説得」と「成功する説得」の違いは?
ホフマン博士は、多くの広告や政治キャンペーン、医療メッセージが脅しや否定に依存していると指摘しています。
たとえば、「あいつに投票すれば生活が破滅する」といった政治広告や、「タバコを吸えばがんになる。財布も臭いも最悪だ」といった健康警告、「地球温暖化が進めば世界は滅びる」といった環境メッセージです。
これらは確かに事実かもしれませんが、脳の恐怖回避装置である扁桃体が作動し、学習や変化を拒絶する状態になってしまいます。
その結果、「怖いから聞きたくない」「うるさいから無視したい」と思わせてしまい、説得が失敗してしまうのです。
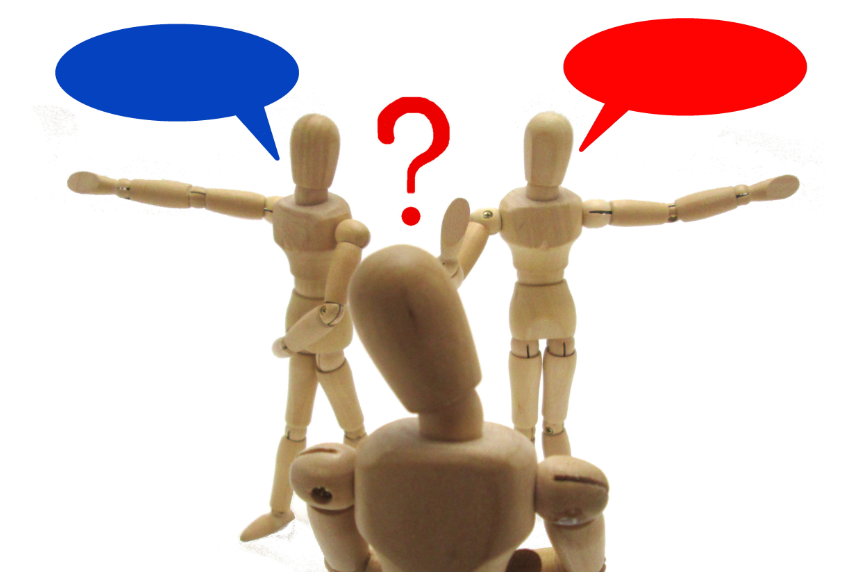
では、どうすれば脳が耳を傾けてくれるのでしょうか。
それは、ポジティブな未来を描くメッセージを使うことです。
たとえば、「禁煙した人の多くが食事がおいしくなり、肌ツヤが良くなり、家族関係も改善したと報告しています」といった健康メッセージがあります。
また、「再生可能エネルギーは新たな雇用を生み、健康被害を減らし、地域を豊かにします」といった環境の話や、「今から投資を始めれば、将来の自由と安心が手に入ります」といった金融の話もあります。
これらはすべて、得られる利益、つまりゲインにフォーカスしているのが特徴です。
脳は損を避けることよりも得をすることに強く反応する性質があり、予想を上回るポジティブな情報には、より多くのドーパミンが放出される傾向があります。
だからこそ、成功する説得は「恐怖の未来を防ぐ話」ではなく、「素敵な未来を実現する話」になるのです。
それらの要素を実際の場面で適用するための説得テクニックを見てみましょう。
脳にやさしい4つの説得テクニック
実際にどのようにして説得すればいいのかについて、ホフマン博士は脳の仕組みに沿った4つのアプローチを紹介しています。
まず1つ目は、ポジティブな驚きを与えることです。
質問やたとえ話を使って相手の常識に小さな穴を開け、「もっと知りたい」という状態を作りましょう。
たとえば、「朝20分の運動だけで集中力が1.5倍になるって知っていましたか?」といった問いかけです。
2つ目は、パーソナライズすることです。

一般論ではなく、相手の文脈に合わせて話すことが大切です。
たとえば、「みんな運動すべきなんです」と言うのではなく、「週末にもっとお子さんと遊びたいなら、平日の疲れを減らす方法がありますよ」と伝えることで、脳が「これは自分に関係ある」と判断します。
3つ目は、得られる利益を強調することです。
損失を避ける話よりも、具体的にどんな利益が得られるかを提示しましょう。
たとえば、「このやり方だと、1週間で作業時間が1時間短縮できます」と言えば、ポジティブな未来がイメージしやすくなります。
4つ目は、自由を与える、つまり選ばせることです。
命令ではなく選択肢を提示することで、相手は自分の意思で決めたと感じ、反発が減ります。
たとえば、「この3つの方法のうち、どれが一番合いそうですか?」という形です。
では、これらの説得テクニックはどんな場面で活躍するでしょうか。
きっとあなたにも関係があります。
あなたも説得テクニックを上手に活用できる
前述の説得法は、さまざまな人間関係に応用することができます。
親子関係であれば、「勉強しなさい」ではなく「勉強を終わらせればゲームをもっと楽しめるよ」と言う方が効果的です。
職場では、「最近ミスが多いな」よりも「以前の成果は素晴らしかった。また最高のレベルに戻れると思うよ」と伝える方が良いでしょう。

医師であれば、患者に対して「このままでは糖尿病になります」と言うよりも、「多くの患者さんが生活を変えて、体が軽くなったと喜んでいます」と伝える方がやる気を引き出せます。
教育現場でも、「今のままだと単位が危ない」より「この方法ならもっと楽に理解できるよ」と話す方が前向きです。
恋人やパートナーとの会話でも、「あなたの考えはおかしい」ではなく「私はこういう考え方が好きなんだ。どう思う?」と聞く方が心を開いてもらえるでしょう。
頑固な人の心を変えるには、正しさよりも、快さや意味を届けることが大切です。
人の心は理屈ではなく、希望と共感で動きます。
脳の報酬システムに寄り添った説得を実践すれば、相手の態度だけでなく、自分自身のストレスも減らすことができるかもしれません。
「どうしても変わってほしい」と願うその人のために、今日から脳にやさしい説得を試してみてはいかがでしょうか。
参考文献
How to Change the Mind of the Most Stubborn Person You Know
https://www.psychologytoday.com/us/blog/motivate/202507/how-to-change-the-mind-of-the-most-stubborn-person-you-know
ライター
矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。
編集者
ナゾロジー 編集部


