電気の流れは普通、電子という粒子が線路のような導線を移動することで起こります。
しかしもし電子がほとんど動かず、「スピン」と呼ばれる性質だけがリレーのように次々と伝わって情報を運ぶとしたら――まるでSFのようだと思うでしょう。
オランダのデルフト工科大学(TU Delft)で行われた最新の研究によって、電子自身ではなく、そのスピンのみが情報を運ぶ『スピン流』を、巨大な磁石を使わず安定的に発生させチップを開発することに成功しました。
電子が動かずスピンのみが流れるこの新技術は、量子コンピュータや省エネデバイスなど未来の情報通信を支える可能性を秘めており、その画期的成果が科学界で注目を集めています。
研究内容の詳細は2025年6月24日に『Nature Communications』にて発表されました。
目次
- 電子を動かさず情報を伝える「スピントロニクス」とは?
- 電子が止まってスピンだけが動く――グラフェンが起こした量子革命
- グラフェンが開いた「スピン流革命」
電子を動かさず情報を伝える「スピントロニクス」とは?

スマートフォンを長時間使っていると、いつの間にか本体が熱くなってしまった──そんな経験は誰しもあるのではないでしょうか。
これは、電子回路の中を電子が移動するときに抵抗が生じ、電気エネルギーの一部が熱として逃げてしまうためです。
もし、このエネルギーのロスをなくすことができたら、もっと効率的で省エネルギーな電子機器が作れるはずです。
こうしたアイデアから登場したのが、近年話題の「スピントロニクス」という新技術分野です。
スピントロニクスは、「スピン」という電子が持つ不思議な性質を利用して情報を伝える技術です。
「スピン」とは電子自身が持つ磁石のようなもので、小さな方位磁石の針が上か下かというように、電子それぞれが決まった磁石の向きを持っています。
通常の電流は、電子が集団で一方向に移動することで電気信号を伝えますが、「スピン流」では、電子はほとんど動かずに、磁石の向き(スピン)の情報だけが電子から電子へと伝達されていきます。
身近な例で例えてると、電子が人間でスピンが人間の「お気持ち(ポジティブとネガディブ)」のようなものだとすれば、人間はそのままに「お気持ち」だけが人づてに伝達されていく状態と言えるでしょう。
結果として電流が流れることはありませんが、それでも情報だけが遠くまで届くのです。
これが、「純粋なスピン電流(スピン流)」と呼ばれるものです。
スピン流の大きな魅力は、熱として失われるエネルギーが極めて少ないことにあります。
電子そのものが動かないので、移動時の抵抗がほぼゼロとなり、発熱やエネルギーのロスを劇的に抑えることができるからです。
もしこれを実用化できれば、スマートフォンやパソコンは今よりずっと省エネで長持ちし、さらにスピンを使った超高速で省電力なメモリやプロセッサなど、未来的なデバイスの実現にもつながります。
また、スピン流は電子の持つ量子的な性質を利用するため、量子コンピュータの性能を飛躍的に高める新技術としても注目されているのです。
そのスピントロニクスの最有力候補として研究が進められてきたのが、グラフェンという炭素原子1個分の厚さしかない素材でした。
グラフェンは薄くて軽く、しかも電子の動きが速いため、スピンの情報を遠くまで運べる理想的な材料とされてきました。
ところが大きな問題がありました。
これまでグラフェンでスピン流を制御するには、大型の磁石を使って強い磁場を加えなければならなかったのです。
これではスマホや小型の電子チップに組み込むのはほとんど不可能でした。
そこで研究者たちは、磁石や磁場を外部から加えることなく、小さなチップの上でスピン流を安定して作り出す方法を探しました。
果たしてスピン流で情報伝達を行うチップのような夢の技術は実現できるのでしょうか?
電子が止まってスピンだけが動く――グラフェンが起こした量子革命
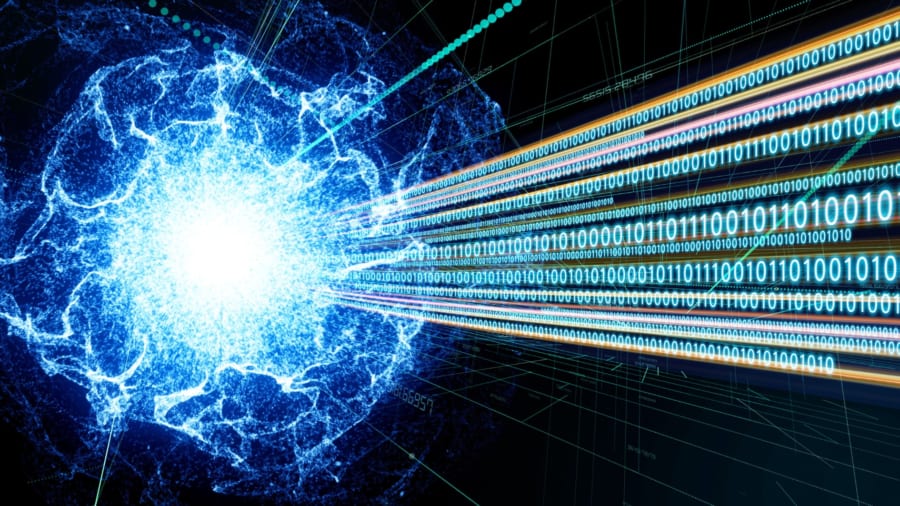
電子を動かさずスピン情報だけを流すチップは実現するのか?
答えを出すため研究者たちは、まずグラフェンのすぐ隣に特殊な磁性材料を重ねるというアイデアを試してみました。
用意されたのはCrPS₄(シーアールピーエスフォー)という特殊な結晶で、クロム、リン、硫黄の原子がミルフィーユのように何層にも積み重なってできています。
このCrPS₄は普通の磁石とは違って、ごく薄い原子層の中にだけ磁性を持つ、不思議な性質を持っています。
研究者たちは、この薄くて平らなCrPS₄の上に、原子一枚分の薄さしかないグラフェンを丁寧に重ね合わせて、小さなサンドイッチ構造を作りました。
この「原子サンドイッチ」には、特別な仕掛けがありました。
グラフェン自体は本来磁性を持っていませんが、CrPS₄と接することで、その磁気的な性質がグラフェンの中にしみ込むように伝わり、電子の性質が劇的に変わります。
具体的には、グラフェンの端に沿って特殊な電子状態が現れ、スピンが綺麗に並びながらも、電子自体はそれほど大きく動かないという奇妙な状態が作られます。
これは「量子スピンホール(QSH)効果」と呼ばれるもので、通常は強い外部磁場がなければ実現できない現象でした。
しかし、今回の実験では、この状態を大きな磁石を使わずに、CrPS₄の持つ磁性だけを活用して実現することに初めて成功しました。
さらに、この実験ではもう一つ興味深い現象が見られました。
「異常ホール効果(AH効果)」という、物質が持つ磁性の影響で電気が勝手に横に曲がって流れる不思議な現象も、同時に観測されたのです。
グラフェンはもともと磁石のような性質を持ちませんが、CrPS₄の影響を受けて磁性を持つようになり、この異常ホール効果が室温近くでもはっきりと観測されるほど顕著に現れました。
これにより、グラフェンが磁性を帯び、しかもQSH効果とAH効果という通常は同時に起こりにくい現象が共存するという、珍しい状況が初めて実証されたのです。
また研究チームは、この特殊な「スピン流」が持つ情報伝達能力についても詳しく調べました。
グラフェンを使ったデバイスの中を、このスピン情報がどれくらい安定して伝わるのかを検証したのです。
すると驚くべきことに、数十マイクロメートルという電子の世界では驚異的な距離まで、スピンの情報がまったく乱れることなく伝わりました。
数十マイクロメートルとは、人間の髪の毛1本とほぼ同じか、数本分の距離に相当します。
こんなに長い距離でも、磁石の向きをそろえたスピンの情報は途中で壊れることがありませんでした。
これは、トポロジカルという特殊な数学的な保護の仕組みによってスピン流が守られているためで、多少の欠陥や障害があっても影響を受けないことを意味します。
研究者たちは、この頑丈なスピン流を「欠陥や障害に対しても頑強なトポロジカルに保護されたスピン流」と表現しています。
今回の実験で特に注目すべきは、従来の研究のように巨大な磁石を使った大がかりな装置が不要で、極めて小さなチップの上で全ての結果を確認できたことです。
これは、スマートフォンやパソコンなど私たちの身近なデバイスに応用可能なスピントロニクス技術が、現実味を帯びてきたことを示しています。
では、この発見は具体的にどのような技術や製品に応用され、私たちの生活を変える可能性を秘めているのでしょうか?
グラフェンが開いた「スピン流革命」
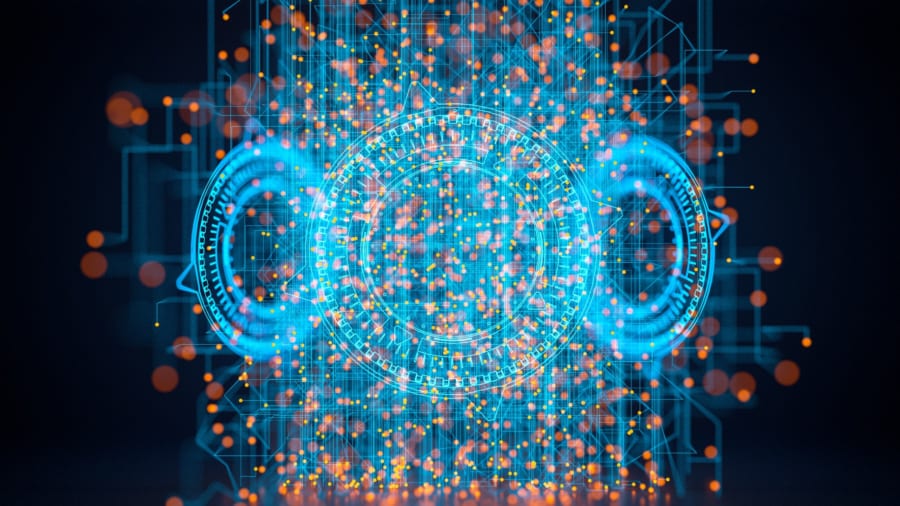
今回の研究によって、「巨大な磁石を使わず、グラフェンという極めて薄い材料の上で安定したスピン情報の流れを作ることが可能である」という画期的な可能性が示されました。
これは単に「磁石なし」でスピンを操れるという便利さだけではありません。
電子機器が抱えてきた発熱やエネルギーロスといった大きな問題を根本から変えてしまうほどの重要な発見なのです。
なぜそんなに重要なのか──それは、現代の電子機器が「熱」との戦いを続けているからです。
スマートフォンやパソコン、さらには巨大なデータセンターまで、電子が動くことで常に熱が生まれ、その熱を逃がすために膨大なエネルギーを使っています。
今回の研究が示したスピン流を使えば、電子そのものを動かさずに情報を伝えることができるため、熱として無駄に失われてしまうエネルギーを大幅に削減できる可能性があります。
その結果、スマホやノートPCは今よりもっと長時間使え、データセンターの電力消費も劇的に下がるかもしれません。
そして何より、現在の電子機器では実現できないほどの省エネルギー性能を持つデバイスが誕生することになるでしょう。
さらにスピン流の応用先として、研究者たちが最も注目している分野があります。
それが量子コンピュータです。
現在開発中の量子コンピュータは、電子や原子などの量子状態を情報処理に使っていますが、量子状態はちょっとした熱やノイズですぐに壊れてしまうという弱点があります。
そのため、離れた場所にある量子ビット(キュービット)同士を結びつける「信号線」が最大の課題となっています。
ここで活躍するのが、今回発見された「トポロジカルに保護されたスピン流」です。
このスピン流はトポロジーという数学的な性質のおかげで外部のノイズや乱れに非常に強く、多少の欠陥や障害があっても安定したままスピン情報を遠くまで届けられます。
そのため、このスピン流を使えば量子コンピュータ内部での情報伝達や、将来の分散型量子コンピュータ間の通信が劇的に改善される可能性があるのです。
さらに広い視野で見ると、今回の研究は「二次元材料」という、わずか原子一層から数層分しかない極薄の材料を組み合わせることで、これまで想像もしなかった新たな機能を引き出すという研究分野に大きな刺激を与えました。
今回はグラフェンとCrPS₄という二つの異なる材料を重ねることで、磁石がないのにスピン流を作るという驚くべき現象が生まれましたが、実はこのような「二次元材料のサンドイッチ」を工夫することで、他にもさまざまな量子現象や特異な物性が生まれることが知られています。
つまり今回の成果は、「材料を重ね合わせるだけで驚くような新しい現象を引き起こせる」という、非常に魅力的な可能性を改めて証明したことになります。
これから研究がさらに進めば、これまでSFの中にしかなかったような省エネデバイスや量子情報通信技術が現実になる日も遠くないかもしれません。
元論文
Quantum spin Hall effect in magnetic graphene
https://doi.org/10.1038/s41467-025-60377-1
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


