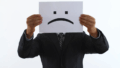スペインのバルセロナ大学(UB)を中心とした国際的な研究グループは、量子力学の世界で原子が壁をすり抜けるように移動する「量子トンネル効果」を使い、極低温の環境で動作する「量子電池」の新しい仕組みを理論的に提案しました。
この量子電池は、特殊なレーザー操作で原子を巧みに誘導することで、一旦フル充電の状態になればエネルギーが安定して保たれ、自然に漏れ出ないことが最大の特徴です。
もしこの新しいタイプの量子電池が実現すれば、量子コンピュータや量子センサーなどの次世代の量子技術デバイスに対して、効率よくエネルギーを供給できるようになるかもしれません。
量子トンネル効果を利用した「魔法の電池」は、私たちの未来にどんな可能性をもたらすのでしょうか?
研究内容の詳細は『Physical Review A』にて発表されました。
目次
- 量子電池の悩み“即時放電”に挑む
- 極低温量子電池は量子トンネル効果で充電できる
- 限界と次の一手:温度・接続・拡張
量子電池の悩み“即時放電”に挑む

私たちが普段使っているスマホやリモコンなどの電池は、基本的に化学反応によって電気エネルギーを生み出しています。
電池の内部では化学物質が反応し、その結果として電子(電気の粒)が移動することで電流が流れ、エネルギーが取り出される仕組みです。
これは古くから知られている仕組みで、現代の多くの電子機器に利用されています。
一方、近年研究されている「量子電池」は、従来の電池とはまったく異なる原理で動きます。
量子電池とは、目に見えないほど小さな世界――つまり「量子」の世界に特有な不思議なルール、「量子力学」を使ってエネルギーを蓄える新しいタイプの電池です。
具体的には、原子や電子といった極小の粒子が持つ量子的な性質(たとえば、粒子が複数の場所に同時に存在するような奇妙な状態)を利用して、エネルギーを蓄えたり取り出したりします。
そのため、量子電池は従来の化学電池では達成できないほど高速でエネルギーを充電したり、大量のエネルギーを素早く引き出したりすることが可能になると考えられています。
こうした期待から、世界中で量子電池の研究が盛んになっています。
実際に理論研究では、複数の粒子を協力させることで充電速度が大幅に上がったり、従来とは比べものにならないほどの大量のエネルギーを一瞬で放出できる可能性が指摘されています。
また最近では、超伝導回路や分子を使った量子電池の小規模な実験が行われ、その基本的なアイデアが徐々に実証され始めています。
しかし、量子電池の開発には乗り越えるべき大きな課題があります。
最大の問題は「エネルギーが勝手に抜けてしまう」ことです。
量子の世界では、電池を充電してエネルギーを蓄えた後でも、そのエネルギーが充電器と電池の間を行ったり来たり振動してしまうのです。
これを専門的には「即時放電」と呼び、せっかく充電したエネルギーが安定して保てないことを意味しています。
わかりやすく例えるなら、コップに水を満タンにしても、小さな穴が開いていて水が少しずつ漏れ出てしまうようなものです。
この現象を解決しないと、量子電池は実用化が難しくなります。
そこで、研究者たちは「エネルギーが漏れない安定な充電方法」を見つけるために、さまざまな工夫をしています。
例えば、電池の内部にある原子を「ダーク状態」と呼ばれる特別な状態にすると、エネルギーが外に漏れにくくなることが知られています。
他にも、「断熱的(アディアバティック)」な操作という方法があります。
これは、ゆっくり丁寧にエネルギーを注ぎ込むことで、エネルギーが他の場所へ逃げてしまうのを防ぐ方法です。
こうした方法は理論的に提案され、一部は超伝導回路を使った量子電池の実験でもすでに実証されています。
また、超低温の原子を使った実験装置でも同様の方法が実現可能だと考えられています。
このような背景のもとで、本研究は「どうすればエネルギーを完全に充電し、それを安定して長時間保てるか」という課題に正面から挑みました。
そのために研究グループが注目したのが「極低温原子」です。
極低温原子とは、原子をほぼ絶対零度(マイナス273.15℃)という極限まで冷やした特殊な原子のことです。
原子をここまで冷やすと、普段は見えない量子の性質が強く現れ、レーザー光で原子を自由自在に動かしたり、原子同士が互いに押し合ったり引き合ったりする力(相互作用)を精密に調整することが可能になります。
このような極低温の原子を利用すれば、従来の方法よりさらに安定で高性能な量子電池が作れるかもしれない――。
研究者たちは、この可能性を実現するための新しい充電法を探究しました。
極低温量子電池は量子トンネル効果で充電できる

それでは、研究グループが提案した「極低温量子電池」の仕組みを詳しく見ていきましょう。
この量子電池では「エネルギー井戸」と呼ばれるものが使われます。
「井戸」といっても、もちろん水が入っているわけではありません。
ここでいう井戸とは、原子が閉じ込められるような、エネルギーの「谷」や「くぼみ」のようなものをイメージしてください。
つまり、原子がこの「谷」に入ると安定し、外に出るためにはエネルギーを使って谷をよじ登る必要があるような構造です。
研究チームは、このエネルギー井戸をエネルギーの高さが異なるように三つ用意しました。
三つの井戸は階段のように並んでいて、一番下の井戸のエネルギーが最も低く、二番目、三番目と上に行くほど高くなっています。
最初に原子は最も低い一番下の井戸に閉じ込められており、これはエネルギーが空の状態、つまり「まだ充電されていない電池」を意味しています。
反対に、もし原子がエネルギーが最も高い一番上の井戸まで移動できたら、それはエネルギーが最大まで溜まった状態、「満充電」を意味します。
つまり、下の井戸から上の井戸に原子を移動させることが、この量子電池を充電するプロセスになるわけです。
しかし、ここで問題があります。
普通に考えれば、原子は自分が入った井戸の中に閉じ込められているため、井戸の外へ飛び出して別の井戸に移動することは簡単ではありません。
特に、一番上の井戸に移動するためには大きなエネルギーを与えて、井戸の「壁」を乗り越えなければならないのです。
ところが、量子の世界には、この常識を覆す驚くべき仕組みが存在しています。
それが「量子トンネル効果」と呼ばれる現象です。
量子トンネル効果とは、原子などの非常に小さい粒子が、普通なら絶対に通り抜けられないはずの壁を、まるで幽霊のように「すり抜ける」ことができる現象です。
これは直感に反する不思議な現象ですが、実際に原子や電子などの小さな粒子ではよく起こっている現象です。
今回の研究チームは、この量子トンネル効果を巧みに利用して、原子を下の井戸から上の井戸へ効率よく移動させる方法を考案しました。
また実際にこの方法がうまく機能するのかどうかを確かめるために、研究者はコンピュータによるシミュレーション(数値計算による模擬実験)を行いました。
その結果、レーザーの光を正しい順番と適切なタイミングで操作すれば、原子はほぼ完全に一番上の井戸まで移動し、最大限までエネルギーを蓄えることが確認されました。
さらに興味深いことに、原子が最終的に到達する一番上の井戸は、「最終固有状態」と呼ばれる特別な状態になっていました。
この「固有状態」とは、量子力学の用語で、簡単に言えば「一度入ったら、外からの影響がなければ自分からは変化しない安定な状態」のことです。
つまり、この一番上の井戸に到達した状態が安定な固有状態であるため、時間が経ってもエネルギーが勝手に失われたり、振動して逃げたりしにくくなるというわけです。
このことが、今回の研究における最大のポイントの一つです。
また、このシミュレーションでは、原子の数を増やした場合の状況も検証されました。
量子電池を作る際には、たった一つの原子だけでなく、多数の原子を同時に使って集団的に充電することで、より多くのエネルギーを蓄えることが期待されています。
今回の研究では原子の数を2個、3個、4個と増やして、その挙動を詳しく調べました。
その結果、原子同士が近くにいると互いに押し合ったり引き合ったりする「相互作用」が働き、興味深い現象が起こることが判明しました。
この相互作用の強さを調整すると、充電後に最終的に溜まるエネルギーが波のように増えたり減ったりするということです。
特に興味深かったのは、原子の数が奇数の場合と偶数の場合でエネルギーが振動するパターンに違いがあったことです。
これは原子の数によって最適な充電条件が変わることを意味しますが、実際にはレーザーの条件や相互作用の強さを調整すれば、奇数であっても偶数であっても満充電の安定状態に導けることが分かりました。
この発見は重要で、これまでの量子電池の研究が、単一の原子や粒子の相互作用が無い理想的な状況を主に想定していたのに対して、実際の多粒子系、つまり複数の原子が互いに相互作用をする現実的な条件下でも安定した充電が可能であることを示したからです。
つまり、今回の研究によって、現実的な環境に近い状況でもしっかりとエネルギーを蓄えられる新しい量子電池の可能性が初めて明確に示されたのです。
限界と次の一手:温度・接続・拡張
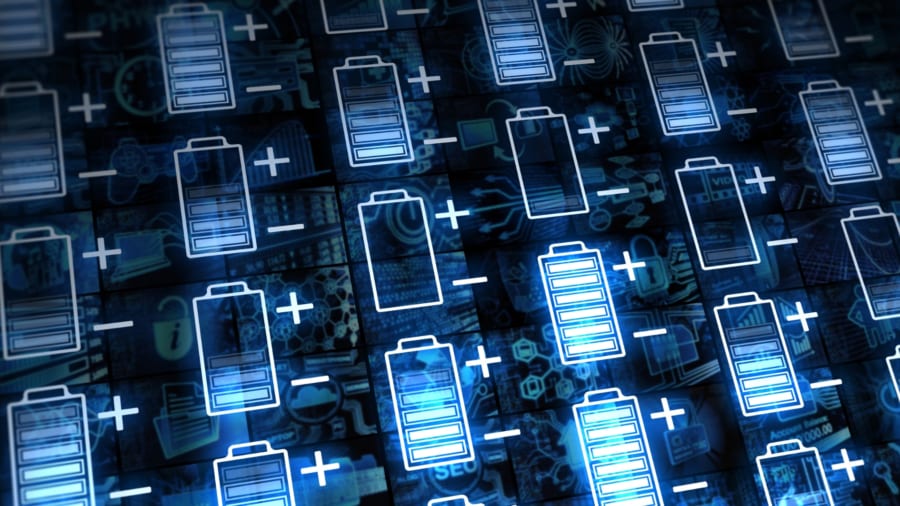
今回の研究で特に重要だったのは、量子電池が抱える「エネルギーを安定して保つ」という難しい課題に対して、まったく新しい解決方法が提案されたことです。
そもそも量子電池の大きな問題は、エネルギーを満タンまで充電したとしても、その後でエネルギーが安定せず、勝手に減ったり揺れたりしてしまうことでした。
これは先ほど説明したような「即時放電」と呼ばれる現象のためです。
電池にエネルギーをためても、時間が経つと充電器と電池の間でエネルギーが行ったり来たりしてしまうため、いつのまにか充電が減ってしまうのです。
これがある限り、量子電池を現実のテクノロジーに使うのは難しいと考えられていました。
ところが、今回の研究チームは、この問題に対して「量子トンネル効果」と「干渉現象」という量子力学特有の現象を活用し、まったく新しい視点から取り組みました。
具体的にどのように解決したかというと、満タンの充電状態を、量子力学の中で特別な「固有状態」に一致させることで解決しました。
「固有状態」というと難しく聞こえますが、シンプルに言えば「非常に安定で、自らは簡単に変化しない状態」のことです。
例えば、コップに水を入れたままテーブルの真ん中に置けば安定していますが、テーブルの端に置けばちょっとした刺激ですぐ落ちてしまうかもしれません。
今回の充電方法は、エネルギーを最も安定な場所(テーブルの真ん中)に置くようなものです。
つまり、この状態にたどり着ければ、エネルギーが勝手に減ったりする問題はほぼ解消されるのです。
さらに、この研究のすごいところは、従来の研究が単一の粒子や理想的な環境を想定していたのに対して、より現実的な多粒子系(複数の粒子が互いに影響し合う状態)でも、安定した充電ができることを明らかにした点です。
実際にシミュレーションでは、複数の原子が同時に存在して互いに押し合ったり引き合ったりする相互作用を考慮しました。
すると、この相互作用を調整することでエネルギーが安定して保てるようになり、粒子数が奇数か偶数かによって充電後のエネルギーの揺れ方に違いが出るという興味深い現象も発見されました。
これは、量子電池が単純な仕組みでないことを示していますが、同時に適切な条件を整えることで、複数の粒子を使った実際的な状況でも安定に充電できることを証明した点で、非常に大きな成果です。
元論文
Stable collective charging of ultracold-atom quantum batteries
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.032205
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部