アメリカのライス大学(Rice University)で行われた最新の理論研究によって、量子力学の不思議な性質である「量子もつれ(量子エンタングルメント)」を使うことで、分子の中でエネルギーが移動する速さを大きく加速できる可能性が示されました。
通常、エネルギーはひとつの決まったルートを通って運ばれると考えられていますが、研究では量子もつれ状態でエネルギーを最初から複数の場所に分散させて送り出すと、まるで複数の道路を同時に通るようにしてエネルギーが高速で目的地まで届けられることが示されました。
もしこの仕組みを応用できれば、人工光合成や次世代の太陽電池といった新しいエネルギー技術への応用にもつながると期待されています。
しかし、なぜ複数経路を同時にエネルギーが量子もつれ状態で通ると、エネルギーが加速するのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年10月1日に『PRX Quantum』にて発表されました。
目次
- 渋滞知らず?量子世界の不思議なエネルギーの運び方
- 複数の経路を同時に通る「量子エネルギー輸送」の不思議
- 量子もつれが開く未来のエネルギー技術への扉
渋滞知らず?量子世界の不思議なエネルギーの運び方

渋滞に巻き込まれたとき、「自分が二人いたら別々の道を同時に走れて、一番早いルートを見つけられるのに」と考えたことはありませんか?
もちろん、現実には私たちが分身することはできません。
しかし量子の世界では、エネルギーそのものが似たようなことを可能にするかもしれません。
普通の感覚では、エネルギーというのは一つのルートをまっすぐ進むイメージですが、量子の世界では「エネルギーの場所」がはっきりと一箇所に決まらず、ふわっと広がった雲のようになれることがあります。
この性質は「非局在化」と呼ばれ、量子の特徴のひとつです。
詰まっていた道から詰まっていない道へ経路を変えて最速で進んでいくというのは、一見すると道から道へのワープのようにも思えるでしょう。
このような量子的な仕組みを、自然界の生き物が実際に利用している可能性が最近の研究で指摘されるようになりました。
例えば植物は太陽の光を受け取り、それを効率的にエネルギーとして利用していますが、こうした生命活動の背後には量子の不思議な仕組みが隠れているかもしれないのです。
例えば植物は、太陽の光を受け取ってエネルギーに変える「光合成」を行いますが、そのときのエネルギー移動は非常に効率的です。
葉っぱの中にある葉緑体では、光を吸収したエネルギーが複雑な分子ネットワークを経て反応センターまでほとんどロスなく届くことが知られています。
この驚くべき効率の秘密を探る中で、科学者たちはもし植物がエネルギー輸送の効率化にこうした量子現象を利用しているなら、それはエネルギーが「非局在化」して複数の経路を同時に通ることができるという、先ほど説明した現象を自然が活用している可能性があります。
そこで研究チームは「量子効果が実際にエネルギー伝達を助けるのか」を確かめるために自然のヒントを踏まえつつ、温度や雑音の影響を含む量子モデル(理論的な仕組み)を設計して調べることにしました。
特に研究チームが注目したのは、植物が実際にやっているかもしれない方法、つまりエネルギーを最初から一つの場所に集中させるのではなく、非局在化、すなわち複数の場所に広げ送り出す方法を試すことです。
もしこの初期条件が有利なら、「自然界の高効率」という観察と、量子効果がエネルギーを加速するという発想が、理論の上で一本につながります。
複数の経路を同時に通る「量子エネルギー輸送」の不思議

複数の経路を同時に通る(非局在化する)と、エネルギー伝達速度が上がるのか?
謎を解明するため、研究チームはまずシンプルな理論モデルをコンピューター上で作りました。
これは、エネルギーを送り出す側と、エネルギーを受け取る側の二つの部分からなる分子モデルです。
送り出す側には複数の小さなサイト(エネルギーを運ぶ分子内のポイント)が存在します。
ここでエネルギーは、まるで飛び石を渡るように「ホップ」と呼ばれる量子的なジャンプを繰り返しながら、受け取る側へと移動します。
ホップできる距離が短ければエネルギーの移動確率は高くなり、距離が長くなるほどその確率は下がりますが、量子の世界ではその確率がゼロにはなりません。
つまり、ごくわずかな確率でもエネルギーが遠く離れた場所へ直接ジャンプする道も残されているのです。
次に、研究チームはこの理論モデルに「環境」の効果も取り入れました。
現実世界では、エネルギーを運ぶ分子は常に揺れ動いていて、その揺れの原因のひとつが温度による熱エネルギーです。
分子が熱で揺れると、エネルギーがスムーズに運ばれるのを妨げることがあるため、この影響を無視できません。
そこで、分子の揺れ(熱による振動)の影響も加え、現実に近い条件に近づけました。
ここで研究チームは、ある重要な比較を行いました。
一つは「エネルギーを一箇所だけに集中させて送り出す場合」。
もう一つは「エネルギーを最初から複数のサイトにふわっと広げて、量子もつれ状態で送り出す場合」です。
この二つを比べ、どちらの方法がより速くエネルギーを目的地に届けられるのかを調べました。
その結果、非常に興味深いことが分かりました。
エネルギーを複数の場所に広げて、量子もつれ状態から送り出したほうが、一箇所から集中させた場合よりも到達スピードが明確に速くなったのです。
なぜそうなるのでしょうか。
実は、エネルギーをもつれさせて送り出すことで、一つの経路だけでなくいくつもの経路を同時に使えるようになります。
普通の感覚では考えにくいですが、量子の世界では「使える道が増えるほど、目的地への移動が速くなる」という特別な仕組みが働いていたのです。
この結果について、研究チームのGuido Pagano氏は「エネルギーを最初から複数の場所に広げることで、1つの場所だけから出発した場合には実現できないスピードで、エネルギーを目的地に届けることが可能になる」と説明しています。
これは、まさに量子世界だからこそ可能になるエネルギー輸送の「隠れた秘密」の一つです。
では、どんな条件でこの「量子の速達便」は一番効果を発揮するのでしょうか。
研究チームの解析によると、エネルギー伝達が最も速くなるのは、量子的な結合の強さと環境による緩和の強さがちょうど釣り合ったときでした。
これは、ブランコを押すときに強すぎても弱すぎても上手く揺れないのと似ており、「臨界減衰」と呼ばれるちょうどよいバランスに近い状態です。
量子結合が強すぎてもエネルギーは行ったり来たりしてなかなか前に進まず、逆に環境の雑音が強すぎても効果が消えてしまいます。
つまり、この「絶妙なバランス」を見つけることがエネルギーの速達に重要だということが分かりました。
実際、自然界の光合成装置でもこのような条件が存在するのではないかと議論されています。
さらに驚くべきことに、量子もつれを使ったエネルギー移動は、熱や揺らぎといった環境変化にも強さを示しました。
多少温度が上がったりノイズが加わったりしても、エネルギーの伝わる「速さ」(平衡化スピード)は比較的安定していたのです。
これは、量子もつれによるエネルギー輸送の速度アップが単なる理論上の不思議現象ではなく、現実の環境でも働く可能性があることを示しています。
また、エネルギー移動の過程で、量子もつれ自体が失われずに受け渡されていたことも確認されました。
送り手側にあった量子もつれが、エネルギーとともに受け手側へとバトンのように渡されていたのです。
こうした結果は、量子効果が継続的に働いていること、そして設計次第で環境に左右されにくい仕組みをつくれる可能性を示しています。
量子もつれが開く未来のエネルギー技術への扉
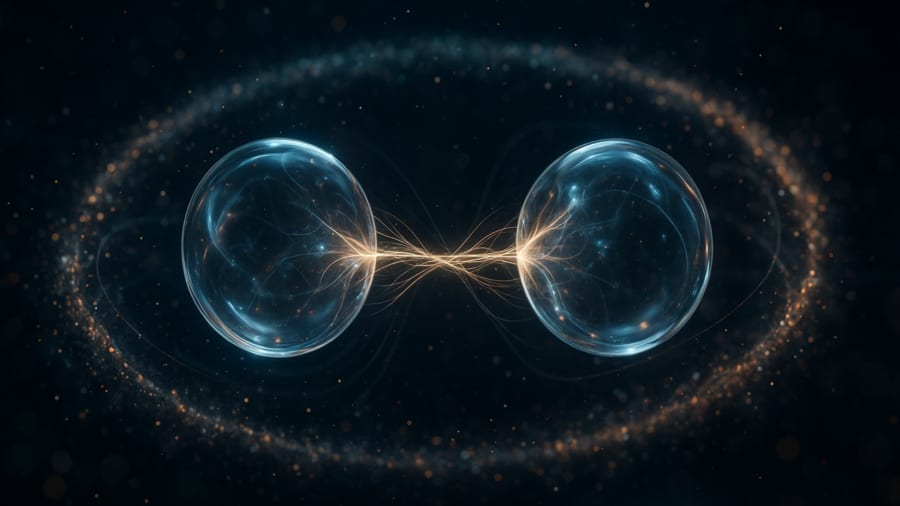
今回の研究成果が示した最も重要なポイントは、量子もつれという特別な量子効果が、エネルギー輸送を加速する可能性を理論的に示したことにあります。
具体的には、量子もつれの状態からスタートしたエネルギーは、従来の単一ルートに限定されたエネルギー輸送に比べて目的地までより効率よく届くことが、シミュレーションの中で示されました。
これはあくまで理論上のモデルでの結果ですが、自然界で実際に見られる非常に効率的なエネルギー輸送の謎に対する重要なヒントとなるかもしれません。
これまでも光合成では、エネルギーがロスなく運ばれることが知られていましたが、その背後に量子の力が働いているかもしれないという考え方は比較的新しいものです。
今回の発見は、この仮説をさらに強力に後押しする結果であり、今後の研究で、生物が本当に量子効果をうまく使いこなしているかどうかを調べるための手がかりとなるでしょう。
さらに重要なのは、今回の研究が示した量子効果が、人工的な技術開発にも生かせる可能性を持っているということです。
特に期待されているのが人工光合成や次世代型の太陽電池など、「太陽光からいかに効率よくエネルギーを取り出すか」を追求する技術への応用です。
現状の太陽電池はエネルギーを光から電気に変える効率に限界があり、科学者たちはその効率を高める新しい仕組みを常に探しています。
今回の研究で示された「量子もつれを利用した効率的なエネルギー輸送」の原理は、まさにそうした次世代のエネルギー技術にとって大きなヒントとなる可能性があります。
さらに幸いなことに、研究チームは実験によって検証できる方法を提案しています。
それが、トラップ型イオンを用いた量子シミュレーターと呼ばれる装置を使う方法です。
量子シミュレーターとは、実際の分子を使わずとも量子現象を再現できる特殊な実験装置のことで、今回の研究で提案されたモデルをリアルな環境に近い条件で再現することができます。
この実験が成功すれば、今回の理論が現実世界でも役に立つことが強く示されることになるでしょう。
また、これまで難しいと考えられていた常温の環境下でも、量子もつれが十分な役割を果たせる可能性を理論的に示したことは重要です。
これにより、生物が自然に進化の過程で量子効果を取り入れているかもしれないという考え方が、より説得力を持つようになります。
研究を主導したDiego Fallas Padilla氏も、「今回の研究は、量子コヒーレンスや量子もつれが、単なる理論的な好奇心ではなく、自然界の設計において重要な役割を担っている可能性を示す一歩となりました」と述べています。
私たちは今、長い間、自然が秘密にしてきたかもしれない量子の世界の一端を、ようやく垣間見始めたのかもしれません。
元論文
Delocalized Excitation Transfer in Open Quantum Systems with Long-Range Interactions
https://doi.org/10.1103/bxwl-sbsn
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


