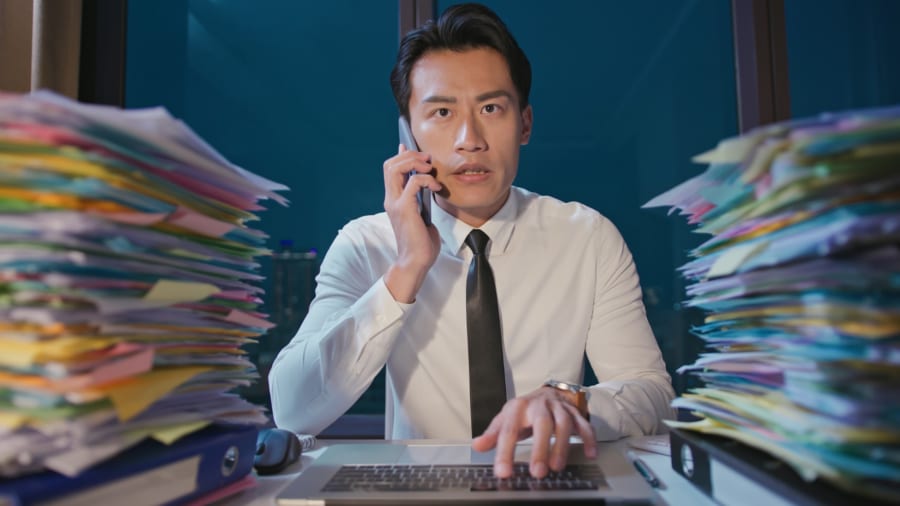中国の南開大学(NKU)と河南工業大学(HAUT)で行われた研究によって「週40時間以上働くと、子どもを持ちたいという意欲が大幅に減る」という結果が示されたのです。
夜勤やオンコール勤務、週末出勤などによって生活リズムが乱され、パートナーとの時間が奪われ、将来への不安を加速させる──そうした負の連鎖こそが、少子化に拍車をかけている原因の一つだと考えられます。
私たちの仕事中心の生活は、未来を切り開くための礎となるのでしょうか、それとも障害となるのでしょうか。
研究内容の詳細は『Biodemography and Social Biology』にて発表されました。
目次
- 時間の罠?子育てと長時間労働の不都合な真実
- 子どもを望む時間すら奪われる労働漬けの生活
- 仕事と家庭は両立できるのか――迫られる“人生”の選択
時間の罠?子育てと長時間労働の不都合な真実
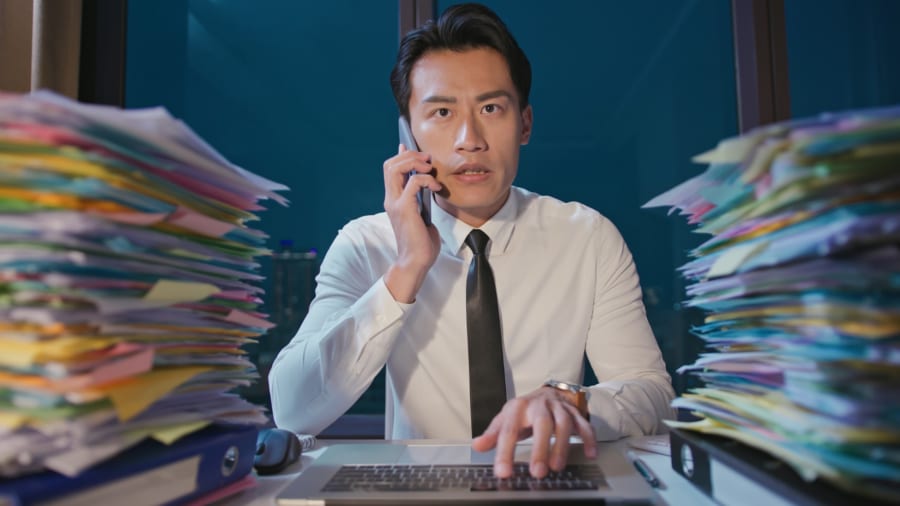
中国ではかつて“一人っ子政策”を長年にわたって維持していましたが、近年は二人、さらに三人の子どもまで認める施策へと大きく舵を切りました。
しかし、それでも出生率の下落は止まらず、人口構造の歪みや高齢化という問題が深刻化しています。多くの人は「住宅費や教育費が高すぎる」「子育て支援が不足している」といった経済的・制度的な要因をまず思い浮かべるかもしれませんが、最近とくに注目され始めているのが「時間的余裕の欠如」です。
長時間労働が家族形成の意欲を損ねているという指摘が、社会のさまざまな場所で聞かれるようになってきました。
たとえば中国都市部でしばしば耳にする「996」という働き方は、朝9時から夜9時まで働き、それを週6日続けるというもので、まるで終わりの見えないマラソンのようです。
日本でも長時間労働が深刻な問題として取り上げられていますが、中国の労働文化も相当ハードで、“余暇はおろか睡眠すら削るのが当たり前”とも揶揄されるほど。
こうした時間的プレッシャーは家庭生活に予想以上の負担をかけるという研究報告は、日本やアメリカ、ヨーロッパなど世界各地からも上がっています。
しかし、中国ほど地域差が大きく、かつ大規模に検証した例はこれまであまりありませんでした。
また、中国の若い世代からは「経済的には豊かになったけれど、心と時間の余裕がない」という声が聞こえます。
キャリアアップのために必死に働きつづけるうちに、いざ子どもを育てようと思ったときに果たして体力や精神的余裕が残るのだろうかという不安が膨らむ──これはある意味、“砂漠を歩き続けるような労働環境で、家族というオアシスを探す”かのようです。
こうした疑問を解き明かすために、中国全土を対象とした大規模調査のデータを用いて、長時間労働と子どもを持つ意欲の関係に切り込んだのが今回の研究です。
子どもを望む時間すら奪われる労働漬けの生活

研究チームは、中国家族追跡調査(CFPS)の2020年版データを活用し、約2万人のサンプルを分析対象としました。
CFPSは年齢・性別・年収・健康状態・家族構成といった多方面の情報を集めているため、「労働時間」と「子どもを持ちたい意欲」が他の要因とどのように関連するかを詳細に検証できます。
さらに、省や都市ごとの地域差も視野に入れながら、“週40時間超”の残業が出生意思に与える影響を調べました。
研究デザインのユニークなポイントは、単に「労働時間」だけでなく、夜勤・週末勤務・オンコール(24時間連絡が取れる状態)など働き方の違いを細かく分類したことです。
夜勤による生活リズムの崩れ、週末勤務で失われる家族との時間、オンコール勤務の精神的ストレス──これらがどの程度、子どもを持つ意欲を下げる要因になっているのかを一括して分析したのです。
すると、労働時間をより細かく区切り、週20時間未満の場合はむしろ出生意欲が高い傾向があることが示されました。
一方で週40時間を超えると明確にマイナス効果が強まり、とくに40〜50時間労働のグループで出生意欲が最も急激に低下していることがわかります。
60時間以上の過重労働では個人差がやや大きくなるものの、全体としてはやはりマイナスの効果が強いようです。
興味深いのは、夜勤・週末勤務・オンコールといった「いつでも仕事モード」に近い人々ほど子どもを持ちたいと思う割合がさらに少なくなる点です。
具体的には、週0~20時間の労働にとどまっている人々(パートタイムや特定のフレキシブル勤務など)では、およそ65%が「2年以内に子どもを持ちたい」と回答しています。一方、週20~40時間のいわゆるフルタイム基準内の労働をしている人では、約50%が同様に「子どもを持つ予定がある」と答えました。
しかし、週40~50時間になると出生意欲は32%まで大幅に低下し、週50~60時間の残業が多い層では25%へとさらに落ち込みます。研究チームによれば、40時間を超えた時点から精神的・体力的負担が急増し、パートナーとの時間や自己啓発に費やす余裕が一気に減ってしまうことが原因の一つとしています。さらに、週60時間以上の過重労働に及ぶ層では、回答者全体の平均こそ22%となっていますが、個人差が大きく、中には「家庭を持つ気力がほとんどない」と答えた事例も散見されたということです。
勤務形態の違いも顕著でした。夜勤や週末勤務、オンコール勤務の経験が「頻繁にある」と答えた人のうち、「2年以内に子どもを持ちたい」とする割合は20%前後とさらに低下します。逆に、フレックス制度の活用が可能な職場やリモートワークが普及している職場では、この数字が35~40%程度にまで回復していることも分かりました。
研究チームは「長時間労働や不規則勤務の多い環境ほど、出産や育児に対して慎重になる傾向が明らかになった。特に週40時間を超えると、心理的負担と時間不足が本格的に出生意欲を下げるようだ」と指摘しています。
さらに、女性の方が男性より残業に対して敏感に反応するという傾向も見られました。
中国でも「子育ては女性が担う」という社会的プレッシャーが根強いため、長時間労働が女性に及ぼす影響はより大きいと考えられます。
また、結婚していない人ほど「これから家族を持つかどうか」を決める段階で長時間労働を理由に躊躇する可能性が高くなる点も印象的でした。
動物においても、厳しい環境下でのストレスが出生率に深く影響を与えることは多くの研究で示されています。
たとえば、エサの不足や気候変動、捕食者の増加などによって動物が慢性的なストレスを感じると、生殖行動そのものが抑制される場合があります。
これは、体力を温存して生存を優先するためにホルモンバランスが変化し、交尾や繁殖に向かうエネルギーが減ってしまうからだと考えられています。
実際に、野生生物の生息環境が損なわれた地域や、家畜でも飼育条件が悪化した場合に、繁殖率が顕著に落ちる例が数多く報告されています。
こうした現象は、人間における長時間労働や不規則勤務が出生意欲を下げる仕組みにも通じる部分があり、「厳しい環境=生殖コストの回避」という生物学的な傾向が、種を問わず存在するといえるでしょう。
なぜこの研究が革新的といえるのか?
第一に、中国全土をカバーする大規模かつ多様なデータに基づき、労働時間だけでなく勤務形態の細分化まで踏み込んでいることが挙げられます。第二に、「20時間未満で出生意欲が上がり、40時間を超えると大幅に下がる」という具体的な労働時間の区切りまで示している点は、今後の少子化対策や働き方改革を考えるうえで大きなヒントとなるでしょう。これらの包括的かつ多角的なアプローチは、中国のみならず世界的な少子化対策にも影響を与える可能性があります。
仕事と家庭は両立できるのか――迫られる“人生”の選択

今回の研究結果は少し想像力を働かせれば、直感的にも理解化できます。
朝から晩まで仕事漬けの日々が続けば、帰宅後に「将来の家族像」を思い描く余裕など到底ないかもしれません。
夜勤のある人は昼夜逆転で心身のリズムが乱れ、週末勤務のある人は家族や友人と過ごす機会が極端に限られます。
オンコール勤務の人は、「いつ呼び出されるかわからない」緊張感の中で休まる暇がほとんどありません。
こうした状況では、「子どもができたらどうしよう」という漠然とした不安が「今はとても無理だ」という諦念につながっても不思議ではないでしょう。
さらに問題を深刻化させる要因として、女性が受ける負担の大きさが挙げられます。
中国でも依然として「子どもの世話や家事は女性が中心」という考え方が残っているため、妊娠・出産そのものに加えて育児・家事の責任を負うプレッシャーが大きいのです。
未婚者にとっては、これから家族計画を立てるかどうかを判断するタイミングであるだけに、長時間労働が負担に感じられれば「結婚や出産は後回しにしよう」と考えやすいのも自然な流れです。
一方で、フレックスタイムやリモートワークの導入など柔軟な働き方を認めている職場では、比較的高い出生意欲が維持されていました。
在宅勤務であれば家事を合間に済ませられますし、フレックス制度があれば通勤ラッシュを避けたり、子どもの送り迎え時間に合わせてスケジュールを調整したりと、生活の自由度が高まります。
こうしたささやかな工夫によって、“子どもを育てながら仕事も続けられる”という実感が得られれば、将来に対する不安はだいぶ軽減されるはずです。
もちろん、この研究は横断的なデータに基づいており、出産意欲が実際の出生率に直結するかどうか、あるいは今後どのように変化していくかについてはまだ不透明な部分もあります。
また、非公式な仕事やフリーランスでの労働がどの程度影響を与えているのか、十分には測定できていない可能性も考えられます。
しかし、大規模データによって「長時間労働が出生率の低下に関わる重要要因」として浮上したことは、大きな意義があります。
経済的支援や住宅政策だけでなく、残業を減らし、柔軟な勤務形態や十分な育児休暇を整えることも少子化対策として不可欠だと強調されたのです。
つい「将来の人口構成」や「社会保障費の増大」といった数字だけに目が行きがちですが、実際に子どもを育てるかどうかの判断は、身近な暮らしの中で感じる“時間のゆとり”や“精神的安定”といった要素に左右されがちです。
国や企業、自治体がそれぞれできることを真剣に考え、実行に移していくことで、「子どもが欲しい」と望む人の背中を押せる社会を作ることができるのではないでしょうか。
「仕事か家庭か」の二者択一ではなく、「仕事と家庭をどうバランスよく両立させるか」。こうした視点が、少子化を食い止めるカギになるのかもしれません。
元論文
Reasons for the continued decline in fertility intentions: explanations from overtime work
https://doi.org/10.1080/19485565.2024.2422850
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部