アメリカのカリフォルニア工科大学(Caltech)・ハーバード大学・Google Quantum AIの合同研究チームによって、観察という行為そのものに限界が生じ得ることを理論的に示しました。
研究では最新の量子コンピューターを用いても物事が進む時間や因果構造、さらには物質の状態(相)など、自然界の根本的な性質すらも十分に知ることが難しいことが示されています。
実際、ある種の問題については、最新の量子コンピューターでも天文学的な時間スケールが必要になり原理的に観測が不可能な「観測の壁」が立ちはだかります。
「観察すれば世界のすべてを理解できる」という私たちの直感は間違いなのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年10月9日に『arXiv』に投稿されました。
目次
- 「観察」そのものが世界を隠している
- 量子が人類に突きつけた観測の限界
- 私たちが見ている世界は幻想なのか?
「観察」そのものが世界を隠している

私たちが観察しているものは、世界そのものなのか、それとも観察という手続きが生み出した影なのでしょうか?
普通に暮らしていると、私たちはつい「世界は観察したとおりに見えている」と思いがちです。
たとえば顕微鏡を使えば、肉眼では見えない小さな微生物がはっきり見えます。
宇宙望遠鏡を使えば、遠くの銀河だって鮮やかに捉えられます。
人間の科学の進歩は、こうした「より詳しい観察」の積み重ねによって着実に進んできました。
言い換えれば、「観察の精度が上がれば、世界の秘密はどんどん解き明かされる」というのが科学の基本的な信念でもあったわけです。
ところが、この直感がまったく通じない世界があります。
それが「量子の世界」です。
量子とは、電子や光子(光を運ぶ粒)といったミクロな粒子のことを指します。
量子の世界では、物質はまるで気まぐれな猫のように振る舞い、観察する行為そのものが状態を変えてしまうことが知られています。
人間が量子の世界を観察しようとすると、観察自体が量子の状態に影響を与えてしまい、肝心の情報が乱れてしまうのです。
さらに困ったことに、量子の粒子たちは「量子もつれ」という奇妙なつながり方をしてお互いに影響し合っています。
量子もつれとは、離れた場所にある粒子同士が、まるで超能力でつながっているかのように、互いの結果が強く関連して表れる不思議な関係のことです。
これはちょうど、離れた場所にある二枚のトランプが、片方をめくった瞬間にもう片方の絵柄が対応して現れるような連動をしているイメージです。
この量子もつれが起こると、系全体の情報は瞬く間にシャッフルされ、手のつけられないほど複雑に絡まりあってしまいます。
物理学者たちは、このような超高速の情報のかき混ぜ現象を「スクランブリング」と呼びます。
情報が一瞬で混ざり合い、もとの意味や形がすぐに分からなくなってしまう現象です。
古典的な世界、つまり私たちが日常的に体感している世界では、情報はゆっくりしか変化しません。
水が流れる川のように、流れが穏やかで、ゆったりと状況を把握することができます。
しかし量子の世界では、この“シャッフル”が驚くほど速く起こるため、ほんの少し観察しただけで、さっきまで見えていた情報が学び取りにくくなることがあります。
私たちが目を向けるまさにその瞬間に、量子の世界はまるで「観察されるのを嫌がるかのように」、その姿を曖昧にしてしまうのです。
こうした難問に対して、近年注目されているのが「量子コンピューター」です。
量子コンピューターは、量子力学そのものを使って計算を行う装置で、古典的なコンピューターでは計算しきれない複雑な量子現象も解き明かせるのではないかと期待されています。
まさに「毒をもって毒を制す」、量子には量子で対抗するという発想です。
しかし、この期待にも思わぬ落とし穴がありました。
その落とし穴とは、量子の世界が、少ない手順や短い操作だけでもあっという間に見かけ上ランダムな状態に見えてしまう、という性質にあります。
トランプならば、通常はカードをよく混ぜるには何回もシャッフルが必要です。
ところが量子の世界では、ほんの短い時間のごく浅いシャッフルでも、すぐにカードの順番がバラバラになっているように観測者の目には見えてしまうのです。
しかし実際には、その乱れは見かけほど完全ではありません。
内部にはまだ以前の情報がかすかに残っており、真のランダムとは限らないのです。
けれども観測者からは、あたかも完全に混ざり切ったようにしか見えないため、そこに潜む構造を見抜くのは難しくなります。
雑なシャッフルでも一見するとカードが束の中でバラバラになっていると「思い込む」のと似ています。
しかし実際には雑なシャッフルでは束の中では前のゲームの手札の影響が残っており、真のランダムな状態ではありません。
子供の頃に下半分を上半分に被せるような雑なシャッフルをして、前と同じ手で上がってしまった経験がある人もいるでしょう。
このような雑な状態を最初に持ってきてしまえば、測定結果も雑になります。
このため現在の技術では、どんなに巧妙に「観察の網」を仕掛けても、その網目より細かい情報の粒はスルリと逃げてしまうかもしれません。
もしこれが本当なら、私たち人類には原理的に観察できない領域があり、物質の性質(相の違い)や、出来事の因果関係、さらには時間の経過のような根源的な性質さえ隠されている可能性があります。
しかしそんな「観察が届かない領域」という壁は、本当に存在するのでしょうか。
もし存在するとしたら、どんな条件で、どのくらい見えなくなってしまうのでしょうか。
まさにこの問題に対して、米カリフォルニア工科大学(Caltech)のトーマス・シュースター博士らの研究チームは、数学と理論の視点から真っ向勝負を挑みました。
量子が人類に突きつけた観測の限界

観察による世界の理解には、そもそも原理的な限界があるのではないか――。
この難問に挑むため、研究者たちはまず「量子コンピューターに未知の量子状態を与え、その状態がどんな『相(フェーズ)』に属しているかを見分ける」という理論的なシナリオを設定しました。
ここでいう「相(フェーズ)」とは、水と氷の違いのようなものを指します。
水は温度によって、固体の氷になったり、液体の水になったり、あるいは水蒸気として気体になったりします。
このような固体・液体・気体という区別を、物理学では「物質の相」と呼びます。
そして、水と氷の違いなら、センサーで硬さを測るという単純な方法でも見分けがつきます。
ある一定以上の硬さを検知すると氷と判断し、それ以外は水と判断する――そんな短い計算手順で済みます。
実際、単純な硬さをもとにした水と氷の違いを見分ける(観察する)計算アルゴリズムはほんの十数行で記述できてしまいます。
ところが、量子の世界では話が違います。
見た目では区別できないのに、内部の量子もつれ(粒子同士の深い結びつき)の仕方が異なるため、別の「相」に属する場合があるのです。
この違いを見分けるには、硬さを測るような簡単な方法では足りず、非常に複雑な計算を行う必要があります。
研究者たちは、このような量子的な相の違いを観測結果として出力するためのアルゴリズムの計算量(問題を解くために必要な処理の多さ)を解析しました。
こうした複雑な計算にこそ威力を発揮すると期待されていたのが、先に述べた「量子コンピューター」です。
理論上、量子コンピューターなら、このような難解な問題も現実的な時間で解けるかもしれない――そんな期待があったのです。
しかし、今回の研究で明らかになったのは、まったく逆の結果でした。
研究チームは、量子物質の相を判別するために必要な計算の量を数学的に解析したところ、ある限界点を超えると必要な計算量が急激に増大して解けなくなってしまうことがわかったのです。
(※具体的には、粒子同士がどれくらい影響し合うかの距離が、扱う問題の規模に応じて大きくなる場合、計算量もそれに伴って指数関数的に増えることがわかったのです。)
まるで、目的地ははっきりしているのに、どんなに性能のいい車に乗っても宇宙の果てまで永遠に到着できないような、そんな不思議な状況が起きてしまうのです。
さらにこのような計算が難しく、観察が困難になる領域は、特別な状況だけに限られないこともわかりました。
むしろ逆で、多くの量子状態に共通して現れる可能性が示されたのです。
さらに驚くべきことに、量子力学特有の不思議な状態だけではなく、「対称性がある量子相」(粒子の並び方やルールに整ったパターンがある状態)や、「古典的な相」(通常の物理学で扱えるような、量子特有の性質がない状態)でさえも、判別が難しくなる場合があるという結果になったのです。
つまり、理論上はきちんと定義できるはずの「相」であっても、現実の観測ではそれを確認できない場合があるということです。
このような観察の限界は、純粋な量子状態(理想的な状態)だけでなく、外部からの影響や雑音を含む混合状態(より現実的な状態)でも同様に起こります。
実際、私たちが日常で扱う多くの量子系は混合状態に近いため、これは理論だけでなく実際の観測にも深く関わる重要な示唆です。
シュースター博士らは論文の中で、「たとえ物質の相が理論的に明確に定義されていても、最悪の場合には、どれほど効率の良い量子コンピューターを使っても、その相を実際に観察して認識することが不可能になることがある」と述べました。
これは衝撃的な指摘です。
言い換えれば、「物質の相は理論上存在していても、私たちはそれを観測で確かめられない状況があるかもしれない」ということです。
まるで、本棚に並ぶ本が確かに存在しているのに、どれほど努力してもその本を開くことができないような、不思議で歯がゆい状況を思わせます。
この発見が伝える本質的な意味は、観察や計算によって学べることには根本的な限界があるという点です。
どんなに優れた観測装置や量子コンピューターを使っても、人間が手がかりを得られない領域が現実に存在する可能性が示されたのです。
シュースター博士らは研究の中でさらにこう述べています。
「我々の研究結果は、進化時間(その状態ができるまでにどれくらい時間がかかったか)や物質の相、因果構造といったいくつかの基本的な物理的特性は、従来の量子実験ではおそらく知ることが難しいことを示しています。これは、物理的観察そのものの本質について、深遠な疑問を提起します。」
この研究は、宇宙のいくつかの性質には、原理的に近づけない限界があり、それが私たちの完全な理解を妨げているのかもしれない、という新たな視点を提示しています。
観察の限界は、量子世界の奥深くに、私たちの想像を超える形で潜んでいたのです。
私たちが見ている世界は幻想なのか?
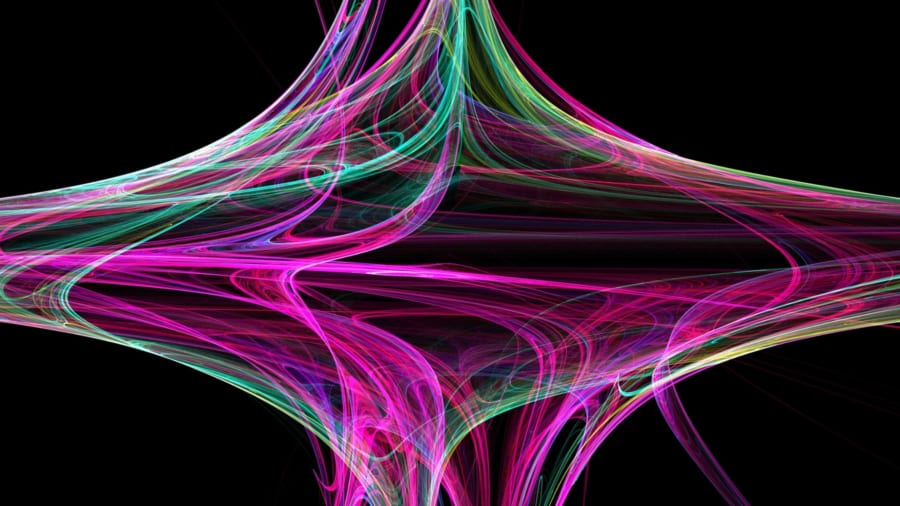
今回の研究は、私たちが普段あたりまえに持っている「観察すれば何でも理解できる」という直感に対して、大きな疑問符を突きつけました。
観察にはどうやら、乗り越えられない壁が存在するようだというのが、この研究から得られた重要なメッセージです。
私たちは科学を進める上で、観察や実験を何よりも信頼してきました。
その信頼の背景には、「自然が隠している情報も、観察技術が進歩すればいつかは明らかになる」という暗黙の期待がありました。
ところが、この研究が示したのは、たとえ最新鋭の装置を使い、究極の計算力を駆使しても、自然の持つ情報のすべてを取り出せるとは限らない、という驚くべき現実です。
これは単なる技術的な限界ではありません。
量子の世界では、情報が猛烈な勢いで混ざり合うため、どんなに鋭い「観察の目」を向けても、その情報は一瞬で散り散りになり、解析や学びが難しくなるのです。
では、このような「観察の限界」が存在するとしたら、私たちにどんな影響をもたらすのでしょうか。
まず一つは、量子コンピューターの研究にとって非常に重要な示唆です。
今回の成果は、「量子コンピューターさえあれば、あらゆる量子の謎が解けるだろう」という万能的な期待に対して、冷静な現実的視点を与えるものでした。
実際、物質の量子状態の相を判別するような一見単純な課題であっても、特定の条件下では量子コンピューターでも実用的に解けないほど複雑になる可能性があることを示しています。
このため量子計算の分野では、どのような課題が「絶対に効率よく解けない問題」なのかを明確にし、それを回避する戦略を立てることが今後の焦点となるでしょう。
さらに、この研究結果は哲学や基礎物理学にも深い示唆を与えます。
私たち人間が世界を観察し、理解し尽くすことが本当に可能なのか――という根源的な問いにまで踏み込むものだからです。
これはちょうど、特殊相対性理論が「光速という速度の限界」を示したように、本研究は「観察による理解の限界」を具体例を通して明らかにした理論的成果だと言えるでしょう。
原理的な壁がどこにあるのかを知ることは、科学の地図に「ここから先は未知の領域」という境界線を描くことに似ています。
私たちが日常で観察する現象の多くは、この壁に阻まれないでしょう。
それでも、人類の知の冒険において、この発見は忘れがたい意味を持っています。
もしかすると私たちが見ていると思っている世界は、観察という限られた現象が引き起こしたエコーのようなものなのかもしれません。
参考文献
A problem that takes quantum computers an unfathomable amount of time to solve
https://phys.org/news/2025-10-problem-quantum-unfathomable-amount.html
元論文
Hardness of recognizing phases of matter
https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08503
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


