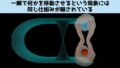私達にとって、とても身近な鳥「カラス」。世界中の神話にも数多く登場してきたほど、人類には古くから馴染みのある存在でした。
ご存知の通り、多くのカラスの体色は真っ黒で、どこに目があるのか分からないほどです。
そのことを示すように、カラスは漢字で「烏(カラス)」と書きますが、この字は「鳥(トリ)」から目に当たる横棒を一本抜いた形から来ています。
今回は、身近だけれど意外と知らない「カラスの生態」に迫ります。
目次
- カラスの基本的な生態
- 知能が高いことが分かる、カラスが見せる行動
- カラスの葬式とは?
カラスの基本的な生態

まず、カラスは鳥類の中で、スズメ目、カラス科に属しています。スズメ目は巨大なグループのため、ほとんどの鳥類がここに属しています。よって、スズメ目の鳥類を全て仲間と呼ぶのは、少々乱暴です。
では、カラスの仲間といえるカラス科には、どのような鳥がいるのでしょう?
カラス科鳥類は、南極を除きほぼ全世界に生息しており、世界に約100種類以上もいます。
日本で見られるカラス科ですと、約5種類程います。最もよく見られる2種類は、皆様よくご存知のハシブトガラスとハシボソガラスです。
カラスと言えば、よく見かけるこの2種の真っ黒な体色のイメージが強いのではないでしょうか?
しかし、一部真っ黒ではないカラス科鳥類もいます。例えば、九州を中心に全国で見られる「カササギ」の体色は、白と黒が混ざっています。オシャレなカラスもいるのですね。
食べ物は何を食べているのでしょうか? おそらく多くの方は「カラスはゴミを食い散らかす」というイメージがあるかと思います。
ほぼそのイメージ通り、動物性のものも植物性のものも、自然食でも加工食品でも、何でも食べる超雑食です。私達がゴミ袋にせっせとネットを被せるのも、カラスが都会で繁殖に成功しているのも納得ですね。
また、カラスは繁殖にあたり、パートナー関係は「一夫一妻制」をとっています。生涯同じパートナーと交尾をするため、毎年つがいを変えるオシドリよりもオシドリ夫婦なのです。
巣立ち後の若い成鳥は、しばらく両親にエサをねだり小さな家族による群れを形成します。「甘えん坊な子供」と「仲の良い両親」から成る群れだと思うと、微笑ましいものですね。
このように街中でもよく見かけるカラスですが、意外と死骸を見かけることは少ないのではないでしょうか? これは、カラスが「街中や低い場所ではなく、森林の高い木の上」への営巣を好むことが理由です。
カラスは、自分の身体が弱っていることを悟ると、その巣に籠もるようになります。
そのまま死んでしまうパターンが多いため、私達は死骸を見かけることが少ないのです。これは、多くの野生動物が、天敵に襲われないよう「他人に弱みは見せない」ポリシーを持っていることが分かる顕著な例です。
「家猫は、死期を悟ると飼い主の前から姿を消す」という話は有名かと思いますが、これもその本能に寄るものです。
そして、カラスはその巣をいつ頃作っているのでしょうか?
カラスは、秋頃になると集団で同じ「ねぐら」に帰るようになります。秋の夕日をバックに、カラスの群れが飛んでいたら、集団でねぐらに帰る所なのでしょう。
カラス達は、この群れの中で情報交換を行ったり、つがいを見つけたりします。やがて春頃になると、巣を作り始め、繁殖や子育てを始めます。
ところで、「ねぐら」と「巣」は別々に作られている別物であることに気づきましたでしょうか? 「ねぐら」は大勢で雑魚寝するための寝室のような場所であり、「巣」は夫婦で子育てをするための一軒家のような場所なのです。
知能が高いことが分かる、カラスが見せる行動

このようなカラスですが「知能が高い鳥」であることは、有名なところでしょう。
身体も鳥類の中では大型であること、雑食性であることも起因して、寿命も野鳥の中では比較的長めです。スズメやツバメが約2年、ハトが約6年であるのに対し、カラスは約8年ほどもあるのです。
知能だけでなく、カラスは視力も優れています。
カラスだけでなく、鳥類は全般的に視力が高い動物ですが、特にカラスや猛禽類は人の約5倍以上の視力を持っています。人が認識できる光の三原色「赤、青、緑」に加え、紫外線までも認識することができるのです。
皆さんは「虹は7色」と教わったのではないでしょうか?これは人間の常識であり、カラスの場合は14色も見えています。私達よりもカラスの方が、雨上がりの虹を見て「わぁキレイ!」と感動しているかもしれませんね。
一方、カラスの知能の高さを示す例としては、以下の事例が挙げられています。
①道具を使って、自分の生活を豊かにする
②生活に必須でない「遊ぶ」という行動をする
③自分に嫌がらせをしてきた人間の顔を記憶し、集団で復讐する
④他者に共感する
というものです。
①に関しては、街中でしばしば目撃例がある「硬いクルミの殻を割るために、車にクルミを轢かせる行動」「蛇口を捻って、水を飲む行動」が有名です。カラスは、周囲の状況をよく観察した上で、人間が使う道具の性能についても十分に理解しているのです。
②に関しては、「電線にぶら下がる行為」「滑り台で滑る行為」等が確認されています。共通点は「生活に必須な行為では無い」という点です。
人間や霊長類など一部の哺乳類も「遊び」という行為をしますが、これらの動物の共通点は「生きることに余裕がある」ということです。カラスも知能が高く、食べ物を取ることだけに必死になる必要がないのです。よって「無駄な行為で楽しむ余裕がある」ということなのです。
③に関しては、「石を投げる」「水をかける」「エアガンで追い払われる」という行為をされたカラス自身やその仲間たちが、「該当人物を襲いに帰ってくる」「その人物の家の窓ガラスを割ったり、所有物に糞をかける」という行為が確認されています。
人の顔を覚えられる記憶力も凄いですが、仲間のカラス達にそれを確実に伝えられる情報伝達能力も凄いのです。
④に関しては、「喧嘩に負けた仲間を慰める行為」が確認されています。
何羽かのカラスに、ある2羽のカラスの喧嘩を見せた実験があります。すると、負けた方のカラスに仲間が近づいていき、慰めるようにつついたり、毛づくろいをしてあげる行為が確認されました。
「動物に感情があること」は認められつつありますが、中々実証が難しい分野です。しかし、知能の高いカラスですから、「人間のように、感情も豊かなのではないか?」と考えられています。
カラスの葬式とは?

カラスの生態については、一部有名なものもあったかと思いますが、「仲間の死に対して、特別な行為を取ること」はあまり知られてはいないのではないでしょうか?
その1つは「ネクロフィリア(屍姦)」というものです。鳥類にはペニスが無いため、総排出腔をこすりつけて交尾を行います。なんと、カラスが仲間の死骸にその行為をする様子が確認されているのです。
「屍姦」と聞くと、「恐ろしくて、世にも珍しいもの」のように感じるのではないでしょうか?
確かに、人間の世界においては、珍しい異常性癖の一つとして知られています。しかし、ネクロフィリア自体はイルカ、リス、カエル、トカゲなどの他の動物においても確認されており、さほど珍しいものではありません。
特に、キース・ムーリカー氏がマガモのネクロフィリアについて発表した論文は、イグノーベル賞を受賞し、世界中で話題となりました。
ネクロフィリアの原因については「繁殖期におけるホルモンの異常で、いつもと違う感覚にとまどい、衝動が押されらなくなっていること」「仲間の死が認識できないこと」などが挙げられていますが、完全には解明されていません。
動物の嗜好を判明させることは難しいですが、ただの変態行為では無いことを祈ります。
また、カラスは仲間の死骸の周りに集まる行為、つまり葬式のように見える行為を行うことがあります。
まず、仲間の死骸を確認すると、その周囲に何羽も集まりだします。死骸を食べることはなく、弱くつつくような行為をすることもあります。
死骸には、猛禽類などの肉食動物や、清掃目的の人間が近寄ってくることがあります。しかし、そのような外敵を確認すると、周りにいたカラス達は甲高い鳴き声をあげて、外敵を追い払おうとする「モビング(擬攻撃)」と呼ばれる行為を盛んに行うのです。
カラスがこのような葬式を行う理由は「死骸の場所から、危険な環境を知るため」「寄ってきた者を確認し、危険な外敵を知るため」と考えられています。
つまり、「仲間の死から、有益な情報を得ようとしている」というのが有力な説です。
しかし、仲間に共感する知能があるカラスですから、仲間の死を悲しんでいる可能性もあるかもしれませんね。
ちなみに、仲間の死を悲しむような行動は、動物界においてはゾウ、霊長類など限られた動物でのみ確認されています。これらの動物は「死骸に近づき優しく接する」「外敵から死骸を守る」などの行動を見せるのです。
「動物の感情を測ること」はとても難しい課題とされています。しかし、もしかすると「私達人間のような、豊かな感情を持った動物がいること」が発表される未来も近いのかもしれません。
ヒトと共に暮らす賢い鳥

カラスは非常に身近な鳥であり、「知能が高いこと」は広く知られているかと思います。
しかし、人間のように「遊び」「他者への共感」まですることには、驚いた方も多いのではないでしょうか?
私達と共通点が多いと知ると、親近感が沸くものですね。
しかも、人の顔もバッチリ覚えられるカラスですから、近所で見かけるカラスは皆さんのことを「いつものあの人だ!」と認識しているかもしれません。
害鳥として扱われることも多いカラスですが、ぜひ愛着を持って接してあげて下さい。
参考文献
Do Crows Mourn Their Dead?, Aishwarya Ahuja
https://www.scienceabc.com/nature/animals/do-crows-mourn-their-dead.html
Crows Sometimes Have Sex With Their Dead, Ed Yong
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/07/crow-necrophilia/565442/
How a dead duck changed my life, Kees Moeliker
https://www.ted.com/talks/kees_moeliker_how_a_dead_duck_changed_my_life
元論文
Occurrence and variability of tactile interactions between wild American crows and dead conspecifics, Kaeli Swift
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2017.0259
ライター
山﨑 実香: 山﨑 実香(やまざき みか) 1991年 東京都 日野市生まれ。 東京大学 大学院 農学生命科学研究科 修士課程 修了後、大手学習塾が運営する科学実験教室の教室長などを務める。 その後、専門である生物学を中心に科学の解説記事を執筆するサイエンスライター、大学職員、フリースクール理科実験講師などとして活動。 歌うことが好きで、運動が苦手。 HP https://mikayamazaki.crayonsite.com/
編集者
ナゾロジー 編集部