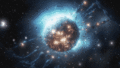「自分は政治に詳しい」と自信たっぷりにSNSの討論へ飛び込む人ほど、実はその場を険悪にし、感情的な対立を深める要因になるかもしれません。
中国の蘇州大学(SUDA)で行われた研究により、政治知識を過大評価する“誤った確信”がオンライン上の議論を過熱させ、互いの溝をさらに広げることが明らかにされました。
こうした「自分の思い込み」を軸にした過信や誤認は、私たちの暮らしや議論にどんな影響を与えているのでしょうか?
研究内容の詳細は『Communication Research』にて発表されました。
目次
- ダニング・クリーガー効果は「顔にレモン汁を塗る男」から始まった
- 1,200人調査で判明:過信する人ほど対立が深まるワケ
- まとめ:オンライン対立の止血策は謙虚さと事実確認
ダニング・クリーガー効果は「顔にレモン汁を塗る男」から始まった

私たちの認知の世界には、ちょっと不思議な“鏡”が潜んでいます。
それは「能力が低い人ほど自分を高く評価し、能力が高い人ほど逆に自信を持てない」という心理現象で、1999年にデイビッド・ダニングとジャスティン・クルーガーが実験を通じて証明しました。
これがいわゆる「Dunning-Kruger効果」です。
彼らが最初に注目したのは、「顔にレモン汁を塗れば監視カメラに映らない」と信じ込んで強盗に及んだある男性のニュースでした。
常識的にはあり得ない発想ですが、本人は“完璧な手口だ”と自信満々。結果は言うまでもなく、あっさり逮捕されてしまいました。
能力や知識の不足を自覚できない――まるでピンボケした鏡の前で「自分は映っていないから安全だ」と思い込んでいるような状態です。
政治の世界でもこの歪んだ“鏡”が問題になっています。
たとえば、「自分は政治に詳しい」と思い込む人ほど過激な意見をSNSに投稿したり、異なる見解を持つ人を頭ごなしに批判したりしがちです。
本来ならば、さまざまな立場の人と話すことは互いの理解を深めるはずでした。しかし現実には、ネット上の議論が罵り合いや人格攻撃に転じ、感情的な対立(アフェクティブ・ポラライゼーション)がますます深まる光景を目にします。
これは例えるなら、運転経験が浅いのに「自分は運転の天才だ」と思い込んでスピードを出しすぎ、ブレーキのタイミングもわからず事故を起こすようなもの。
過度な自信が招く“見誤り”は、他者への攻撃だけでなく、自らの評価を正しくできないという点でも危ういのです。
そしてこうした「自分の確信が間違っているかもしれない」という視点が欠落すると、政治以外の領域でも大きなリスクが生まれます。
こうして見えてくるのは、「自分が知らないことを知らない」という認知の限界が、社会の様々な場面で対立や誤認を引き起こしている可能性です。
民主主義の基本にあるはずの“多様な意見交換”が過熱した対立の火種になるのも、犯罪捜査が誤った疑いを生み人権侵害に繋がるのも、その背景には往々にして「過度な自信」や「知識の欠如」が隠れています。
そこで今回研究者たちは、「政治におけるDunning-Kruger効果がオンライン上での議論や対立構造にどのような影響を及ぼすのか」を検証することにしました。
1,200人調査で判明:過信する人ほど対立が深まるワケ

研究者たちはまず、韓国の一般市民約1,200名を対象にオンライン調査を行いました(最終的に第1波で1,175名が回答し、第2波でも948名が継続回答)。
この調査では、政治知識に関する10問程度のクイズを用意し、その正答率を“実際の知識レベル”とみなしました。
ところが、その平均正答率は約48%にとどまったのにもかかわらず、参加者のうちおよそ6割が「自分は平均以上に政治に詳しい」と回答していたのです。
クイズの成績が最下位25%に入る人でさえ、約4割が「自分は上位のほうだ」と思い込んでいたことが判明しました。
これは、服のサイズを測ってみたら実際にはMサイズなのに、「自分はLサイズを着るべきだ」と信じているようなものです。
次に研究者たちは、「SNS上で反対意見を持つ人(クロスカッティング・ディスカッションの相手)と、どれくらい頻繁にやり取りをしているか」を質問しました。
回答者のうち、約35%が「週に1回以上は別の政治的立場の人と意見を交わしている」と答えています。
本来なら、こうした交流は互いの視野を広げる機会になると期待したいところです。
しかし1か月後に行った追跡調査(第2波)のデータを分析してみると、“過度に自分の知識を高く見積もっている人”ほど、意見が食い違う相手に対して批判的な投稿や“嫌い”ボタンを押す行動が増える傾向が強く、結果として感情的な対立(アフェクティブ・ポラライゼーション)が深まってしまうことがわかりました。
具体的には、自分を過大評価している層では、クロスカッティング・ディスカッションに積極的に参加しているほど否定的な反応を示す割合が約1.5倍に高まるという統計的な関連が見られたのです。
いっぽう、実際のクイズで高得点を取りながら「もっと勉強が必要だ」と謙虚に考えている人たちの場合は、クロスカッティング・ディスカッションへの参加がむしろ対立感情を弱める方向に働く可能性が示唆されました。
こうした“謙虚な知識人”に分類されたグループでは、反対意見に直面しても否定的な反応を示す割合が他のグループよりも**およそ20%**低かったのです。
自分の理解不足を認める姿勢が、結果的には安全運転へとつながるイメージです。
最終的にこの調査から浮かび上がったのは、「実際の能力」よりも「自分の能力をどう認識しているか」がオンライン討論の雰囲気を左右する重要な要因になっているという点です。
過度な自信に基づく批判や攻撃が積み重なると、SNS上での議論は建設的な議論どころか、深刻な罵り合いや敵意の増幅につながりやすい。
そして、いったん感情的な溝が生まれてしまうと、時間が経つにつれ対立はますます根強くなってしまう――研究者たちは、そうした悪循環を断ち切る方法を模索することが、社会の分断を食い止めるカギではないかと指摘しています。
まとめ:オンライン対立の止血策は謙虚さと事実確認

今回の研究が示唆するのは、「議論を増やせば分断が解消される」という一般的な期待が、必ずしも現実には当てはまらない可能性があるという点です。
むしろ、自分の政治知識を過剰に信じ込んでいる人たちは、反対意見を聞けば聞くほど攻撃的な反応を示し、その結果、かえって感情的な対立を深めるリスクがあることがわかりました。
言い換えれば、“よかれと思って議論の場を広げても、参加者の認知バイアスによっては火に油を注ぐ”状況が起こり得るのです。
このような現象は、以前から社会心理学の分野で「確証バイアス」や「選択的接触」と呼ばれ、議論の最中に自分の信念を確認する情報ばかりを選択し、都合の悪い事実には耳をふさぐ傾向として報告されてきました。
今回の調査結果は、そうした傾向をさらに強める要因として「自分の知識を過大評価する心理」が大きく影響しているかもしれないことを示唆しています。
たとえば、一部の研究では、オンライン上で自信たっぷりに政治的意見を述べる人ほど、実は論拠が不十分な“似非ニュース”に踊らされやすい傾向があるというデータも出ています。
さらに興味深いのは、今回の調査において「自分はまだ勉強不足かもしれない」という謙虚さを持つ人が、異なる意見を受け入れる柔軟性を示した点です。
たとえば他の研究でも、「知的謙虚さ」の度合いが高い人ほどSNS上の政治的討論で相手の主張を一旦受け止め、補足情報を探す行動をとりやすいという結果が見られています。
こうした姿勢は、オンライン討論だけでなく、職場や学校など日常的な場面でも建設的なコミュニケーションを促進する要素となるでしょう。
ただし、この研究にはいくつかの限界も指摘されています。たとえば、参加者自身の自覚や記憶に依存するアンケート調査であるため、実際の書き込みやコメント履歴を全て確認したわけではないこと、そしてデータの収集地域や文化的背景が特定の国(今回の場合は韓国)に限られていることなどです。
国や文化が異なる環境では、同じようなパターンが見られるかどうかはまだ十分に検証されていません。
それでも、「オンライン討論がかえって感情的な対立を強める」メカニズムの一端が、こうした“過度な自信”によって引き起こされる可能性を具体的なデータで示した点は、非常に興味深いといえます。
今後は、たとえばSNSのインターフェースに“ファクトチェックを促す機能”や“意見を発信する前に自分の知識を再確認できる仕組み”を導入するなど、情報環境側の工夫も議論されるかもしれません。
あるいは学校教育やメディアリテラシーの観点から、自分の知識を客観視し、誤りを認める力を育むプログラムを充実させることが、社会的な分断を和らげる手段の一つとして期待されます。
政治的対立が激化しがちな今の時代だからこそ、自分の“知識の鏡”をときどき拭いてみる姿勢が、健全な議論と穏やかな共存への糸口になるのかもしれません。
元論文
How Political Overconfidence Fuels Affective Polarization in Cross-cutting Discussions
https://doi.org/10.1177/00936502241301174
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部