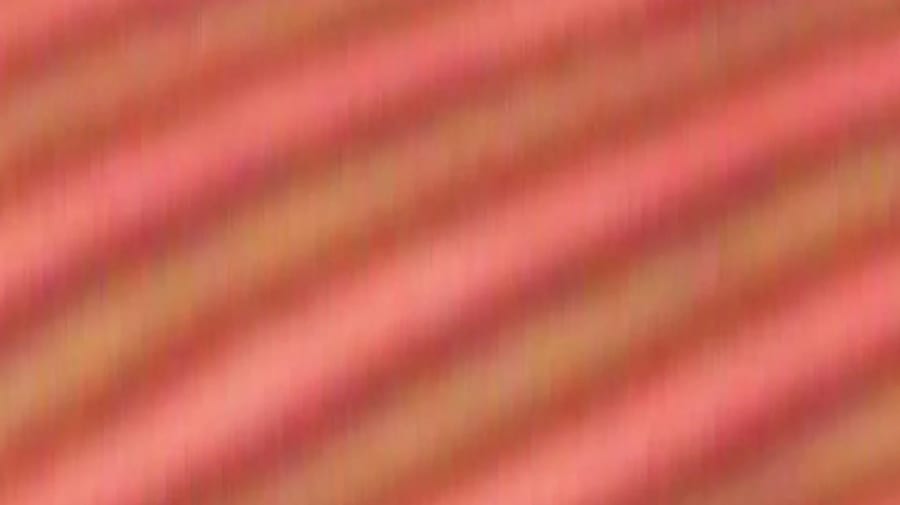空間ではなく「時間」に規則が生まれる不思議な結晶――「時間結晶」。
一見SFのようなこの物質状態を、アメリカのコロラド大学ボルダー校(CU Boulder)を中心とした研究チームが、ついに私たちの目で直接観察できる形で実現しました。
これまでの時間結晶は主に量子レベルの微小なスケールで確認されており、特殊な装置を使わなければ人間が直接見ることは困難でした。
しかし今回の研究では、スマートフォンやテレビ画面にも使われている液晶という身近な材料を使い、一定の強さの光を当てるだけで、周期的な刺激を加えなくても液晶内に「時間の格子」と呼ばれる規則的な模様が自発的に現れることが示されたのです。
目に見える時間結晶の誕生は、過去10年にわたり議論されてきた新概念の実証であり、偽造防止の「タイム透かし」や新しい光学素子など未来の応用への道も拓く成果です。
いったいなぜ液晶に光を当てるだけで時間に秩序が生まれるのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年9月4日に『Nature Materials』にて発表されました。
目次
- 時間にも結晶ができる?~新概念への挑戦~
- 時間の秩序が目で見える目で見る「時間結晶」
- 「時間結晶」の応用:時空間パターンで偽造防止
時間にも結晶ができる?~新概念への挑戦~
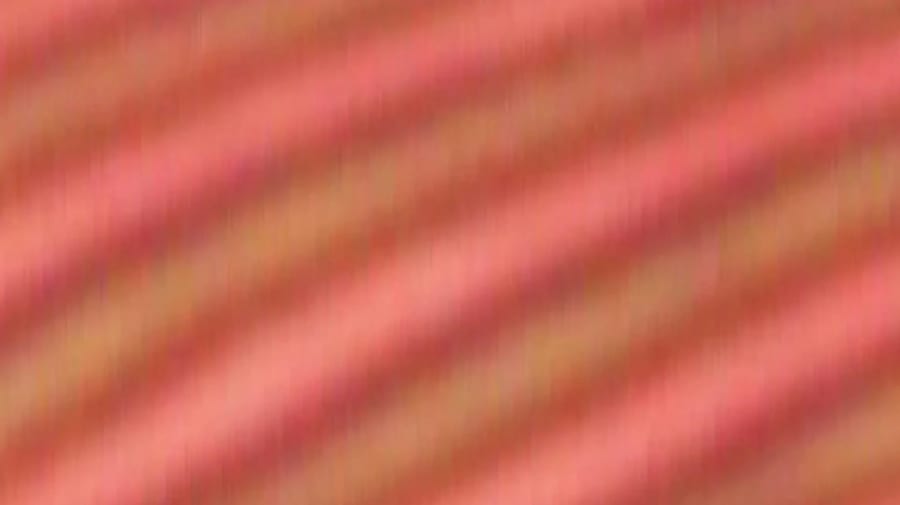
私たちが日常的に目にする「結晶」は、原子が決まった間隔で規則的に並んでいる構造のことを言います。
砂糖や塩、宝石のダイヤモンドなど、自然界には数多くの結晶が存在し、それらは全て「空間に規則的な模様(パターン)がある」ことが共通しています。
ところが2012年にノーベル物理学賞を受賞した物理学者のフランク・ウィルチェック博士は、この「結晶」という概念をまったく新しい方向へ広げました。
博士は「空間だけでなく、時間にも結晶のような規則性が現れる状態が作れるのではないか」と考え、「時間結晶」というまったく新しい概念を提唱しました。
(※博士が最初に考えた「永遠に周期運動が続く物質状態」というアイデアは、のちに理論的に実現不可能であることが示されています。そのため現在では、外から何かしらのエネルギーを与えることで周期的な運動を生じる「時間結晶」の研究が主流となっています。)
ここで重要になるのが、「時間の対称性」という考え方です。
私たちが普通に暮らしていると、時間の流れは一定のリズムで常に同じだと思えますよね。
ところが、ある条件で外部から一定のリズムの刺激を与えると、刺激された物質自身がまったく違う自分独自のリズムで動き始めることがあります。
これは、与えられたリズムとは異なる周期を物質自身が生み出し、「時間の対称性」が自発的に破れることを意味しています。
ただし、振り子時計のように外から周期的にエネルギーを加えて動かすものは、物質自体が生み出した周期ではないため、「本当の時間結晶」とは言えません。
最近では、こうした周期的な刺激(専門的には「周期駆動」と呼びます)がなくても自発的に周期運動が起きる、より理想的な「連続時間結晶」も観測されるようになりました。
しかし、これらの報告の多くは極めて小さな粒子を扱った量子系(ミクロな世界の物理現象)での研究であり、人間の目で直接観察できるスケールのものではありませんでした。
さらに、時間方向だけでなく空間の対称性も同時に破れる「時空結晶(じくうけっしょう)」という、さらに高度な現象も提唱されましたが、これまでは理論上のアイデアに留まり、実験的な実現は量子系でも古典的な系でも報告されていませんでした。
そこで本研究のチームは、私たちが日頃スマートフォンやテレビの画面で見慣れている「液晶」という非常に身近な材料を使って、この「連続的な時空結晶」の実現を目指しました。
具体的には、特別な周期的な刺激を与えなくても、「時間」と「空間」の両方に自発的に規則が生まれるような液晶の状態が実現できるかを探求しました。
もしこれが成功すれば、「時間結晶=量子の世界だけ」というこれまでのイメージを覆し、人間が肉眼でも確認できるようなスケールで「真の時間結晶」が実現したことを、はじめて証明できることになります。
時間の秩序が目で見える目で見る「時間結晶」
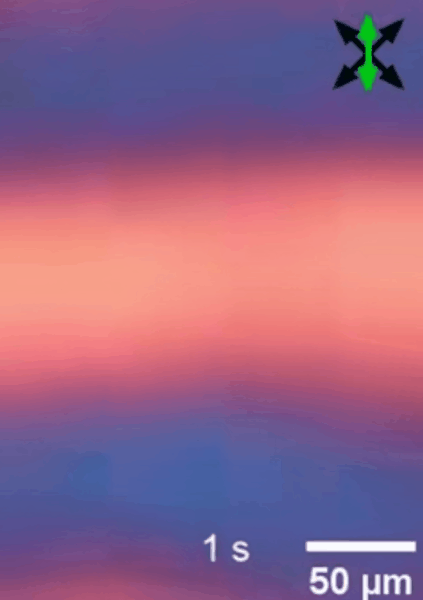
では、今回の研究チームが実際に行った「目で見える時間結晶」を作り出す方法を、順を追ってわかりやすく見ていきましょう。
時間結晶を人間が直接見える大きさにするには、肉眼で見える規模の材料を使う必要があります。
そこでチームは、まず液晶を使った小さな実験用のセル(薄い箱のような容器)を作りました。
液晶はスマートフォンやテレビのディスプレイに使われる身近な材料で、細長い分子が一定方向に並ぶことで知られています。
このセルの上下にあるガラス板の内側には、光を当てると向きが変化する性質をもつ特殊な色素(染料)が薄く塗ってあります。
この液晶セルに、一定の強さをもつ青い光(光の波の向きをそろえた偏光)を当てると、不思議なことが起こります。
まず、この青い光を浴びたガラス板表面の染料分子が光に反応して向きを変え始めます。
その染料分子が向きを変えると、近くにある液晶分子も、その染料の新しい向きに合わせて動き出します。
このとき、液晶分子は一斉に同じ向きにそろうのではなく、染料の向きに引っ張られるように少しずつねじれたり、ゆがんだりしながら並んでいきます。
すると液晶の内部には、この「ねじれ」や「ゆがみ」が繰り返し起こることで、小さな縞(しま)模様のような構造が自然に生まれてきます。
この小さな縞模様は、液晶分子が作り出す「トポロジカル・ソリトン」と呼ばれる安定した粒(ドメイン)が規則的に並んだもので、安定性が高く簡単には壊れません。
さらに興味深いのは、この縞模様が静止したままではなく、一定のリズムで明るくなったり暗くなったりと、まるで「液晶の中に時間の波が生まれた」かのように動き続ける点です。
つまり、外からは一定の光が当てられているだけで周期的な合図は与えられていないにもかかわらず、液晶自体が自分で作り出したリズムで振動し始めるのです。
この現象こそ、今回の研究で実現を目指した本物の「時間結晶」の特徴的なふるまいなのです。
研究チームは、この不思議な縞模様をより詳しく調べるために、偏光顕微鏡という特殊な顕微鏡で液晶セル内部の様子を動画撮影しました。
その結果、一定の条件で約4.6秒ごとに縞模様が変化することが確認されました。
さらに、この時間結晶は1平方ミリメートル以上という、人間の目でも確認できるほどの大きさで実現できました。
次に、研究チームはこの時間結晶の安定性をテストするため、さまざまな実験を行いました。
まず温度を変えてみたところ、縞模様のリズムは維持されながらも、そのリズムが温度によってゆっくりになったり速くなったりと、連続的に変化しました。
また、青い光の強さを変えても、一定の範囲内ならばリズムが崩れないことがわかりました。
さらに、光の強さにわずかな乱れ(ノイズ)を加えても、この時間結晶の周期的な秩序は崩れませんでした。
一時的に液晶内部の模様が少し乱れてしまうことはありましたが、時間が経つと自然に元の規則正しい模様へと自己修復されました。
これらの観察結果から、周期的な合図(例えば、一定周期での外部刺激)がなくても、この液晶の中に自律的で安定した「時間の秩序」が自然に現れていることが明確に示されました。
また、縞模様が外部の周期的刺激によらずに自発的に発生し、一定の基準を満たしたことから、これまで理論的に考えられていた「真の時間結晶」の有力な実験的証拠となったのです。
「時間結晶」の応用:時空間パターンで偽造防止
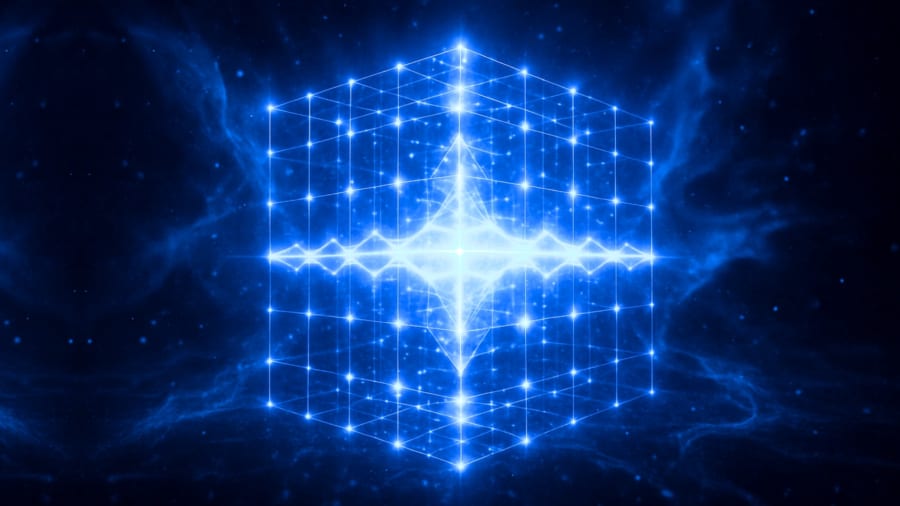
今回、実際に目で見えるサイズで実証された時間結晶は、ただ面白い現象というだけでなく、私たちの生活を豊かにする新技術につながる可能性を秘めています。
その中でも特に注目される応用の一つが、偽造防止技術です。
紙幣やパスポートのような大事な書類に、この時間結晶を利用した特殊な薄い液晶膜を組み込めば、普段は静止した普通の模様にしか見えませんが、特定の光を当てると模様が一定のリズムで変化を始めます。
まるで隠された「時間の透かし」のように模様が動き出すため、普通の透かしや印刷技術では真似できず、新しい偽造防止タグとして役立つと期待されます。
しかも液晶材料と非常に少ない色素だけで実現できるため、コストも低く抑えられる可能性があります。
また、時間結晶は情報の記録技術にも大きなインパクトを与えるかもしれません。
現在、私たちがスマートフォンなどで使っているバーコードやQRコードは、二次元の静止したパターンで情報を記録していますが、時間結晶を使えば、そこに「時間」という新しい次元を追加できます。
つまり、パターンが時間とともに変化する「2次元+時間」の三次元バーコードが可能になります。
同じ大きさのバーコードでも、パターンが動いて変化することで、格段に多くの情報を入れることができます。
研究チームの計算によれば、この方法なら1秒間に10万ビットを超える情報を理論上記録できる可能性があると見積もられており、これは動画のように変化するバーコードを作るイメージです。
さらに、このような時間変化を利用したバーコードは多少のノイズや誤差にも強く、情報伝送におけるエラーの発生を抑えることが期待されます。
液晶の時間結晶は、光を扱う技術にも新たな可能性を与えるでしょう。
例えば、現在の光通信は情報を光の明るさや波の向き(偏光)の変化で伝えていますが、時間結晶を使えばこれらを特定のリズムで周期的に変える特殊な光学素子(光を制御する部品)を作ることができます。
将来的に周期をさらに高速化できれば、通信のタイミングをより精密にコントロールしたり、情報量を大幅に増やしたりすることにもつながるでしょう。
さらに複数の異なる周期をもつ時間結晶を組み合わせることで、複雑で独特な「時空間パターン」が生まれます。
このパターンは人の指紋のように一つ一つが異なるため、情報セキュリティ分野で「暗号の鍵」として活用できる可能性も示唆されています。
研究チームは、特に時間結晶の周期を組み合わせて生じる独自のパターンを、本人確認の認証システムなどに応用することを提案しています。
つまり、時間結晶が情報セキュリティや通信技術において革新的な役割を果たす可能性があるのです。
また、今回の研究成果は純粋な科学的好奇心という観点からも非常に興味深いものです。
研究チームは、液晶のような「柔らかい物質(ソフトマター)」にはまだ発見されていない時間結晶現象が数多く眠っている可能性を指摘しています。
この研究がきっかけとなり、液晶以外のソフトマターの中にも新たな「時間結晶」が次々と発見されるかもしれません。
つまり、この成果は単なる技術的な発見ではなく、新しい科学の分野が開拓される可能性を秘めているのです。
私たちはこれまで、空間的な秩序(結晶構造)を目で見て利用してきましたが、今回の研究は人類が「時間に刻まれた秩序」を直接観察し、それを実際に役立てる新しい段階に入ったことを示しています。
絶え間なく変化し続ける不思議な縞模様は単なる珍しい現象ではなく、「空間と時間にまたがる新しい秩序」を私たちが理解し始め、その扉を開けつつあることの象徴とも言えるでしょう。
元論文
Space-time crystals from particle-like topological solitons
https://doi.org/10.1038/s41563-025-02344-1
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部