アメリカのMIT(マサチューセッツ工科大学)で行われた研究によって、1970年代から理論的に存在が予言されていた「ホフスタッターの蝶(量子蝶)」がついに直接確認されました。
これは、電子が磁場と周期的なポテンシャルの両方を感じることで、エネルギーが複雑に分裂し、フラクタルな“蝶の羽”のようなパターンを描く現象です。
従来は実験室レベルを超える強大な磁場が必要と考えられ、半世紀近く“幻の存在”とされてきました。
しかし今回、“ねじれた二層グラフェン”という特殊な材料を用いることで、わずか数テスラ程度の磁場でもこのフラクタル構造を捉えることに成功したのです。
現実に現れた“量子蝶”はいったいどんな新しい物理を見せてくれるのでしょうか?
研究内容の詳細は『Nature』にて発表されました。
目次
- 数千テスラの壁を越えて──“宇宙級磁場”の常識を覆す挑戦
- 幻の量子蝶が今ここに──理論だけだった存在の“捕獲”
- 変幻自在な量子蝶、意外な相関で舞い続ける
数千テスラの壁を越えて──“宇宙級磁場”の常識を覆す挑戦

昔から「ホフスタッターの蝶」という現象は、地球磁場の何千万倍もの超強力な磁場がなければ実現できない――そう言われ続け、長らく“幻の存在”とみなされてきた現象があります。
この現象を考えるには原子がきれいに並んだ結晶という“整然とした道路”の上を、電子という“粒子の車”が走っているイメージから入るといいかもしれません。
そこに、さらに“磁場”という大きな“風”が吹きつけます。
すると、ふつうならスムーズに走り抜けるだけの道路が、強い風によってあちこち歪み、入り組んだ迷路のように姿を変えます。
電子たちは、その“ねじれた道路”の上を振り回されながら走行するうちに、複雑に分割されたり、入り組んだ隙間をすり抜けたりして、さまざまなエネルギーレベルを繰り返し行き来するようになります。
ですがこうして無数に折り重なった電子たちのエネルギーレベルはランダムなものにならず、拡大しても拡大しても同じような模様が現れる“不思議な図形”=“フラクタル”の形をとるのです。
しかも、その模様が理論上、まるで蝶が羽を広げるように左右対称に美しく展開すると予想されていることから「ホフスタッターの蝶(量子蝶)」と呼ばれるようになりました。
このような対称性やフラクタル性は普段はアートやコンピュータの図形で見かけることもありますが、電子のエネルギーといったもので同様の模様が現れると予想されたのは当時としてはとても画期的でした。
ところが、“理論的には”存在するはずのこのパターンを、実験の場で直接捉えることは極めて困難でした。
なぜなら、結晶格子スケールの細かな電子の運動と、電子が受ける磁場の両方を同時に十分強く作用させるためには、単純計算で数千テスラもの膨大な磁場が必要だと考えられてきたからです。
数千テスラといえば、たとえば研究所で一般的に使われる10テスラ程度の超伝導磁石をはるかにしのぐ規模で文字通り天文学的な規模です。
実験室にそんな巨大な磁場をつくり出せる装置など存在せず、当然ながらほとんどの研究者は「面白い理論だけど、まず実現は不可能だろう」と一種の憧れに近い目で眺めてきました。
もし本当にこの蝶が観察できるなら、電子がどのようにエネルギーの階層を作り、さらに折り重なった状態を組み替えているのかを知る手がかりになる可能性があるからです。
量子ホール効果など、すでに知られている現象とも深い関わりがあり、さらに「強相関電子系」と呼ばれる複雑な世界を理解する道具としても使えそうだ――そう考えた研究者たちは、少しでも小さい磁場でこの蝶を“羽ばたかせる”方法を熱心に探してきました。
そんななか登場したのが、「モアレ超格子」と呼ばれる技術です。
グラフェンという炭素の一層シートを、ほんのわずか(たとえば0.6度くらい)ねじって重ねると、干渉によって“モアレ模様”という大きな周期構造が生まれます。
原子スケールではない、もっと大きな周期ができるわけです。
これは、ふだん0.24ナノメートルほどの距離しかない原子の並びが、何十ナノメートルもの広い間隔をもつ格子になったように見えるということです。
間隔が大きくなれば、それだけ弱い磁場(数テスラ)でも“蝶の模様”が出やすくなる、という考え方です。
そうすると、今まで「数千テスラが必要」と言われていたものが、現実的な磁場で実現できるかもしれない――こうして、ずっと夢物語に近かったホフスタッターの蝶が、実際に観察できるチャンスが見えてきました。
幻の量子蝶が今ここに──理論だけだった存在の“捕獲”
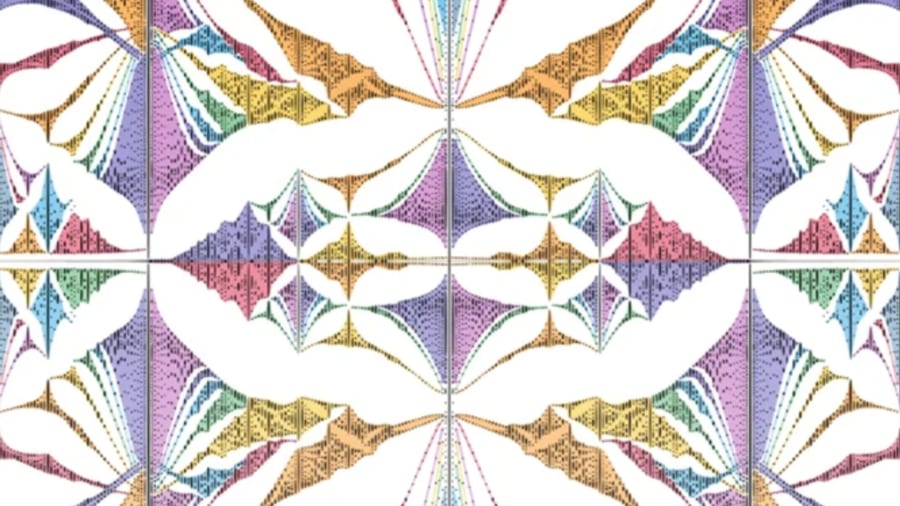
研究者たちはまず、二枚のグラフェン(炭素原子がハチの巣のように並んだ極薄いシート)を、わずか約0.6度の小さな角度で重ねるという特殊な方法を試しました。
グラフェンというのは、炭素原子がハチの巣のように並んだ「とても薄いシート」です。
このシートを二枚用意して、2枚目をほんの少し(約0.6度ほど)ねじって重ねると、波紋が重なるように「モアレ模様」という大きな周期のパターンが生まれます。
それは、プールに石を2つ落としたとき、波が干渉し合ってできる複雑な模様をイメージすると分かりやすいかもしれません。
ただし、実際にはこの模様はナノメートル(1ミリの100万分の1)以下という極小の世界で起きているので、普通の顕微鏡ではとても見えません。
ここで登場するのが、極低温(とても冷たい環境)でも作動できる「STM(走査型トンネル顕微鏡)」と「STS(分光手法)」です。
STMは、針の先をサンプルのごく近く(原子数個分ほどの隙間)まで近づけ、ごくわずかな電圧をかけると流れる“トンネル電流”を測定する装置です。
その電流の変化を地図のように可視化することで、サンプル中の電子たちの「エネルギーの分布」がわかるというわけです。
さらにサンプルの下に“ゲート電極”という仕組みを入れ、電圧をかけることで“電子の数”を増やしたり減らしたりできます。
お菓子の入ったビンに例えるなら、「ビンの中にどれだけお菓子(電子)が入っているか」を自由に変えながら、ビンの中の様子を手に取るように調べられるイメージです。
さて、こうして電子の数や磁場の強さなど、いろいろな条件を組み合わせると、ある時、エネルギーバンド(電子のとるエネルギーの範囲)が波紋のように「バリバリッ」と分裂していく様子が見えてきました。
これが、かつて理論でしか語られなかった「ホフスタッターの蝶」のフラクタル模様です。
フラクタルというのは、拡大しても同じような模様が何度も出てくる特徴をもつパターンのことで、雪の結晶やシダの葉っぱなどが身近な例。
この量子の世界で、それがまるで蝶の羽の模様のような形をして現れるため、「ホフスタッターの蝶」と呼ばれています。
しかも、調べてみると、磁場が弱い時には電子同士の結びつきが強くて“ギャップ”と呼ばれる隙間ができるのに、磁場を強くすると不思議とその相互作用が弱まり、バンドが広がってしまう、という意外な動きも見つかりました。
これは、単純な理論では説明できないほど複雑な要素(スピンやバレーなど量子の性質)が、蝶の羽ばたきに影響を与えているからだと考えられています。
なぜ今回の成果がすごいのか?
第一に、長年「数千テスラ級の超強力な磁場がなければ観察できない」と思われていたホフスタッターの蝶を、モアレ超格子によってわずか数テスラ程度でも観察できると証明した点です。
第二に、これまで理論や間接的な測定から推測するしかなかった量子現象を、STMの“分光画像”というはっきりした形でとらえられた点にあります。要するに、電子たちがどんなバンド構造を作り、どんなふうに分裂や再配置を起こしているかを“直接見る”ことができたわけです。
これによって、ねじれた二層グラフェンのような“モアレ材料”には、私たちがまだよく知らない「トポロジカル相」や「超伝導相」といった新しい物性が隠れている可能性がさらに高まったといえます。
わずか0.6度のねじれが生み出す量子の舞台で、電子たちが踊る姿を最前列から観察する――それが今回の研究の意義です。かつては理論上だけの“幻”とされてきた量子のフラクタル模様が、ついに“リアルな”実験データとして私たちの前に現れた瞬間でもあります。
変幻自在な量子蝶、意外な相関で舞い続ける

今回の測定でもっとも印象的なのは、「ホフスタッターの蝶」が見せるフラクタル模様が、実はいつも同じ姿をしているわけではなく、磁場や電子の数(充填率)によってリアルタイムに形を“変えて”いる、という点です。
理論的には、結晶格子と磁場の周期性が組み合わさった結果として生まれる“美しい”分裂パターンが想定されていました。
しかし実際には、その“美しさ”の背後に、電子同士のクーロン相互作用やスピン・バレーと呼ばれる量子自由度の秩序化が複雑に入り込み、一見するとただのシンプルな蝶模様とはかけ離れた動きを見せるとわかったのです。
たとえば、磁場を弱めたときにこそ現れる特別なギャップ(電子が詰まって流れなくなるエネルギーの“すき間”)が、磁場を強くするにつれてむしろ消滅していく、という逆転現象はその代表例です。
従来の「量子ホール効果」のイメージでは、磁場を強めれば強めるほど電子の動きが制限され、相互作用が強まって絶縁状態が増えるケースが多いはずでした。
しかし今回の実験では、ホフスタッターの蝶が“羽ばたき”を大きくするにつれ、バンドが広がって相互作用が抑えられるような状態へ移行する場面が、実際のスペクトルの中にくっきりと映し出されたのです。
まるで、舞台の照明が強くなるほどダンサー同士の連携が乱れ、息を合わせづらくなるかのような、そんな不思議な光景といえるでしょう。
さらに特筆すべきは、「自己相似性」と呼ばれるフラクタルの本質的な特徴に関しても、実験結果が単なる教科書的描写を超えた“リアルな姿”を明らかにしたことです。
理論の世界では、ある特定の磁束比(1/3や1/4のような“きれいな分数”)のときに、蝶の羽根が拡大・縮小しても同じような模様が繰り返されることが示唆されていました。
しかし実際に測定してみると、確かにその通り美しい相似パターンが現れる瞬間がある一方で、磁場がわずかにズレた途端に、まるで別の蝶に変身したかのようにギャップの位置やバンドの幅が劇的に動いてしまうのです。
いわば、顕微鏡で覗いたミクロな世界の蝶が、“ある条件”ではきちんと幾何学的な羽模様を見せてくれるのに、“その条件”をほんの少し外すと、羽ばたき方そのものが大きく変わる、という興味深い姿がとらえられました。
こうした知見が示すのは、ホフスタッターの蝶が単なる“数学的ファンタジー”ではなく、実在する電子系の強相関やトポロジカル性、さらには量子自由度を統合した“複合的なステージ”になっているという事実です。
フラクタル模様が保持されるかどうか、どこでギャップが開くか閉じるか、そしてバンドがどのようにエネルギー空間を埋め尽くすか――これらの要素には、磁場と格子という枠組みだけでは解ききれないほど多彩な因子が絡んでいるのです。
そして何より注目すべきは、そうした多彩な因子がかもしだす量子ドラマを、“実験室スケールの磁場”で観察できるようになったことです。
もはや数千テスラ級の磁場を追い求める必要はありません。
モアレ超格子を巧みに利用し、適切な角度と温度、測定手法を組み合わせることで、蝶の羽根をじっくりと拡大し、その多層的な相関のパターンをすくい上げる――このアプローチは、今後さらにさまざまなモアレ材料に広がり、私たちがまだ見ぬ量子相や超伝導、トポロジーといった“深い森”を切り開くかもしれないのです。
結局のところ、フラクタルとは“一見すると同じ模様が繰り返される”ように見えながら、その実、観察条件がわずかに変わるとまったく違う表情を見せる神秘に満ちた世界。
ホフスタッターの蝶は、そのフラクタルの妙を私たちに存分に味わわせながら、同時に強相関物質や量子ホール系の理解をぐっと深めてくれる、極めて有望な舞台だと言えるでしょう。
参考文献
Quantum fractal patterns visualized
https://www.eurekalert.org/news-releases/1075053
元論文
Spectroscopy of the fractal Hofstadter energy spectrum
https://doi.org/10.1038/s41586-024-08550-2
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


