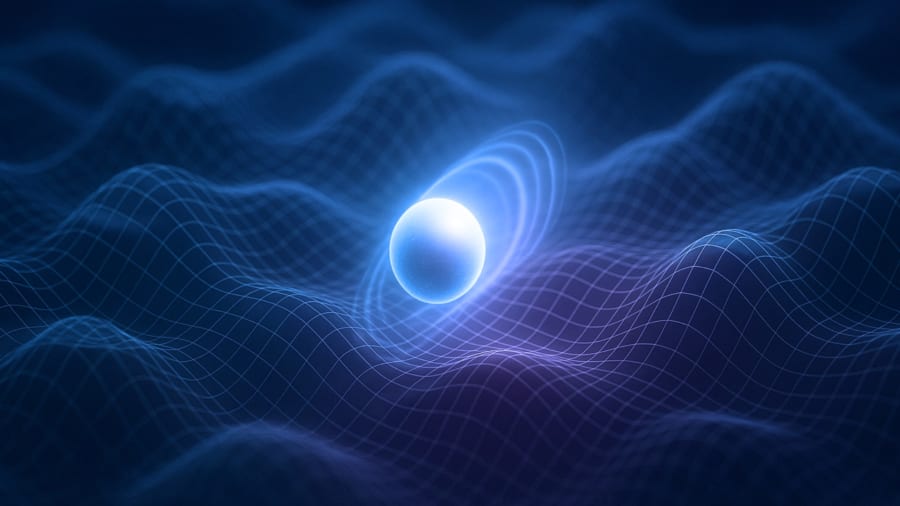アメリカのスティーブンス工科大学(Stevens Institute of Technology, SIT)とコロラド州立大学(Colorado State University, CSU)、さらに米国国立標準技術研究所(NIST)などの研究者によって行われた最新の理論研究により粒子が「真空の揺らぎ」によって動かされることで、ごくわずかな時間の歪みが起こる可能性があることが指摘されました。
これはアインシュタインの特殊相対性理論で知られる「高速で動くほど時間が遅れる」という現象の、さらに量子的なバージョンともいえるものです。
もしこの現象が実験で確認されれば、量子力学と相対論という二大理論の間に新しい橋をかける手がかりとなり、私たちがこれまで当然だと思ってきた「時間」の概念そのものを見直すきっかけになるかもしれません。
では、止まっているはずの原子がなぜ量子的に揺れ、時間の進みまで変えてしまうのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年9月11日に『arXiv』にて発表されました。
目次
- 空間の揺らぎが粒子を運動させると時間は遅れ始める
- 量子力学が見つけた時間のにじみ
- 量子の世界が教えてくれた「ぼやける時間」の正体
空間の揺らぎが粒子を運動させると時間は遅れ始める
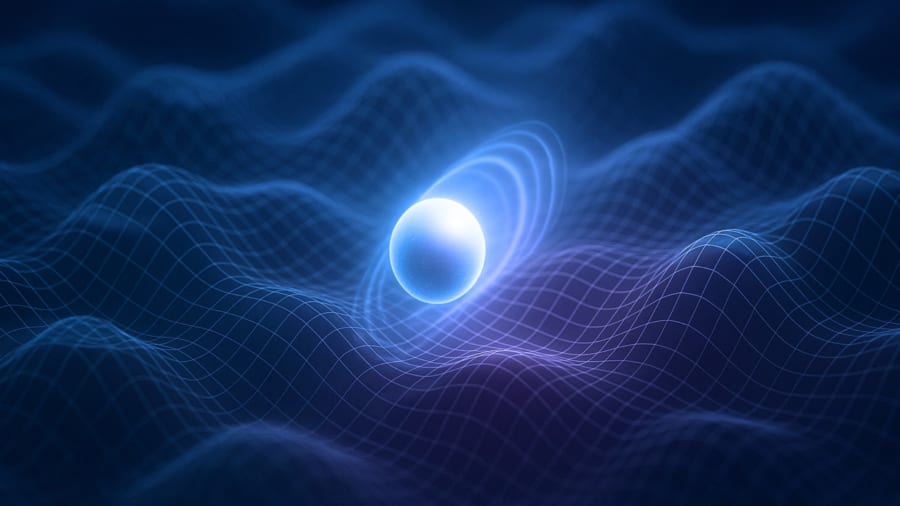
時間というものは、いつどこでも誰にとっても同じように流れている――。
私たちは普段、このように考えて生活しています。
ところが、今からおよそ100年前、物理学者のアルバート・アインシュタインはまったく異なる考え方を提唱しました。
それが「特殊相対性理論」です。
特殊相対性理論によれば、実は時間の流れというものは「誰にとっても同じ」ではありません。
特に、高速で動く物体の中では時間の進みが遅れるという驚くべき現象が予測されました。
これは「タイム・ディレーション(時間の遅れ)」と呼ばれる現象です。
有名な例として、宇宙船に乗った双子の兄弟の話を聞いたことがある人も多いでしょう。
双子の兄は宇宙船に乗り込み、地球から離れて光の速さの99.995%という猛烈な速さで1年間の宇宙旅行に出ます。
すると、宇宙船の兄にとっては確かに1年が経ちますが、地球に残った弟が過ごした時間は、なんと100年も経ってしまっています。
これが「双子のパラドックス」や「浦島効果」と呼ばれる特殊相対性理論の有名な思考実験です。
では、宇宙船ではなく、私たちの日常により身近な世界、例えば私たちが正確な時間を刻むために使う「原子時計」ではどうでしょうか?
原子時計とは、原子が持つ固有の振動を利用して時間を測る超高性能な時計です。
特に近年では、「光学原子時計」と呼ばれる、原子の光の振動を使った時計が登場し、その精度は何億年に1秒の狂いしか生じないほど驚異的なものになっています。
しかし、精度が高くなればなるほど、これまで気にする必要がなかった極めて小さな現象が、時計の進みに影響を及ぼしてきます。
その一つが「第二次ドップラー効果(Second-Order Doppler Shift、略称SODS)」と呼ばれるものです。
私たちは日常でドップラー効果という言葉を、例えば救急車のサイレンが近づいてくると音が高くなり、遠ざかると低くなる現象として知っていますが、SODSはこのドップラー効果のもっと小さくて繊細な「第二段階の効果」なのです。
原子の熱運動は一見すると単に震えているだけに思えますが、立派な運動であり、しかもその速度はかなり高速です。
実際、最新の光学原子時計を使った実験では、この原子の振動によるSODSの効果を10⁻¹⁷という極めて細かいレベルまで注意深く考慮しています。
なぜなら、時計の精度が非常に高いため、原子がわずかに動くだけでも時間の進みに影響が出てしまい、正確な時計としての役割を妨げてしまうからです。
当然、原子時計という正確さが命の装置にとって、このような相対論的な時間の遅れは望ましくありません。
だからこそ科学者たちはレーザー冷却という特別な方法を使って、原子の動きをほぼ止まった状態まで冷やしてしまいます。
しかし、ここで一つ新たな疑問が生まれてきます。
絶対零度まで冷却できたとしたら、熱運動は止まり粒子の時間の遅れはなくなるのでしょうか?
特殊相対性理論では「観測者からみて完全に止まっている物体には時間の遅れは生じない」とされていますが、量子力学の視点では事情が少し違うのです。
実は量子力学の世界では、物質をどんなに冷却しても原子を完全に静止させることはできません。
絶対零度という物理的な最低温度に近づいても、原子は「零点振動」という目に見えない微かな揺れを続けているからです。
これは原子がまるで止まっているように見えても、実際はごく微かに振動し続けていることを意味します。
つまり相対論では「止まった原子には時間遅れがない」とされますが、量子論では「止まったように見える原子でも微妙に揺れ続けているため、その振動が時間の流れを変える可能性がある」ということになるのです。
では一体、この量子力学特有の揺らぎによって時間の進みがどのように変化するのでしょうか?
量子力学が見つけた時間のにじみ

研究チームが今回取り組んだテーマは、「量子の世界で生じる時間の遅れを正確に計算する」というものでした。
まずチームは、現在最も精度が高い時計の一つである「単一イオンの光学原子時計」(例えばアルミニウムイオン時計)を想定し、その時計の原子の動きを量子力学の視点で詳しく調べました。
ここで言う単一イオンとは、電気的な力で真空中に浮かべられたただ一粒の原子のことです。
光学原子時計は、このようなイオンが光を吸収したり放出したりする時の非常に安定した振動を利用して、極めて正確に時間を刻んでいます。
通常、このような原子時計では、原子がどのように動くかを予測するとき、古典物理学(私たちが日常で経験する物理)を用いて考えられていました。
古典物理学の世界では、「止まっている原子は時間の遅れを生まない」とされます。
しかし、今回の研究チームは、量子力学の理論を用いることで、古典物理学では見落とされていた新しい現象を発見したのです。
まず興味深いのは、「零点振動(れいてんしんどう)」という現象によって起こる時間の遅れです。
零点振動とは、量子力学の基本的な原理に基づき、どんな物体でも絶対に完全に静止することはできない、という不思議な性質から生じる微かな振動のことです。
つまり、どれほど温度を下げて動きを抑えても、イオンは目に見えないほど小さく揺れ続けているということです。
この微細な揺れがある限り、原子時計が刻む時間にもほんの少しのずれが生じてしまいます。
このズレを検出する方法として研究者たちは「量子もつれ」に着目しました。
量子もつれ(りょうしもつれ)とは、量子力学特有の現象で、二つの物体がまるで離れていても一体のように振る舞い、一方の状態がもう一方に瞬時に影響を与える不思議な結びつきのことです。
研究チームが特に注目したのが、「スクイーズ状態」という特別な量子状態を利用した場合です。
スクイーズ状態とは、イオンの動きをある一方向だけに非常に強く絞り込み、それ以外の方向では大きく広げることで、原子の持つ不確かさを意図的にコントロールした状態を指します。
これは、例えば手に持った粘土をある方向にギュッと握りしめると、別の方向に粘土が広がってしまう現象に似ています。
このようにイオンの量子状態を意図的に偏らせると、時計の内部で時間を刻む原子の振動と、その原子の微妙な動きが「量子もつれ(量子的な繋がり)」で互いに結びついてしまいます。
今回の場合では、イオンの動きと時計の振動がこの量子もつれの状態になり、その結果として時計が刻む信号に目に見えるほどの変化が現れることが計算上分かりました。
具体的には、時計が示す信号の「可視性(かしせい)」――つまり時間を刻む原子の振動の周期性や鮮明さ――が、約7%も低下すると予測されました。
この7%という変化は、ごく小さいように思えるかもしれませんが、原子時計の世界では非常に大きな変化と言えるでしょう。
さらに、時計の周波数(原子が1秒に刻む振動の回数)にも約3.8×10⁻¹⁷という極めて小さなずれが生じると計算されました。
とても微小なずれですが、原子時計の精度が高ければ高いほど、このわずかなずれが重要な意味を持つのです。
では、この変化を直感的に理解するにはどう考えればよいでしょうか?
例えば、私たちが音楽を聴いているとき、複数の楽器が同じリズムで演奏すればきれいなハーモニーが生まれますが、リズムが少しでもずれると、演奏が濁ったように聞こえますよね。
これと同じように、時計の中で振動する原子のリズムが量子もつれの影響で二つの異なる速さで同時に進んでしまうと、本来なら鮮明でシャープな「時計の刻み」がわずかにぼやけてしまう、という現象が起こるのです。
こうした結果から研究チームは、量子力学の世界では真空の揺らぎによって時間が「曖昧ににじむ」ような現象が起こり得る可能性を示しました。
これは「時間」という私たちにとって最も身近で基本的な概念にも、実は量子力学的な謎が潜んでいることを示唆する、とても興味深いサインだと言えるでしょう。
量子の世界が教えてくれた「ぼやける時間」の正体

この研究が示したことは、私たちにとって当たり前に流れている「時間」にも、実は量子力学的な不思議な揺らぎが潜んでいる可能性がある、ということです。
現代の原子時計は、その高い精度によって私たちの生活に正確な時刻を提供していますが、この新しい量子的な現象がもし実際に観測できたとしたら、時計の設計や補正方法はこれまで以上に精密で緻密なものになるでしょう。
さらにこの発見は、量子力学と相対性理論という、現代物理学を支える二大理論の間に新たな橋をかける、非常に重要な役割を果たす可能性もあります。
しかし、この研究はまだ理論的な段階にとどまっています。
この量子的な時間の揺らぎを実際に観測するためには、現在の原子時計が持つ精度をさらに超える、極めて高度な実験技術が必要なのです。
そのため、これらの理論が私たちの目に見える形で証明されるまでには、もう少し時間がかかるかもしれません。
それでも今回の研究成果が大きな意味を持つのは、「時間そのものが量子的にぼやけるかもしれない」という抽象的だった考えを、具体的な数字を用いて明確に示し、実験によって確かめるための具体的な道筋を描き出したからです。
特に興味深いのは、原子時計で使われるイオンをより軽いもの(例えばホウ素10)に置き換えることで、この量子的な効果がさらに強く現れる可能性が指摘されている点です。
理論的には、その効果によって時計の信号の鮮明さが最大で約24%低下することも予測されています。
これは、「ぼんやりしていた時間の輪郭」がさらにはっきりと浮かび上がってくるような状況に例えることができるでしょう。
また、この研究で示された量子効果の測定方法は、原子時計だけでなく、他の様々な量子物理学の実験系にも活用できる可能性が期待されています。
例えば、量子力学と重力理論の境目という、現代物理学でも特に重要で難しい分野の研究に、新しい突破口をもたらすことになるかもしれません。
今後、実際の実験でこの量子的な時間の揺らぎが観測されることになれば、私たちはこれまで経験したことのない、新しい形で「時間」という概念を見つめ直すことになるでしょう。
元論文
Quantum signatures of proper time in optical ion clocks
https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.09573
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部