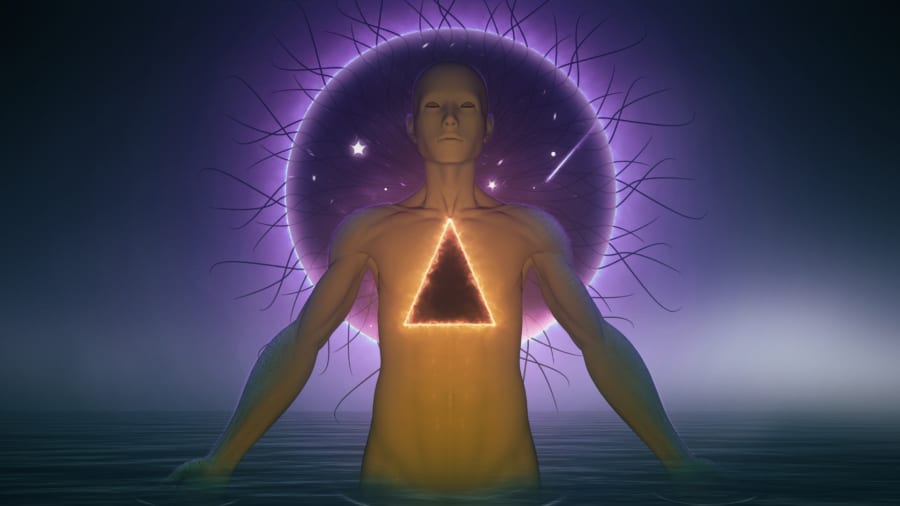スペインのバルセロナ大学で行われた研究により、疑似科学を強く信じる人ほど、偶然の一致に意味を見出し、「運命」や「未知の法則」のせいだと考える傾向があることが示されました。
また本来のコイントスでは表や裏が続けて出ることはごく普通なのに、疑似科学を信じやすい人ほど、同じ面の連続を“嫌がる”クセが強く現れていました。
これは「偶然を深読みするクセ」と「ランダムの読み違い」という二つの小さな“脳のクセ”が、気がつかないうちに私たちの信じる情報の質を左右している可能性を示しています。
では、こうした脳のクセはどのようにして疑似科学への信じ込みにつながっていくのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年10月28日に『Applied Cognitive Psychology』にて発表されました。
目次
- 疑似科学の餌食になる人はどんな性質を持っているのか?
- 疑似科学を信じやすい人は偶然を必然だと感じやすい
疑似科学の餌食になる人はどんな性質を持っているのか?

「こんなの偶然なわけがない」――人は時に、単なる偶然に「見えない力」や「運命」を感じてしまうものです。
例えば、ある友人のことを考えていた瞬間にその人から電話がかかってきたり、時計を見るたびに同じ数字の並び(ゾロ目)を目にしたりすると、私たちは思わず特別な意味を勘ぐってしまいます。
日常にはこのような「奇妙な偶然」が溢れており、大半はただの偶然ですが、私たちの脳はそれを放っておかず、何かしらのメッセージを見出そうとするのです。
しかし、偶然の一致に深い意味を見出しすぎることは、時に私たちを誤った方向に導きます。
たとえばルーレットで赤が5回続くと「そろそろ黒が出るはず」と思ってしまう「ギャンブラーの誤謬(ギャンブラーの勘違い)」や、バスケでシュートが続けて入ると「今は手が温まっている」と信じてしまう「ホットハンド効果」など、私たちはランダムな出来事にも“それらしいストーリー”をつけてしまうのです。
疑似科学は、まさにこの「物語好きな脳」をうまく利用します。
たまたま頭痛が引いたタイミングと怪しいパワーストーンや高価なツボを買った時期が重なると、それらが「効いた」と考えてしまいます。
健康食品、スピリチュアル系のセミナー、量子ヒーリング……こうしたものがビジネスとして成立する背景には、「偶然の改善を、その商品のおかげだと思い込む」心理が静かに働いています。
これまでの研究では、超常現象などを信じる人が、偶然経験やランダムの誤解と結びついていることが報告されてきました。
しかし「ホメオパシー」「波動調整」といった“いかにも科学風”の疑似科学にも、同じ心のクセが関わっているのかどうかは、十分に体系的には調べられていませんでした。
(※ホメオパシーは「病気を引き起こす物質を水で何度も薄めていくと、その水に病気を治す力が宿る」「水に含まれる原因物質は薄ければ薄いほど病気を治す効果が高い」「希釈し過ぎて原因物質の分子が1つもなくなっても水には病気を治す情報が残っている」という疑似科学です。)
そこで今回研究者たちは、偶然に意味づけしてしまう傾向がある人が、疑似科学を信じやすいかどうかを調べることにしました。
疑似科学を信じやすい人は偶然を必然だと感じやすい

偶然に意味づけしてしまう傾向がある人は、疑似科学を信じやすいのでしょうか?
答えを得るため研究者たちは心理学を学ぶ学生108人を対象に、さまざまな疑似科学への賛成度を1〜7段階で答えるアンケートに回答してもらいました。
次に、「これまでどんな不思議な偶然を経験してきたか」「それを何のせいだと思うか」を尋ねる質問票に答えてもらいました。
最後に、パソコン画面上でコイントスとサイコロ振りを“自分の手でランダムに”再現させる課題に取り組んでもらいました。
結果はかなりハッキリしていました。
まず、疑似科学を信じる度合いが高い人ほど、「意味のある偶然」を多く経験したと報告していました。
たとえば、「誰かのことを考えていたら、その人から連絡が来た」といった経験数が多く、そうした経験数のスコアと疑似科学への賛成度には弱〜中程度の相関(つながり)が見られたのです。
さらに、「その偶然は何が原因だと思うか」を尋ねると、疑似科学をあまり信じない人ほど「ただの偶然」と答える一方で、強く信じる人ほど「運命」「普遍的なつながり」「まだ見つかっていない物理法則」など、非ランダムな力のせいだと考えやすいことがわかりました。
偶然の意味づけそのものが、信念の強さと結びついていたのです。
そして、この研究で一番「ニヤリ」としてしまうのがコイントス課題の結果です。
本物のコイントスでは、表が連続したり裏が連続したりすることがあります。
しかし参加者たちにコインの裏表のパターンを「本物のコイントスらしく」見える並びとして作成してもらうと、疑似科学を信じやすい人ほど、同じ面が連続することを避ける並びを作成したのです。
これらの結果は、偶然に意味を見出し「出来事どうしをすぐに因果関係でむすびつけてしまう」クセや、「本物のランダムにはもっとバラバラ感があるはずだ」と自然な反復まで不自然だと感じてしまうクセが、疑似科学の信じやすさに強く関連していることを示しています。
今回の発見から言えるのは、偶然の出来事をどう解釈するかという私たちの脳のクセが、信じる情報の質を左右しうるということです。
身の回りの些細な偶然に「何かのメッセージだ」と感じやすい人は、その感じ方自体が原因となって、エビデンスの乏しい疑似科学にも引き寄せられやすくなるのかもしれません。
逆に言えば、偶然を過剰に深読みしないようにしたり、ランダムな現象の正しい理解を広めたりすることが、疑似科学に惑わされない社会づくりにつながる可能性があります。
研究チームも、たまたま起きた出来事で早合点しないことや結果の偏りだけでランダムでないと判断しないことの重要性を指摘しており、そうした教育的介入によって科学リテラシーを高められるかもしれないと述べています。
元論文
Random Sequences, Experienced Coincidences, and Pseudoscientific Beliefs
https://doi.org/10.1002/acp.70133
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部