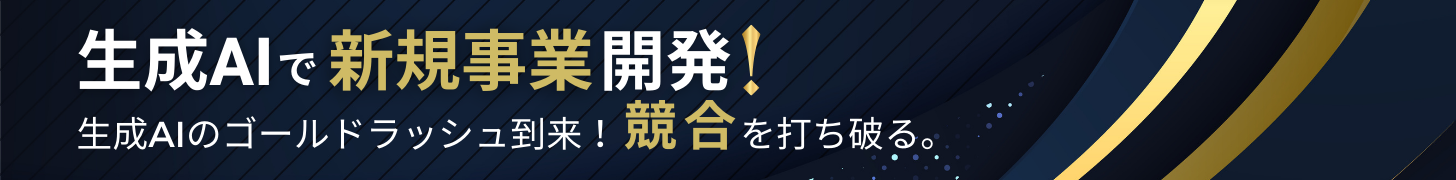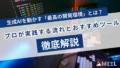- 現時点での導入事例は限定的だが、国内外で検証・PoCが本格化
- 生成AIは自然言語処理・意思決定支援で既存AIを補完
- 需要予測、EPA対応、倉庫業務など幅広い領域で活用余地
物流業界は急速な経済成長と消費者ニーズの多様化によって、複数の重大な課題に直面しているのをご存知でしょうか?
特に2024年4月施行の働き方改革関連法によって、トラックドライバーの時間外労働が年間960時間までに制限されたことで、深刻な人手不足や輸送効率の低下が懸念されています。※1
この記事では、そうした状況に対する解決策の一つとして生成AIの導入に焦点を当てて解説します。物流業界でのAI活用法を知ることで、物流・需要の予測、配送ルートの最適化、倉庫管理の効率化など、多岐にわたる業務での効率化とコスト削減が実現できると実感できます。
ぜひ、最後までご覧ください。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
そもそも生成AIとは?
生成AI(ジェネレーティブAI)は従来のAIと異なり、単に情報を整理・分類・検索するだけでなく、学習したデータに基づき新しいコンテンツを生み出すAIのことです。指示に応じて文章を生成する「ChatGPT」などが特に有名ですね。
一方、従来のAI(機械学習型AI)は、与えられたデータをもとに「分類・予測・検出」などを行うのが主な役割です。たとえば、過去の輸送データをもとに渋滞リスクを予測する、倉庫内で不良品を検出する、といったタスクは機械学習AIが得意としています。
生成AIの強みは、こうした従来AIの分析結果をもとに「次に取るべき行動」や「改善提案」などを自然言語で提示できる点にあります。物流業界では、天候・交通・荷主のスケジュールといった変動要因を分析し、生成AIが報告書や指示文のドラフト作成を支援するなどの実証実験が一部で進んでいます。
現時点では検証段階ですが、今後は現場と管理をつなぐ橋渡し役としての活用が期待されています。
なお、生成AIについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

物流業界が今抱えている課題

物流業界は現代の急速な経済成長と消費者ニーズの多様化に伴い、複数の重大な課題に直面しています。特に深刻な悩みが次の3つです。
- 長時間労働の慢性化
- 配達頻度の増加
- ドライバーの高齢化
これらの問題は、業界全体の効率と持続可能性に影響を及ぼしており、労働環境の改善や効率化技術の導入を急ぐ必要があるとされています。
長時間労働の慢性化
物流業界では長時間労働が慢性化しています。
国土交通省のデータによると、令和4年の全産業平均の労働時間は2,124時間であるのに対し、中小型トラックドライバーの平均労働時間は2,520時間、大型トラックドライバーは2,568時間と、全産業平均を大きく上回っています。
また、賃金も全産業平均より低い状況が続いており、長時間労働・長距離運転・低賃金という労働環境がドライバー不足の一因となっています。
配達頻度の増加
電子商取引(EC)市場の拡大により、宅配便の取り扱い個数が増加しています。この影響で、配達頻度が増加し、それに伴い受取拒否や再配達の件数も増えました。
また、個人宅への小口配送が増えたことで配送1回あたりのトラックの積載率は低下傾向にあります。積載率の低下は効率性の低下を意味しており、再配達の増加と合わせて、物流業界の新たな課題となりました。
こうした課題に対応するため、国土交通省と経済産業省は再配達削減に向けた取り組みを継続的に推進しています。「再配達削減PR月間」などのキャンペーンを通じて一定の成果が見られる一方、2024年4月に施行されたトラックドライバーの時間外労働上限規制により、依然として業界全体の負担は大きい状況です。※2
このため、再配達の効率化や業務自動化を目的としたAI技術の導入が、さらに注目を集めています。
ドライバーの高齢化
ドライバーの高齢化も深刻な問題となっています。
総務省の「労働力調査」によると、トラック運転者の年齢構成は高齢化が顕著で、45歳以上の割合が半数を超える状況が続いています。※3
さらに、トラックドライバーの職場環境は、他の産業と比較して賃金が低く、労働時間が長いことが指摘されています。これにより、若い世代のドライバーの増加が見込めず、既存の高齢ドライバーに依存する傾向が強まっているのが現状です。
物流DXと生成AIの融合が加速【2025年最新動向】

近年、物流業界では「物流DX(デジタルトランスフォーメーション)」が本格化しています。特に2025年以降は、生成AIを中心としたAIツール群が、サプライチェーン全体の自動化と可視化を支える技術として注目されています。
最新の生成AIモデル(GPT-4o、Gemini 2.0など)は、テキストや画像だけでなく、数値・センサー・音声データまで処理可能です。これにより、倉庫内の在庫データと輸送トラッキング情報を統合し、リアルタイムで需給予測を自動修正する仕組みが実現しつつあります。
さらに、AIが社内文書・マニュアル・ドライバー日報などを自動要約する「ナレッジマネジメント支援」も拡大。現場とバックオフィスの両方で、生成AIによる知識共有の効率化と意思決定のスピード向上が進んでいます。
物流業界でAIができること
現時点では、物流業界で生成AIの本格導入事例はまだ少ないものの、2025年現在、国内外で実証実験やPoC(概念実証)が本格化しています。ここからは、物流業界におけるAI(従来の機械学習)などの最新動向と、今後活用が期待される具体的なユースケースを分野別にご紹介します。
物流・需要の予測
物流業務の効率化や最適化を進めるうえで、需要予測は重要な基盤です。商品が「いつ・どこで・どれだけ必要になるか」を正確に見通せるかどうかが、在庫管理や配送計画の精度に直結します。
生成AIは、従来の数値モデルを補完する形で、より多様な情報を分析し、予測の質を高める役割を担います。たとえば、膨大な自然言語データや市場トレンド、天候・SNS・ニュースなどの外部要因を解析することで、需要変動の兆候をいち早く察知し、関係部門にインサイトを提供します。
急なイベントや予期せぬ需要スパイクといった事象も、予測モデルにフィードバックする情報源として活用され、従来の統計モデルや機械学習モデルの精度向上に貢献します。
また、生成AIは予測結果をもとに、意思決定者向けの要約レポートやシナリオ比較資料を自動生成。在庫戦略や配送計画の立案を支援し、需給ギャップの最小化・在庫削減・配送効率の向上といった成果も期待できます。
カスタマーサポートの強化
物流業界でも、コールセンターや配送問合せ対応などのカスタマーサポート業務は人手不足が深刻です。そこで注目されているのが生成AIの導入です。従来のルールベースでは対応が難しかった自由記述型の問い合わせにも柔軟に応答でき、より自然な対話体験を提供できます。
生成AIは、顧客の文脈や感情を読み取りながら最適な回答を自動生成できるため、より満足度の高いカスタマーサポートが実現可能です。また、過去の対話履歴や社内ナレッジを継続的に学習し続けることで、応対品質の一貫性を保ちつつ、複雑な問合せにも対応できる自動化の精度が向上していきます。
リスクの洗い出し
物流業務では、事故・遅延・在庫過不足・人的ミスなど、日々さまざまなリスクが潜在しています。これらをいかに早期に検知し、先回りして対応するかが、安定したオペレーションの鍵となります。
生成AIは、リスク管理において情報の解釈と意思決定支援の両面で活用が進んでいます。たとえば、事故や在庫不足に関する過去のレポートや業務日報を分析し、潜在リスクの傾向や共通パターンを要約・可視化。
さらに、特定リスクに対する対策シナリオを複数提示し、それぞれの影響を自然言語で説明することも可能です。これにより、現場と経営層の迅速かつ正確な判断を後押しします。
顧客行動の分析
物流業界でも、ラストワンマイルでの体験やECユーザーからの声をどう活かすかが競争力に直結しています。生成AIを活用することで、従来の数値分析だけでは見えづらかった顧客行動の文脈や動機を深く理解することができます。
たとえば、レビューや問い合わせ内容などの非構造データを解析し、感情や意図を反映したサービス改善提案を自動生成することが可能です。また、セグメントごとに最適化されたプロモーション文やレコメンド文の生成にも応用でき、より高精度なパーソナライズ施策を実現します。
紙媒体からの脱却
物流現場では、納品書や受領書、日報など紙ベースの帳票処理が今も多く残っています。これらはデジタル化が進みにくい領域とされてきましたが、生成AIとOCRの連携により新たな打開策が生まれつつあります。
生成AIは、読み取った帳票や手書きメモの内容を文脈ごとに理解し、作業指示・報告書・メール文面などに自然な形で自動変換することが可能です。
これにより、単なるデジタル化にとどまらず、文書処理や情報伝達の自動化が実現し、ヒューマンエラーの削減や業務スピードの向上につながります。さらに、紙の使用量削減による環境負荷の軽減と、運用コストの最適化も期待できます。
人材配置の最適化
ドライバー不足や繁閑差への対応など、物流業界では日々の人員配置が重要な業務課題となっています。AIは、過去の配送実績や需要予測データをもとに、最適な人員配置を支援します。
さらに生成AIを組み合わせることで、スキルや経験といった定量化が難しい情報も、文書や面談記録などから抽出し、適材適所の人員アサインを提案することが可能になります。また、配置に関する判断理由の説明文やシフト変更連絡の自動作成も行えるため、現場とのコミュニケーション負荷を軽減し、運用の透明性向上にもつながります。
配送ルートの最適化
燃料高騰・ドライバー不足・新人への引き継ぎなど、配送現場ではルート最適化の重要性が年々高まっています。配送ルートの最適化には、リアルタイムな交通状況・天候・地理情報などを活用したAIの分析が有効です。
さらに生成AIを活用することで、最適化の結果をドライバーや現場スタッフに自然言語でわかりやすく伝達したり、ルート変更の理由や注意点を自動説明することが可能になります。
また、過去の配送記録やドライバーのフィードバックから改善点を抽出し、実務に即したルート戦略の提案を行うなど、現場との接続性を高める支援も実現します。
居眠りの防止
ドライバーの高齢化や長時間運転による疲労リスクが高まる中、事故防止の対策強化が物流現場で求められています。AIは、運転パターンや顔認識技術を活用して居眠りの兆候を検知し、リアルタイムに警告を出すことで事故リスクを低減します。
さらに生成AIを組み合わせることで、検知ログの要約・警告履歴のレポート自動作成・注意喚起文の生成など、運行管理者との情報共有を効率化できます。こうしたシステムは、安全性の向上にとどまらず、運行業務の可視化・業務効率化にもつながる重要な取り組みといえます。
倉庫管理の最適化
人手不足や在庫変動への対応が求められる中、倉庫管理の効率化は喫緊の課題となっています。AIの予測モデリングにより、需要に応じた在庫の最適化や保管効率の改善が実現可能です。
さらに生成AIを活用すれば、分析結果をもとに在庫補充のタイミングを自動提案したり、作業員向けにわかりやすいピッキング指示や動線ガイドを生成することもできます。また、日報やクレーム履歴などのテキストデータを分析し、レイアウト改善や業務フローのボトルネックを自然言語で提示することで、倉庫全体の運用効率をさらに高めることが可能です。
仕分け・入庫の自動化
物流現場では人手不足が続き、属人的な仕分け・入庫作業の標準化と自動化が求められています。倉庫内の仕分けや入庫作業は、AIとロボティクス技術の連携により高精度で自動化が可能です。コンピュータビジョンとセンシングAIを活用し、商品種別や数量を即時に識別して最適な保管場所へ自動割当てを実現します。
加えて生成AIを活用することで、入庫状況や作業エラーの報告書を自動生成したり、オペレーター向けに作業マニュアルや異常対応ガイドを自然言語で作成することも可能です。
現場のナレッジを自動で言語化・可視化することで、教育工数の削減・業務の属人化防止・運用の透明性向上に貢献します。
検品の効率化
検品工程は、精度・スピード・記録の標準化が求められる領域です。AIによる画像認識を活用することで、商品の外観や破損、ラベルミスなどをリアルタイムに判別し、検品作業のスピードと精度を大幅に向上させることが可能です。
さらに生成AIを組み合わせることで、検品結果の要約・傾向レポートの自動生成や、発見された不備に応じた対応手順書の作成が自動化できます。品質管理の透明性向上だけでなく、現場担当者との情報共有の効率化、ナレッジの標準化にも貢献します。
輸入品目の分類
輸入品目の分類業務では、正確さとスピードが求められます。AIは、商品の特徴をベクトル化し、過去の類似品データや関税・規制情報と照合することで、迅速な品目分類を実現します。
さらに生成AIを活用すれば、分類根拠や関税コードの選定理由を自然言語で説明したり、新規商品の規制情報を自動で要約して提示することも可能です。これにより、誤分類リスクの低減に加え、担当者の判断負担を軽減しながら、分類業務の標準化・効率化を実現できます。
適用できるEPAの検索
国際物流において、輸出先ごとに異なるEPA(経済連携協定)の適用可否を確認する作業は煩雑で時間がかかる業務の一つです。生成AIは、商品の属性情報・取引国・最新の貿易法規などの条件をもとに、適用可能なEPAを瞬時に検索し、関税削減の可能性を提示します。
たとえば、担当者が「○○の商品をブラジルに輸出したい」と自然言語で質問すると、生成AIが複数のEPAを横断的に照合し、最適な協定と根拠を明示したうえで結果を返答します。
これにより、関税申告における確認作業の省力化、法規対応の正確性向上、意思決定の迅速化といった効果が期待できます。
自動運転・ロボティクスとの連携が進む

ここまで、物流業界が抱える現状の課題を見てきました。次に、2025年現在どのように生成AIが物流DXと融合し、業界変革を後押ししているのかを解説します。
2025年の時点では、自動運転技術と生成AIの連携が次のフェーズに入りつつあります。自動運転技術やロボティクスの進展とあわせて、生成AIが交通状況やスケジュール情報を統合的に可視化し、運行管理者への支援情報を自然言語で提示する試みが一部で進められています。現在は実証段階が中心ですが、将来的には意思決定支援の中核を担う可能性があります。
これにより、自動運転トラックのオペレーションはより安全かつ効率的に進化しています。
一方、倉庫内ではAI搭載のロボティクスが入庫・仕分け・検品作業を自律的にこなし、作業員の口頭指示やチャット指示を生成AIが解釈して動作に変換するインターフェースも登場。これは、現場オペレーションが「人間×AIの共同判断」へと移行していることを示しています。
政府もこの潮流を後押ししており、2024年6月に施行された「物流の効率化及び革新の促進に関する法律(通称:物流効率化推進法)」では、AI・ロボット導入に対する補助金制度や税制優遇策が拡充されました。これにより、中小事業者でも生成AI技術の導入が現実的な選択肢となっています。
なお、生成AIの導入で解決できる具体的な課題や企業の成功事例について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
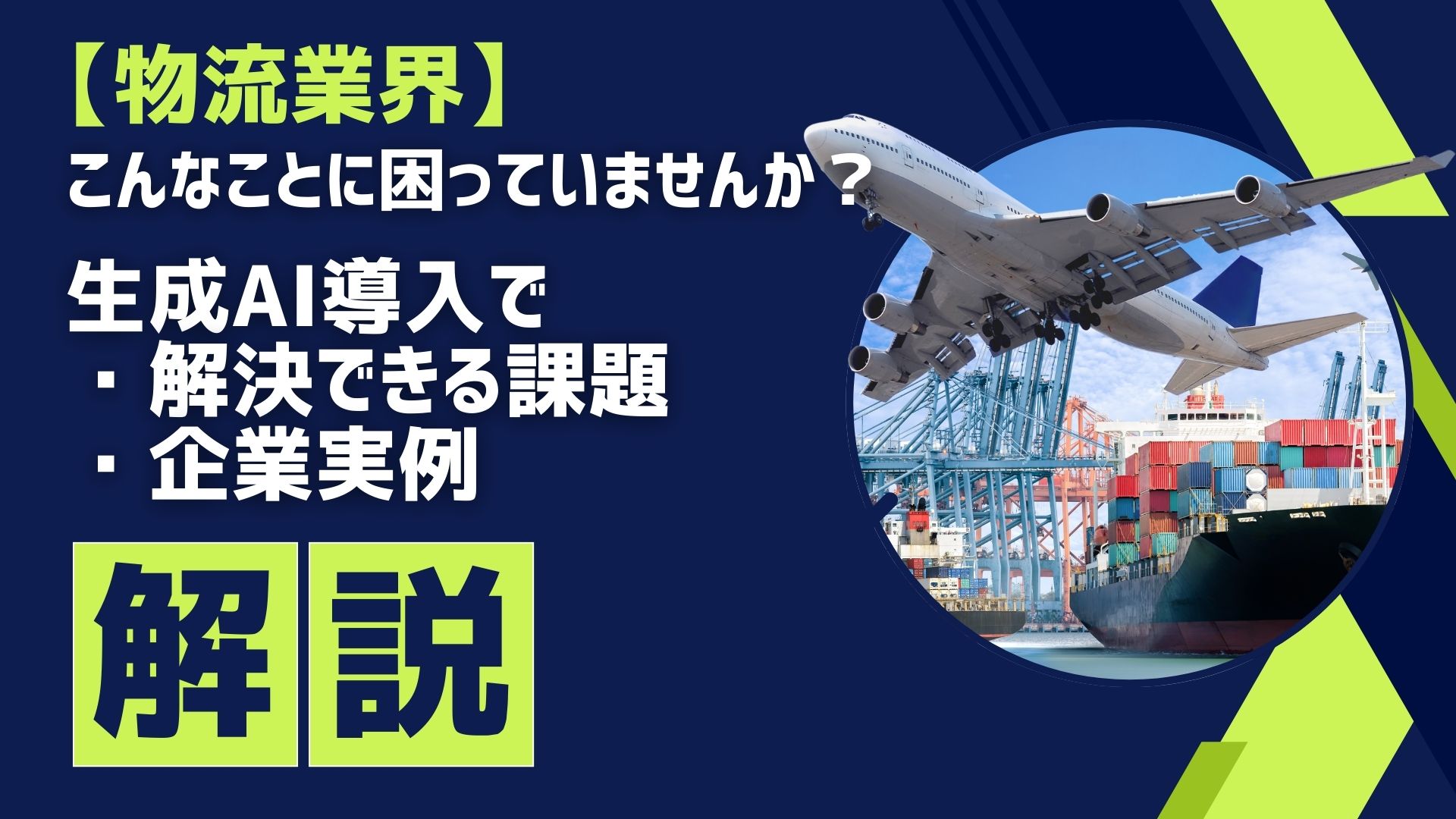
物流業界でのAI導入事例3選
AIの導入事例を3つピックアップし、具体的な事例とその成果をご紹介します。これらの事例から、AIがどのように現場で活用されているのか、また、それが業務プロセスやサービス提供にどのような影響を与えているのか、一緒に見てみましょう!
【ユアサ商事株式会社】生成AIによる配送ルートの最適化で積載効率10%アップを達成!
ユアサ商事株式会社は、自社便の積載率向上とコスト削減を目的としてLoogiaを導入しました。
Loogiaは配車計画をAIで自動作成。ベテランドライバーのノウハウを蓄積して、新人ドライバーでも効率的な配送ルートで運行できるようになるAIツールです。
Loogiaは使いやすく、ドライバーアプリも直感的に操作可能である点が評価されています。実際に導入後、物流センターでは積載率が10%アップ、自社便の配送個口数が月間15%増加したそうです。※4
【株式会社ニチレイロジグループ】賞味期限読み取りAIソリューションを採用して処理速度約2秒を達成!
ニチレイロジグループでは、Automagiが開発した賞味期限読取AIソリューションを採用したことで、物流現場の効率化とDX化が進んだと評価されています。
このソリューションは、画像からAIを用いて賞味期限を自動で読み取るもので、実際の現場での読み取り精度は93%以上、処理速度は約2秒を実現したそうです。※5
賞味期限の読み取りのようなシンプルながらも正確さが求められる作業では、AIのスピードと精度は圧倒的だと言えますね。
【出光興産株式会社】配船計画に生成AIを導入して輸送効率20%アップを達成!
出光興産で、AI技術を用いた海上輸送(配船)計画の実証実験を行いました。
実験では、製油所から油槽所への製品輸送を模擬するシミュレーターとAIによる配船最適化モデルを構築。その結果、輸送効率を最大約20%改善する配船計画を作成できたそうです。※6
使用した深層強化学習技術は、囲碁や将棋などのゲームで世界チャンピオンを破るなどして知られていますが、社会課題への応用はその複雑さから困難とされていました。
しかし、本実験では深層強化学習だけでなく、複数のアルゴリズムを組み合わせることによって最適なルートを出力することに成功したようです。
従来の配船計画は熟練者の経験に大きく依存していたようですが、自動化する試みが成功したことは、技術革新の大きな一歩だと感じます。将来的には、完全自律型の物流システムが実現するかもしれませんね。
物流業界における生成AIについてのよくある質問(FAQ)
なお、生成AIを導入した企業の成功事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
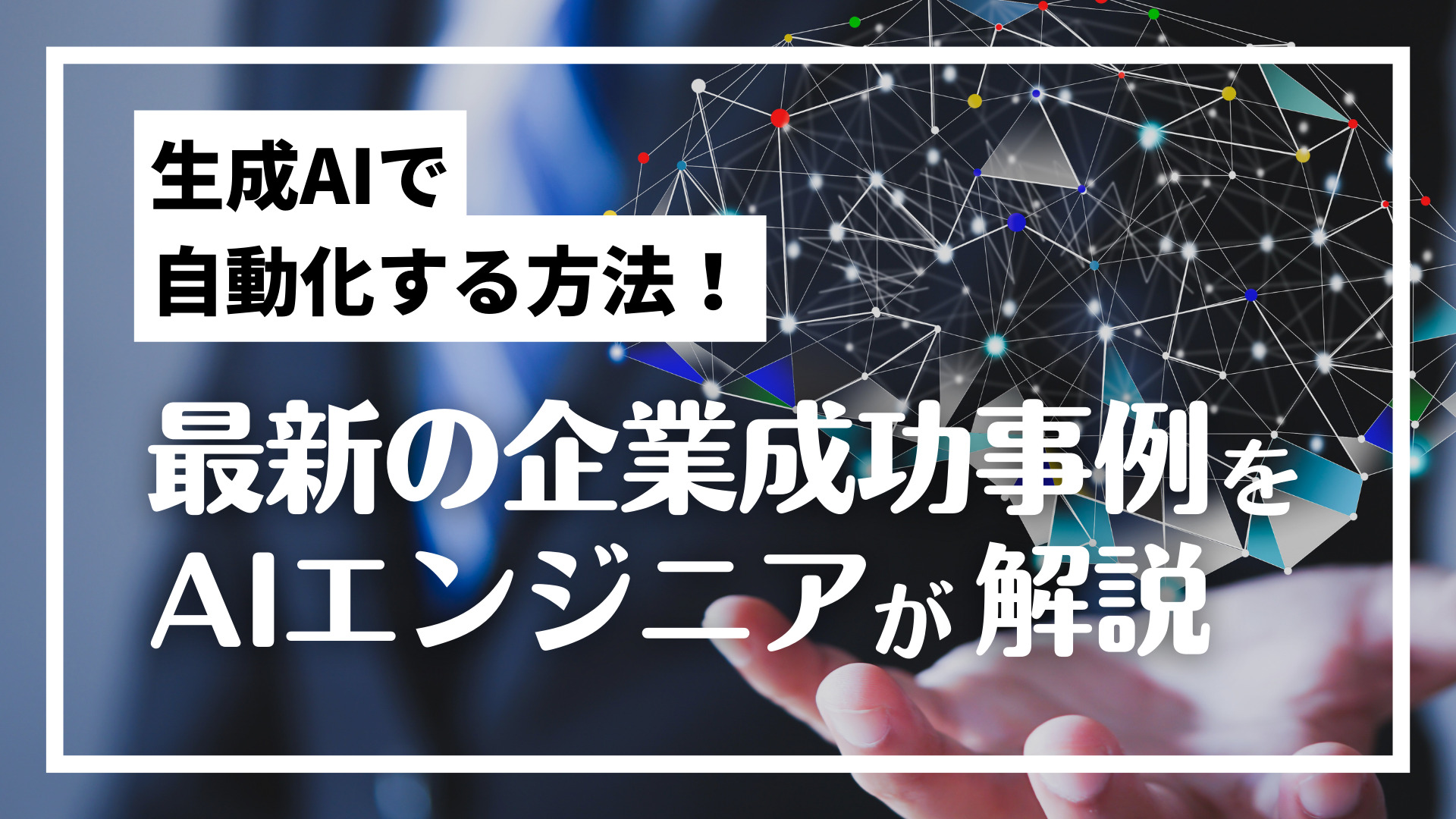
生成AIの力で物流業界に革命を
生成AIの進化と応用が進めば、物流の未来はさらにスマートになります。たとえば、AIが作成した最適ルート計画に基づいて、自動運転トラックやドローンが物資を届ける世界が現実となるでしょう。
こうした移動体の制御はリアルタイムAIや強化学習によって担われますが、生成AIはその裏で、配送計画の説明生成やトラブル時のユーザー対応、報告書の自動作成といった「人とAIの橋渡し役」として重要な役割を果たします。人手不足や運送コストといった課題も、AI技術の融合によって大幅に軽減されるはずです。
そして、私たちの想像を超えるスピードで、世界はよりスマートに、よりつながった社会へと進化していくことでしょう。

最後に
いかがだったでしょうか?
物流DXや生成AI活用の最適解を、自社の課題に合わせて具体的に描けるようになります。現場と経営をつなぐ実践的な活用ポイントを、貴社向けに整理してお伝えします。
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。
︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。
- ※1:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
- ※2:https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331005/20230331005.html
- ※3:https://www.stat.go.jp/data/roudou/2.html
- ※4:https://loogia.jp/cases/yuasa/
- ※5:https://www.automagi.jp/news/insight-ai_pressrelease20200408/
- ※6:https://www.idemitsu.com/jp/news/2020/200630_1.html

【監修者】田村 洋樹
株式会社WEELの代表取締役として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。
これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。