一般的にコイントスは「裏と表が出る確率は五分五分」だと考えられています。
そのためコイントスは、サッカーやアメフトなどのスポーツでも、どちらが先攻かを決めるフェアな方法として利用されます。
こうした確率は、途方もない回数を繰り返した場合に現れる傾向だと言われています。
しかし世の中には様々な硬貨があり、いろんな投げ方をする人たちがいます。現実で本当に途方もない回数投げたときに、どうなるのかはまだ誰も検証してはいません。
そこで、オランダのアムステルダム大学(University of Amsterdam)に所属するフランチシェク・バルトシュ氏ら研究チームは、さまざまな種類の硬貨とトスを行う参加者を集めて実に35万757回ものコイントスを行う実験を実施しました。
もし本当にコイントスが公平ならば、これだけの回数を繰り返した場合、表と裏の出る確率は50%に限りなく近似するはずです。
果たして結果はどうなったのでしょうか?
この実験の詳細は、2023年10月10日付でプレプリントサーバ『arXix』にて報告されています。
目次
- コイントスの確率の微妙な偏りを追求する人々
- 35万回以上のコイントスが「弾く前と同じ面が出やすい」ことを証明
コイントスの確率の微妙な偏りを追求する人々

コイン表面の刻印や厚さの違いを考えると、コイントスの確率には微妙な偏りがあると考えられます。
もちろん一般的には、それら微妙な差は無視されており、「コイントスの結果は五分五分」だと捉えられています。
しかし一部の科学者たちは、それら微妙な差を追求したかったようです。
例えば2007年には、アメリカの数学者ペルシ・ディアコニス率いる研究チームがコインを弾くプロセスを分析しています。
彼らは高速度写真に基づいて物理パラメータを測定し、次の結論に達しました。
「コインを弾く前と同じ面が出る確率は約51%である」
つまり、コインの「表側」を上に向けてコイントスすると「表側」が出る確率がやや高く、「裏側」を上に向けた場合は「裏側」が出る確率がやや高いというのです。
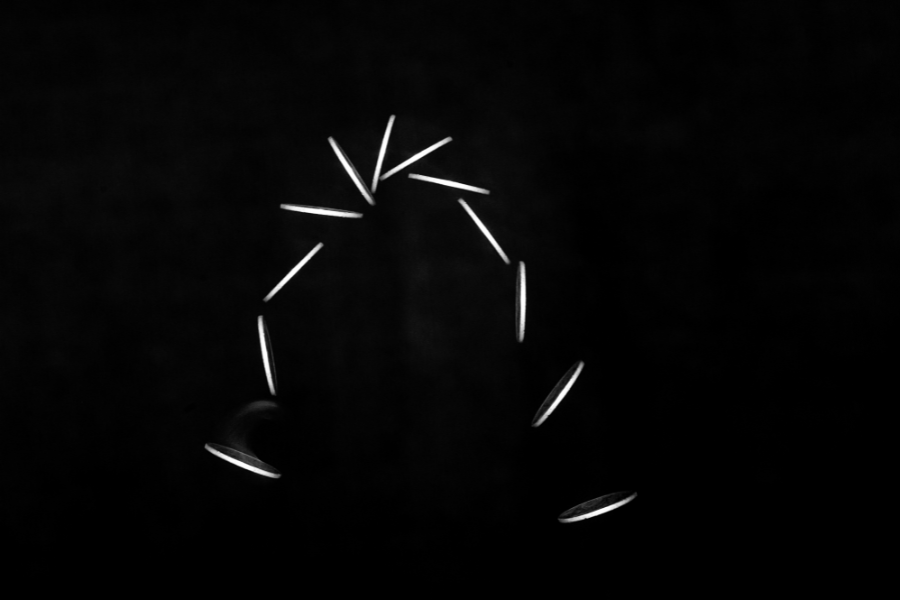
この結果を受けて、多くの人は「やはり誤差レベルだ」と言うでしょう。
「五分五分ではないようだけど、これくらいだったら特に気にしないし、確かめる必要もない」と考える人は多いかもしれません。
しかし、近年流行しているソーシャルゲームのガチャではSSRとされる希少な景品の排出率が1%未満に設定されており、これを小数点単位で変更されてもかなり排出率に影響することを実感している人は多いでしょう。
十分な公平性が必要とされる世界では、1%の確率のズレはかなり無視できない数字です。
そのためコイントスの確率について、十分な回数で検証し表裏の出る正確な確率を「何とかして確かめたい」という猛者たちがあらわれました。
アムステルダム大学のバルトシュ氏率いるヨーロッパ中の研究者たちが、実際にコイントスして結果に偏りがあるのか確かめたのです。
35万回以上のコイントスが「弾く前と同じ面が出やすい」ことを証明
今回の実験では46カ国で鋳造されたコインが使用され、48人がかりで、合計35万757回ものコイントスが行われました。
「参加者たちがひたすらコイントスし続ける」様子は、YouTubeで公開されているため、時間がある人はチェックしてみると良いでしょう。
動画の中では皆が黙々とコインを弾いており、後ろの焚火の映像とも相まって、まるで何かの儀式のようです。
そして狂気のコイントス実験の結果、確率はやはり五分五分ではないことが明らかになりました。
コインを弾く前と同じ面になる確率は50.8%だったのです。
この結果は、数学者ディアコニス氏の2007年の研究結果と一致しています。
コイントスにはほんの僅かな偏りがあることを証明したのです。

では、この事実を知っていることで、私たちにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか。
バルトシュ氏は、次のように述べています。
「コイントスの結果に1ドルを賭けて(つまり参加費1ドルで負ければ没収、勝てば2ドル獲得)、その賭けを1000回繰り返した場合、平均して19ドル稼げます」
1回だけの勝負だと負ける可能性も高いですが、何百回以上もの複数回の勝負であればこの僅かな差がじわじわと響いてきます。
賭け金が大きければそれだけ利益も大きくなるため(例えば1000ドル賭けた勝負なら1万9000ドル:約280万円の利益)、いくらか夢があるように思えるかもしれません。
この事実を知ったあなたは、今後コイントスする際には、コインが弾かれる前にどちらが上を向いているかをチェックし、それと同じ側を選べば有利になるはずです。
ただ実物のコインを使ったコイントス・ギャンブルの勝負に1000回も連続で乗ってくれる人はいないでしょうが。

また今回の実験は、様々な人と硬貨で実施しているため、(現実の状況には近いかもしれませんが)条件にばらつきがあることを考慮すべきです。
実際研究チームは、コイントスの仕方と結果は人によってばらつきがあり、同じ面が出やすい人もいれば、全くその傾向が無い人もいたことを指摘しています。
とはいえ、数学的に証明されていた理論を、実際実験して再現できたというのは重要な事実でしょう。
多くの人たちは、このような手間のかかる実験をわざわざやることの意義に疑問を持つかもしれません。
しかし理論的な予測は理想的な条件で計算された結果であって、現実どうように振る舞うのかは実際やってみなければわかりません。
物理学者たちは常に、理論の予測が複雑な要素の絡む現実で試しても通用するかどうかに興味を持っています。
そこが理論物理学者と実験物理学者の違いでもあり、物理学は理論と実験の2つの結果が一致して初めて事実と認められます。
コイントスは現実では様々な人達が様々な種類のコインを使って行うものであり、投げ方のクセやコインの形状によってバラつきが生まれます。
その上で現実でどのような結果が見られるのかを、非常に多くのデータを取って検証することは、一見バカバカしいように見えても重要な実験と言えるでしょう。
次回私たちが参加するコイントスに偏りがあるかどうかは、誰にも分かりません。しかしどうしても負けたくない勝負では、今回の報告を気に留めておく価値はあるかもしれません。
今後は、ぜひ弾かれる前のコインに注目してみてください。
記事に加筆修正を行いました。
参考文献
Coin Tosses Are Not 50/50: Scientists Toss 350,757 Coins And Prove Old Theory
https://www.iflscience.com/coin-tosses-are-not-5050-scientists-toss-350757-coins-and-prove-old-theory-71047
Flipped coins found not to be as fair as thought
https://phys.org/news/2023-10-flipped-coins-fair-thought.html
元論文
Fair coins tend to land on the same side they started: Evidence from 350,757 flips
https://arxiv.org/abs/2310.04153
ライター
大倉康弘: 得意なジャンルはテクノロジー系。機械構造・生物構造・社会構造など構造を把握するのが好き。科学的で不思議なおもちゃにも目がない。趣味は読書で、読み始めたら朝になってるタイプ。
編集者
ナゾロジー 編集部


