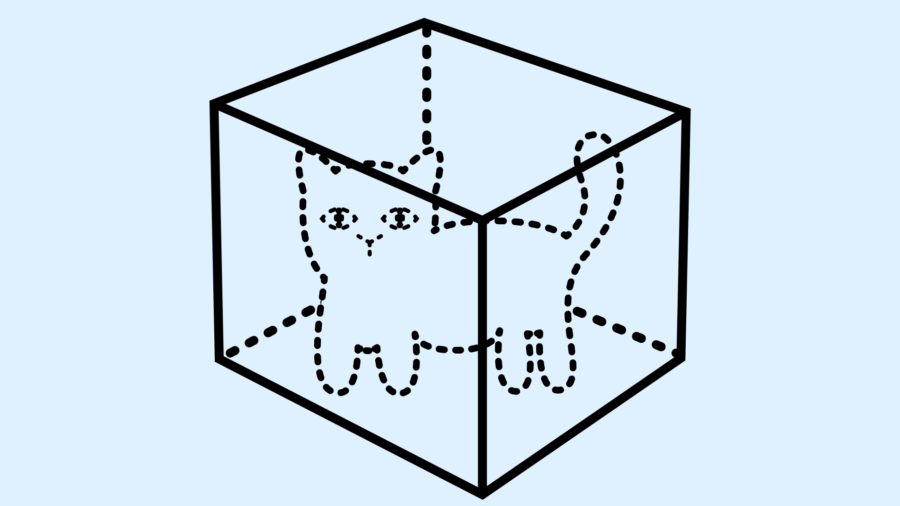量子力学の世界にたびたび登場する「シュレディンガーの猫」は、“生きている”とも“死んでいる”とも言えない不思議な重ね合わせ状態として知られています。
ところがオーストリアのインスブルック大学(UIBK)で行われた研究によって、その猫が「熱」を帯びた状態にまで広がりを見せるという驚くべき結果が報告されました。
これまで、量子干渉を観測するには徹底した冷却で不純物を減らすことが必須とされてきましたが、実験装置を極低温に維持したまま外部から雑音を注入し、見かけ上“熱い”混合状態を作り出すことでシュレディンガーの猫を生成できる可能性が示されたのです。
一体、どうやって熱いシュレーディンガーの猫をつくり出したのでしょうか。
研究内容の詳細は『Science Advances』にて発表されました。
目次
- 極低温猫の時代は終わった?量子の重ね合わせに潜む温度問題
- 「熱いシュレーディンガーの猫」生成プロジェクト
極低温猫の時代は終わった?量子の重ね合わせに潜む温度問題
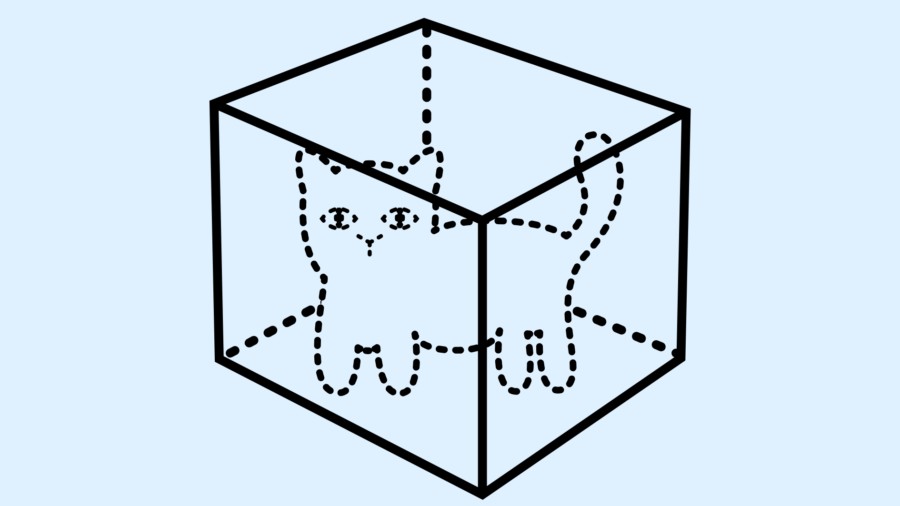
量子力学の世界において、「シュレディンガーの猫」といえば、生きているとも死んでいるとも言えない不思議な両義的存在として有名です。
想像の中の箱を開けると、猫は同時に両方の状態にあるという――どう考えても常識に反する設定が、なぜか理論的には成り立ってしまうことが、私たちの直感を大きく揺さぶってきました。
ところが、実際の実験でこの“猫状態”を再現しようとすると、どうしても猛烈に冷却しなければならないのが従来の常識でした。
ほんのわずかの温度上昇やノイズがあるだけで、せっかくの量子干渉がかき消されてしまうからです。
たとえるなら、とても繊細な砂の芸術作品を、あらゆる振動や風から必死に守り続けるようなイメージでしょう。
しかしそもそも、シュレディンガーのオリジナルな発想の中での猫は“普通の動物”です。
体温があって、外界の揺らぎをもろに受ける、いわゆる生々しい“温かみ”を持つ存在として描かれています。
それにもかかわらず、これまでの実験が狙ってきたのは温度や雑音を極限まで下げた“冷たい猫”でした。
これは仕方のないことでもあります。
量子の干渉現象はちょっとした熱エネルギーや環境の乱れですぐに壊れてしまうというのが、長い間の定説だったからです。
あたかも冷凍庫の扉をうっかり開けっぱなしにするとアイスクリームがすぐ溶けてしまうように、ちょっとでも熱が入り込むと量子の面白さが台無しになる――誰もがそう信じていました。
ところが近年、わざわざ冷やしこまなくとも、熱や雑音を抱えたままでも量子力学特有の干渉を引き起こせるはずだという議論が、研究者の間で盛んに交わされるようになりました。
そこで今回の研究では、実験装置そのものは約30ミリケルビンという極低温に保ちながらも、外部から雑音を注入して見かけ上“熱い”シュレディンガーの猫を生成できるか調べることにしました。
「熱いシュレーディンガーの猫」生成プロジェクト

熱いシュレーディンガーの猫は作れるのか。
謎を解明すべく研究者のとった手段はかなり大胆でした。
ふつうなら、ちょっとでも雑音を減らすためにキャビティ(共振器)をとことん冷やしておきたいところを、あえてその“冷やし”を妨げる形で雑音を注入し、「温かい状態」から重ね合わせを生み出そうとしたのです。
方法はおおまかに、次のステップで説明できます。
まずマイクロ波共振器に熱っぽい(=雑音が多い)状態を用意します。
このままだと量子干渉なんてすぐ壊れてしまいそうですが、研究者たちはトランスモン量子ビットという特殊な素子をうまく使って、この“熱の入った”状態を左右に分けるような操作を行いました。
そして最後に、その2つの分かれた状態を重ね合わせるような仕組みを使うことで、猫が「生きていて、死んでいて、しかも熱い」という不思議な状態をつくり出したわけです。
結果、「本当に熱い状態でも、ちゃんと量子的干渉が起きている」という証拠がつかめました。
量子力学ではWigner関数という方法で状態を可視化できるのですが、熱雑音を抱えたはずの状態がはっきりと負の値(干渉パターン)を示したのです。
これは今まで「熱があると干渉は壊れる」と信じられてきた常識を大きく揺るがす発見と言えます。
もし本当に熱があっても重ね合わせを維持できるなら、実験装置を極低温にしなくてはいけない制約がある程度ゆるみます。
そのおかげで、もっと幅広いシステムでも量子効果を利用できるかもしれません。
もちろん、まだまだ課題は残ります。
熱雑音を取り除かない分、干渉を維持できる時間の長さや制御の精度など、より詳細な検証が必要になるでしょう。
それでも今回の結果は、量子の世界において「必ず冷却が必須」という一種の固定観念を揺さぶりました。
量子的な干渉現象が、実は私たちが考えていたよりも“たくましい”可能性を示唆しているのです。
今後は、他の物理系やさらなる高温領域でも同様の実験が行われることで、シュレディンガーの猫にまつわるパラドックスがいよいよ“熱を帯びた”まま表舞台に立ちそうです。
元論文
Hot Schrödinger cat states
https://doi.org/10.1126/sciadv.adr4492
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部