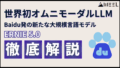夏が「暑すぎ」て、地球の気候変動のヤバさを感じている人は多いでしょう。
けれどその暑さは、地面の上だけの話ではありません。
ブラジル北部アマゾン川流域のテフェ湖(Lake Tefé)で、2023年秋に数百頭もの淡水イルカが一斉に命を落とすという衝撃的な事件が起きました。
湖面にはピンク色のアマゾンカワイルカや灰色のトゥクシ(アメマス)が次々と浮かび上がり、地元の人々や研究者が呆然と立ち尽くしたといいます。
当初はウイルスや水質汚染などさまざまな可能性が取り沙汰されましたが、調査が進むにつれ、湖の一部では人でさえ長時間浸かっているのはキツイ41℃という異常な水温が記録されていたことが明らかになります。
もはや温泉状態ですが、なぜ湖の水がそこまでの高温に熱せられたのでしょうか?
その謎を解くために、ブラジルのマミラウア研究所(英:Mamirauá Institute for Sustainable Development/葡:Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá)を中心とする国際研究チームは、現地観測と衛星データを組み合わせて原因の特定に挑みました。
この研究の詳細は、2025年11月付けで科学雑誌『Science』に掲載されています。
目次
- なぜ湖は温泉状態になったのか?
- 湖でイルカたちの死骸発見が6週間にわたって続いた
なぜ湖は温泉状態になったのか?
研究者たちはまず、「なぜテフェ湖の水温がここまで上昇したのか」「それは偶然なのか、それとも気候変動の兆候なのか」を確かめるため、現地での精密観測を行いました。
アマゾン流域はもともと高温多湿で日射も強い地域です。
しかし通常であれば、昼に温まった湖の表面は夜のあいだに冷やされ、熱が空気中に逃げることで湖全体の温度が安定します。そのため、日中がいくら暑くても、湖全体が“お湯”のように熱くなることはありません。
ところが近年、干ばつの影響で湖の水位が下がり、水深が浅くなっていました。浅くなると太陽光が湖底まで届きやすくなり、熱が湖全体にすぐ伝わってしまいます。
さらに、この干ばつで湖底の泥が舞い上がって水が濁っていたため、太陽光を効率よく吸収しやすい状態になっていました。
加えて、2023年は晴天が続き、風も弱まっていました。風が少ないと水面からの蒸発や熱の放出が進まず、夜間の冷却もほとんど効かなくなります。昼に受けた太陽の熱が夜にリセットされず、翌日に持ち越されて積み重なる、というサイクルが何日も続いていたのです。
2023年の事例では、雲のない日が11日間続いたと報じられており、その結果、湖の水温は数十日掛けて40度近くに達し、淡水生物の生存限界を大きく超える状態になったと予想されるのです。
チームはアマゾン各地の湖で、水温、風速、日射量、水深、濁度を高精度センサーで測定しました。とくに水深2メートル前後の湖では、昼間の水温が急上昇し、夜になっても十分に冷えきらない状態が続いていました。
それでも、昼と夜の温度変動は最大13℃に達しており、この激しい水温の変動は、湖の生物にとって極めて過酷な状況となっていました。
湖でイルカたちの死骸発見が6週間にわたって続いた
研究によると、アマゾン川流域のテフェ湖(Lake Tefé)では、この異常な高温によって少なくとも約209頭の淡水イルカが死亡したと報告されています。その死骸は約6週間にわたって発見が続き、現地の研究者たちは「過去に例のない生態系の危機」と指摘しています。
研究チームが観測した中央アマゾン10の湖のうち5か所で昼間の水温が37度を超え、最高41度に達していました。
これは人であっても長く入浴し続けることは辛い温度で、淡水生物の生存限界を超えています。
夜間も十分に熱は逃がせず、湖全体が昼間の熱を抱え込んだまま“サウナ状態”となっていました。
イルカや魚類は限られた温度範囲でしか生きられず、41度という水温は体内の酵素反応や呼吸機能を破壊します。さらに、水温が上がると水に溶け込む酸素(溶存酸素量)が急激に減り、「熱くて息ができない」環境になります。
研究者たちは、テフェ湖での大量死はこの「高温」「低酸素」「浅い水深」という三つの条件が重なった結果だと指摘しています。
魚やイルカは涼しい深場に逃げようとしても、湖が浅いため避難できず、数日間続いた熱波の中で次々と力尽きていったと考えられます。
研究では、1990年から2023年までに過去30年以上の衛星データを解析した結果、アマゾン流域の湖では平均水温が10年ごとに約0.6℃ずつ上昇していることが明らかになりました。
これは、今回の高温が単なる一時的な異常ではなく、長期的な温暖化傾向の上に生じた現象であることを示しています。つまり、アマゾンの湖はすでに「慢性的に熱くなりやすい状態」に変わりつつあったのです。
研究チームは、この現象はアマゾンに限らず世界各地の浅い湖や湿地帯で、今後も同様の「水中の熱波」が頻発するおそれがあり、魚類・水鳥・両生類など多くの生物に影響を及ぼす可能性があると警鐘を鳴らしています。
確かに、日本でもこの条件を満たしやすい田んぼで似たような問題が起きていることが指摘されているため、遠いアマゾンの話では済まないかもしれません。
また、水温の上昇に伴って有害藻類の増殖や病原体の活性化が進む危険もあります。
研究者たちは、こうした異常高温がどの地域でどの頻度で発生するかを予測するため、モデルの改良と長期モニタリングの強化を提案しています。
さらに、現地の保全策としては、湖水の深さや水路の連結性を維持すること、湖岸の植生を回復して日射を和らげること、異常高温の早期警戒と避難体制を整えることなどが検討されています。
どれも小さな取り組みのように見えますが、生態系を守るためには欠かせない対策です。
私たちが感じた“この夏の暑さ”は、陸上だけでなく湖や川の中にも及んでいます。
アマゾンの湖で起きた悲劇は、気候変動がどれほど深く自然界に浸透しているかを示す警鐘です。
今後は、人間の暮らしと同じように、水中の命を守る視点を持つことが求められています。
元論文
Extreme warming of Amazon waters in a changing climate
https://doi.org/10.1126/science.adr4029
ライター
相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。
編集者
ナゾロジー 編集部