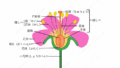夜中に何度も息が止まり、朝起きても疲れが抜けない。そんな「睡眠時無呼吸症候群」は、実は身近な病気です。
これは大きないびきの原因でもあり、日中の強い眠気で仕事や運転に支障が出す要因にもなります。
本格的な治療には専用の機器を使った「持続陽圧呼吸療法(CPAP)」が必要ですが、これは装着感や音が気になって続けられないという声も少なくありません。
ところが最近、インド・ジャイプールにあるエターナル・ハート医療研究センター(Eternal Heart Care Centre and Research Institute)の研究チームが、驚きの代替法を検証しました。彼らはなんと「法螺貝を吹く」ことが呼吸筋トレーニングとなり、睡眠時無呼吸症候群の症状を改善する可能性があるというのです。
この研究の詳細は、2025年8月に科学雑誌『ERJ Open Research』に掲載されました。
目次
- 眠りを邪魔する“静かな病気”と、その意外な改善法
- 法螺貝がもたらした眠りの変化と、その意味
眠りを邪魔する“静かな病気”と、その意外な改善法
イビキがうるさい、日中に眠気が強い、そんな人は「睡眠時無呼吸症候群」という病気の可能性があります。
この病気は、眠っている間にのどの奥がふさがってしまい、呼吸が何度も止まってしまいます。息が止まると血液の酸素が減り、脳が何度も目を覚ますため、熟睡できません。その結果、日中に強い眠気が出たり、集中力が落ちたり、さらには高血圧や心臓病の危険も高まります。
治療としては、就寝中にマスクをつけて空気を送り込み、気道を開いたまま保つ「CPAP療法」がよく使われます。ただこれは効果は高いのですが、気軽に利用できるものではなく、マスクのつけ心地や機械の音が気になって、続けられない人も多いのです。
機材の貸出が必要なため、そもそも軽症や中等度の場合はCPAPが処方されないこともあります。
こうした事情から、もっと手軽で続けやすい方法が求められてきました。
近年の研究では、眠っている間に気道がふさがるのを防ぐため、のどや口周りの筋肉を鍛える方法が提案されています。
その中で注目を集めたのが、オーストラリアの先住民が伝統的に演奏するディジュリドゥという管楽器が、吹く動作でのどの奥の筋肉を強く使うため、睡眠時無呼吸症候群の改善に効果が見られるという報告です。
ディジュリドゥは珍しい楽器ですが、この演奏者の中に「以前よりイビキが減った」「眠りが深くなった」と話す人がいるこを知った医師が広く調査してみたところ、睡眠時無呼吸症候群の改善と相関が発見されたというものです。

同様に、口やのどの筋肉を鍛える体操でも改善が見られています。いずれも、筋肉を強化して眠っている間に気道がつぶれにくくすることが狙いです。
そこでインドの研究チームが同様の効果があるのではないかと目をつけたのが、古くから宗教儀式や合図に使われてきた「法螺貝」です。
強く息を吹き込むこの動作は、のどから胸の奥までの呼吸筋を一度に使うため、筋力アップの効果が期待できます。さらに、音を出すときの振動が鼻やのどに伝わり、呼吸に関わる部分の働きを高める可能性もあります。
今回の研究では、中等度の患者38人をランダムに2つのグループに分け、一方は法螺貝を吹き、もう一方は深呼吸を6か月間続けてもらいました。法螺貝グループは、15分間の練習を週5日、自宅で行い、毎月通院して吹き方の確認を受けました。
眠気の強さ、睡眠の質、そして睡眠中に呼吸が止まる回数を調べ、開始前と6か月後を比べました。こうして、「伝統楽器での呼吸トレーニング」が本当に役に立つのかを確かめる挑戦が始まったのです。
法螺貝がもたらした眠りの変化と、その意味
研究では日中の眠気を点数化する“エプワース眠気尺度”というものを用いて、眠気を数値化して法螺貝を用いた治療効果を調査しました。
結果はトレーニング開始から6カ月ではっきりと表れました。
法螺貝グループでは、日中の眠気を示すスコアが平均14.6から9.6に下がり、約3分の1も改善しました。深呼吸グループはほとんど変化がなく、差は歴然でした。
睡眠の質も向上し、法螺貝グループではスコアが1.8ポイント改善。数字が低いほど質が良いことを示すため、眠りの深さや連続性が良くなったと考えられます。一方、深呼吸グループは改善が見られませんでした。
さらに、睡眠1時間あたりの呼吸の止まりやすさも減りました。法螺貝グループでは平均で4回以上少なくなり、特に夢を見る時間帯(レム睡眠)での改善が目立ちました。この時間帯は心臓や脳に負担がかかりやすく、改善は将来的な健康リスク低下にもつながると考えられます。

面白いことに、このトレーニングを行った参加者は首回りが平均1センチ細くなっていました。首回りが細くなると、気道が広がりやすくなり夜間の酸素濃度も改善されます。酸素の状態が改善することは、心臓や血管への負担を減らす意味でも重要です。
研究チームは、この効果は「のどや呼吸筋の力がついたこと」が大きいと見ています。法螺貝吹奏は息を長く強く吐き続けるため、口やのどの奥の筋肉から胸の筋肉まで幅広く鍛えることができます。その結果、眠っている間の気道の閉じやすさが減り、呼吸が安定したと考えられます。
もちろん、この結果は1つの施設で行われた小規模な試験のものです。より多くの人や地域で再検証する必要があり、訓練をやめた後どれくらい長く効果が続くのかも分かっていません。また、一般の人がこれを真似する場合にどう続けてもらうか、正しい吹き方をどう広めるかも課題です。
それでも、この研究は「楽器を吹く」というユニークな行為が健康に役立つ可能性を示しました。
特別な機械に頼らず、自宅で続けられる習慣が、ぐっすり眠るための新しい選択肢になり得るとしたら、それは非常に有効な事実です。
法螺貝を吹くと言ってもなかなか簡単に真似は出来ないでしょうが、長く強く息を吹くという行為が喉を鍛えたり、首周りを補足し、睡眠中の呼吸を安定させるという知見が深まっていけば、今後もっと実施しやすいトレーニングが色々と登場するかもしれません。
元論文
Efficacy of blowing shankh on moderate sleep apnea: a randomised control trial
https://doi.org/10.1183/23120541.00258-2025
ライター
相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。
編集者
ナゾロジー 編集部