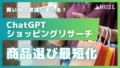日本のアニメ監督、宮崎駿氏の作品には、深い森やその奥で静かに息づく妖精のような生き物がたびたび登場します。
そんな“ジブリ的な世界観と作品”に敬意を示し、新種のヤマタニシに「宮崎駿」氏の名前が用いられました。
はるかインドの山あいの森で本当に見つかったことが報告されています。
インドの野生動物保護団体「Thackeray Wildlife Foundation」 を中心とする国際チームは、西ガーツ山脈のティラリ森林で、殻に細かい毛を生やす陸生ヤマタニシの新種を発見しました。
このヤマタニシには、宮崎駿氏の名前にちなんだ学名「Lagocheilus hayaomiyazakii sp. nov.」が与えられています。
この研究成果は、2025年10月14日付の『Journal of Conchology』(PDF)に掲載されました。
目次
- 宮崎駿氏に称える名前!?新種の毛深いヤマタニシ「Lagocheilus hayaomiyazakii」
- 新種のヤマタニシが見つかった経緯は?
宮崎駿氏に称える名前!?新種の毛深いヤマタニシ「Lagocheilus hayaomiyazakii」

今回見つかった新種の正式な学名は、Lagocheilus hayaomiyazakii(ラゴケイルス・ハヤオミヤザキ)です。
最大の特徴は、殻の表面に生えた多数の「毛」です。
殻のいちばん外側をおおう薄い層である外皮が糸のように伸びて、毛のような突起をつくっているのです。
長いものは0.6ミリほどに達し、殻全体の高さが4〜5ミリ程度しかないことを考えると、かなり存在感のある毛だといえます。
これらの毛は殻の模様に沿ってらせん状の列になって生えています。
乾燥すると寝てしまったり折れたりしますが、水をかけると元のように立ち上がることも観察されています。
そして殻そのものは、小さくて円錐形をしています。
らせんの頂上部分が少し高く突き出しており、殻の開口部は丸に近い形ですが、殻の内側の壁とくっつく部分に小さな切れ込みがあるのが特徴です。
殻の表面には、太くて間隔の広い輪っか状の溝がよく発達しており、この点も見分けるときのポイントになっています。
では、なぜこのヤマタニシに宮崎駿氏の名前がつけられたのでしょうか。
論文では、種小名 hayaomiyazakii は、「日本の著名なアニメーター・映画監督であり、スタジオジブリの共同創設者でもある宮崎駿氏をたたえるラテン語化した名前であり、アニメーション映画への貢献を記念して命名した」と説明されています。
深い森の中でひっそりと暮らす小さな毛深いヤマタニシという姿は、宮崎作品の中に登場する森の片隅に住む不思議な生き物を思い出させるところがあります。
研究者たちは深い森に潜む不思議な小動物を思わせる毛深いヤマタニシに、森や生命を生き生きと描く宮崎作品を重ねたのかもしれません。
こうしてインド西ガーツの小さなヤマタニシは、日本のアニメ文化と科学をつなぐ存在として名前を刻まれることになりました。
では、この新種はどのようにして発見されたのでしょうか。
新種のヤマタニシが見つかった経緯は?
このヤマタニシが見つかったのは、インド西ガーツ山脈北部です。
標高およそ730メートルの半常緑樹林で、雨量が多く、苔むした岩や落ち葉が地面をおおうような環境で発見されました。
研究チームは、この地域のヤマタニシの多様性を調べるために調査を行い、そこで複数の生きた個体と殻を採集しました。
生きている個体は、モンスーン期にあたる6〜7月の日中の時間帯に、苔の生えた岩の上や木の根元のあたり、落ち葉に囲まれた岩の表面で見つかっています。
殻の色と形が周囲の岩に似ており、さらに泥でよごれていることも多いため、注意深く見ないと見逃してしまうような目立たない存在です。
研究チームはまず、殻の大きさ、形、模様、開口部の構造、殻の毛の有無といった見た目の特徴を詳しく測定し、南インドやスリランカから知られている近縁の Lagocheilus 属の種と比較しました。
その結果、このヤマタニシが新種であることが分かりました。
特に若い個体では殻の表面にたくさんの毛が生えており、この点が他の種との大きな違いになっています。
また、この発見によって Lagocheilus 属の分布が、これまで知られていた場所からおよそ540キロメートル北まで一気に広がることも明らかになりました。
これは、西ガーツ北部のヤマタニシがまだ十分に調べられておらず、今後もさらなる新種が見つかる可能性を示しています。
ちなみに、生物の学名には、形や色の特徴が由来になっているものもあれば、生息地の名前が入っているものもあります。
その一方で、今回のように尊敬する人物や、科学や文化に大きく貢献した人の名前を種小名として使うことも珍しくはありません。
今後、新種Lagocheilus hayaomiyazakiiの名前が使用されるたびに、宮崎駿氏がどれほど偉大なことを成し遂げてきたかも語られることでしょう。
参考文献
Researchers discover new species of hairy snail in Tilari forest region
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolhapur/researchers-discover-new-species-of-hairy-snail-in-tilari-forest-region/articleshow/124587995.cms
元論文
First record of the genus Lagocheilus W.T. Blanford, 1864 (Caenogastropoda: Cyclophoridae) from the northern Western Ghats, India, with the description of L. hayaomiyazakii n. sp.(PDF)
https://doi.org/10.61733/jconch/4557
ライター
矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。
編集者
ナゾロジー 編集部