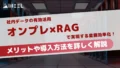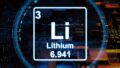オランダのライデン大学(Leiden University)とスイスのテラ・クオンタム(Terra Quantum)による最新の研究で、私たちの宇宙はこれまでに約4回のビッグバン(宇宙の誕生)とビッグクランチ(宇宙の収縮)を繰り返しており、未来に残されたサイクルも最大で10回程度しかない可能性があることが示されました。
もしこの仮説が正しければ、現在およそ138億年とされる宇宙の年齢は、単に現在のサイクルの年齢にすぎず、過去すべてのサイクルを含めた総年齢は約620億年にも及ぶと推測されます。
信じがたい話に思えますが、注目すべきは、これは単なる空想ではなく、次世代の観測で実際に検証できる具体的な予言を伴っている点です。
もしこの周期宇宙論が支持されれば、ビッグバンは一度きりの出来事ではなく、有限回の「輪廻転生」を持つ――そんな世界観に変わるかもしれません。
果たして私たちは繰り返す宇宙の中にいるのでしょうか?
今回は試験的に「ざっくり解説版」を最後のページに入れておきました。
研究内容の詳細は2025年8月19日に『Preprints.org』にて発表されました。
目次
- 私たちは「5度目の宇宙」に生きている?
- 最大であと10回—宇宙の残りサイクル数を予測した方法
- 宇宙が繰り返すなら、私たちはどうなるのか?
私たちは「5度目の宇宙」に生きている?

ひょっとすると、私たちは「5度目の宇宙」に暮らしているのかもしれません。
そんな突拍子もない想像が、最近では現実味を帯びてきました。
時間も空間もビッグバン(最初の大爆発)で始まったと学校で習いますが、宇宙好きなら一度は「ビッグバンの前には何があったのだろう?」と疑問に思ったことがあるでしょう。
実は科学の世界でも、この疑問は長年根強く残っていて、サイクリック宇宙論(宇宙が膨張と収縮を永遠に繰り返すという仮説)が研究されてきました。
これなら「宇宙の始まり」を特別扱いせずに済むため、哲学的にも魅力があります。
近年ではノーベル賞物理学者ロジャー・ペンローズ氏がコンフォーマルサイクリック宇宙(CCC)という、宇宙が無数のサイクル=aeonを繰り返すモデルを提唱しました。
「今の宇宙の前にも別の宇宙があったかもしれない」と示唆され、さらに宇宙背景放射の中に前の宇宙の痕跡を探す研究も報告されています。
ところが、宇宙が繰り返し生まれ変わるという発想には大きな壁がありました。
それはエントロピー(乱雑さの尺度)の問題です。
宇宙が膨張と収縮を繰り返すたびにエントロピーは増え続け、各サイクルは前のサイクルよりも「乱雑」になっていきます。
このため完全に同じ状態に戻る「真の循環」は難しく、100年近く前から「宇宙は繰り返せないのでは?」とも言われてきました。
一度散らかった宇宙は、二度と元通りにならないというイメージです。
最近では、この問題を解決するために「各サイクルで宇宙が極端に膨張しエントロピーを希釈する」という新しいモデルも提案されましたが、それでも「永遠の過去」は作れず、やはり何らかの始まりが必要になると考えられています。
では、今回の研究は何が違うのでしょうか。
研究チームはQMM(Quantum Memory Matrix:量子メモリ行列)という全く新しい理論枠組みでこの難題に挑みました。
QMMでは、時空そのものを無数の小さな「メモリセル」の集合体と考えます。
各セルは素粒子の通過や重力・電磁気力など、あらゆる相互作用の情報を記録する装置のように働き、宇宙全体が巨大なメモリーバンク(記憶庫)として機能するとされます。
宇宙は進化するだけでなく「記憶する」存在だというわけです。
ただし、各セルには情報を書き込める容量が限られています。
物質が崩壊する際に発する量子情報(エントロピー)がセルに刻まれ、情報の書き込みが限界に達した領域では、空間がリセットされて新たな膨張が始まる(ビッグバウンス)と考えられます。
つまり宇宙はサイクルごとに「情報の帳簿」に記録を残しながら、物理的な状態は初期化して再スタートするのです。
この仕組みでは熱的エントロピーは各サイクルで局所的に減らせる一方で、情報(インプリント・エントロピー)は単調に増加し続けるため、宇宙に「時間の矢」が生まれると説明されています。
まるで宇宙が自分の履歴を書き留める日記を持っているようなイメージですが、この大胆な発想によって、長年「エントロピーの壁」と呼ばれてきた問題を乗り越えようとしているのです。
この量子メモリ行列(QMM)モデルが解き明かそうとする問いは、大胆でありながらシンプルです。
「宇宙はこれまで何回バウンス(収縮と再膨張)を経験したのか?」
「この宇宙にはあと何回サイクルが残されているのか?」
そして「すべてのサイクルを通算した“宇宙の年齢”はどれくらいになるのか?」
普通なら測りようがないと思われるこの壮大な疑問に対し、研究チームは巧みなアプローチで答えに挑んでいます。
最大であと10回—宇宙の残りサイクル数を予測した方法

では、研究チームはどうやって「宇宙のサイクル数」を数え上げたのでしょうか?
鍵となるのは、宇宙背景放射や銀河分布など、現在の宇宙に刻まれた情報から「宇宙の履歴」を逆算するという発想です。
QMMモデルでは、各サイクルで一定量の情報(インプリント・エントロピー)が宇宙に書き込まれます。
そのため、今の宇宙に蓄積された情報量を調べれば、「これまで何回サイクルを経たか」が推定できることになります。
研究チームは、宇宙マイクロ波背景放射の精密観測、バリオン音響振動、宇宙年代測定、銀河の大規模構造データなど最新の宇宙観測データから、現在の情報インプリント量を推定しました。
さらに、修正されたフリードマン方程式(宇宙の膨張を支配する方程式にインプリントの効果を加えたもの)を数値的に統合し、過去から未来への宇宙サイクルの推移をシミュレートしました。
その結果、このモデルが現在の宇宙を再現するためには、少なくとも過去に約4回(3.6±0.4回)のサイクルが完了している必要があることがわかりました。
また、ヒルベルト空間セルの有限容量(情報の書き込み限界)まで、あとどれくらい余地があるかを評価すると、理論的な上限では最大約9.7回、実効予測としては約8.5回程度のサイクルが残り得るとされています。
さらに不確定性を含む予測では、宇宙はあと約7.8回の膨張・収縮サイクルを経て「最終サイクル」に達する可能性が示唆されました。
要するに、今の宇宙は「5代目」前後であり、最終的には「およそ12前後のループ」で循環宇宙は終了する計算になります。
残りのサイクルが完了すると、時空の情報容量(エントロピー)が完全に飽和し、それ以上バウンスは起こらなくなります。
つまり、新たなビッグバンが発生しなくなり、宇宙はもはや縮んで再生することなく、ゆっくりと膨張を続ける終幕フェーズに入ると考えられます。
この推定が正しければ、宇宙の「情報的な年齢」は約620億年に達し、現在知られている138億年という年齢はその一部に過ぎないことになります。
モデル上は、無秩序の蓄積ペースなどからこうした値が導き出されており、数字のインパクトに思わず息を呑む内容です。
さらにこの研究では、各サイクル間で「何が引き継がれるか」についても考察されています。
QMMモデルでは、ビッグバンで前の宇宙の痕跡が完全消滅するわけではなく、情報のゆらぎ(インプリント場)として新宇宙に持ち越されるとされます。
簡単に言えば、前の宇宙で蓄積されたゆがみやムラが、次の宇宙のスタート時点に反映されるということです。
シミュレーションによれば、この情報ゆらぎは新生宇宙で過剰密度(情報の井戸)として振る舞い、重力の作用でどんどん成長します。
その結果、一定の臨界値を超えた部分では、原始ブラックホール(PBH)が形成されることが示されました。
特に、ゆらぎスペクトルの傾きパラメータを調整すると、太陽質量程度のPBHが多数できて暗黒物質の候補になり得ることや、さらにスペクトルを青(小スケール強め)にすると月質量級以下のPBHが生成して、宇宙の暗黒物質の大部分を占めるケースもあると報告されています。
興味深いことに、この場合でも現在の観測(重力マイクロレンズ効果による検出制限)に矛盾しない範囲でPBHを作れるとされます。
つまり、「宇宙が何度も繰り返す」という大胆な仮説が、逆に暗黒物質の正体=多数の原始ブラックホールというシンプルな解を導く可能性があるのです。
実際、研究では各サイクルで原始ブラックホール(PBH)が約100万個形成されると予測され、これが蓄積されて宇宙全体で莫大な数のPBH連星合体が起こる計算になります。
またPBHの存在は、宇宙初期(赤方偏移z>10)に予想以上に大きなブラックホールやクエーサーが見つかる問題に対する自然な解決策にもなり得ます。
大質量星の暴走成長なしに説明が難しかった超高赤方偏移のクエーサーも、各サイクルで種PBHがばらまかれると考えれば「思ったより早く巨大小銀河核が存在していてもおかしくない」というわけです。
情報ゆらぎが残る影響は他にもあります。
たとえば、ブラックホールの情報パラドックス(ブラックホールに落ちた情報は消えるのか?)について、このモデルは「情報は消えず、時空そのものに記録される」と主張しています。
ブラックホールが蒸発しても、かつて飲み込んだ物質の情報は周囲の時空セルに刻まれて残るため、パラドックスは解消されるという考え方です。
さらに、このインプリント場(情報ゆらぎ)は宇宙初期のインフレーション後の宇宙にも微妙な痕跡を残し、重力レンズ効果や宇宙背景放射のゆらぎパターンにCMBのスペクトル歪みなどを与える可能性が予測されました。
これらの特徴は、将来の観測ミッション(次世代CMB観測計画や重力波望遠鏡、銀河サーベイ)によって検証可能です。
研究チームは「この仮説は絵空事ではなく、近い将来に実験的なテストが可能だ」と述べています。
総じて今回の結果は、宇宙が有限回のサイクルで終焉を迎える可能性と、その舞台裏で情報がどのような役割を果たしているかを示唆するものでした。
それは同時に、暗黒物質問題や宇宙論上の情報問題への挑戦的な解答でもあります。
宇宙が繰り返すなら、私たちはどうなるのか?

今回の研究は、宇宙論と量子情報理論を結びつける大胆なアプローチによって、「宇宙はいくつサイクルを繰り返せるのか?」という壮大な問いに体系的な定量推定を示しました。
最新モデルによると、私たちの宇宙はすでに約4回のビッグバンとビッグクランチを経験しており、あと8回ほど同じサイクルを繰り返した末に最終的な膨張段階に移行する可能性があります。
この数字は、宇宙が循環しつつも有限の寿命しか許されないかもしれないという点で、非常に刺激的です。
宇宙論の枠組みが変われば、私たちの存在への見方も変わるでしょう。
この研究が正しければ、宇宙は単なる偶然の一度きりの出来事ではなく、情報を蓄積しながら進化するシステムだったことになります。
そうなれば、「なぜこの宇宙に生命が存在するのか」「物理定数はなぜこの値なのか」といった問いも、前のサイクルからの情報継承という観点で議論できるかもしれません。
さらに実利的な面でも、暗黒物質の起源やブラックホール情報の行方といった難問に答えが出ることで、将来的に新しい物理法則やエネルギー源の発見につながる可能性もあります。
例えば原始ブラックホールが暗黒物質なら、その観測や利用法が研究されるでしょうし、ブラックホールから情報を取り出せるなら量子情報技術にブレークスルーをもたらすかもしれません。
実際、QMM理論の一部は量子コンピュータのエラー訂正にも応用できることが示されており、理論物理が情報工学へ寄与するという予想外の成果も生まれています。
研究チームは試験的に量子計算機上で「痕跡演算」を実装し、従来より高精度に量子状態を復元することに成功しました。
このように「宇宙は記憶する」という発想は、純粋理論にとどまらない広がりを持っています。
もっとも、このモデルはあくまで現時点では理論的な仮説です。
観測的に裏付ける証拠はこれから探していく必要があります。
例えば、宇宙背景放射に前サイクル由来の特徴的なパターン(μ歪みなど)が残っているか、重力波バックグラウンドに情報ゆらぎ起源の信号が混じっていないか、といった点は今後数十年で明らかになっていくでしょう。
さらにいえば、この仮説が正しいとしても「最初の宇宙」はどこから来たのかという疑問は依然として残ります。
QMMのアプローチがこの指摘を乗り越えられるかは、今後も専門家の間で議論が続いていくでしょう。
とはいえ、この研究がもたらしたものは大きいといえます。
あえて言うなら、宇宙そのものを「計算する存在」と見立てた発想の勝利でしょう。
宇宙論に情報という概念を持ち込むことで、従来はバラバラに考えられていた問題(宇宙の始まり、暗黒物質、ブラックホール情報など)に一本の筋を通すことに成功したのです。
補足ですが、QMMという考え方は宇宙論だけでなく、量子コンピュータのエラー訂正への応用研究にも登場しています。
QMMの応用研究
実はこのQMMという概念、宇宙論だけでなく量子コンピュータのエラー訂正への応用研究にも登場しています。研究チームは別途、QMMを用いた誤り耐性手法を提案しており、ハードウェアへの実装実験では繰り返し符号との組み合わせで論理量子ビットの忠実度(計算結果の正確さ)が94%に向上したと報告しています(PR段落2)。宇宙の「量子メモリ」発想が地上の量子計算にも応用できるとは興味深いですが、これはあくまでPR情報であり、本記事の宇宙論モデルとは直接の関係はない点にご注意ください。
宇宙の「量子メモリ」という発想が地上の量子計算にも応用できるというのは興味深い話ですが、これはあくまで応用研究の例であり、本記事の宇宙論モデルとは直接の関係はありません。
このような統一的な視点は、今後の宇宙論研究に新たな道を拓く可能性があります。
また論文やデータは公開されており、他の研究者が計算コードやシミュレーション結果を検証できる環境も整っています。
科学の世界では仮説は厳しく試されて初めて評価が定まりますが、この壮大な仮説も例外ではありません。
ビッグバン仮説の「ビッグバン」という言葉も、もともとはこの仮説を揶揄する意味で生まれたという歴史があることも忘れてはいけません。
無限に思える宇宙でさえ有限のサイクルを生きているとしたら、その事実を知ること自体が私たちの宇宙観に新たな深みと謙虚さを与えてくれるでしょう。
元論文
Counting Cosmic Cycles: Past Big Crunches, Future Recurrence Limits, and the Age of the Quantum Memory Matrix Universe
https://www.preprints.org/manuscript/202508.1391/v1
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部