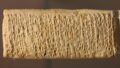暴力によるトラウマは、心の奥底に刻みこまれるだけでなく、私たちの遺伝子にも何らかの“痕跡”を残すのではないか――。
シリアの三世代にわたる難民家族を対象に実施された新しい研究が、その問いに一石を投じました。
アメリカのフロリダ大学(University of Florida)人類学部門を中心とする研究チームによれば、親や祖父母が暴力を体験した際に起こるDNAメチル化(遺伝子の化学的変化)が、子どもや孫世代に引き継がれる可能性を示唆しています。
この見解は決して孤立したものではありません。
ホロコーストやルワンダ虐殺の生存者とその子孫を対象にした先行研究でも、似たようなエピジェネティック変化が見られたとの報告があるのです。
しかしながら、学界では「本当に遺伝的に伝わっているのか?」「伝わる仕組みは何なのか?」といった点をめぐり、議論が続いています。
アイカーン医科大学(マウントサイナイ)の神経科学者、レイチェル・イェフダ氏は「これは、世代を超えたトラウマの生物学的痕跡を調べるための本当に素晴らしい試み」と評価する一方で、「まだ“証明”と呼べる段階にはなく、解釈には慎重さが必要」とも指摘します。
舞台となるシリアでは、40年以上にわたり内戦や政治的迫害などの暴力が途切れたことはありません。
1980年代に行われた市街爆撃や、2011年の紛争激化など、幾度となく繰り返されてきた惨劇が、現地の人々に深い心的外傷を与えてきました。
今回の研究は、こうした複数の暴力期を経て避難を余儀なくされた難民家族のDNAを精密に分析し、世代間で共通するメチル化パターンが存在するかどうかを探っています。
科学界を揺るがすこの発見は、暴力の傷痕が私たちの身体の“設計図”にも書き込まれ、次世代へと受け渡される可能性を問いかけるものです。
果たしてトラウマの記憶は、どのようにして未来へと連鎖し得るのか――本記事では、その最前線に迫ります。
研究内容の詳細は『Scientific Reports』にて発表されました。
目次
- 人間でも暴力体験の遺伝を示唆する研究が増えている
- 暴力はDNAに刻まれるのか? シリア難民が示す世代間のトラウマ遺伝
- トラウマ遺伝の衝撃と限界:私たちは何を学ぶべきか
人間でも暴力体験の遺伝を示唆する研究が増えている

トラウマと呼ばれる心の傷は、しばしば「忘れられない記憶」として語られます。
しかし近年の研究によれば、その“記憶”は脳だけでなく、私たちの遺伝情報を読み取る仕組みにも刻まれている可能性が示唆されています。
こうした考え方を支えるのが、胎児期の環境が将来の疾患リスクや発達に影響を与えるとするDOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)仮説です。
もともとは栄養不足や毒素への曝露などが取り沙汰されてきましたが、暴力や虐待といった心理的ストレスもまた、DNAの「メチル化」という化学的タグを通じて“体に刻まれる”のではないかというわけです。
実際、ホロコーストの生存者やルワンダ虐殺の生存者とその子孫を対象にした研究では、親世代の恐怖体験が子どもの遺伝子上のメチル化パターンに反映されている可能性が報告されています。
DNAの配列自体は変わらなくても、あたかも「ノートに貼られた付箋」のようなメチル化の変更が、遺伝子のオンオフを左右するのです。
ただ、ヒトの受精や妊娠の初期段階では、いったん多くのエピジェネティック修飾が“リセット”されるとされており、「いったいどうやってトラウマの痕跡が次の世代へと渡るのか?」という疑問は長らく残っていました。
動物を使った研究では、母親が極度のストレス下にあると、子ども世代どころか孫世代までも振る舞いや体質に変化が生じるケースがあるといいます。
ごく一部のDNA領域は“リセット”の網をかいくぐるという報告もあり、人間の場合にも同様のメカニズムが存在するのではないかと予想されています。
こうした視点から見ると、シリアの状況はまさに“エピジェネティックの長期的影響”を確かめるのに、ある意味で悲しいほど適した条件をそろえています。
1979年の反乱鎮圧から1982年のHama市攻撃、さらに2011年以降の政情不安と内戦――国全体が四十年以上、ほぼ途切れることなく暴力と恐怖の中にあり、何世代にもわたって家族が避難を余儀なくされてきました。
そんな苦難の歴史をくぐり抜けた人々は、「心の痛み」を超えて、もしかすると「体にこびりつく傷痕」をも抱えているのかもしれません。
そこで今回研究者たちは、シリア難民三世代の家族を対象に、直接的な暴力体験・妊娠期の胎内暴力曝露・祖母の妊娠時期における生殖細胞レベルでの暴力曝露を比較し、DNAメチル化パターンを網羅的に解析することにしました。
暴力はDNAに刻まれるのか? シリア難民が示す世代間のトラウマ遺伝

今回の調査には、シリアからヨルダンへと逃れた三世代の家族48組・合計131名が参加しました。
1980年代に起きた暴力を体験しながら妊娠していた祖母世代、2011年以降の紛争で直接暴力にさらされた母と子ども世代、そして暴力にさらされなかった対照群(16家族)の三つのグループに分けて比較したのが大きな特徴です。
しかも、血液ではなく口腔内の細胞(ほほの内側の粘膜)からDNAを採取したという点もユニークです。
難民キャンプや移動先の地域で、何度も血液を採取するのは難しい場合が多いですが、この方法なら比較的手軽かつ安全に検体を集められます。
研究チームは、そこに含まれるDNAを“くまなく捜査”するように約85万カ所のメチル化パターンを解析し、暴力の経験やタイミング(直接・胎内・生殖細胞レベル)による違いを徹底的に調べました。
結果として、まず見つかったのは“直接暴力を体験した人々”のDNAにおける、いわば「特有の足跡」です。
ここには21もの部位で特徴的なメチル化変化が認められ、子ども世代と母親世代の双方に現れていました。
一方で、1980年代の暴力を目撃した祖母と、その娘、さらに孫にも共通して14カ所の変化が残っていたことも見逃せません。
これは“祖母が妊娠中に感じたストレス”が、まだ受精前の「生殖細胞」にまで影響を与えた可能性を示唆するものです。
興味深いのは、いずれの暴力期を体験していない対照群には、こうした変化が見られなかったという点です。
まるで砂浜に残る足跡のように、特定のDNA領域が「暴力を経験したかどうか」を指し示しているようにも思えます。
また、妊娠期(胎内)曝露については、他の二つのグループほど顕著な差分メチル化は検出されなかったと報告されています。
この点について研究者たちは、「生殖細胞レベル」や「直接暴力」ほどの大きなインパクトが胎内曝露には見られなかった可能性があり、詳細をさらに調べる必要があると指摘しています。
さらに、子ども世代の一部にはエピジェネティック上の“年齢加速”とも言える変化が確認されました。
これは、実際の年齢よりも早く細胞が“老化”しているように見える指標のことで、特に妊娠期に暴力を浴びた母体から生まれた子どもで顕著だったといいます。
こうした細胞レベルの“老化促進”は、将来的な健康リスクやストレス耐性の変化などに結びつく可能性が指摘されており、大きな関心を集めています。
エピジェネティック上の“年齢加速”とは、実際の誕生日で示される年齢よりも、細胞が“老けている”ように見える現象です。
年齢を重ねるにつれて私たちの体内ではさまざまな変化が起こりますが、そのペースが予想より速い人がいる、というイメージです。
いわば、年齢という名のカレンダーを半年早回しにめくっているような状態と考えるとわかりやすいかもしれません。
ではなぜ、その“早回し”が起こるのでしょうか。
ここで関わってくるのが「エピジェネティック(表現型可塑性)」という仕組みです。
DNAの配列自体には変化がなくても、そのDNAにくっつく化学的なタグ――メチル基(メチル化)など――が付いたり外れたりすることで、ある遺伝子が活性化したり、逆に抑え込まれたりします。
こうしたエピジェネティックな変化は、例えるなら本の文章そのもの(DNA配列)は書き換えずに、欄外に付箋やマーカーでメモを書き足すようなもの。
大掃除や衣替えのように、外部環境やストレスによって付箋が増えたり貼り替えられることで、細胞の働きが変化しやすい仕組みなのです。
実際には、エピジェネティックな年齢を測る「エピジェネティッククロック」という方法があり、ここではDNAにおける特定のメチル化箇所を指標にして、“細胞の老化度”を数値化します。
もしこの指標が同じ年齢層の平均より高ければ、「生物学的には実年齢より先に進んでいるかもしれない」と推測されるわけです。
人によっては、過度のストレスや栄養状態、生活習慣などの影響で、この“時計の針”が速く進む場合があります。
逆に、健康的な暮らしや運動習慣が、時計の針をゆっくりにする可能性も報告されています。
エピジェネティックな変化の面白いところは、DNAの配列自体を大掛かりに作り替えることなく(これは進化的には時間がかかる工程です)、比較的短期間で細胞の状態を変えられる点にあります。
いわば、遺伝子レベルの「緊急モード」や「高速モード」が働いて、環境に合わせた素早い対処が可能になるのです。
ところが、この素早い適応がうまく働かない場合や、逆に過剰に働きすぎた場合には、細胞が必要以上に“老化”へと進んでしまうリスクが高まるのではないか――ここに注目することで、私たちはストレスや生活環境がもたらす健康リスクを、従来の“カレンダー年齢”以上に正確に測れるかもしれないと期待されています。
なぜこの研究が革新的なのか?
第一に、多世代にわたる追跡は人間社会では非常に難しく、大規模な家族集団を対象に「直接的・妊娠期・生殖細胞レベル」という異なる暴力曝露を比較した事例はきわめて珍しいからです。
第二に、DNAのメチル化は“リセット”されると考えられてきたのに、祖母が体験したトラウマが娘や孫の世代で同じ部位に刻まれていたことは大きな驚きでした。
これらの結果は、「遺伝子配列が変わるわけではないのに、環境からのシグナルが世代を超えて遺伝のように伝わり得る」という新しい仮説を、より強く支持するものとなっています。
これまで「脳や心理の問題」として捉えられてきたトラウマが、DNAの化学的なタグを通じて次世代に受け継がれていくかもしれない――その可能性を、実証的に示した点こそが、本研究の最も革新的なポイントなのです。
トラウマ遺伝の衝撃と限界:私たちは何を学ぶべきか

今回の研究結果は、暴力によるトラウマが次世代へと受け継がれ得るという考えを、具体的なDNAメチル化の変化として示唆するものです。
とはいえ、この発見がすぐに「トラウマは必ず遺伝する」と断言する根拠になるわけではありません。
たとえば、“祖母の体験した恐怖が孫に伝わる”ことを説明する上で、メチル化による世代間継承が唯一のメカニズムとは限らないのです。
親世代の子育てスタイルや生活環境、社会的影響もまた、子どもの精神状態や体の反応に大きく関わります。
さらに、DNAの配列自体が変化したわけではないため、トラウマの痕跡がどこまで健康や行動に影響を及ぼすのかは、まだ見通せません。
実際、動物実験では「ストレスに強くなる」方向に働く場合があるとも報告されており、メチル化の変化は“悪い結果”だけを意味するわけではありません。
つまり、エピジェネティックな変化は環境への素早い適応策である可能性も否定できないのです。
また、サンプルサイズの限界や、すべての家族が同じ条件で育ったわけではないことを考えると、結果の再現性については今後の研究での検証が不可欠となるでしょう。
比較的少人数の難民コミュニティを対象に行われた本研究は、「大きな謎に挑むための第一歩」という位置づけと見るのが妥当かもしれません。
実際、研究者の中には今回の発見を歓迎しつつも、口腔粘膜以外の組織でも同様の変化が起きるのかや、子孫に及ぶメチル化パターンがどれほどの期間持続するのかなど、多くの疑問点を指摘する声があります。
それでも、本研究が投げかけた問いの重みは小さくありません。
ホロコーストやルワンダ虐殺の事例と照らし合わせても、人間の体は「心が受けた傷」をただの記憶として残すだけではなく、遺伝子レベルの書き込みとして保持している可能性が改めて浮上してきたからです。
私たちがストレスやトラウマと呼ぶものの本質に、まだ未知の領域が広がっていることを示す――そこにこそ、この研究の最大の意義があります。
次に何が起きるのか、私たちの遺伝情報がどのように“環境”と対話しているのかは、これからのさらなる調査と検証が明らかにしていくでしょう。
元論文
Epigenetic signatures of intergenerational exposure to violence in three generations of Syrian refugees
https://doi.org/10.1038/s41598-025-89818-z
Leukocyte Methylomic Imprints of Exposure to the Genocide against the Tutsi in Rwanda: a Pilot Epigenome-Wide Analysis
https://doi.org/10.2217/epi-2021-0310
Influences of Maternal and Paternal PTSD on Epigenetic Regulation of the Glucocorticoid Receptor Gene in Holocaust Survivor Offspring
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13121571
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部