吸血鬼モノの物語ではしばしば、人間の血液は彼らにとって完全な栄養食であると表現されています。
たとえば『人間は摂取した栄養分を血液に乗せて全身に届けるため、血液には必要な全ての栄養分が含まれている』…などなど、ナルホドと思わせるセリフもみられます。
では、人間が人間の血をそのまま主食にすることはできるのでしょうか?
答えから言えば、どうやら「ダメ」なようです。
数滴の血液ならば問題ありませんが、大量の血液を飲んだ場合、最悪死ぬことになるようです。
私たちの体内を流れている血液に、どうして死ぬほどの毒性があるのでしょうか?
目次
- 「血を大量に飲んでも大丈夫?」専門家「ダメみたいです」
- 他人の血は感染症を引き起こす
「血を大量に飲んでも大丈夫?」専門家「ダメみたいです」

人間の体内を流れる血液は、古くからその人物の精力を内包していると考えられていました。
たとえば「血の伯爵夫人」と呼ばれたエリザベート・バートリ(1560~1614年)は、若い娘を殺害して採取した血を浴びることで、若返りを目指したとする逸話が伝えられています。
一方、近年の研究では、血液の内部には細胞の年齢を決定する因子が存在する可能性が示されています。
また運動好きなマウスの血を輸血することで、脳機能がブーストするという興味深い結果も得られています。
さらにオスとメスのマウスの体を縫い合わせた上でメスの子宮をオスの体内に移植し妊娠させた研究では、メスマウスと血液を共有することでオスも妊娠できることが示されました。
ただ、どの場合も、一方のマウスの血液を直接もう一方のマウスの血管に直接流し込むことで効果が発揮されています。
血液を単に浴びたり飲んだりするだけでは、残念ながら若返りや脳機能ブースト、オスで妊娠する効果は得られません。
では、栄養分として血液を飲むことに意味はあるのでしょうか?
さきほどの吸血鬼の主張のとおり、血液に多くの栄養分が含まれているのは確かです。
しかし血液は栄養分を運ぶ以外に、細胞に酸素を届ける役割も担っており、赤血球には酸素をくっつけて運ぶために多量の鉄分が含まれているのです。
鉄分不足が解消されてお得と思うかもしれませんが、それは間違いです。
鉄は生命を維持するのに必須な元素ではありますが、多すぎる鉄は人間にとって有毒です。
血液に含まれる鉄分の量は、肉や脂にくらべると遥かに多くなっており、ゴクゴクと大量に飲んでしまうと「ヘモクロマトーシス」と呼ばれる鉄過剰の病気になってしまい、疲労や関節痛、性欲の低下、肌の黒ずみなどの症状を引き起こし、肝硬変・糖尿病・心不全を併発させることがあるのです。
では他の動物の血を長期にわたりエサにしている吸血コウモリの場合はどうなのでしょうか?

これまでの研究により吸血コウモリには、血に含まれる鉄などのミネラルが吸収されるのを防ぐ遺伝子があることが知られています。
そのため吸血コウモリは鉄過剰になることなく、血を栄養分にできるのです。
では人間の遺伝子を組み変えて、同じようにミネラルの吸収を抑える遺伝子を獲得できれば、血を主食にできるのでしょうか?
残念ながら答えは「NO」です。
自分ではない血には、鉄分よりも遥かに恐ろしい危険が潜んでいるからです。
他人の血は感染症を引き起こす
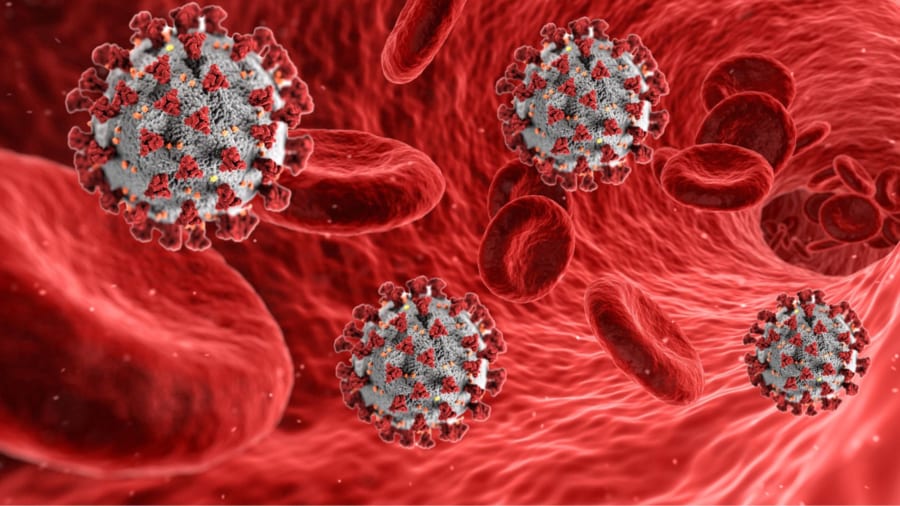
よく知られている通り、血液は感染症の温床でもあります。
HIVやB型肝炎、C型肝炎などを引き起こすウイルスなどは感染者の血液に含まれているため、不用意に粘膜に接触したり輸血した場合には、他人に感染してしまうからです。
他にも血液に接触することで引き起こされる感染症には梅毒なども知られています。
第二次大戦以前は、他人の血が危険であるという認識が薄かったため、野戦病院で兵士たちの治療を行っていた医者や看護師の多くが血をかいした感染症のせいで犠牲になっています。
さらに他の動物の血液となると危険度は跳ね上がります。
犬や猫、ヘビやカエルなど、人間ではない動物の血液には、人間の免疫能力が上手く対処できない未知のウイルスや細菌が潜んでいる可能性があるからです。
血液の魅力に囚われ吸血鬼と呼ばれた歴史上の人物は何人か耳にしますが、本物の血液には特に人間にとってのメリットはないようです。
やはり吸血鬼を気取って飲むならトマトジュースが妥当なのでしょう。
参考文献
Is it OK to drink blood?
https://www.popsci.com/health/people-drink-blood/
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


