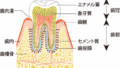フィンランド・ヘルシンキ大学(University of Helsinki)で行われた大規模研究により、投票に行かなかった人は、同じ期間に投票に行った人に比べて男性では亡くなるペースが1.73倍、女性でも1.63倍になることが示されました。
さらに、事故や暴力、アルコールなどによる病気以外の死因では、非投票者の亡くなる危険が約2倍(男女とも)に達し、この差は学歴による死亡差を上回っていました。
研究チームは、投票行動そのものが健康状態や社会とのつながりを映す「補助指標」になり得る可能性を指摘しています。
では、なぜ「投票する・しない」という社会的な行動が、人の寿命にまで影響しているのでしょうか?
研究内容の詳細は2025 年 11 月 4 日に『Journal of Epidemiology & Community Health』にて発表されました。
目次
- 投票行動が「寿命」に影響するの本当か?
- 318万人の21年間に渡る調査が明かした「投票と寿命」
- 病院の問診票に「投票に行くか」が加わるかもしれない
投票行動が「寿命」に影響するの本当か?

「投票に行かない人ほど早く亡くなりやすい」――そんな話を聞けば、にわかには信じがたいでしょう。
実際、選挙に足を運ぶかどうかと健康状態は、一見関係がないように思えます。
多くの人にとって投票は義務や権利であっても、「体に良い行動」と考える人はほとんどいないでしょう。
投票所に行くには多少歩くことになりますが、数年に一度のその運動で健康が大きく変わるとは考えにくいものです。
もちろん、今回の研究が調べたのは「運動量」ではありません。
研究者たちが注目したのは、社会とのかかわりそのものでした。
近年、医療や公衆衛生の分野では、遺伝や生活習慣だけでなく、社会的な要因が健康に影響することが明らかになっています。
たとえば経済状況、教育水準、人とのつながりなどがそれにあたります。
こうした社会的要因が悪化すると、地域とのつながりが薄れたり、生活の中で困難を抱えたりして、健康管理が行き届かなくなる場合があります。
その結果、過度な飲酒や安全対策を怠るといったリスクの高い行動につながることもあるのです。
そして投票という行動は、社会との関心やつながりをどれほど保てているかを映す鏡のようなものかもしれません。
実際、これまでの調査でも「投票に行く人の方が健康状態が良い傾向がある」ことは報告されてきました。
ただし、これまでの多くの研究はアンケートに基づいており、回答する人の記憶違いや「良く見られたい」という気持ちによる回答の偏りが避けられませんでした。
また、健康状態を客観的に測ること自体が難しく、投票と健康の本当の関係を正確に捉えきれなかったのです。
この壁を越えるため、フィンランドのヘルシンキ大学を中心とした研究チームは、実際の投票記録と死亡データを組み合わせるという前例の少ない方法を用い、投票と死亡の関係をより客観的に調べました。
もし本当に「投票しない人ほど早く亡くなりやすい傾向がある」のだとしたら、それは私たちの社会にどんな意味を持つのでしょうか?
318万人の21年間に渡る調査が明かした「投票と寿命」

投票に行かないと死亡の危険度は本当に高くなるのか?
この疑問を確かめるために、研究チームはまず1999年にフィンランドで行われた国会議員選挙の公式投票記録を分析しました。
対象は30歳以上の全有権者で、実際に投票したかどうかの情報を統計局の人口・死亡データと照合しています。統計局のデータには年齢や教育水準、死亡の有無や原因などが含まれており、選挙日から2020年末までの約21年間にわたって一人ひとりの生存状況が追跡されました。
最終的なサンプルは約318万人(男性は約151万人、女性は約168万人)にのぼり、追跡期間中に延べ105万人以上が亡くなりました。
これほど大規模で長期間にわたる追跡により、研究チームは投票の有無と死亡率との関係を統計的に詳しく分析しました。
その結果、投票に行かなかった人ほど死亡の割合が高いことが明確に示されました。
特に際立っていたのは、男女ともに共通してこの傾向が見られた点です。
具体的には、投票しなかった男性は投票した男性より亡くなるペースが1.73倍、女性では1.63倍という大きな差でした。
これは「投票しないこと」と「早く亡くなること」に強い関連があることを示しています。
さらに、この「投票の有無による死亡の差」は、教育水準による死亡差よりも大きいことがわかりました。
(※日本の2010–2015年の30–79歳の全国データでは、大卒・大学院(高学歴)層と比べて中卒層の死亡率は、男性で1.36倍、女性で1.46倍であり、高卒の死亡率は男性で1.16倍、女性で1.24倍でした。米国でも教育差が平均余命に大きく表れます。米国では大学院修士以上の人は、高卒未満より14.7年、高卒より8.3年長いと報告されています。)
社会経済的地位を示す学歴差よりも、投票行動の違いのほうが寿命に大きく影響していたというのは、研究者たち自身も驚く結果でした。
では、どんな死因でこの差が大きくなるのでしょうか。
分析によれば、投票に行く人と行かない人の死亡の差が最も大きく現れたのは、外因死と呼ばれる病気以外の原因でした。
外因死とは、交通事故、暴力事件、アルコールが関係する事故などの死亡を指します。
統計では、投票しなかった人は投票した人に比べ、こうした病気以外(外因)による死亡の危険度が男女とも約2倍に達していました。
また、若い世代ほど投票の有無による死亡の差が大きいこともわかりました。
特に50歳未満の比較的若い成人では、投票しなかった人の死亡率が投票した人より顕著に高かったのです。
一方で、75歳以上の高齢層では、投票した男性の死亡率が投票しなかった女性より低いという、通常の男女差を逆転させる現象も確認されました。
一般的に女性は男性より長生きしやすいですが、「投票しない」という要因はその生物学的利点をも打ち消してしまうほど強い関連を示しました。
さらに、こうした差は所得によってもわずかに異なり、低所得の男性では不投票による死亡の上昇幅が他の層よりも9〜12%ほど大きい傾向がみられました。
全体として、この研究は性別や年齢を問わず「投票しないこと」と「早世(若くして亡くなること)」との間に強い関連があることを明らかにしました。
過去の研究では、高学歴の人ほど投票率が高く、また健康で長生きしやすい傾向が示されていました。
しかし今回の分析では、教育(学歴)の影響を取り除いても、死亡の差の大部分は残りました。
たとえば、年齢と学歴を同時に考慮しても、非投票者の亡くなるペースは男性で1.64倍、女性で1.59倍と依然として高く、学歴だけでは説明できませんでした。
ではなぜ、投票に行かない人の方が危険な亡くなり方をするのでしょうか。
明確な因果関係はわかっていませんが、一つの可能性は社会とのつながりや生活習慣の違いにあります。
投票に行かない人は、地域や人との関わりが薄かったり、生活に困難を抱えていたりする傾向があるのかもしれません。
その結果、健康管理が難しくなり、過度な飲酒や安全対策を怠るなど、リスクの高い行動につながることがあります。
今回の結果は、「投票に行かない」という行動が、社会的な孤立や生活上の困難と結びついている可能性を示しています。
言い換えれば、社会に関心を持ち、参加する人ほど心身の健康度が高いとも考えられるでしょう。
投票という一見地味な行動が、私たちの人生の長さにまでつながっているということです。
病院の問診票に「投票に行くか」が加わるかもしれない

今回の発見は、「政治参加(社会との関わり)と寿命が無関係ではない」ことを示しました。
これまで、死亡の危険度は教養や収入、生活習慣などと結びつけて考えられることが多くありました。
しかし今回の研究は、投票という社会的な行動もまた、社会的にどれほど活動的かを示す有力な“予測の手がかり”になり得ることを明らかにしました。
一方で、研究者たちはこの結果が「相関関係(関わり)」であり、因果関係そのものではない点を強調しています。
当然ながら「投票しないから早く亡くなる」と断定できるわけではありません。
研究チームも、「健康状態や障害などによって投票に行く体力や気力が奪われてしまうこともある」と述べています。
この点を確かめるには、複数回の選挙を追跡する長期研究で、投票習慣と健康状態の変化を見ていく必要があるでしょう。
とはいえ、今回の研究は国の全有権者を対象にした、非常に大規模で客観的な分析でした。
得られた知見は今後の研究の基盤となり、他の国や文化で同じ傾向が見られるかを探るうえでも重要な一歩です。
さらに、将来的には投票率を上げる取り組みが健康にも良い影響を与えるかどうかを検証するような研究にもつながるかもしれません。
この結果が伝えるメッセージは重く、私たちに多くの問いを投げかけます。
投票という行為は、政治的な意思表示だけでなく、自分の健康や生活の安定を映す“鏡”でもあるのかもしれません。
研究チームは「投票に関する情報は医療や保健の現場でも役立つかもしれない」と述べています。
たとえば、これまで毎回投票に行っていた人が急に行かなくなったとしたら、それは健康状態の悪化や生活の困難を示す早期のサインである可能性があります。
医師や地域の保健担当者が投票率の変化に目を向けることで、従来の健康診断では見逃してしまうような社会的な孤立や心の健康の問題を早めに察知できるかもしれません。
もしかしたら病院の問診票に「最近の選挙に行きましたか?」という質問を加えるのも、患者の生活背景を理解する手がかりになるかもしれません。
また、この研究はもう一つの重要な課題を浮き彫りにしました。
それは、健康状態が悪い人ほど政治に参加しづらく、その声が政治に届きにくいという現実です。
選挙に行けないほど体調を崩していたり、社会的に孤立していたりする人々の意見が政治に反映されにくいとすれば、民主主義の公平性という点でも見過ごせません。
今回の研究は、健康格差と政治的な格差が重なり合う「負の連鎖」に注意を促しています。
もし、これまで投票に行ったことがない人や、最近行かなくなってしまった人がいるなら、それは単に政治への関心の問題ではなく、自分と社会とのつながりをもう一度見直すサインなのかもしれません。
元論文
Voting is a stronger determinant of mortality than education: a full-electorate survival analysis with 21-year follow-up
https://doi.org/10.1136/jech-2025-224663
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部