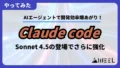英国のレディング大学(University of Reading)を中心とした研究チームによって、恐竜の骨の化石の表面にコケのようなオレンジ色の地衣類が優先的に繁茂していることが科学的に明らかになりました。
研究者たちは地衣類が化石骨の表面の最大約50%を覆うのに対し、すぐそばにある普通の岩石には1%未満しか生えていないと報告しています。
また研究ではこの結果を利用して空中を飛ぶドローン(小型の無人航空機)を使い、地衣類の特殊な反射パターンを目印にして空から化石を探すという新しい方法を実証しました。
この方法が発展すれば、これまで困難だった化石の発見を効率的に進められる可能性があります。
しかし、なぜ地衣類たちは骨の化石の上で優先的に繁殖していたのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年11月3日に『Current Biology』にて発表されました。
目次
- 化石が好きなコケの噂は本当なのか?
- 恐竜の化石に群がるオレンジ色の地衣類の謎を科学が解明
- 化石探しに革命を起こす
化石が好きなコケの噂は本当なのか?

化石探しというのは古生物学者にとってはとても骨の折れる作業です。
広大な大地を地道に歩き回り、小さな骨のかけらを根気よく探すほかありません。
新しい化石を見つけるのは、運が良ければというレベルの話なのです。
長年、この非効率な方法を何とか改善したいと研究者たちは願ってきました。
そこで最近注目され始めたのが、空からの探査です。
ドローン(小型の無人飛行機)を飛ばして上空から地表を撮影し、映像から化石を探す手法が試されています。
しかし、大きな問題がありました。
肝心の化石の骨は背景の土や岩と見た目がほとんど変わらないため、ドローンが撮った写真だけではなかなか骨を見つけられないのです。
ところが、現場の研究者たちは以前から不思議なことに気づいていました。
「化石が多く見つかる場所では、なぜかコケのようなオレンジ色の地衣類がよく目立つ」という声が以前から挙がっていたのです。
Royal Tyrrell博物館の古生物学者であるカルブ・ブラウン博士も、「露出した化石骨が集まる場所では、骨そのものより先にオレンジ色の地衣類の“草原”が目に飛び込んでくることもしばしばです」と指摘しています。
オレンジ色のコケの正体とは?
オレンジ色のコケと言われているのはRusavskia elegans(ルサヴスキア・エレガンス) と Xanthomendoza trachyphylla(キサントメンドーサ・トラキフィラ)という2種類の地衣類です。これら地衣類とコケは見た目はそっくりですが生物学的には全く別の種となっており、地衣類は菌と藻類の混ざった複合生命のような存在です。またこの地衣類たちは共に乾燥に強く、特にカルシウムを多く含んだアルカリ性の岩石や骨の表面を好んで生育するという性質が確認されています。色がオレンジになる理由は、これらが属するテロスキステ科(Teloschistaceae)の多くが持つアントラキノン系色素によるものです。
このような経験的な感覚は以前からありましたが、それが科学的なデータで確認されたことはこれまでありませんでした。
1980年には「人工衛星からでもオレンジ色の地衣類が見つけられるかもしれない」と予測した研究者もいました。
しかし、このような話はあくまで噂レベルであり、本当に地衣類が化石探しに役立つのか、誰もはっきりした答えを持っていませんでした。
そこで今回、国際的な研究チームが本格的にこの謎に取り組みました。
地衣類は本当に恐竜の化石の骨を好んで生えるのか?
もしそうなら、その性質をうまく利用して化石の在処を空から発見できるかもしれない——こうした大胆な仮説を、科学的なデータを使って確かめようとしたのです。
果たしてこの「地衣類=化石の目印」仮説は本当なのでしょうか?
本当にオレンジ色の小さな生態系が、巨大な恐竜の化石を見つけ出すための道しるべになるのでしょうか?
恐竜の化石に群がるオレンジ色の地衣類の謎を科学が解明

「地衣類は本当に化石の骨を好んで生えているのか?」
この問いに答えるために、研究チームは実際にカナダ・アルバータ州の恐竜州立公園にある恐竜化石が密集する「ボーンベッド」という場所で詳しい調査を行いました。
まず、研究者たちは現地で化石が集まる場所を探し、地表に露出している化石の骨とその周囲に転がっている岩や土の表面を詳しく調べました。
次に、それぞれの表面にどれくらい地衣類が生えているかを細かく記録しました。
これは「化石の骨」と「周囲の岩石」のどちらに地衣類がたくさん生えているかを統計的に確かめるためです。
その結果、化石の骨の表面ほど地衣類が集中的に生えているという強い傾向が見つかりました。
逆に、骨のすぐそばに大量に転がっている鉄分を含んだ石(鉄岩)には、地衣類があまり生えていないことが分かりました。
つまり、地衣類はただ単に「そこにあるもの」に無差別に生えるのではなく、明らかに「化石の骨」を好んで選んでいる可能性が示されたのです。
実際、研究チームが観察した最も顕著な例では、地表に露出した化石骨の表面のおよそ50%が地衣類で覆われていましたが、そのすぐ隣にある普通の岩石では1%未満しか地衣類が生えていないと報告されています。
これはかなり驚くべき差と言えるでしょう。
撮影された現地の写真を見ても、大きな恐竜の骨がオレンジ色の地衣類でびっしり覆われている一方、そのすぐ周囲の地面にはほとんど地衣類がない様子が明確に映っています。
先にも触れたように、まるで骨が特別な魅力を持っているかのように地衣類が選択的に生えることが、視覚的にも確認されたのです。
研究チームは、ここで「色」に注目しました。
地衣類や化石の表面は、それぞれ特有の「光の反射パターン(スペクトル)」を持っています。
これは、地表が光を受け取って、それをどの色の光として跳ね返すかという性質です。
実際に地衣類の反射パターンを調べてみると、地衣類は青い光(波長400〜500ナノメートル付近)をあまり反射しませんでしたが、逆に赤外線(近赤外から短波赤外の波長800〜1400ナノメートル付近)では非常によく反射することが分かりました。
これに対し、化石の骨そのものやその周囲の岩石、砂地などは、こうした特有の反射パターンがなく、すべて似たような反射をしていました。
そのため、人の目や普通のカメラでは化石の骨を見つけるのは難しいのです。
ここで研究チームは、「地衣類だけが持つ特別な反射パターン」を利用するアイデアを思いつきました。
その反射パターンを目印にすれば、地衣類が覆っている化石の骨を空からでも見つけられるかもしれないと考えたのです。
これを可能にするために開発されたのが、地衣類特有の反射パターンを画像データから識別する「LSR/NDLI」という新しい解析手法です。
いよいよこの手法を使って、研究チームはドローンを飛ばして実際に空中から化石を探す実験を行いました。
ドローンには特殊なカメラを取り付けて、上空約30メートルから地表を撮影しました。
その撮影した写真をこの新しい手法で解析したところ、地表に露出している地衣類に覆われた化石の位置を、ドローンが未学習分類(あらかじめ教えなくても自動でグループ分けする方法)で抽出することに成功しました。
最後に、研究者たちはなぜ地衣類がここまで化石の骨に好んで生えるのかを考察しました。
恐竜の骨には微細な穴がたくさんあり、そこに水分や栄養素を貯め込むことができるため、地衣類にとって最適な「居住地」になるのではないかと考えられています。
さらに、骨の表面はアルカリ性でカルシウムなどのミネラル分が豊富であり、これが地衣類の好む環境条件にも一致しています。
まさに、化石の骨は地衣類にとって栄養が豊富な「貯水タンク付きのオアシス」のような存在だったのです。
化石探しに革命を起こす

今回の研究で明らかになったのは、オレンジ色の地衣類という現代の小さな生き物が、約7500万年前に生きていた恐竜の遺骸(化石)の発見に役立つということです。
地衣類が恐竜の骨に特別に多く繁茂する理由は、先にも触れたように、骨の表面に多くの小さな穴が空いていて、水分や栄養素を保持しやすいからだと考えられています。
こうして地衣類が骨を目印にしてくれるおかげで、私たちは遠く離れた現代から化石の位置を空からでも見つけることができるようになったのです。
まさに、オレンジ色の地衣類が空中から化石の在処を知らせてくれる「天然のビーコン(目印)」として働いていると言えるでしょう。
今回の研究で特に重要なのは、この地衣類を利用した新しい探査手法を提案したことです。
ドローン(小型の無人航空機)を使って空から地衣類の位置を特定し、化石を探すという発想は非常にユニークで実用的なアイデアです。
これまで化石発掘というのは、広大な荒野を多くの人が何日もかけて歩き回るという大変な労力が必要でしたが、この方法を使えば短時間で広い範囲を調査することが可能になります。
また、この方法がさらに発展すれば、将来的にはドローンだけでなく航空機や人工衛星による広域調査へと応用できる可能性があります。
実際に研究チームのリモートセンシング(遠くから地表を観測する技術)を担当した専門家も、「今回のドローンを使った調査は、より広い地域を航空機や衛星で調べるための最初の重要なステップになるでしょう」と期待を述べています。
こうした技術が発展すれば、広大な荒地や人が入りにくい地域の調査も容易になり、調査にかかる時間や費用を大幅に減らすことができます。
また、人が直接歩き回ることが減れば、その地域の自然環境への負担も少なくできます。
ただし、もちろんこの方法にはまだ限界があります。
最も重要な制限としては、地衣類が生えるためには化石の骨が地表に出ている必要がある点です。
地中に深く埋まってしまった化石については、この方法で見つけることはできません。
また、この手法が有効であることが確認されているのは、カナダの恐竜州立公園のように比較的乾燥した地域です。
湿度が高く植物が生い茂っている地域や、土砂で完全に埋もれてしまっている化石については、オレンジ色の地衣類を頼りに探すことは難しいでしょう。
それでも、今回の研究成果は化石探しの方法を大きく進化させるきっかけになると期待できます。
研究チームは今後、この地衣類を目印とする方法が、世界中の他の地域でも同様に使えるかを調査する計画を立てています。
もし近所にポツンと不自然に地衣類が生えている場所があったら、調べてみるのもいいかもしれません。
元論文
Remote sensing of lichens with drones for detecting dinosaur bones
https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.09.036
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部