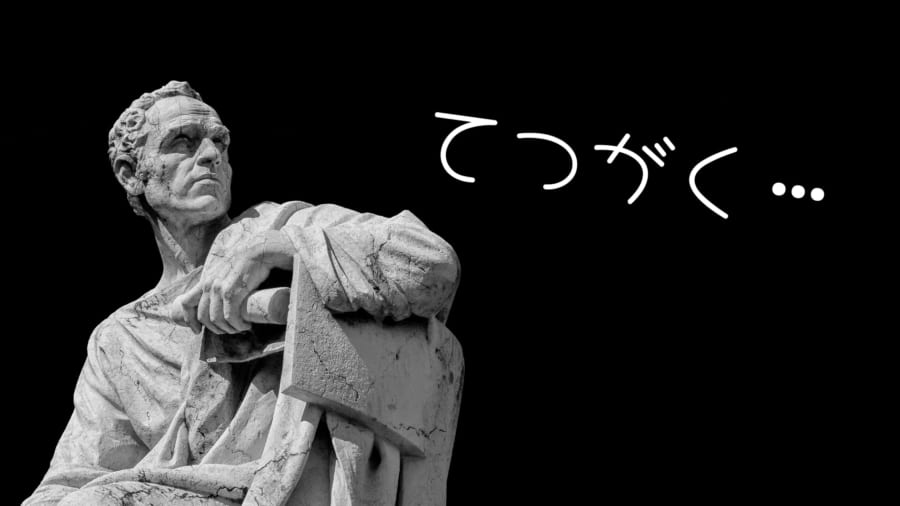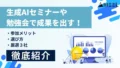哲学を専攻すると本当に「頭が良くなる」のでしょうか?
そんな疑問に、アメリカのウェイクフォレスト大学(Wake Forest University)などで行われた研究が答えを出しました。
結果は明快です。
哲学科の学生は、卒業時点で言語力と論理力では全専攻中トップであり、知的な好奇心や多様な視点を受け入れる姿勢といった思考習慣でも上位を占めました。
そして何より重要なのは、入学時の学力の差を考慮に入れてもなお、この「思考力の伸び」が確認された点です。
長年語られてきた「哲学は人を賢くする」という命題が、これまでで最も強力なデータによって後押しされたのです。
哲学にはどんな秘密が隠されていたのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月11日に『Journal of the American Philosophical Association』にて発表されました。
目次
- 哲学はなぜ効くと言われる
- 哲学は人を賢くする?大規模データで検証
- どこまで言える?伸びの意味
哲学はなぜ効くと言われる
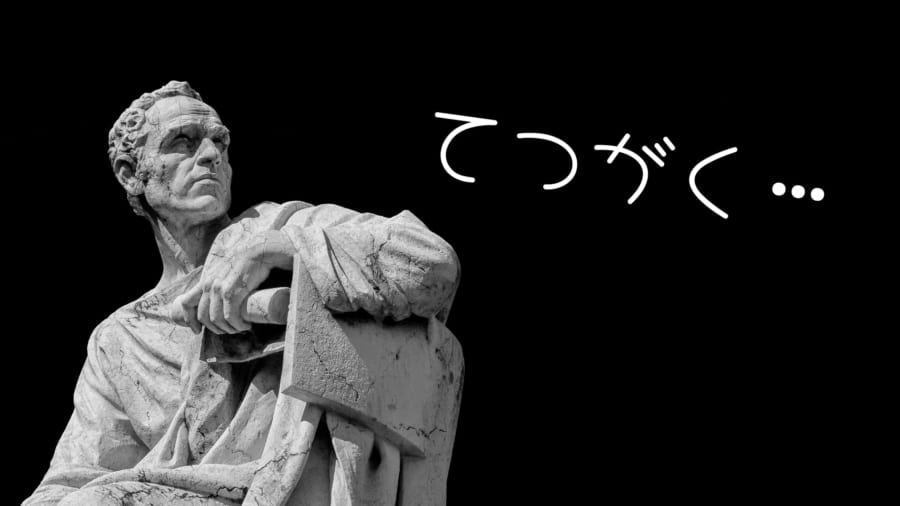
哲学と聞くと、あなたは何をイメージするでしょうか?「難解な話をずっと考え込んでいる学問」と思うかもしれません。
実際そのイメージは、あながち間違っていません。
昔から哲学は、「人間の頭を鍛える」と言われてきました。
なぜでしょう?それは哲学が「言葉」と「論理」を駆使して、物事を深くじっくり考える訓練を行う学問だからです。
こうした訓練を繰り返すうちに、複雑な問題を解きほぐす力や、自分や他人の意見を客観的に検証する力が鍛えられると言われています。
こうした評判を裏付けるデータもあります。
1980年代頃からアメリカでは、哲学を専攻した大学生は、他の専攻よりも大学院入学試験や法律専門大学院試験で高得点を取る傾向があることが報告されています。
ここで登場する試験には、GRE(Graduate Record Examination)とLSAT(Law School Admission Test)の2つがあります。
GREは大学院への入学試験で、主に「言葉の力」と「数学の力」を評価します。
一方、LSATは法律専門大学院への試験で、「論理的な思考力」と「文章を理解する能力」を問うテストです。
哲学科の学生たちは、特に「言葉の運用能力」と「論理的思考力」を評価する試験項目で、目立って良い成績を収めていました。
さらに哲学を学んだ人は、そうでない人に比べて、「じっくり物事を考える習慣」や「異なる意見にも耳を傾ける開放的な態度」が高いことも分かっています。
こうした事実をもとに、多くの大学の哲学科やアメリカ哲学協会は、「哲学を学ぶことで思考力が鍛えられる」と宣伝しています。
ところが、ここで注意しなくてはならない問題があります。
それは「もともと頭がいい人が哲学を選んでいるだけではないのか?」という疑問が根強く残っていることです。
たとえば、もともと言語能力が高く、いろんなことに興味を持ちやすい好奇心旺盛な学生が哲学に集まっているとしましょう。
そうすると当然、卒業時の成績や思考習慣においても哲学科の学生の平均値は高くなってしまいます。
つまり哲学という教育そのものに力があるのではなく、学生が最初から優秀だから結果的に良く見えているだけ、ということになってしまいます。
実際、この研究でも、入学時点で哲学を専攻しようと考える学生は、他の学生よりも言葉の運用力や好奇心、さらには異なる意見を受け入れる姿勢などの点で、すでに高いスコアを持っていたことが確認されています。
そのため、哲学という専攻が本当に人の能力を伸ばしているのかどうかは、丁寧な検証が必要だったのです。
こうした疑問に決着をつけるため、今回アメリカにあるウェイクフォレスト大学とノースカロライナ大学チャペルヒル校の共同研究チームは、大規模な調査を行うことにしました。
そこで今回、ウェイクフォレスト大学とノースカロライナ大学チャペルヒル校の研究者たちは「哲学が好きな人は元から頭が良かった説」と「哲学には頭を良くする効果がある説」のどちらが正しいかを検証する大規模調査を行うことにしました。
果たして哲学そのものに頭を良くする効果はあったのでしょうか?
哲学は人を賢くする?大規模データで検証
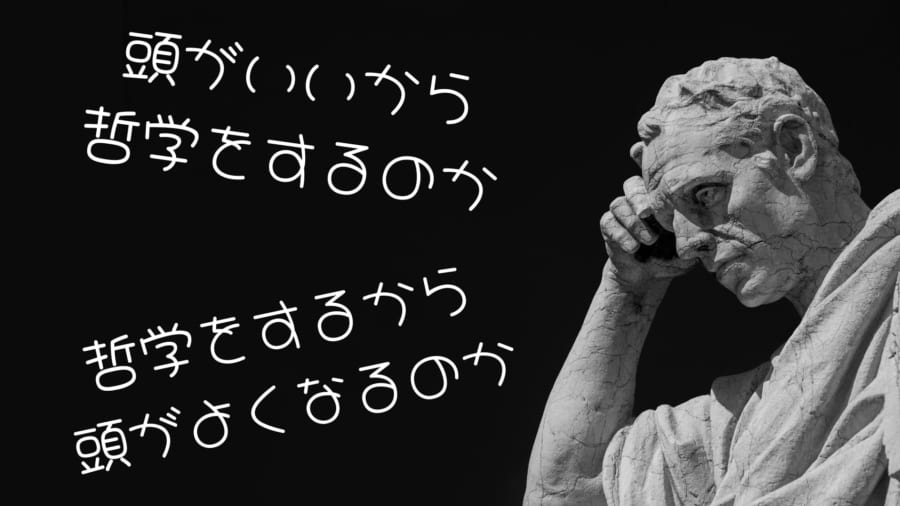
今回の研究チームは、「哲学を学ぶと本当に頭が良くなるのか?」という問いを、できるだけ公平に調べようとしました。
しかし「哲学を学ぶことで頭が良くなるのか」を確かめるのは、簡単ではありません。
なぜかというと、哲学を選ぶ学生はそもそも優秀な人が多いからです。
最初から頭の良い人が哲学を選び、そのため哲学科の成績が高くなっている可能性もあるのです。
これを「自己選抜」と呼びますが、この影響を取り除かなければ、本当に哲学の学習が力を伸ばしたかどうかは判断できません。
そこで研究者たちは、アメリカ全土にある800を超える大学から集まった約60万人もの学生のデータを使って、この問題に挑むことにしました。
まず、大学入学時に学生たちが受けるSATという試験の結果を見て、それを元に学生たちがもともと持っていた能力の差を推測します。
SATとは、高校生が大学に進学する際に受ける標準的な学力試験で、主に「言葉の能力」と「数学の能力」を測るものです。
このSATの点数を参考にすれば、「最初の時点でどれくらい優秀だったか」を大まかに把握できます。
その上で、大学卒業前に受ける2種類の別の試験の結果と比較することで、「入学後にどれだけ能力が伸びたのか」を調べることにしました。
1つ目はGREという大学院入試のテスト、2つ目はLSATという法科大学院の入試テストです。
GREは大学院に入るための試験で、「言葉を使う力」と「数学を解く力」を試すものです。
LSATは法科大学院への入学試験で、特に「論理的な思考力」と「文章を正しく理解する能力」を測る試験です。
つまり、この調査で研究者がやったことは、「入学時の能力が同じだったとして、卒業するとき哲学科の学生のほうがテストで高い点数を取っていたかどうか」を統計的な方法で調べる、ということです。
最初のスタート地点をそろえることで、哲学を学ぶという行為自体が学生の能力を伸ばしたのかどうかを、より正確に判断できるわけです。
ただし、SATでは完全には論理的な思考力を測れないという限界があるため、結果を見る際には注意が必要になります。
さらに研究チームは、テストだけでなく学生の「考える習慣や姿勢」にも注目しました。
大学1年生の時と4年生の卒業間近の時に、学生自身にアンケートを行い、「どれくらい自分から進んで新しい知識を求めるようになったか」「意見が違う人の考え方を理解しようとするか」といった姿勢を自己評価してもらったのです。
これらは専門的に「Habits of Mind(探究心や批判的に考える習慣など)」と「Pluralistic Orientation(異なる考え方を柔軟に受け入れる姿勢)」と呼ばれています。
そして、こうして丁寧に集められ分析されたデータから、興味深い結果が浮かび上がりました。
まず最初に、哲学を専攻した学生は、言葉の力(GREの言語部門)と論理的な思考力(LSAT)に関して、卒業時の成績が他の専攻よりもはっきりと高くなっていたのです。
具体的には、GREというテストの「言語推論」の部門では、哲学科の学生の平均点が他専攻より33点も高く、LSATでも2点ほど高くなっていました。
こうした差は統計的にも明らかで、偶然とは考えにくい、信頼できる差であることが確認されています。
ただし、同じGREでも数学部門の結果には、哲学専攻と他の専攻の間にほとんど差がありませんでした。
つまり哲学は、数学の力を伸ばすことにはあまり貢献しなかったということになります。
またアンケートの結果では、哲学を専攻した学生は卒業までの間に、他専攻の学生と比べて「探究心」や「批判的な考え方」、「異なる意見を受け入れる柔軟性」などがはっきりと高まっていました。
この向上は入学時の能力差を調整した後でもはっきり確認され、伸びの幅は小さめでしたが確かな効果が見られました。
特に「Habits of Mind(良い思考習慣)」では哲学科が全ての専攻の中でトップ、「Pluralistic Orientation(多様な視点を受け入れる態度)」でも6位と上位を占めました。
さらに研究者たちは、「哲学科は特に優秀な学生だけが卒業前のテストを受けるから高いのでは?」という別の疑問も調べました。
結果として、そうした偏りが哲学科にだけ特別にあるという証拠は見つかりませんでした。
つまり、この研究は、「もともと頭がいい人が哲学を選んだため」だけでは説明できない、哲学そのものの効果をしっかりと示したと言えるのです。
以上の調査結果から、哲学を大学でしっかり学ぶことは、特に「言葉を扱う力」や「論理的に考える力」、そして「探究心や柔軟な考え方」といった知的な能力や習慣を着実に伸ばすのに役立つ、ということがわかったのです。
どこまで言える?伸びの意味
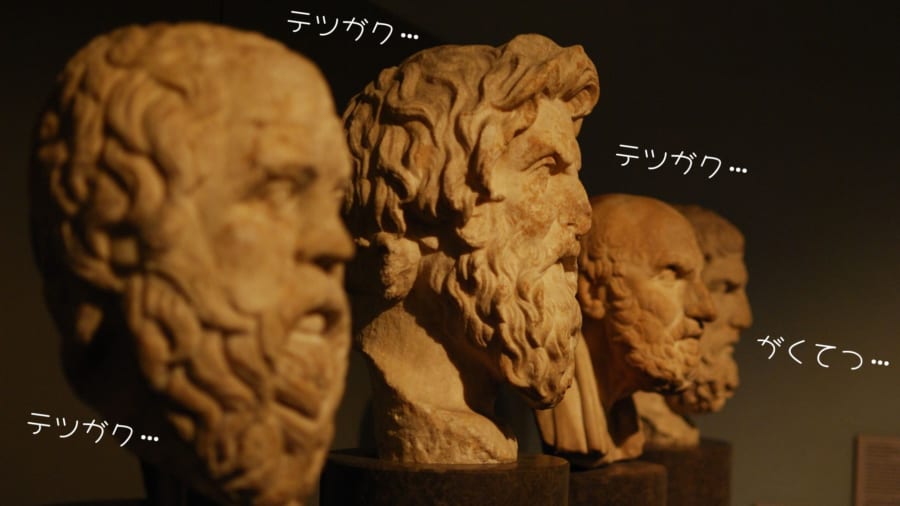
今回の研究は、「哲学で論理力が伸びる」という主張に対し、これまでで最も強力な裏付けを与えるものです。
長年「哲学をやると頭が良くなる」と言われつつも決め手に欠けていた議論に、大規模データと綿密な分析で答えを提示しました。
その意味で本研究は、哲学の教育的価値を再評価する転機となるかもしれません。
あえて言うなら、哲学は「言葉と論理、思考習慣を鍛える『頭のトレーニング』」なのかもしれません。
それは知識の暗記ではなく、言葉と論理を使って考え抜く反復練習だからです。
前提を疑い、反論に耐える議論を組み立て、概念を精密に定義し、結論がどこまで妥当か突き詰める——哲学の授業で日々行われるこうした知的エクササイズが、まさに思考力という“筋肉”を鍛えているのでしょう。
今回の研究結果は、この「哲学の思考トレーニング効果」をデータで裏付けた形です。
もちろん、哲学を学べば誰でも魔法のように突然賢くなれるわけではありません。
基礎的な学力や資質がある程度重要なのは事実です。
それでも本研究が示したように、入学時点の能力差だけでは説明できない伸びが哲学専攻の学生に見られたことは注目すべき発見です。
特に重要なのは、4年間の大学教育で付いた差が確認された点であり、「大学で何を学ぶか」が人の思考力に与えるインパクトを雄弁に物語っています。
実際、「もともとどれだけ頭が良いか」だけでなく、「大学で何を学んだか」も人の成長に関わることが示唆されたのです。
現代はAIが台頭し、大学教育の価値が見直される時代ですが、こうした中で従来「役に立たない」と揶揄されがちだった哲学の価値が今回の成果によって見直されるかもしれません。
人間にしかできないクリティカルシンキング(批判的思考)の重要性が増す今、哲学を通じて培われる言語力・論理力や知的な柔軟性は、まさにAI時代に求められる「人間ならではの力」と言えるでしょう。
さらに今回の知見は、教育の在り方や進路選択にも示唆を与えそうです。
近年、実学志向やSTEM(科学・技術・工学・数学)偏重の風潮の中で、哲学をはじめ純粋な人文学の価値が見過ごされがちでした。
しかし哲学科の学生が培う思考スキルは、他分野の学生を凌ぐほど強力だという結果は、大学教育で何を重視すべきかを問い直す材料となります。
研究の著者らも、哲学教育の効果を今回確認したことで「教育の本来の目的」に立ち返る議論に繋げたいと述べています。
個人のキャリアにおいても、「就職に直接役立つスキル」だけでなく生涯にわたって自分の頭で考える力が重要であることを、本研究はデータで示していると言えるでしょう。
高校生・大学生のみなさんも、進路を選ぶ際には「自分の頭を鍛える学び」という観点で哲学に目を向けてみると、新たな可能性が開けてくるかもしれません。
元論文
Studying Philosophy Does Make People Better Thinkers
https://doi.org/10.1017/apa.2025.10007
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部