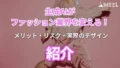オーストラリアのニューサウスウェールズ大学(UNSW)で行われた研究によって、1978年にイギリスで初めて「試験管ベビー」が誕生して以来、体外受精(IVF)で生まれた赤ちゃんの総数が世界で1300万人を突破していることが示されました。
この40年間で、体外受精による赤ちゃんの誕生ペースは急速に加速し、現在では世界で35秒に1人がIVFによって生まれていると推定されています。
特にデンマークやオーストラリアなど、高所得国では政府による支援や公的補助が進んでおり、オーストラリアでは35歳以上の母親の10人に1人が体外受精で子どもを授かっています。
研究チームは「体外受精はすべての人に平等に与えられるべき“権利”である」と主張しています。
体外受精技術の進歩は私たちの社会に何をもたらし、またどのような課題を浮き彫りにしたのでしょうか?
研究内容の詳細は『Fertility and Sterility』にて発表されました。
目次
- なぜ累計を数えたのか
- 40年で1300万人、さらに増加中
- 体外受精を基本的な権利に
なぜ累計を数えたのか
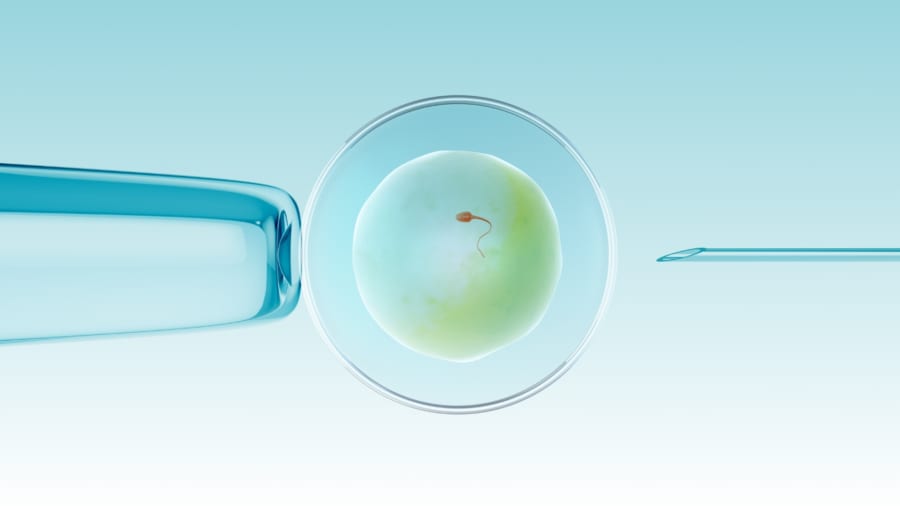
体外受精は、子どもが欲しいけれどなかなか授かれない人たちにとって希望を与えてきました。
日本でも1983年に最初のIVF児が生まれ、技術の進歩とともに治療の件数もどんどん増えてきました。
さらに、2022年の4月からは日本でも保険が使えるようになり、経済的にも受けやすい治療になってきました。
今では体外受精は「特別な医療」ではなく、「当たり前の治療」に近づいています。
では、世界中ではこれまでに何人の赤ちゃんが体外受精で生まれてきたのでしょうか?
これまでも各国では、毎年のIVF出産数は報告されてきました。
しかし、「世界全体でこれまでに何人が体外受精で生まれたのか?」という合計人数をまとめて調べた研究はこれまで存在しませんでした。
そこで今回、国際的な研究チームは改めて、体外受精でどれほどの子供が生まれたのかを調べることにしました。
果たして世界全体で体外受精で生まれたこどもたちはどれほどの数になっていたのでしょうか?
40年で1300万人、さらに増加中

世界全体で体外受精で生まれた子供はどのくらいいるのか?
答えを得るため研究者たちは国際的な不妊治療のデータベース(ICMART)に報告された、101か国の体外受精に関するデータを分析することにしました。
この中には、どれくらいの人が治療を受けたのか、どれくらいの赤ちゃんが生まれたのかといった情報が含まれています。
ただし、すべての国や病院が正確に報告しているわけではありません。
中には記録がなかったり、一部のデータしか提出していないところもあります。
そこで研究者たちは、報告されていない国や病院のデータを予測して補う方法(統計的推定)を使いました。
たとえば、クリニックの数から全国の治療件数を見積もったり、妊娠の報告だけで出生数がない場合には、流産率などを考慮して計算を行いました。
このようにしてできるだけ正確な数を出したところ、1978年から2018年の40年間で、世界中で少なくとも約983万人〜1302万人(およそ1000万〜1300万人)の赤ちゃんが体外受精で生まれたと推定されました。
これは、これまで考えられていたよりも多い人数です。
また、グラフで見ると、特に2000年ごろから体外受精での出産が一気に増えていることがわかりました。
地域別の累計出生数を詳しく示すと、まず ヨーロッパ全体では約360万〜450万人のIVF児が誕生しており、これは世界最多です。
次いで アジア全体が約300万〜400万人、北アメリカ(主に米国とカナダ)が約140万〜160万人となっています。
ヨーロッパの数字が突出している背景には、各国政府による治療費助成や保険適用の手厚さがあります。
またオーストラリアでも公的補助が進んでおり、国内全体で16人に1人(約6%)がIVF児で、年齢を35歳以上の母親に限れば、10人に1人が体外受精による出産という高い割合になります。
研究チームは2018年以降の伸びも推計しました。
その結果、さらに2018年以降にも追加で約300万〜400万人のIVF児が生まれたと推計されました。
これらを合計すると、2024年時点の累計は世界で約1300万〜1700万人に達すると計算されます。
これは人口2,600万人あまりのオーストラリアの半数以上に相当する規模であり、体外受精が世界中で広く普及し、数多くの命を生み出してきたことがわかります。
体外受精を基本的な権利に

今回の研究では、体外受精(IVF)によってすでに世界で1300万人以上(最大で1700万人)の赤ちゃんが誕生していることが明らかになりました。
これはとても大きな数字であり、体外受精という技術が、子どもを持ちたいと願う多くの人たちにとって、どれだけ大きな助けになっているかを示しています。
もはや体外受精は、特別な人たちだけの医療ではありません。
たとえば、オーストラリアでは全体の約6%、デンマークでは約10%の赤ちゃんが体外受精で生まれているとされています。
(※2022年の確定データでは日本でも約10%が体外受精で生まれていると報告されています。彼らが小学生になったら、30人クラスのうち3人は体外受精を介して生まれてきたことになります)
これは、体外受精が「最後の手段」ではなく、「当たり前の選択肢」として広がっていることを意味します。
しかも、体外受精を利用しているのは、夫婦だけではありません。
独身女性や同性カップルなど、さまざまな家族の形が広がる中で、IVFは新しい命を迎えるための大切な手段になっています。
研究チームは、この技術が医療面だけでなく社会的にも大きな意味を持つと強調しています。
実際、技術もどんどん進歩しています。
昔は双子や三つ子が多く生まれるリスクもありましたが、今では1回の治療で1つの受精卵だけを使う方法が広まり、双子以上の出生率は3%未満にまで下がっています。
お母さんや赤ちゃんの安全にも配慮された進化です。
一方で、課題もあります。体外受精は高度な技術と設備が必要で、治療費も下がったと言っても高額です。
そのため、お金に余裕がある人や、制度が整った国に住む人だけが受けやすいという現状があります。
たとえば、日本では2022年から保険が使えるようになり、以前よりは身近になりましたが、世界にはまだ治療を受けたくても受けられない人がたくさんいます。
研究チームは、「体外受精はすべての人に平等に与えられるべき“権利”である」と主張しています。
もうひとつの問題は、「体外受精があるから、いつでも子どもができる」と考えてしまう人がいることです。
でも実は、年齢が上がるにつれて卵子の質や数は減ってしまい、体外受精の成功率も下がってしまうのです。
たとえば、35歳の女性で体外受精の成功率は約30%ありますが、40歳になると約15%、42歳では約10%にまで下がってしまいます。
つまり、「年をとっても大丈夫」と思っていると、うまくいかずに心や体、お金にまで大きな負担がかかってしまうことがあるのです。
体外受精はすばらしい技術ですが、それだけに頼るのではなく、「子どもを持ちたい」と思ったときに社会がしっかり支えるしくみも必要となるでしょう。
元論文
How many infants have been born with the help of assisted reproductive technology?
https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2025.02.009
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部