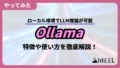ノルウェーのオスロ大学(University of Oslo)やロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ(UCL)、アメリカのインディアナ大学キンゼイ研究所(Kinsey Institute)などが協力して行った最新の調査により、この10年ほどの間にマスターベーション(セルフ行為)をする人が男女とも増えていることが明らかになりました。
調査は16歳~44歳の男女を対象に、1999〜2001年と2010〜2012年の二つの期間に実施され、1ヶ月の間にセルフ行為をした女性は37.0%から40.3%へ、男性は73.4%から77.5%へ増えました。
特に16〜24歳の若い男性では、セルフ行為を行った割合が約9.4ポイントも上昇しており、この変化が特に注目されています。
一体なぜ、若い世代を中心にセルフ行為をする人が増えたのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年9月11日に『The Journal of Sex Research』にて発表されました。
目次
- 自慰回数は時代と共に変わるのか?
- なぜマスターベーションの回数が増えているのか?
- なぜ人類はマスターベーションをするのか?
自慰回数は時代と共に変わるのか?

マスターベーション、つまり「自慰行為」について、昔から根強い偏見があります。
よくあるのは、「恋人やパートナーがいない人が仕方なくするものだ」といったイメージです。
でも、本当にそうでしょうか?
実際のところ、恋人やパートナーがいる人でもマスターベーションをしていることは珍しくありません。
では、なぜ私たちはこんな誤解をしてしまうのでしょう?
この問題を理解するには、歴史的な背景に目を向ける必要があります。
かつて、欧米を中心にマスターベーションは宗教的にも医学的にも「有害な行為」と考えられてきました。
例えば19世紀のフランスの医学者デランドは、著書のなかでマスターベーションをこう表現しています。
多くの若者が、自らの『罪なる行為』が、健康や体力の基盤を密かに蝕んでいることにまったく気づいていない。
Many a young man … totally unconscious that his criminal act was sapping to the very foundation his health and strength. (L. Deslandes, 1839)
また、19世紀後半のアメリカで健康改革運動を行ったジョン・ハーヴェイ・ケロッグも、次のように書いています。
独習の悪癖(自慰)は、精神錯乱の最も一般的な原因の一つである。
That solitary vice is one of the most common causes of insanity(『Plain Facts for Old and Young』1881年改訂)
こんな風に、かつての社会ではマスターベーションは健康を害する「悪行」とみなされ、罪悪感や羞恥心を植えつけられてきました。
こうした背景から生まれた「マスターベーション=恥ずかしい」「異常なこと」というイメージが、現代まで根強く残っているわけです。
ところが、近年ではこうした偏見に対する見直しが進んでいます。
科学の研究が進んだ結果、マスターベーションが体や心に悪いという根拠はほとんど見つかっていません。
それどころか、最近の研究レビューでは、マスターベーションがストレスを減らしたり、睡眠の質を高めたりすることと関連があることが報告されています。
つまり、マスターベーションにはむしろ健康面で良い影響がある可能性が示唆されつつあるのです。
実際、かつては「恥ずかしい」「隠すべきこと」とされたセルフ行為ですが、徐々に文化的な偏見が薄れ、特に女性のマスターベーションについての社会的な許容度が高まってきたという指摘もあります。
ただ、こうした社会的変化が進む一方で、男性と女性とではセルフ行為をどういう状況で行うかに違いがあるという研究結果も以前から知られていました。
男性はパートナーとの性行為が少ないときに、その不足分をマスターベーションで補う傾向があるのに対し、女性は逆にパートナーとの性生活が充実しているときほど、セルフ行為も積極的に行う傾向があるという報告があったのです。
2000年前後のイギリスの調査でも、男性は性交の回数が増えるほどセルフ行為の頻度が低くなり、女性は性交の回数が多いほどセルフ行為の頻度も高くなるという傾向が示されていました。
しかし既存の研究は統一性がなく、大きな傾向を捕らえるには十分とは言えませんでした。
そこで今回、イギリスの研究チームが着目したのが、1999〜2001年と2010〜2012年に行われたイギリス全国調査(Natsal-2とNatsal-3)という2つの大規模調査データです。
マスターベーションに時代による変化や男女差はどの程度あるのでしょうか?
なぜマスターベーションの回数が増えているのか?

研究チームは今回、マスターベーション、つまりいわゆる「セルフ行為」が、この約10年ほどで本当に増えたのかを調べるため、大規模なデータを分析しました。
使用されたのは1999〜2001年(Natsal-2)と2010〜2012年(Natsal-3)に実施されたイギリスの全国調査です。
これはイギリスの全国的な調査で、性に関するさまざまな質問をランダムに選ばれた一般市民に尋ねたものです。
調査方法は概ね同様で、「この1ヶ月の間にマスターベーションをしましたか?」といった質問を参加者がコンピュータ上で自分で回答しています。一部の項目は測り方に差がある可能性があります。
このため、回答者は周囲を気にすることなく、正直な回答をしやすいよう配慮されています。
まず調査対象として、1999〜2001年では16歳〜44歳の男女11,161人、2010〜2012年では同じ年齢範囲の男女9,902人のデータを比較しました。
また2010〜2012年の調査では、年齢の範囲を広げて16歳〜74歳までの男女15,162人にも調査を行い、年齢やパートナーとの関係状況、宗教や健康状態などの個人の特徴が、セルフ行為をする頻度とどのように関係しているかも調べました。
では、実際の結果を見てみましょう。
まず、この10年ほどの間に「セルフ行為」を行う人は、男女とも明らかに増えていました。
調査によると、16〜44歳の女性では、過去1ヶ月の間にセルフ行為をしたと答えた人の割合が37.0%から40.3%に増えました。
男性の場合はさらに高く、73.4%から77.5%に増加しています。
特に注目したいのは、「若い世代ほどこの増加傾向が強い」ということです。
16〜24歳の若い男性では、10年前に比べてセルフ行為をした人が73.2%から82.6%へと、9.4ポイントも増えています。
実にこの年齢の男性の5人に4人以上が、過去1ヶ月の間にセルフ行為をしたことになります。
研究チームは、この不思議な変化の背景として「インターネット環境とスマートフォンの普及」という要素を挙げています。
2000年代に入ると、インターネットが急速に普及し、スマートフォンの登場により動画やアダルトコンテンツなどをいつでもどこでも見ることが可能になりました。
要は、「セルフ行為に最適な環境が手のひらの中に収まった」とも言えるわけです。
実際、研究者たちは「ポルノの主な利用目的がセルフ行為であることを考えると、ポルノへのアクセスが容易になったことが、セルフ行為の頻度増加を後押しした可能性があります」と述べています。
また女性の場合、セルフ行為への社会的な偏見がこの10年で弱まったことが、より多くの女性がセルフ行為を試すきっかけになった可能性もあります。
なぜ人類はマスターベーションをするのか?

この調査結果の面白い点は、セルフ行為が増えたのが「恋人やパートナーがいる人」だったということです。
「セルフ行為」と聞くと、「パートナーがいない寂しい人がやるもの」というイメージが根強いですが、実際には逆の傾向がはっきり出ていました。
調査によれば、恋人や配偶者など「安定したパートナーがいる人」や「カジュアルな恋人がいる人」では、セルフ行為をする人の割合が男女ともに10年前より大きく増加しています。
例えば、「パートナーがいる女性」の場合、10年前は1ヶ月間にセルフ行為をした人は約4割弱でしたが、2010〜2012年の調査では4割を超えるまでになりました。
男性でも同様に、パートナーがいる人ほどセルフ行為を行う割合が増え、76.1%(安定した関係)/87.7%(カジュアルな関係)と高水準になっています。
一方で、「恋人やパートナーがいない人」の間では、10年前とほとんど変化がありませんでした。
パートナーがいない女性では1ヶ月間のセルフ行為の実施率は20.2%とほぼ横ばい、男性でも67.7%とほぼ変わらなかったのです。
ここで、疑問が生じます。
なぜ「恋人がいる人ほどセルフ行為をするようになった」のでしょうか?
普通に考えれば、パートナーがいれば性的欲求は満たされやすいので、セルフ行為は減りそうなものです。
ところが実際には、その逆の現象が起きているのです。
では、セルフ行為の増加はパートナーとの性行為が減少した結果、足りない部分を補うために増えたのでしょうか?
それとも、性的な価値観の変化がセルフ行為をより自由な「自己表現」として楽しめる状況を作ったのでしょうか?
このような疑問を明らかにするため、研究チームは調査結果をさらに詳しく分析しました。
マスターベーション(いわゆるセルフ行為)の頻度が増えていることが分かった研究チームは、「セルフ行為をする理由」についてさらに踏み込んで調べました。
ここで興味深いのが、「セルフ行為をする理由は人によって異なり、さらに男女間でも違いがある」という結果です。
まず、今回の調査では、パートナーがいる人たちの間でもマスターベーションが増えていましたが、実際にパートナーとの性行為の頻度とセルフ行為の頻度を比べてみると、男女で対照的な傾向が現れました。
女性の場合、パートナーとの性行為の回数が多ければ多いほど、セルフ行為も頻繁に行う傾向がありました。
これは、一見不思議な結果です。
パートナーとの性行為で満たされているなら、わざわざセルフ行為をする必要はないと思うかもしれません。
ところが女性にとっては、パートナーとの性生活が充実しているからこそ、セルフ行為という「別の形の楽しみ」も積極的に取り入れている可能性があることが示唆されました。
一方で男性の場合は逆でした。
パートナーとの性行為の頻度が多い人ほど、セルフ行為をする割合が低くなっていました。
これはつまり、男性にとってのセルフ行為が「パートナーとの性行為が不足したときの埋め合わせ(代用品)」として機能している傾向があることを示唆しています。
パートナーとの性行為で十分満足しているなら、あえてセルフ行為をする動機は少なくなるというわけです。
しかし、研究チームがさらに分析を進めたところ、この男女の違いはもっと複雑で、一面的に捉えるのは危険だということが分かってきました。
特に重要なポイントとして浮かび上がったのが、パートナーとの性生活の「満足度」や「性的な問題」が、男女問わずセルフ行為をするかどうかに深く関係しているということです。
たとえば、「本当はもっとパートナーとセックスをしたいのに、実際には頻度が少なくて不満だ」という人や、「自分やパートナーが性的な悩みや障害を抱えていて、性生活がうまくいっていない」という人では、セルフ行為をする割合が男女関係なくともに高くなる傾向がありました。
これは先に触れた「男性は代用品として、女性はプラスアルファとしてセルフ行為をする」という単純な図式とは少し違います。
セルフ行為がただパートナーとの性の不足を補う「代替行動」になることもあれば、パートナーとの性行為が十分であってもさらに楽しみを深める「補完行動」になることもあるわけです。
つまりセルフ行為は、その時の状況や感情次第で、男性でも女性でも全く違う役割を果たしていることが明らかになりました。
「セルフ行為」を食べ物にたとえるならば、通常時は、女性にとってはお腹がいっぱいでもついつい楽しんでしまう「別腹のデザート」のような位置づけと言えます。
一方、男性にとっては「普段の食事が足りない時に登場する非常食」のようなものでしょう。
しかし、パートナーとの関係がうまくいかないときは、男女の差は消えてしまい性別を問わず人はセルフ行為に走ってしまう傾向があるわけです。
研究チームも、「マスターベーションにはパートナーとの関係をさらに良くする『補完的な側面』と、関係がうまくいかないときの『代替的な側面』の両方があり、状況に応じてその役割が変わっているようだ」とまとめています。
まさにこのセルフ行為の「状況次第の役割変化」が、今回の調査の重要な発見の一つと言えるでしょう。
今回の研究からは、私たちが普段あまり人に話さない「セルフ行為」、いわゆるマスターベーションが、実は社会や文化の変化によって、位置づけや意味を大きく変えている可能性があることが明らかになりました。
研究チームは今後、この研究成果を踏まえて、より詳細な調査を計画しています。
次回のイギリス全国調査(Natsal-4)は2022年から2024年にかけて実施が完了しており、現在はデータ分析が進行中です。
これによって、新型コロナの影響やスマートフォン時代の真っ只中での性行動や意識が、今回の結果からさらにどう変わったのかが、近い将来明らかになるでしょう。
元論文
Trends in Masturbation Prevalence and Associated Factors: Findings from the British National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles
https://doi.org/10.1080/00224499.2025.2555053
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部