熱や頭痛を感じたとき、ごく自然に手に取る鎮痛薬アセトアミノフェン。
実は、多くの国で最も一般的に使われるこの薬が私たちのリスク感覚を変え、いつもより大胆で危険な行動を引き起こすかもしれない——そんな驚きの研究結果が、アメリカのオハイオ州立大学(OSU)で行われた研究によって明らかになりました。
この研究では、3つの実験にわたり合計545名以上のボランティアが参加し、いずれの実験も1,000mg(Extra Strength相当)のアセトアミノフェンを1回投与して検証しています。
日常生活で頻繁に服用されるこの薬が、私たちの意思決定にどのような影響を与えているのでしょうか?
研究内容の詳細は『Social Cognitive and Affective Neuroscience』にて発表されました。
目次
- 薬が感情にまで効く? アセトアミノフェンの謎
- 痛みだけでなく怖さも止めるアセトアミノフェンの衝撃
- なぜアセトアミノフェンで恐怖が薄れる? 脳と薬の深い関係
薬が感情にまで効く? アセトアミノフェンの謎

アセトアミノフェンという薬は、多くの人にとって「頭痛や発熱が起きたときにまず手を伸ばす安心の相棒」です。
夜中に不意に電気が消えたとき、どこにあるのかもはっきり覚えていないのに、探せば意外とすぐ見つかる懐中電灯のように、いつも生活のそばにある存在といえるでしょう。
そのおかげで、実際にどんな作用をもっているのかを深く考える機会はあまりありません。
薬局で買った総合感冒薬や市販の頭痛薬の成分表をよく見ると、アセトアミノフェンが配合されていることがほとんど——つまり、わたしたちは意識していないだけで、頻繁にこの薬に助けられているのです。
ところが近年の研究では、アセトアミノフェンが「身体の痛み」をやわらげるだけでなく、「心の痛み」や「感情の強さ」にまで影響を及ぼす可能性がある、と注目されるようになりました。
たとえば、人間関係のトラブルで落ち込んだときの“心の痛み”や、他人の苦しみを見たときに共感する気持ちが、アセトアミノフェンを服用すると弱まるかもしれないというデータが出てきたのです。
さらに驚くことに、ネガティブな映像を見たときの嫌悪感だけでなく、ポジティブな画像を見たときのワクワク感までも“少し鈍くなる”のではないかという報告があり、つまりこの薬はわたしたちの「感情全般」を少しだけ麻痺させる効果をもつ可能性があるのです。
この「感情を緩和・鈍化させる」作用が話題になる理由は、私たちの行動が感情に強く左右されているからです。
よく「理屈ではわかっていても、感情が追いつかない」などといいますが、実際、リスクのある状況でどこまで踏み込むかは、論理よりも“怖い・怖くない”といった感情が決め手になることが多いのです。
もしアセトアミノフェンによって「不安」や「恐怖」といったネガティブな感情が弱まってしまうと、私たちが危険を危険と感じにくくなる恐れが出てきます。
実際、リスクを好むか嫌うかは「アフェクト・ヒューリスティック」という考え方でも説明されています。
これは、難しい計算をしなくても“直感的な感情”で判断してしまう人間の特性です。
たとえば、少しでも不安を感じれば「これは危ない」と足を引っ込めるし、逆に「面白そう!」と胸が高鳴れば多少の危険を冒してでも行動してしまう。
つまり、アセトアミノフェンのように感情を鈍くする薬は、この“怖い or 楽しい”という直感スイッチを誤作動させる可能性があり、結果として「まぁ大丈夫だろう」と高を括って、破裂寸前の風船にさらに空気を送り込むような行為に踏み切ってしまうかもしれません。
さらに、アセトアミノフェンは19世紀末から研究が始まり、20世紀に入って鎮痛・解熱薬としての地位を確立し、今や「約600種類以上の市販薬」に含まれると言われるほど幅広く流通しています。
アメリカでは週に一度は何らかの形で服用している成人が23%もいるという統計もあり、まさに世界的に最も一般的な鎮痛薬のひとつといえます。
友人との飲み会の前にちょっとした頭痛を抑えるために飲むこともあれば、仕事中に熱を我慢できずに一錠……という具合に、ほとんど無意識のうちに使われている薬と言えるでしょう。
こんなにも多くの人が使っているならば、その影響が「感情」にとどまらず「重大な意思決定や行動の選択」にまで波及している可能性は見過ごせません。
たとえば、運転中の判断や、投資などで大きなお金を動かす際の度胸の加減、さらには手術などの医療行為を選択する場面でも、リスク感や不安感が薄まったまま判断すると、思いもよらないミスや後悔が生まれるかもしれないのです。
アセトアミノフェンが持つこの意外な心理的影響に、多くの研究者や医療関係者が注視するようになってきました。
そこで今回、研究者たちは「アセトアミノフェンを飲むと、本当にリスクの高い行動をとりやすくなるのか」を実験的に検証することにしたのです。
さらに、「そんな行動の変化はどういう心理的メカニズムによって起こるのか?」「危険度をどのように認知しているのか?」を詳細に調べるため、複数の実験やアンケートを組み合わせ、参加者たちの意思決定を隅々まで観察していきました。
痛みだけでなく怖さも止めるアセトアミノフェンの衝撃

研究チームは、まず複数の実験で合計500名以上のボランティアを対象に、二つのグループに分けました。
一方のグループには「痛みに効く成分入り」のアセトアミノフェンを、もう一方には「ただの水かもしれない」偽薬(プラセボ)を飲んでもらいます。
しかも、どちらを飲んだかは当の本人も、実験を担当するスタッフもわからないように工夫されています。
これは、心理的な先入観や「薬を飲んだから効いているはず」という思い込みを排除するための“二重盲検”方式です。
まるでコインを投げてAチームとBチームに分け、それぞれに“味がそっくりなお茶”を飲ませるイメージを想像すると分かりやすいでしょう。
ただし、中には有効成分が含まれているため、本当に“感情や判断力”が変化するのかを客観的に測れる仕組みです。
その後に行われた“メインイベント”が、BART(Balloon Analog Risk Task)というコンピュータ上の風船ゲームでした。
画面にはしぼんだ風船が表示され、参加者はボタンを押すごとにプシュッ、プシュッと空気を入れていきます。
風船を膨らませれば膨らませるほど「仮想のお金」がもらえますが、ある時点で突然パンッと破裂し、それまで貯めた分がゼロになるというリスクも伴うため、参加者は「どのあたりで止めるか」を自分で判断しなくてはなりません。
このタスクはあたかも薄氷の上を歩くようなドキドキを作り出すので、人がどの程度リスクをとりたがるかをビジュアルに捉えられるのです。
加えて研究チームは、アンケート調査でもリスク評価を測定しました。
たとえば「友人の秘密をSNSで暴露したら?」や「危うい投資案件に資金を全投入すると?」といったシチュエーションを思い浮かべてもらい、「どのくらい危険か」「どのくらい魅力的か」を直感的に数値化させる形式です。
こうすることで、行動面だけでなく、頭の中でのリスク認知も把握しようとしたわけです。
結果はとても示唆的でした。
アセトアミノフェンを飲んでいたグループは、そうでないグループよりも、風船をより大きく膨らませる(=リスクをとる)傾向が強い場合が多かったのです。
同時に、危険度を低く見積もる(「これくらいなら大丈夫」と思う)回答も増える傾向にありました。
ただし3つの実験のうち1つは明確な差が見られなかったため、「すべての状況でリスクが増大する」とまでは言えません。
しかし、すべてのデータを統合した解析では有意にリスク選好が高まる結果が示され、研究チームは「アセトアミノフェンを服用していると危険度を控えめに見積もる→もう少し続けても平気と感じる→風船が割れるリスクが増す」という連鎖を指摘しています。
この研究のどこか革新的だったのか?
第一に、世界で広く使われる鎮痛薬が脳や心の深い部分にある“怖さ”の感覚へ影響し、行動を左右している可能性を実験的に示した点です。
第二に、BARTなどのユニークな課題を使うことで、単なるアンケート結果の推測ではなく“実際にどれだけ危険な行動をとるか”を可視化できたことが大きな特徴です。
さらに、偽薬との比較を行う二重盲検という厳密な方法で、「アセトアミノフェンだと知っているから大胆になる」という思い込みの影響を排除した点も評価されます。
こうした複数の実験を総合し、「誰にでも身近な鎮痛薬が、私たちのリスク選好をわずかに増幅させるかもしれない」という疑問が浮かび上がりました。
研究者たちは「アセトアミノフェンを使うな、という話ではなく、こうした心理的影響があることを知ったうえで、意思決定に臨むことが大切」とコメントしています。
今回の結果は今後の議論をさらに活性化させる強い材料となるでしょう。
なぜアセトアミノフェンで恐怖が薄れる? 脳と薬の深い関係
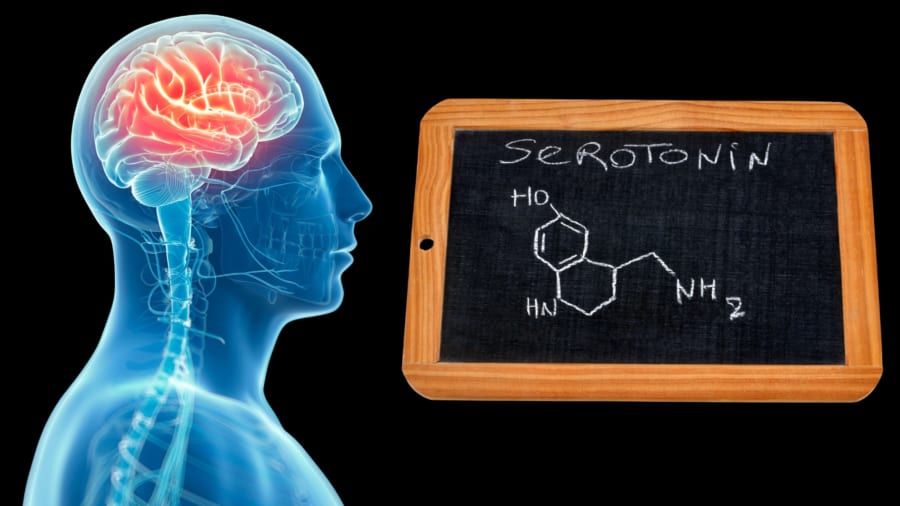
今回の研究でいちばん衝撃的なのは、「アセトアミノフェンが体の痛みだけでなく、“リスクを怖いと感じる感覚”までも和らげているかもしれない」という点です。
多くの人は頭痛や発熱を抑えれば、それで慎重さや警戒心まで変わってしまうとは想像しません。
しかし実験データからは、不安を抑える経路や、ミスを察知する脳の信号が弱まり、その結果リスクの大きい行動を選択しやすくなるケースがあることが見えてきました。
たとえば、失敗を意識したときに脳で生じる“エラーポジティビティ(Pe)”という信号がアセトアミノフェン摂取中には低下するとの報告があり、同様に前部島皮質(危険を察知して緊張状態を生み出す場所)にも影響しているのではないか、と指摘されています。
これらの神経メカニズムを正確に解明するには、プロスタグランジン以外の受容体や神経伝達物質との関係をさらに探らなければなりません。
「バニロイド受容体」「カンナビノイド受容体」「セロトニン系」などがどこまで“恐怖ブレーキ”に関わっているのかは、まだ未知の部分が大きく、今後の研究が期待されます。
また、現実世界でのリスクシーンはBARTよりもはるかに多様です。
大きなお金を投資するとき、車を運転するとき、家族の医療選択をするとき——もしアセトアミノフェンによって危険感覚が少しでも鈍るなら、思わぬ意思決定ミスを招く可能性も否めません。
それでも研究者たちは「過度に怖がる必要はないが、知識を持って使うことが重要」と強調しています。
1,000mgの服用がすべての人に同じ影響を与えるわけでもなく、異なる体質や状況で効果は変動しうるからです。
結局のところ、この研究は「鎮痛薬といえども、感情やリスク感覚に影響を及ぼす可能性がある」ことを数字で示した初めての大きな一歩といえます。
「痛み止めなんて、よくある薬」という認識が、実は私たちが思っている以上に深いレベルの意思決定にまで影響しているかもしれない。
こんなにも身近な薬に未知の面が隠れているのだとすれば、私たちはもう一度、日常で無意識に服用しているものについて、少しだけ慎重になったほうがいいのかもしれません。
とはいえ「アセトアミノフェンを禁じる」わけではなく、痛みを抑えつつも危険判断への影響を理解しておく——このバランスこそが、研究者たちが伝えたかった最大のメッセージでしょう。
元論文
Effects of acetaminophen on risk taking
https://doi.org/10.1093/scan/nsaa108
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


