切り傷がかさぶたになって自然に治るように、私たちの体には「治癒能力」があります。でも、もし腕や足を失ってしまったら、それは元に戻ることはありません。
ところが自然界には、失った体の一部をまるごと再生できる生き物たちが存在します。たとえばトカゲは尻尾を、サンショウウオは脚や心臓までも再び生やすことができます。
両生類や爬虫類は、進化的には哺乳類よりも前の段階にある生物たちです。そのため、この事実は人間を含む哺乳類たちが、進化の過程でこの強力な再生能力を捨てたことを意味しています。
では哺乳類はなぜ、再生という“最強の回復能力”を、進化の過程で封印したのでしょう?
その答えは、進化の裏に潜む「見えない代償(トレードオフ)」を知ることで、見えてくるかもしれません。
目次
- 哺乳類の体には、なぜ再生能力がないのか?
- 哺乳類が再生能力を捨てた進化上の4つの理由
- 進化とは「捨てる選択」でもある
哺乳類の体には、なぜ再生能力がないのか?
驚くべきことに、私たち人間を含む哺乳類の体内にも、四肢や臓器を再生するための遺伝子回路が隠されています。実際、サンショウウオやゼブラフィッシュといった、両生類や魚類など哺乳類よりも進化的に古い動物たちは、失われた手足、心臓、さらには脊髄までも再生する能力を備えています。
こうした能力は決して“魔法”ではなく、特定の遺伝子群の働きによって実現されていることが、近年の研究でわかってきました。そして驚くべきことに、これらの遺伝子の多くは哺乳類のゲノム内にも存在しているのです。
つまり、人間を含む哺乳類も、本来は再生能力を持ちうる“設計図”を受け継いでいるということになります。
しかし現在、それらの遺伝子は私たちの体の中でほとんどが**オフ(不活性化)**にされており、実際に再生は起きません。
ところが、サンショウウオやトカゲなどの再生能力を研究する中で、科学者たちはこうしたオフになった遺伝子を再びオンにすることで、哺乳類でも再生を促すことができる可能性を見出しています。たとえば、2024年の研究では、あるタンパク質の働きを抑えるだけで、失明したマウスの網膜が再生し、視力が回復するという成果も報告されました。
ここで、自然な疑問が浮かびます。
もし私たちの体にも再生能力を引き出すスイッチがあるのなら、なぜそのスイッチは最初から“オン”になっていないのでしょうか?
現在、研究者たちが有力視しているのは、以下の4つの進化的仮説です。これらは単独ではなく、相互に補完し合う複雑な要因として働いたと考えられています。
哺乳類が再生能力を捨てた進化上の4つの理由
【仮説1】がんの抑制とのトレードオフ仮説
再生とは、損傷を受けた組織において細胞が活発に分裂し、新たな組織を形成する過程です。ところが、この細胞の活発な増殖は、制御が破綻すればそのまま“がん”に直結します。
実際、ヒトを含む哺乳類では、p53やRbなどのがん抑制遺伝子の働きが非常に強力で、細胞がむやみに分裂しないよう厳しく監視されています。
これは高寿命・高代謝・大型化した体の構造を維持する上で不可欠でしたが、その代償として、再生に必要な細胞分裂の柔軟性を失ったと考えられています。
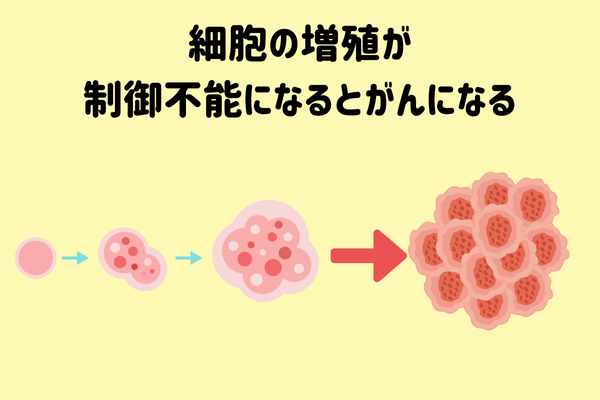
一方、サンショウウオなど再生能力の高い動物は、がんになりにくいにもかかわらず、がん抑制のために哺乳類ほど強力な分子機構を持っていないことが報告されています。これは、彼らが“暴走しない再生”を実現する別種の制御系を持っている可能性を示唆していますが、その詳細はまだ完全には解明されていません。
これだけ聞くとサンショウウオの方が優れた生命に感じますが、ただ、ここには体の構造の単純さが関係している可能性が指摘されています。
両生類や爬虫類に比べて、哺乳類は臓器の構造や機能がはるかに複雑で、神経系も高度に発達しています。たとえば、人間の脳は数百億の神経細胞から成り、複雑な記憶や感情、行動を制御しています。一方で、サンショウウオなどは神経系が比較的シンプルで、臓器の層構造や細胞の種類も少ない傾向があります。
このような構造の違いは、再生においても大きな意味を持ちます。シンプルな構造であれば、失われた部分をある程度“テンプレート”のように再現することが可能ですが、複雑な構造になると、再生過程でほんのわずかな誤差が致命的な機能不全につながる恐れがあります。
つまり、再生が可能かどうかは、「再生する能力そのもの」よりも、「再生によって何を再現するか」が問題なのです。
そのため、再生能力を維持するには、サンショウウオのように体の構造が単純であることが進化的に必要だった可能性があります。逆に、哺乳類のように高性能で複雑な身体構造を持つ動物では、むしろ不完全な再生がリスクになるため、その能力は進化の過程で徐々に抑制されていったのかもしれません。
【仮説2】免疫系の進化的衝突仮説
再生が成功するためには、組織内に炎症が少なく、細胞の変化に対して寛容な環境が必要です。
ところが哺乳類では、傷ができると即座に獲得免疫系が強力な炎症反応を起こし、損傷部位を繊維で閉じてしまう=瘢痕化(はんこんか)する方向に進みます。
瘢痕化というのは、組織が傷を修復する際に、本来の細胞構造や機能を再生せず、繊維質な“傷跡”として治る現象を指します。
これは感染症リスクの高い環境で有利だったと考えられます。炎症反応によって細菌やウイルスの侵入を素早く防ぎ、傷口を閉じてしまえば、短期的な生存率が上がるからです。
この戦略は「再生よりも応急処置を優先する」という方向への進化であり、免疫システムの進化が再生能力を犠牲にしてしまったという可能性を示しています。
【仮説3】恒常性・組織安定性の優先仮説
サンショウウオが脚を再生できるのは、その損傷部位の細胞が一度「未分化」の状態に戻るからです。
彼らは手足や尾を切断しても、「芽体(ブラステマ、英:blastema)」と呼ばれる未分化な細胞のかたまりを作り出し、そこから新しい組織を再構築します。
これは、いわば体の一部を「最初から作り直す」ようなプロセスです。
そして驚くべきことに、彼らはこの再生過程をがん化させずにコントロールする仕組みを持っています。たとえば細胞の分裂がきちんと途中で止まるようになっており、無限に増殖し続けるようなことがありません。
この能力は一見万能のように思えますが、再生能力にも「コスト(代償)」が存在します。
たとえば、再生には大量のエネルギーと時間がかかります。サンショウウオが脚を再生するには数週間以上かかります。その間、逃げることも、繁殖することもままならず、捕食者に襲われるリスクが高まります。
また、再生能力を維持するには、体の中に「いつでも変化できる未分化な細胞」を抱えておかなければなりません。これは、生体の安定性や成熟した神経系の発達と相反する問題です。
高度な学習能力や複雑な社会行動を発達させたヒトのような動物にとっては、むしろ組織の安定性の方が重要だったと考えられます。
「未分化状態への巻き戻し」は、体の構造や機能を一時的に不安定化させるリスクをはらんでおり、哺乳類は各器官の構造と機能を維持する恒常性を重視した結果、「細胞が変化できる柔軟性」を抑えるよう進化したと考えられるのです。
再生能力と身体機能の安定性の間には、機構的に両立することが難しい壁があるのです。
【仮説4】ライフサイクルと環境適応の違い
再生能力の高さは、「再生が間に合う」環境で初めて役に立ちます。
サンショウウオやトカゲなどは動きが遅く、比較的安全な水辺や森林に生息し、捕食圧を逃れる手段として尻尾の再生などが機能します。
対照的に、哺乳類の多くは活動的で捕食圧も高く、傷を負ったらすぐに逃げねばなりません。再生に数週間を要するよりも、その間を応急処置でしのぐことのほうが生存に直結するという環境下では、瘢痕化(はんこんか)という早急な修復メカニズムの方が有利だったと考えられるのです。
さらに哺乳類は「早熟・短期繁殖戦略」をとる種も多く、長寿で再生力を維持するよりも、短命でも多くの子を残すことに適応していた可能性もあります。
進化とは「捨てる選択」でもある
ここまで見てきたように、哺乳類が再生能力を失った背景には、がん、免疫、恒常性、環境といった複数の要因が絡み合った進化的判断があったと考えられるのです。
重要なのは、「再生能力=無条件で優れている」というわけではないことです。
進化とは、常に「ある能力を得るために、別の能力を捨てる」トレードオフの連続です。哺乳類は、再生という能力を抑える代わりに、高度な神経系、優れた免疫防御、複雑な行動様式を発達させることができたのです。
とはいえ、私たちの体にはいまだに、その「再生の設計図」が眠っています。近年の再生医療やゲノム編集技術の進歩により、こうした“封印された力”を再び目覚めさせようとする試みが進んでいます。
たとえば、視細胞を再生して視力を回復させたマウスの実験、皮膚や心筋の再構築、さらには人工的に「芽体(ブラステマ)」を生成して四肢や器官の再生を誘導しようとする研究も始まっています。
自然環境の中では、生き延びるために「素早く傷をふさぐ」戦略が有利でした。けれど現代の私たちは、医療という支えのもとで、安全に時間をかけて回復に専念することができます。
つまり、かつて進化が“捨てざるを得なかった”能力を、今の私たちは改めて取り戻せる環境にいるのです。
もちろん、そこには大きな壁もあります。がん化のリスク、免疫との干渉、そして生命操作にまつわる倫理的な課題――再生を再び可能にするには、これらすべてを慎重に乗り越える必要があります。
サンショウウオは腕を生成できるのに、なぜヒトにそれができないのか? その問いは「ヒトがどのような進化の道を選んだのか」という問題の答えでもあります。
哺乳類は、再生の力をあえて手放し、その代わりに「長寿」「知能」「社会性」といった複雑で洗練された生き方を獲得しました。
それでも、もし未来の医療がこの壁を乗り越え、再生の力を安全に呼び戻すことができたなら――それは単なる医学の進歩ではなく、私たちが一度手放した進化の“もう一つの選択肢”を、自らの手で再び選び取るという行為になるのかもしれません。
元論文
To regenerate or not to regenerate: Vertebrate model organisms of regeneration-competency and -incompetency
https://doi.org/10.1111/wrr.13000
The human ARF tumor suppressor senses blastema activity and suppresses epimorphic regeneration
https://doi.org/10.7554/eLife.07702
Tumor suppressors: enhancers or suppressors of regeneration?
https://doi.org/10.1242/dev.084210
Complex Tissue Regeneration in Mammals Is Associated With Reduced Inflammatory Cytokines and an Influx of Regulatory T Cells
https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01695
ライター
朝井孝輔: 進化論大好きライター。好きなゲームは「46億年物語」
編集者
ナゾロジー 編集部

