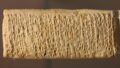新型コロナウイルスのパンデミックによって、ワクチンに対する安心感や信頼感はこれまで以上に大きな話題となってきました。
ところがアメリカ・オハイオ州にあるMiami University(MU)とカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)が中心となって行った研究によって、「ワクチンをどう考えるか」という私たちの心の持ちようが、実際の抗体の量や副反応の出方、さらにはストレスや幸福感などの心理状態にまで影響を及ぼす可能性があるといいます。
たとえば、「このワクチンは効くはず」「自分の体はきっと上手く対応するだろう」というポジティブな気持ちで接種を受けると、接種後のストレスや副反応が少なくなり、逆に「副反応があるのはワクチンが効いている証拠だ」ととらえると、抗体の増え方にまで変化が見られたというのです。
こうした“心”と“体”の驚くべきつながりが解明され始めたことで、単なる「有効率」だけでは語り尽くせないワクチン接種の新たな側面が浮かび上がっています。
では、具体的にどのような研究が行われ、どんな結果が得られたのでしょうか。
本記事では、その最新の知見と今後の期待される応用について、わかりやすく解説していきます。
研究内容の詳細は『Brain, Behavior, & Immunity – Health』にて発表されました。
目次
- 一見“気のせい”が、実はカギを握るかもしれない
- ワクチン副反応は“効いている証”なのか? 驚きの新研究
- 知られざる心理要因:ワクチン接種を変えるヒント
一見“気のせい”が、実はカギを握るかもしれない

世界規模で猛威を振るった新型コロナウイルスは、WHOの推計によれば全世界で7億7000万人を超える感染者と約690万件の死亡例をもたらし、社会に大きな混乱を引き起こしました。
感染拡大を食い止める切り札として、アメリカでは3種類のワクチン(J&J、Moderna、Pfizer)が短期間で開発され、多くの人々が接種を受けています。
これらのワクチンは有効かつ安全とされながらも、接種を受けた後の抗体の上がり方や副反応、接種に対する感情や不安の感じ方が人によって大きく異なるのも事実です。
一方で「心や考え方」という心理的な要素が、実際の体の反応や健康状態に深く作用することが、近年の研究で次々に明らかになってきました。
たとえばストレスを「自分の成長に役立つもの」と考える人は、“害にしかならない”と思い込んでいる人よりも前向きにストレスを乗り越えたり、体内のホルモン変化がプラスに働いたりすることが報告されています。
また、医療現場でも「プラセボ効果」「ノセボ効果」という言葉が示すように、薬や治療に対する期待や不安の度合いが、実際の治療効果や副作用の出方を左右する現象も知られています。
たとえば、アレルギー治療を受ける子どもに対して「症状があるのは治療が効いている証拠だよ」と前向きに捉えさせるだけで、不安が軽減されるうえに治療効果が上がる例も報告されてきました。
こうした話は一見「気持ちの問題」と片付けられがちですが、最近ではワクチンという実社会での大規模接種の場面でも、心理的な要因が「心身にどんな影響を与えうるのか」に注目が集まり始めています。
「ワクチンは自分を守ってくれるに違いない」と思う人と、「副反応が怖いから何が起きるかわからない」と思う人とでは、ワクチン接種後の体験がまるで違うものになるかもしれない――そう考えると、私たちの考え方(マインドセット)を変えるだけで副反応への恐怖を和らげたり、実際の免疫反応を改善したりできる可能性があるのではないか、と期待が高まっているのです。
そこで今回研究者たちは、「ワクチンに対する信念や思い込みが、実際に接種後の抗体量や副反応、さらに人々の気持ちの変化にどのような影響を与えるのか」を体系的に検証することにしました。
ワクチン副反応は“効いている証”なのか? 驚きの新研究

研究チームはサンフランシスコ湾岸エリアに住む成人、合計534名を募集し、それぞれがJ&J(1回接種)、ModernaやPfizer(2回接種)など異なるワクチンを受けるタイミングにあわせてデータを集めました。
まず、ワクチンを打つ直前の朝に「このワクチンはどれくらい効果があると思うか」「自分の体はしっかり対応できると思うか」「副反応はワクチンが効いている証拠だと感じるか」など、考え方(マインドセット)を測定。
加えて、接種当日から5日間は、毎日どんな副反応が出たか、どれくらいストレスや不安を感じたか、どれくらい幸せだったかを簡単な日記のように記録してもらいました。
さらに研究のユニークな点として、参加者の血液を採取し、ワクチン接種から1か月後と6か月後の中和抗体量を精密に測定したことがあります。
つまり、「考え方」と「実際の免疫反応」や「気持ちの変化」を同時に追跡し、どのように結びついているのかを具体的に検証できるようにしたのです。
結果、「ワクチンがきっと自分を守ってくれるはずだ」と確信している人ほど、実際に接種後に体調を崩すリスクが低く、不安な気持ちが少なくなる傾向が見られました。
具体的には、「接種当日に熱や頭痛などの副反応をどの程度経験したか」「どれほどストレスや落ち込みを感じたか」といったデータを詳しく調べた結果、ポジティブにワクチンを捉えている人ほど副反応が少なく、さらに接種直後の不安感やストレス値も低く抑えられていたのです。
加えて、全体的な気分に関しても、悲しい気持ちが薄らぎ、幸福感や安心感が高まるという“心理的メリット”も得られていました。
こうした傾向は、たとえば「絶対に副反応が出ないはず」と思い込んでいるわけではなくても、「ワクチンを打てて良かった」「やっとこれで自分や周囲の人を守れる」といった前向きな気持ちが背景にあると、自然に心と体が落ち着きを保ちやすくなる、と考えられます。
一方で、より興味深い結果が示されたのは、「副反応はむしろワクチンが効いている証だ」という認識を持っていた人たちに関する部分です。
「もし熱や頭痛が出ても、“自分の免疫が全力で働いている証拠だ”とポジティブに受け止められる」という姿勢があると、長期的に見ると1か月後や6か月後の抗体価(ワクチンがどれだけ免疫を高めているかを示す値)が高くなるという傾向が見られました。
つまり、「副反応=悪いもの」と思い込むのではなく、「ちゃんと免疫が作られているんだ」と前向きに捉えるだけで、体の反応がさらに後押しされている可能性がある、というわけです。
しかも、この“副反応は効いているサイン”というマインドセットは、実際に副反応が多く出る人ほど強いわけでもなく、経験した副反応の程度とはあまり関係がなかった、という点が非常にユニークでした。
「副反応が出ても出なくても、自分の中ではそれを前向きに解釈しよう」と構えている人ほど、接種後の抗体量がしっかり上がっていたようなのです。
一見すると「それは思い込みでは?」と感じられるかもしれませんが、研究者たちは、こうした“心の持ち方”が健康や治療効果に及ぼす影響が、実際に測定した生理学的指標(抗体価)ともリンクしていることに驚きを隠せない様子でした。
もしかすると「ポジティブに捉える人」は、接種後に適度に休養を取ったり、体を冷やし過ぎないよう気をつけたり、周囲のサポートを上手に利用したりするのかもしれません。
あるいは、脳や神経、ホルモン系の調整が働いて、自然治癒力や免疫力を高めるシステムが促進されている可能性もあります。
いずれにせよ、結果からは「ワクチン接種を受けるときの心理的な態度」が身体に影響を及ぼすことを示唆しており、研究者自身も「心理要因は決して無視できない」と再認識したといいます。
「思い込み」が身体や免疫反応にまで影響を及ぼす背景には、人間の脳や神経系と、免疫・ホルモン系が相互作用する仕組みがあると考えられています。
たとえば「プラセボ効果」や「ノセボ効果」と呼ばれる現象はその典型例です。
薬剤そのものに大きな作用がなくても、「効くはずだ」という期待があると脳が痛みを抑える物質を分泌しやすくなったり、逆に「副作用が怖い」という不安があると症状が出やすくなったりすることが、これまでの実験で確認されています。
実際、痛み止めや鎮静薬を与えられる際に「よい効果がある」と伝えられるか、「悪い反応が出るかもしれない」と伝えられるかだけで、まったく同じ薬剤でも体の反応が大きく変わるケースがあるのです。
こうした「心の持ちよう」と「身体のはたらき」の関係は、脳から放出される神経伝達物質やホルモンが、血管や免疫細胞に作用するルートを介して説明されることが多いです。
たとえばポジティブな期待感を抱くと、ストレスを感じたときに分泌されるコルチゾールなどのホルモン量が抑えられたり、痛みを和らげるエンドルフィンやオキシトシンといった物質が増えたりすることが報告されています。
結果として、免疫が過度に抑制されにくくなり、体が回復しやすい状態を保つことができるのです。
一方、ネガティブな思い込みを抱えると、不安や恐れといった感情がより長引きやすく、身体の警戒システムが過度に働いたままになってしまう可能性が高まります。
その結果、体力を消耗するだけでなく、免疫バランスが乱れやすくなり、疲れやすかったり、症状が重く感じられたりすることがあるのです。
ストレスや健康状態に関するマインドセットを扱う先行研究でも、同様のメカニズムが観察されています。
たとえば「ストレスは害にしかならない」という考え方と、「ストレスは成長や学びのチャンス」という考え方では、同じ出来事を体験してもホルモンの分泌量や血管の拡張・収縮の仕方が異なり、最終的には集中力や体調にまで影響が及ぶのです。
また、慢性疾患やがん治療での研究でも、患者自身の「病気や治療に対する見方」が痛みや疲労感、または免疫指標に影響を与えることが繰り返し示唆されています。
ワクチン接種の場合も同じように、「副反応はワクチンが効いている合図だ」という前向きな認識があると、体が多少の不調を“歓迎すべきサイン”として受け止められます。
そのため過度な不安や警戒のループに陥らず、結果的に体の調節機能や免疫応答がスムーズに働きやすくなるのかもしれません。
言い換えれば、心理的プレッシャーを過剰に感じずに済むことで、身体が自分の持つ防御反応を最大限に発揮できるのでしょう。
逆に「副反応が出たらどうしよう……」と必要以上に心配していると、ノセボ効果(悪い効果が出やすくなる現象)のように免疫システムが乱れやすく、症状も深刻に感じられやすいのかもしれません。
このように、思い込みや期待感が体に及ぼす影響は、生理学的にも心理学的にも複数のルートを通じて説明できるため、小さく見えて実はとても大きな差を生み出す可能性があります。
私たちの意識ひとつで、脳がどう反応するかが変わり、そこから先の免疫細胞やホルモン分泌、さらには日常生活の習慣(休養の取り方や食事の仕方など)までも連鎖的に変わっていくからです。
科学者たちは、こうした「マインドセットの力」をより正しく理解して活用することで、ワクチンをはじめとする医療行為の効果をさらに高め、患者や一般の人々の不安を軽減できるのではないかと期待しています。
今回の発見によって、ワクチン接種にまつわる議論はさらに広がるかもしれません。
これまでは「ワクチン自体の有効性や安全性」にばかり注目が集まりがちでしたが、そこに「人々の考え方」や「心の在り方」という新しい視点を組み合わせることで、より有益な接種体験を作り出すヒントが得られるのではないでしょうか。
たとえば、接種前の説明資料や医療従事者の声かけのなかに、「副反応があったとしても、体がきちんと働いているサインなんですよ」というメッセージを添えるだけでも、不安を多少なりともやわらげ、ポジティブな気持ちでワクチンを受けられるかもしれません。
研究チームは今後、「このような心理的アプローチが、実際にどれほど大きな効果をもたらすのか」をより詳細に検証していきたいとしています。
こうした研究が進めば、近い将来、ワクチンだけでなくさまざまな医療・健康の分野において、「考え方」をうまく使って効果や満足度を高める新しいスタイルが普及するかもしれません。
知られざる心理要因:ワクチン接種を変えるヒント
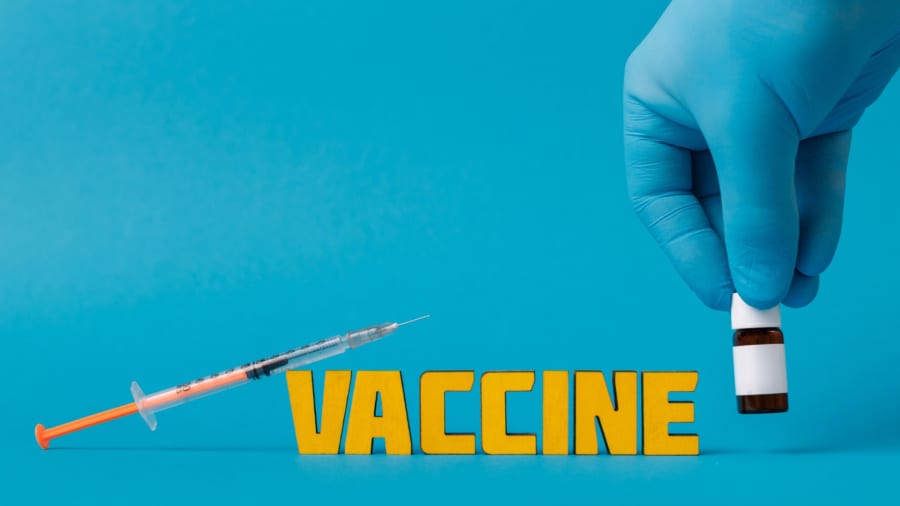
今回の研究によって浮かび上がった最大のポイントのひとつは、「副反応はワクチンがきちんと効いているサインだ」と認識している人ほど、後に測定した抗体量が高い傾向がある、という事実です。
普通、副反応というと「体に負担がかかっている証拠」や「ワクチンが怖い」というネガティブなイメージが先行しがちですが、この研究では逆に、「症状がある=免疫がちゃんと働いている」というポジティブな捉え方をする人たちのほうが、体内の免疫反応がより活性化している可能性が示唆されました。
一方、この考え方をしている人が必ずしも副反応の数や種類が多いわけではない、という結果も興味深い点です。
つまり「副反応があればそれでよし、もし出なければそれはそれでラッキー」と、どちらに転んでもネガティブに捉えない姿勢が、実際の身体のはたらきにも影響しているかもしれないのです。
一方、「ワクチンの効果を強く信じている」「自分の体はちゃんと対応できる」といったポジティブなマインドセットそのものが、直接的に抗体価の高さに結びついた、というデータは得られませんでした。
研究チームによると、そもそも参加者の多くがワクチンに好意的だったことなどが理由として考えられるそうです。
しかしながら、こうしたポジティブな考え方が接種後の副反応を軽減し、不安を下げ、ストレスや悲しみを和らげ、結果的により幸せな気分でいられた傾向があるのも事実です。
この面から見れば、「どのような姿勢や思い込みを持つか」は、身体だけでなく精神面への影響が大きいと言えます。
ただし、この研究にはいくつかの限界もあります。
被験者が主にワクチン接種への意欲が高い人たちであったため、接種に対して否定的あるいは不安の大きい層がどのような反応を示すのかは必ずしも明らかではありません。
また、結果は相関関係を示すものであり、厳密な意味で「マインドセットが変われば抗体が上がる」という因果関係を証明したわけでもないのです。
心理学の実験では、マインドセットを意図的に変化させる介入(たとえばポジティブな情報を与える短い動画や説明資料など)を行い、その前後で明確に体や心の反応の変化を測定するアプローチが今後の課題となるでしょう。
それでも、今回のデータからはワクチン接種をめぐる「心の持ち方」の多様なかたちが見て取れます。
症状が出たとしても「ああ、ちゃんと免疫が動いているんだな」と考えれば、体へのダメージというよりも防御力がアップしているサインのように感じられますし、そもそも「このワクチンは自分を守る力になるはずだ」という期待感が強いほど、不安やストレスが少なく快適な接種体験を得られます。
逆に、強い不安や否定的な印象を持ったまま接種に臨んだ場合、実際の副反応や感情面でより負担が増してしまう可能性があるのです。
研究チームによれば、今後はさまざまな年齢層やワクチン接種への態度が異なる人々を対象に、より多様なマインドセットがどのように体験や免疫に影響を与えるかを調べていく計画があるそうです。
こうしたデータがさらに蓄積されれば、医療機関や自治体がワクチン接種前の説明のしかたを工夫したり、接種会場での声かけに活かしたりといった、新しいアプローチの可能性が広がるでしょう。
ワクチンそのものを改良するだけでなく、人々の心の準備や気持ちの持ちようを少し変えるだけで、接種後の体験がポジティブになり、結果的に社会全体の健康水準が向上する――そんな未来が待っているのかもしれません。
元論文
Brain activation patterns reflecting differences in music training: listening by ear vs. reading sheet music for the recognition of contexts and structures in a composition
https://doi.org/10.1093/cercor/bhaf072
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部