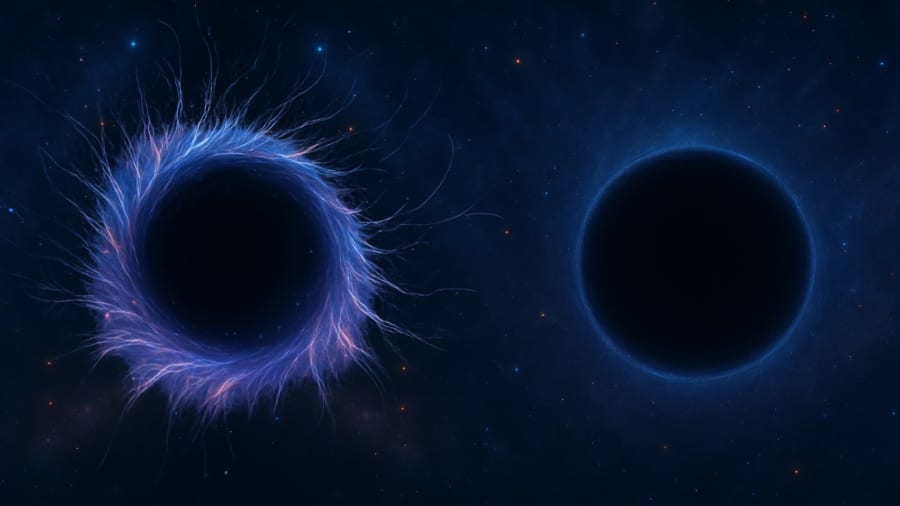ブラックホールには『毛』が生えているのでしょうか?
これは決して冗談ではなく、ブラックホールと情報の消失をめぐる先端物理の問題です。
この問題に対してデンマークのニールス・ボーア研究所(NBI)を中心とする国際的な研究チームが、ブラックホール同士の合体で発生する「重力波」を詳しく調べるたところ、ブラックホールはハゲており「ツルツル」であることが示されました。
ブラックホールの毛とは何か?
そしてなぜ研究者たちはブラックホールがハゲているかを気にしているのでしょうか?
研究内容の最新版は2023年8月24日に『arXiv』にて発表されました。
目次
- ブラックホールの毛を巡るパラドックス
- ブラックホールはツルツルか、それともフサフサか?
- 「ツルツル」か「産毛」かで物理学の未来が変る
ブラックホールの毛を巡るパラドックス
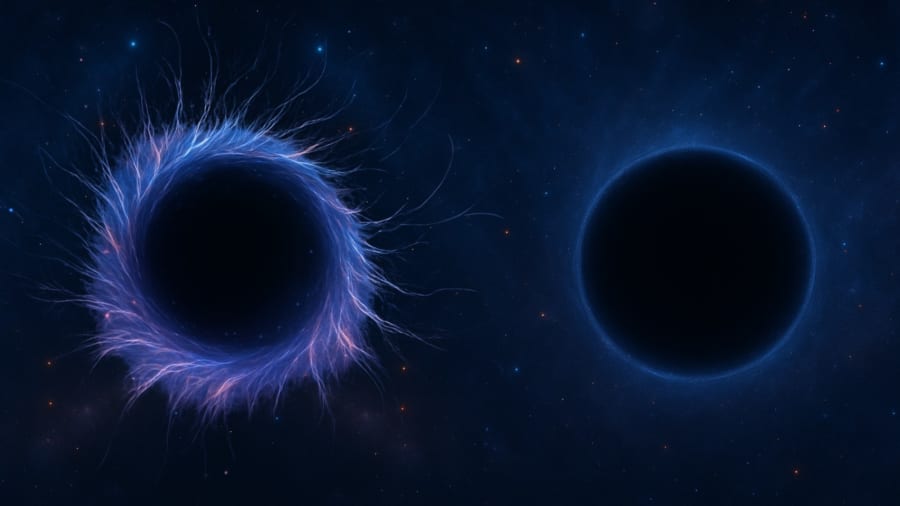
ブラックホールという名前を聞くと、多くの人はすべてを飲み込む真っ黒な穴を想像するでしょう。
この奇妙な天体について、約100年前にアインシュタインが考えた「一般相対性理論」という物理学の基本的な理論では、非常に不思議な予言がなされています。
それは、「ブラックホールは、たった3つの要素だけで完全に説明できる」とする考えです。
この3つとは、①質量(どれくらい重いか)、②自転(どれくらい速く回転しているか)、③電荷(電気的な性質)のことです。
この3つの値さえ決まれば、ブラックホールの見た目や特徴は全て決まってしまう、というのが「ブラックホール無毛定理(むもうていり)」と呼ばれる理論です。
ここで言う「毛」とは、天体の細かな特徴を髪の毛にたとえた表現です。
私たちが知っている普通の星や惑星は、色々な大きさや形、磁場や物質の成分といった数多くの特徴(つまり「フサフサの毛」)を持っています。
しかし、ブラックホールは極端に単純で、まるで「ツルツルの頭」のように特徴がほとんど無いというわけです。
この無毛定理は理論としてはとても美しいのですが、困った問題も抱えています。
ブラックホールは宇宙空間で星などを次々と飲み込みますが、この理論通りなら飲み込まれた星がどんな星だったのか、その詳しい情報(例えば星を構成していた元素や元の状態)がブラックホールの外から見えなくなってしまいます。
情報が完全に消えてしまうか、ブラックホールの内部に封じ込められてしまうかのどちらかになってしまいますが、実際のところ、それらの情報がどう扱われているのかは、はっきりとは分かっていません。
この問題が重要な理由は、私たちが日常的に見ている世界(古典的な世界)と、ミクロの世界(量子力学)で起きることとの間に、深刻な矛盾が生まれるからです。
私たちが暮らす日常の世界では、例えば紙を燃やすと元の形や書かれていた情報は完全に失われてしまうように見えます。
一方、極めて小さい世界の現象を扱う量子力学の世界では、「情報は決して失われない」とされます。
どういうことかというと、紙を燃やしたとしても、燃えた紙の灰や煙、さらに空気中に散らばった分子や熱エネルギーなど、すべての小さな粒子やエネルギーの動きを完全に追跡できれば、理論上は元の情報を取り戻せる、という考え方です。
量子力学では「情報が消えたように見える」のと「実際に情報が消える」のは全く違うことだと区別しており、「情報は絶対になくならない」という原則を守っています。
ところがブラックホールは、この量子力学の原則を脅かしてしまいます。
ブラックホールに飲み込まれた情報が本当に消えてしまうとすると、「情報は失われない」という量子力学のルールと正面から矛盾します。
この深刻な問題は「ブラックホールの情報パラドックス」と呼ばれ、物理学における大きな謎のひとつとなっています。
そこで、このパラドックスを解決するために「ブラックホールにも目には見えない非常に小さな特徴があり、それが情報を記録しているのではないか?」という仮説が登場しました。
これは「量子的な毛(りょうしてきなけ)」と呼ばれるもので、ホーキング博士をはじめとする科学者が提案しました。
特にブラックホールの表面にはとても弱いエネルギーの粒子(「ソフトな毛」)が存在していて、そこに情報が隠されているのかもしれないという考え方です。
ただし、この量子的な毛は非常に弱く、現在の技術でははっきりと観測することは困難です。
そのため科学者たちは、まず量子力学を考えず、一般相対性理論の範囲内でブラックホールが本当に「毛がない」のかを観測によって調べようと考えました。
一般相対性理論が正しいなら、ブラックホールが合体するときに発生する重力波(時空の波)も、ブラックホールの質量と自転だけで完全に決まるはずです。
逆に言えば、実際のブラックホール合体から発生する重力波を観測すれば、「毛」があるのかどうかを調べられるわけです。
近年になって「重力波望遠鏡」という新しいタイプの望遠鏡が登場し、ブラックホールの合体を実際に観測できるようになりました。
これにより、多くのブラックホール合体イベントから出る重力波を使って、「本当にブラックホールには毛がないのか?」という理論を検証する研究が活発に行われるようになったのです。
ブラックホールはツルツルか、それともフサフサか?

ブラックホールには本当に「毛」がないのでしょうか?
この不思議な疑問を解明するために、科学者たちはブラックホール同士が衝突・合体する瞬間を観察しました。
とはいっても、実際にブラックホールを目で見ることはできません。
なぜならブラックホールは、光さえも飲み込んでしまうほど強い重力を持っているからです。
そこで研究者たちは、ブラックホールの衝突で発生する「重力波(じゅうりょくは:時空のさざなみ)」という特別な波に注目しました。
重力波とは、宇宙で大きな物体が激しく動いたときに生じる「時空のさざなみ」のようなものです。
ブラックホールが2つ合体すると、新しく1つの大きなブラックホールが誕生します。
そのとき、この新しいブラックホールは、まるで巨大な鐘が鳴るように震えます。
この「震え」は短い時間で徐々に弱まって消えていきますが、この現象を科学者たちは「リングダウン(鳴り止み)」と呼んでいます。
実はこの振動には、複数の「固有振動モード(こゆうしんどうモード:特徴的な揺れ方)」があります。
固有振動モードとは、簡単に言えば「音色」や「音程」のようなもので、ブラックホールそれぞれが持つ特徴的な振動パターンのことです。
ギターやピアノの弦がそれぞれ特有の音色を出すのと似ています。
これまでの研究では、ほとんどの場合、観測で確実に捉えることができたのは、この振動モードのうち最も強く明確な「1種類の音色」だけでした。
ブラックホールがもっと複雑な振動パターンを持つ可能性も指摘されてはいましたが、非常に弱い信号だったため、明確な証拠はなかなか得られませんでした。
ところが、今回の研究では特別な工夫によって解析方法を改善し、それまで気付かなかった「二つ目の振動モード(音色)」を発見することができました。
これは非常に重要な進展です。
なぜなら、1種類の音色だけを調べるよりも、2種類の音色を調べるほうがブラックホールの正体をより詳しく調べられるからです。
ちょうど、ある楽器を「ド」の音だけで聞くよりも、「ド」と「ミ」のような2つ以上の音を聞くことで、よりはっきりその楽器の特徴をつかめるのと同じです。
もしブラックホールに理論で予想されていない「毛」(特別な性質や特徴)があるなら、この2つの振動モード(音色)の間に何らかのズレや違いが現れる可能性があります。
つまり、ブラックホールの特徴が本当に質量と自転だけでは説明できない何かがあるなら、振動のパターンも理論から少しズレてしまうはずなのです。
しかし、今回の解析結果では、二つ目の振動モードを加えて詳しく分析しても、どちらの振動モードも単一のブラックホール(つまり質量と自転だけで決まるブラックホール)の特徴として説明できることがわかりました。
この結果は、アインシュタインが考えた一般相対性理論で予測された振動パターンとぴったり一致しており、理論と観測結果との間に矛盾は見つかりませんでした。
言い換えれば、今回調べたブラックホールに限って言うならば、余計な特徴(毛)は見つからず、本当に「質量と自転だけで説明できるシンプルなブラックホール」であることが示されたことになります。
科学者たちは、この解析を始める前には「もしかすると理論にはない『余計な特徴』が見つかるかもしれない」と期待もしていました。
しかし、今回の分析結果からは、そのような新しい物理を示す兆候は見つかりませんでした。
これはつまり、現時点の観測技術や対象となったブラックホールでは、アインシュタインの予言を超える新たな性質を発見することは難しい、ということを示しています。
この研究の特に注目すべき点は、「二つの音色を同時に捉える」という難しい観測が現行の観測装置でも可能だったことです。
本来なら、こうした複雑な振動パターンをはっきり捉えるには、さらに進化した次世代の観測計画(2030年代に予定されている高感度な望遠鏡)が必要だと考えられていました。
しかし今回は、GW190521という特別に大きく強い重力波を放った非常に珍しいブラックホール合体の観測データを使ったことで、この難しい観測を一足先に達成できたのです。
研究者たちは、現在の技術でもここまで詳細なブラックホールの振動を検出できたことに大きな驚きと喜びを感じています。
「ツルツル」か「産毛」かで物理学の未来が変る
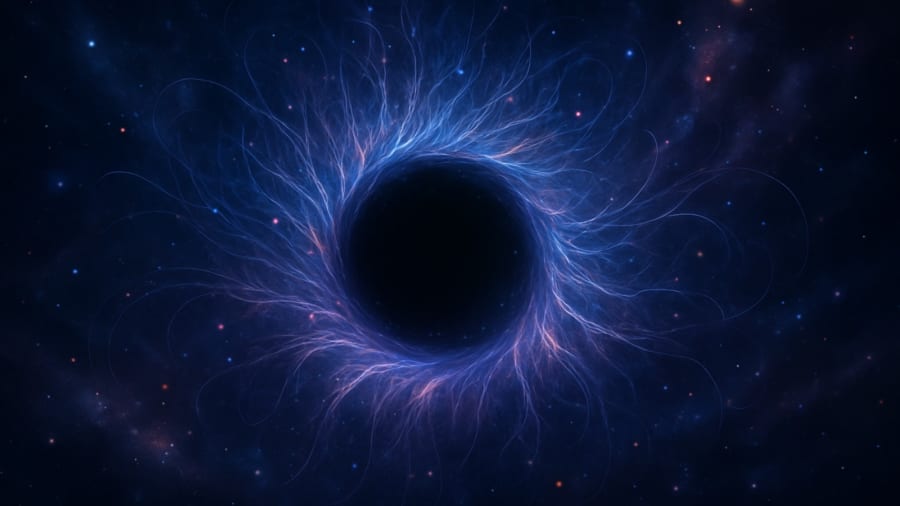
今回の結果は、ブラックホールがまさに一般相対性理論の予言する通りの“シンプルな姿”であることを強く裏付けるものでした。
100年以上前にアインシュタインが提唱した理論は、ブラックホール同士の衝突という極限の現象でもなお正しさを発揮したのです。
観測された振る舞いに少しの破綻も見いだせなかったことは、一般相対性理論の堅牢さを改めて示すと同時に、私たちが捉えている天体が紛れもなく理論通りの「ブラックホール」であることの証明とも言えます。
ブラックホールに関する先駆的な理論研究を実証したこの成果は、重力波天文学という新しい観測分野の大きな勝利でもあります。
逆に言えば、量子力学が要請するような情報の手がかり(量子的な毛)は、少なくとも現状では表に現れないことになります。
とはいえ、情報パラドックスという難題が解決したわけではありません。
たとえばブラックホールには「量子的な毛」が存在するという考え方があります。
通常の手段では見えないごく微妙な特徴がブラックホールの表面近くに備わっており、それが量子的な効果によって失われた情報を記録・伝達しているのではないか、という発想です。
ただし、このような量子的な産毛は非常に微弱なため、現在の重力波観測の感度では明確に捉えることが難しいと考えられています。
さらにブラックホールには、私たちの知らない仕組みで情報を保持する何かが潜んでいる可能性もあります。
理論物理学者たちは、ブラックホールの地平線付近に想像を絶する過酷な現象(ファイアウォールやファズボールといった仮説)を仮定するなどして、この矛盾に挑み続けています。
もし将来的に重力波のさらなる精密観測によってごく僅かな「ズレ」やブラックホールからのエコー信号などが検出されれば、そうした量子効果の一端が示されるかもしれません。
そのためにも、今後計画されているより高感度な重力波望遠鏡(日本のKAGRAの改良や欧州のLISA計画など)の活躍に期待がかかっています。
もし将来の観測でさらに精度が上がっても、ブラックホールが完全に「ハゲ」のままであることが確認されれば、量子重力理論の構築に向けて別のアプローチが必要になるでしょう。
逆に、わずかでも「毛」の兆候が見つかれば、物理学に革命をもたらす大きな発見になる可能性があります。
いずれにしても、ブラックホールの謎に迫るこれらの研究は、宇宙そのものの理解を深めるだけでなく、量子論と重力理論を統一するという物理学最大の難問に立ち向かう重要な手がかりとなるでしょう。
元論文
Black hole spectroscopy: from theory to experiment
https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.23895
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部