イギリスのケンブリッジ大学(University of Cambridge)を中心とした国際研究チームがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を使って行った研究によって、宇宙が誕生して1秒も経たないうちに誕生した可能性のある「裸に近い巨大ブラックホール」が発見されました。
このブラックホールは太陽の約5,000万倍の質量をもち、その質量は母銀河に存在する星の総量の少なくとも2倍以上にもなります。
この異常なブラックホールの発見は、ビッグバンから1秒未満の間に極端な高密度環境で直接誕生したとされる「原始ブラックホール(PBH)」などの星を吸い込まずに巨大化した「重い種」の可能性を強く示唆しています。
研究内容の詳細は2025年9月3日に『arXiv』にて発表されました。
目次
- 星の生まれる前から存在したブラックホール
- 宇宙最初の1秒でブラックホール誕生か?
- 銀河より先にブラックホールが誕生した?
星の生まれる前から存在したブラックホール

宇宙にはさまざまなブラックホールがありますが、特に銀河の中心にある「超大質量ブラックホール」は、数百万~数億個分の太陽が集まったほどの巨大さを持ちます。
例えば、私たちの天の川銀河の中心にも、このような超巨大なブラックホールが存在しています。
このようなブラックホールはどうやってできたのでしょうか?
これまでの天文学では、ブラックホールは星が一生を終えるときの「超新星爆発」という大爆発を経て誕生すると考えられてきました。
太陽より何十倍も重い星が寿命を迎えて大爆発すると、その中心がぎゅっと潰れて小さなブラックホールができます。
こうしてできた小さなブラックホールは、その後、周りにあるガスや星などの物質を少しずつ引き寄せ、長い時間をかけて徐々に大きく成長すると考えられていました。
しかし最近の観測では、この考え方では説明できない謎が見つかっています。
なんと、宇宙が誕生してからたった数億年しか経っていない非常に早い時代に、すでに超巨大なブラックホールが存在していたという証拠が見つかったのです。
これは驚くべき発見でした。
なぜなら、星の誕生と死を経てゆっくりブラックホールが育つという従来の考え方では、宇宙の初期にそれほど巨大なブラックホールが生まれる時間的な余裕がないからです。
この新しい謎に対して提案されたのが、「原始ブラックホール(PBH)」という仮説です。
この仮説によると、宇宙の始まりであるビッグバンの直後、宇宙は想像を絶するほどの超高密度で満たされていました。
このような超高密度の状態では、ちょっとした密度の偏りがあっただけでも、その部分が自分自身の重力で一瞬にして崩れ落ち、ブラックホールが誕生した可能性があるのです。
通常、ブラックホールができるには、星のような巨大な物質が重力で潰れる必要がありますが、ビッグバン直後の高密度宇宙では、ごくわずかな偏りでもブラックホールを簡単に生み出せるほど物質がぎっしり詰まっていたのです。
こうして生まれたのが「原始ブラックホール(PBH)」です。
原始ブラックホールが普通のブラックホールと違うのは、星が誕生するずっと前の、宇宙の誕生からたった1秒以内という超初期に生まれたという点です。
つまり、星や銀河が形成される前から宇宙にはすでにブラックホールが存在していた可能性があるのです。
もし原始ブラックホールが存在するとすれば、それらは宇宙最初の「重いタネ(ヘビーシード)」となり、その後に銀河や星の形成を引き起こす引力の源となったかもしれません。
さらに、この原始ブラックホールは宇宙の謎の一つである「暗黒物質(ダークマター)」の正体の候補としても議論されています(ただし、これは今回の研究結果から直接導かれたわけではありません)。
暗黒物質とは、目には見えないけれど重力を持ち、宇宙の物質の多くを占めていると考えられている謎の物質です。
原始ブラックホールがもし暗黒物質の一部だとすれば、なぜ暗黒物質が見えずに重力だけを通じて宇宙に影響を与えているのかも説明できるかもしれません。
このように、原始ブラックホールは超大質量ブラックホールが宇宙の初期に存在している謎だけでなく、宇宙全体を理解するための新たな鍵になる可能性があるのです。
では、どうすればこれらの仮説を確かめられるのでしょうか?
宇宙最初の1秒でブラックホール誕生か?
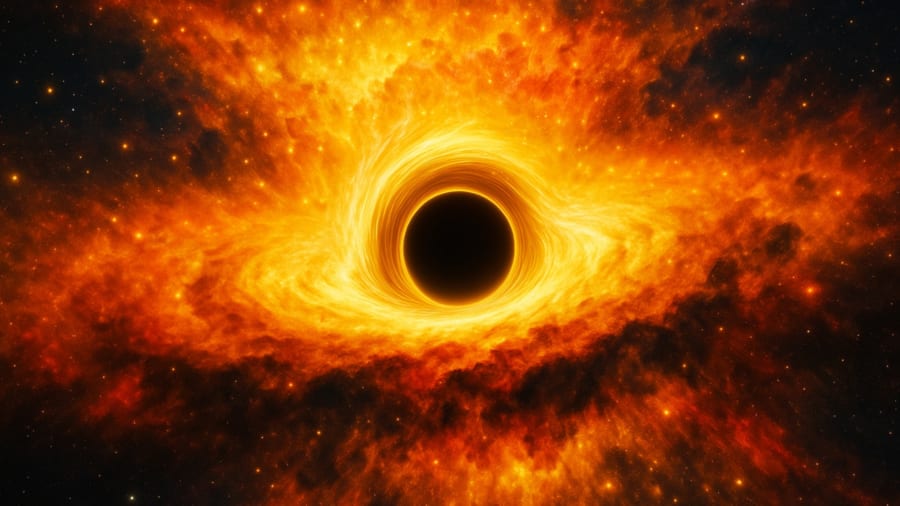
どうすればビッグバンから1秒未満で誕生した原始ブラックホールがあることを確かめられるのか?
この謎の答えを得るには、初期宇宙の非常に遠い場所を実際に観測して詳しく調べる必要があります。
しかし、宇宙は非常に広く、遠くの天体の光は地球に届くころには非常に弱くなってしまいます。
そこで活躍するのが、2021年末に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)です。
JWSTはハッブル宇宙望遠鏡の後継機で、赤外線という目に見えない光を使って観測を行います。
赤外線は宇宙空間にあるガスや塵を通り抜けやすく、非常に遠くて古い時代の光を鮮明にとらえることができます。
このためJWSTは、宇宙が生まれてまだ間もない時期の星や銀河、ブラックホールを観測するための最適な望遠鏡として、大きな期待を寄せられてきました。
JWSTが観測を始めて以来、研究者たちは宇宙の非常に遠い場所にある謎の天体を次々と発見しました。
それらは赤外線で観測すると非常に赤く、小さな光点として見えるため、「リトル・レッド・ドット(LRD)」と呼ばれるようになりました。
LRDの正体は明らかになっていませんが、多くの天文学者は、これらが宇宙初期に生まれたばかりの超巨大ブラックホールではないかと考えてきました。
今回の研究で注目された「QSO1」も、そうしたリトル・レッド・ドット(LRD)の一つです。
このQSO1は赤方偏移(光が宇宙の膨張によって赤く引き伸ばされる現象)が7.04という非常に遠い天体で、宇宙が誕生してから約7億年後の姿を私たちに見せてくれています。
通常、このように遠い天体の光は非常に弱く、詳しく調べることは困難です。
ところが、幸運なことにQSO1の手前には「Abell 2744」という非常に巨大な銀河の集まり(銀河団)がありました。
銀河団のような巨大な天体は強い重力を持っているため、その背後から届く光の通り道が曲げられ、地球から見るとまるで虫眼鏡を通したように光が拡大されます。
この現象は「重力レンズ効果」と呼ばれ、宇宙の天然の虫眼鏡のような役割を果たします。
ケンブリッジ大学のイグナス・ユオジュバリス博士らの国際研究チームは、この重力レンズ効果を利用し、JWSTの高性能な赤外線の分光観測装置を使ってQSO1を詳しく調べることに挑戦しました。
分光観測とは、光を色(波長)ごとに分けて、その天体がどのような成分でできているか、またどのような動きをしているかを調べる方法です。
観測の結果、QSO1の内部にあるガスが、何か重い天体の周りを回転していることがわかりました。
これは、中心に非常に重い物体があって、その強い重力に引き寄せられたガスがその周囲をぐるぐると回っていることを意味しています。
より詳しく解析すると、この中心にある重い物体の質量は太陽の約5000万倍もあり、非常に巨大なブラックホールであることが判明したのです。
さらに驚くべきことに、このブラックホールが存在する銀河(母銀河)にある星の質量を最大限に見積もっても、その星々の合計の質量はブラックホールの半分にも満たないことが分かりました。
普通は銀河全体の質量のごく一部しかブラックホールの質量は占めませんが、QSO1の場合、ブラックホールが銀河よりも重いという異常なバランスになっています。
私たちの天の川銀河の中心にあるブラックホールの質量は銀河全体の質量の30万分の1程度であると考えられており、このQSO1がいかに特異な存在であるかが理解できるでしょう。
このことから研究チームは、この天体を「最も『裸』に近い巨大ブラックホール」と表現しています。
通常なら銀河が主役でブラックホールがその中に隠れているはずなのに、この天体ではブラックホールだけが目立っていて、銀河の存在感は極めて薄いのです。
銀河より先にブラックホールが誕生した?
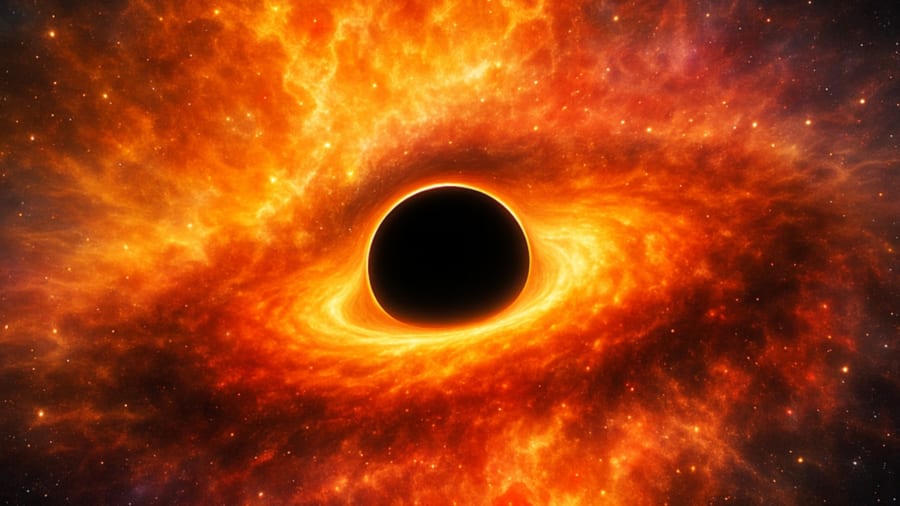
では初期宇宙にぽつんと存在する「裸のブラックホール」――この発見が意味するところは何でしょうか?
現在、天文学者が注目している仮説のひとつが、「重い種(ヘビーシード)」という考え方です。
この考え方は、ブラックホールが星からゆっくり育つのではなく、宇宙が始まったばかりの非常に早い段階から、すでに巨大な状態で存在していたというものです。
「重い種」の候補として、研究者たちは「直接崩壊ブラックホール(DCBH)」と「原始ブラックホール(PBH)」という二つのモデルを挙げています。
まず「直接崩壊ブラックホール(DCBH)」とは、初期宇宙に存在した巨大なガスのかたまりが、星を経ることなく直接ブラックホールになったものです。
この過程が起こるためには非常に強い紫外線が近くに存在することが重要ですが、QSO1の観測ではそのような紫外線の強い光は確認されていません。
もう一つの可能性が、「原始ブラックホール(PBH)」と呼ばれるものです。
これは宇宙が誕生した直後の非常に密度が高かった時期に、密度のわずかな偏りが重力で一気に崩れ落ち、ブラックホールが誕生したという仮説です。
原始ブラックホールは宇宙が誕生してからたった1秒以内に生まれたとも言われ、非常に早くから宇宙に存在していた可能性があります。
もっとも、これだけで原始ブラックホールの存在が証明されたわけではありません。
実際に観測されている映像は原始ブラックホール誕生の瞬間ではないからです。
また今回観測されたQSO1のブラックホールが仮に原始ブラックホールだった場合でも太陽の5000万倍という質量に達する過程で、急速に物質を吸い込んだり、他のブラックホールと合体したりして成長した可能性もあります。
では、こうしたブラックホールの謎を今後どのようにして解き明かしていくのでしょうか。
一つの方法として、JWSTや今後開発されるさらに高性能な望遠鏡を使って、他の「リトル・レッド・ドット」や遠い場所にあるクエーサー(明るく輝く銀河の中心核)を詳しく観測し、質量や化学的な特徴を比較していくことが挙げられます。
複数の天体で同じような巨大ブラックホールの証拠が見つかれば、原始ブラックホールや直接崩壊ブラックホールといった仮説の真偽に一歩近づけるはずです。
さらに、次の10年以内には次世代の「重力波望遠鏡」と呼ばれる観測装置が登場し、宇宙の初期から現代までにブラックホール同士が衝突して合体したときに生じる「重力波」という時空の波を観測できるようになると期待されています(ただしこれは今回の研究とは直接関係のない将来的な展望です)。
これにより、宇宙初期にどれくらいブラックホールが存在したのかをさらに詳しく調べることができるかもしれません。
もし原始ブラックホールが実際に存在することが証明されれば、それは宇宙の歴史や物理学の基本的な考え方を根本から変える重大な発見となります。
つまり、これまでの「銀河ができてからブラックホールが育つ」という考え方ではなく、「ブラックホールが最初に生まれ、その周囲に銀河ができた」という全く新しい宇宙像が生まれる可能性があるのです。
原始ブラックホールは、星のように自分で光ったりせず、見えないまま宇宙空間を漂います。しかも重力があるため、周囲にある星や銀河に影響を与えることができます。
この「見えないのに重力だけが存在する」という特徴が、まさにダークマターの性質そのものなのです。
また、これまでの観測ではダークマターの正体が何なのかまったく分からず、仮説に基づく粒子(未知の素粒子)を探す実験でも決定的な証拠が見つかっていません。
そこで、原始ブラックホールのように「既に存在しているけど非常に見えにくい物体」なら、ダークマターの正体として説明がつきやすいからです。
もちろん、今回観測されたQSO1はまだたった一つの例にすぎません。
しかしこれから先さらなる観測と理論研究によって、この驚くべきシナリオの真偽が解明されていくことでしょう。
元論文
A direct black hole mass measurement in a Little Red Dot at the Epoch of Reionization
https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.21748
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部


