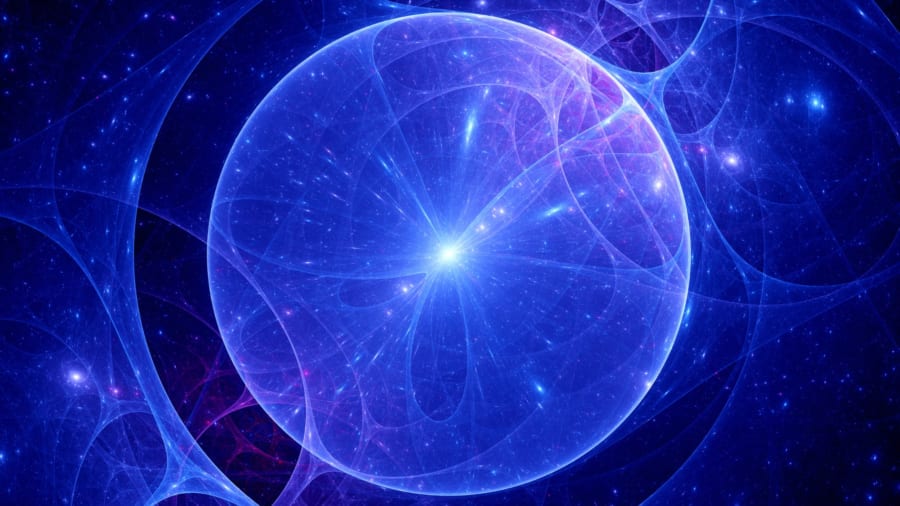スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH Zürich)で行われた研究によって、室温環境のままガラス粒子の「性質だけを冷却」し、量子純度92%というこれまでにない高純度の量子状態に到達させることに成功しました。
従来、このような大きな粒子の量子的な振る舞いを観測するには、極低温にまで冷やす大がかりな装置が不可欠でした。
しかし今回の実験では回転運動というガラス粒子の「特定の性質」のみを選択的に量子状態に近づけることで、粒子全体の温度を下げずにこの記録的な純度に到達しています。
研究内容の詳細は2025年8月6日に『Nature Physics』にて発表されました。
目次
- 「常温で量子現象」への長い道のり
- 巨視的物体の性質のみを量子状態にする
- 物体の性質だけを冷却する技術が量子技術を変える
「常温で量子現象」への長い道のり
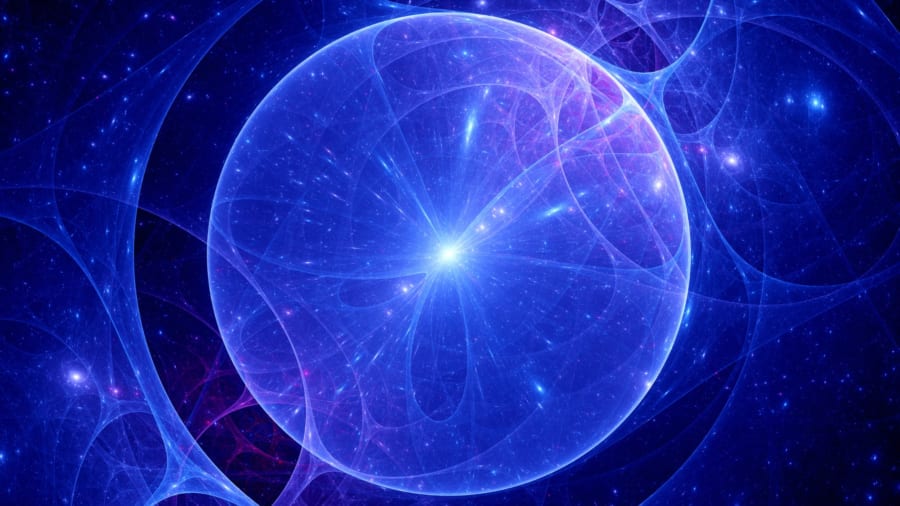
量子物理の不思議な現象は、ふつうは原子や分子のような、とても小さな世界でしか見られません。
しかし、それよりもずっと大きな物体でも、同じように量子のふるまいが起こるのかどうかは、長年にわたって多くの研究者の関心を集めてきました。
この疑問を解き明かすため、世界中で実験が続けられています。
当初は、ごく単純な分子を対象に実験が行われていましたが、その後、研究の対象は次第に大きな分子へと広がりました。
たとえば、炭素原子が60個集まったフラーレンという球状の分子では、量子の波のような性質が観測され、さらに数百個の原子からなる分子でも同様の現象が確認されています。
最近では、ナノサイズの微粒子や、非常に小さな「機械振動子」と呼ばれる装置を使った実験でも、量子的な揺らぎや「基底状態」(これ以上エネルギーを下げられない静かな状態)への冷却が少しずつ成功するようになってきました。
ただし、物体のサイズが大きくなったり温度が高くなったりすると、まわりの環境との相互作用が強くなり、量子の繊細な特徴はすぐに失われます。
このため、量子状態を作るには、粒子を外界からできるだけ切り離し、熱による揺らぎを抑える必要があります。
その手段として、真空中に粒子を浮かせて隔離し、さらに環境全体を絶対零度(−273.15℃)近くまで冷やす方法がよく使われてきました。
実際、比較的大きな「振動子(オシレーター)」を量子の基底状態に近づけるには、極低温冷却に加えて、レーザーやフィードバック制御などの高度な技術を組み合わせる必要があります。
そうした努力の結果として、極低温では非常に高い純度が得られていましたが、今回の室温実験はそれらを上回る純度に到達しました。
(※ここでいう「純度」は、基底状態にいる確率とは少し異なる、量子状態の混ざり具合を示す指標です。)
一方で、室温のままでこれを実現するのは非常に困難であり、これまでの記録では、粒子を光で浮かせて制御する「レヴィテーション系」で純度47%(n ≈ 0.6)、粒子を固定する「クランプ系」で純度34%が限界でした。
つまり、「常温で量子の静けさを引き出す」という挑戦は、長らく夢物語のように考えられてきたのです。
そんな中、今回の研究チームは画期的な方法を選びました。
それは、粒子全体を冷やすのではなく、特定の性質(たとえば回転などの自由度)だけにエネルギーを集中して抜き取るという戦略です。
粒子の他の部分は熱いままでも、その一部分だけを冷却すれば量子的な性質を引き出せると考えました。
実際の実験では、粒子の「回転運動」の揺れだけを狙って静め、量子的状態(基底状態)にすることを目指しました。
巨視的物体の性質のみを量子状態にする
今回の研究では、直径およそ120ナノメートルのシリカ(ガラス)ナノ粒子が使われました。
この粒子は非常に小さいものの、多数の原子が集まった“かたまり”であり、量子実験の対象としては大きめの存在です。
しかも完全な球ではなく、わずかに楕円形で向きに偏りがある「異方的」な形状を持っています。
研究チームはこの特徴を活かし、レーザー光で作った「光のお椀(光ピンセット)」に粒子を閉じ込め、真空中に浮かせました。
すると、粒子はコンパスの針のように一定方向に落ち着きながら、その方向を中心に小さく揺れる「回転振動(リブラション)」を始めます。今回の研究は、この揺れに注目して冷却を試みたものです。
粒子の回転からエネルギーを取り除くため、レーザー光と鏡で構成された精密な光学装置「ファブリ・ペロー共振器」を使用しました。
レーザー光は、粒子にエネルギーを与えることも奪うこともできるのですが、今回は後者――つまりエネルギーを奪う作用がより強くなるように、共振器の調整を行いました。
これにより、粒子が揺れるたびにレーザー光が“ブレーキ”のように働き、揺れが減衰していきます。
この結果、回転運動のフォノン占有数は平均 n = 0.04 まで低下し、純度(purity = (2n+1)^−1)は約92%に達しました。
これは、回転運動がほぼ量子力学でいう基底状態(最も静かでエネルギーの少ない状態)にあり、熱的な乱れがごくわずかしか残っていないことを意味します。
重要なのは、この冷却が粒子全体を冷やすことなく、室温環境で回転運動という一つの性質(自由度)だけが“凍りついた”ように静まったのです。
この実験は、「一部分の性質だけを冷やす」というアプローチが有効であることを示しました。
つまり、対象の粒子全体が高温のままであっても、回転のような特定の運動だけを選んで冷却することで、量子的な状態を作り出せることが実証されたのです。
今回の純度92%という成果は、室温での実験としては過去最高水準であり、極低温の先行システムよりも高い純度を達成しました。
物体の性質だけを冷却する技術が量子技術を変える

今回の成果は、「粒子全体ではなく、ある性質(自由度)だけを冷やす」という発想が、実際にうまく機能することを示しました。
実験では、粒子の内部が高温のままであるにもかかわらず、回転の自由度だけを、量子力学でいう「基底状態」に近い静けさまで冷やすことができたのです。
つまり、まわりの環境を氷点下まで冷やさなくても、量子的な振るまいを引き出せることが証明されたのです。
この方法は、これまでの常識では考えにくかった新しいアプローチであり、量子物理の応用範囲を大きく広げる重要な一歩だといえるでしょう。
この成果によって、回転するような物体の量子性を、安定した、そして信頼できる条件で調べる道が開かれました。
言いかえれば、たとえ大きな粒子であっても、その一部分の性質(自由度)を選んで量子状態にすることが可能だとわかったのです。
こうした考え方は、これまでよりもずっと大きなスケールで量子現象を扱えるようになる可能性を示しています。
また、この「部分冷却」という新しい方法は、量子技術を実際に社会で役立てるためのカギにもなりそうです。
これまでは、量子効果を引き出すために大がかりな冷却装置が必要でしたが、それがいらなくなれば、装置の小型化や実験の手軽さにつながります。
これまで絶対零度に近い環境が必要だった研究が、将来は室温でもできるようになる可能性が見えてきたのです。
とはいえ、今回の実験は、あくまでも特殊な形をしたナノ粒子の「回転運動」だけに適用したものです。
すぐにすべての物体や運動にこの方法が使えるわけではなく、ほかの種類の動きや、異なる形・素材の粒子にも応用できるかどうかは、今後の研究で確かめていく必要があります。
それでも、「室温で量子純度92%」という結果は、量子の静けさを常温の世界に持ち込めることを初めて実証した、記念碑的な成果です。
かつては夢のように思われていた「熱い粒子の一部の性質だけを冷やして量子状態にする」という挑戦に、今回、明確な答えが示されたのです。
この成果をきっかけとして、量子物理の研究はさらにスケールを広げ、私たちの生活に役立つ技術としても新たな展開を迎えることでしょう。
元論文
High-purity quantum optomechanics at room temperature
https://doi.org/10.1038/s41567-025-02976-9
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部