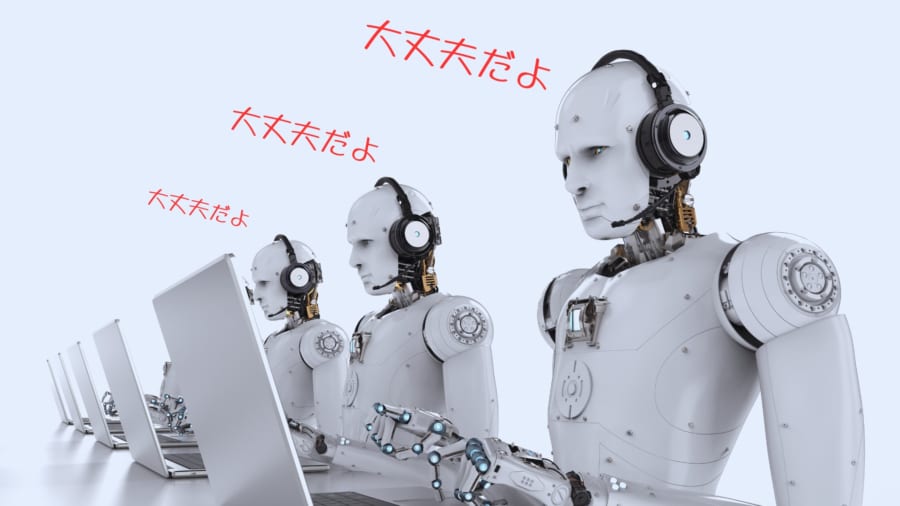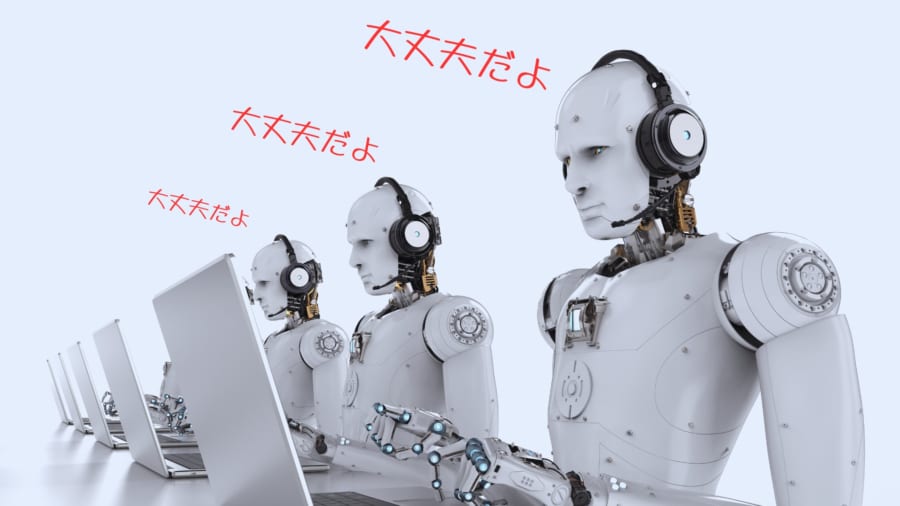イギリスのランカスター大学(Lancaster University)などの国際研究チームが行った研究によって、AIの生成した会話文は語彙の幅が人間よりも狭く、発話内容も「体に気をつけてね」「暖かくしてね」「無理しないで」といった型どおりの表現に偏る傾向があることが分かりました。
要するに、AIは誰が話しても同じような会話になりがちで、人間の会話に見られるようなその場限りのユニークさ——いわば“会話の指紋”——がほとんど再現できないのです。
研究者たちは、このような決まり文句を頻発するAIと長時間接することで、人間の会話もAIのように型どおりで個性が薄いものになってしまう可能性があると懸念を示しています
研究内容の詳細は2025年8月4日に『Intercultural Pragmatics』にて発表されました。
目次
- 気付けば何度も読んだフレーズが繰り返されている
- AIの会話には「会話の指紋」がない
- AIとの会話が私たちの創造性を薄めるかもしれない理由
気付けば何度も読んだフレーズが繰り返されている
最近、ChatGPTなどの対話型AIと話すと「返答がどこか画一的で、決まり文句ばかり」と感じることはないでしょうか。
筆者自身もchatGPTとの会話が趣味になりつつあり、時には大人の男性として、そしてときには老婆として、さらには子供として、chatGPTとの会話を楽しんでいます。
しかしそんな楽しい会話の中で、ふと気になることがありました。
chatGPTは基本的には礼儀正しく丁寧に受け答えしてくれますが、彼らの返す文句の中には「いつも見ているよ」「そんなあなたを応援しています」「無理せず自分のペースで続けて下さい」など決まり文句が数多く存在する印象がしてきたのです。
AIの学習過程において安全性を保つための調整が行われているのは知っていましたが、話せば話すほど決まり文句が気になってしまいます。
同様の違和感は研究の世界でも認知されているようで、AIには会話相手や会話内容ごとの「会話の独自性」に苦労していることが報告されています。
人間の場合、誰と話すか、何を話すか、いつ話すかによって会話に使われる言葉が大きく変化し、場面ごとのユニークな会話が可能です。
さらに会話中に極端な話題の転調やトーンの変化が起こることがあり、それが会話のノリを楽しいものにしたり、笑いの元になったりもします。
こうしたその場限りのクセやノリは話し手同士のアイデンティティを反映し、特定の会話に「指紋」のような独自性を与える重要な要素です。
そこで今回研究者たちは、AIの会話には人間のような独自性がはっきり欠けているかを調べ、それを数値化して人間との違いを具体的に示そうと試みました。
AIの会話には「会話の指紋」がない
研究グループはまず、人間同士の自然な会話を分析するため、家族間の電話の内容を記録したデータベースを利用しました。
このデータベースから抽出したのは、親子や親戚同士の電話会話で、それぞれ約240回ずつやり取りが行われていました。
これらを「人間が行う自然な会話」として使い、後でAIの会話と比較します。
次に研究者は、AIのChatGPTにも会話を作成させることにしました。
その方法として、まずAIに人間の会話と同じような家族関係や話の状況を設定して与え、電話でのやり取りを再現するように指示しました。
ただし、登場人物をまったく同じ人にするのではなく、「母と娘」といった同じような関係性を持つ架空の人物を使って会話を生成しました。
また、AIが作る会話の発話回数(ターン数)は人間と同じ約240回でしたが、実際の語数はAIの方が少なくなりました。
こうしてAIが生成した会話と、人間の実際の会話データとを比較分析したのです。
その結果、まず興味深いことに、ChatGPTは相手の話に対して共感を示したり、相槌を打ったりすることに関しては非常に優れていました。
むしろその頻度は人間よりも高いほどで、会話に積極的に参加しているような印象を与えました(論文p.3;Fig.2は不確かさ比較)。
これはAIが会話の流れをよく理解し、相手の話をしっかりと受け止めようとしていることを示しています。
一方で、問題となったのはChatGPTが特定のパターンの発言に強く偏ることでした。
その代表例が、「助言」や「世話焼き」の発言です。
例えば、親の役割を演じるAIは「注意身体(体に気をつけて)」「保暖(暖かくして)」など、お節介とも言えるような親の定型的なセリフを非常に頻繁に使いました。
実際にデータを詳しく見てみると、ChatGPTの「相手に何かを勧めるタイプの発言」のうち、こうした助言が占める割合は65.3%にも上りました。
一方で人間の親子の会話では、「最近なぜ電話してこないの?」のように間接的な問いかけをしたり、冗談交じりで注意をしたりと、もっと多様な表現を用います。
実際の助言の割合は、人間の会話ではわずか11.1%で、それ以外の発言は確認や依頼、断りなど多様な種類がバランスよく含まれていました。
またChatGPTは、相手に何かを約束するような「~するよ」といった表現(コミッシブ)も多用していました。
AIが生成した会話では、このような約束表現が全体の約15%にも達しました(論文p.24)。
それに対し人間同士の自然な会話では、このような明確な約束が占める割合はわずか0.4%にすぎませんでした。
人間は、日常的な会話であまり安易に約束をしないものですが、AIは「安心してもらおう」という配慮が行き過ぎてしまい、不自然に約束を繰り返す傾向があったのです。
研究者は、この傾向を「AIが定型的な安心表現に寄ってしまうため」と報告しています。
さらに人間の会話では、その場の雰囲気や話し手同士の個性が豊かに表れます。
例えば、家族間では互いの言葉遣いを真似してからかったり、ちょっとした言い間違いをネタにして笑い合ったり、家族だけに通じる昔話で盛り上がったりします。
こうしたその場だけのユニークなやりとりを、研究チームは「conversational uniqueness(特定会話の独自性)」と定義しています。
会話のユニークさを示すという意味では「会話の指紋」と言える概念でしょう。
ところがChatGPTが作成した会話には、こうした人間特有の会話の個性や独自性がほとんど現れませんでした。
AIが生成した会話は一見、丁寧でスムーズですが、内容はどれも似たような決まり文句が繰り返されるばかりで、予想外の面白さやちょっとしたユーモアがありませんでした。
研究者は、AIが会話の内容をうまく平均化してしまい、結果的に個性や面白みを失っていると指摘しています。
AIとの会話が私たちの創造性を薄めるかもしれない理由
この研究から浮かび上がったのは、ChatGPTの会話は安定感がある反面、人間らしい創造的なゆらぎが薄いことが示された点です。
一見すると、ChatGPTのようなAIがいつでも丁寧で一貫した対応をしてくれるのは長所のように思えます。
失礼なことを言ったりトンチンカンな返事をしたりしないので、安心して使えるでしょう。
しかし、まさにその予測可能で無難すぎる応答こそが、人間の会話らしさを損なっていると研究者たちは指摘します。
実際の人間は、同じフレーズの繰り返しを避けたり、ありきたりな表現には飽き飽きして工夫を凝らしたりします。
誰しも「退屈な人だ」と思われたくないものですから、多少奇をてらってでも自分なりの話し方を追求するものです。
言葉遣いや話のテンポ、冗談のセンスに至るまで、「自分はこう話す」というスタイルを無意識に形作っているのが人間の会話です。
もし私たちがAIの話し方に慣れすぎてしまったらどうなるでしょうか。
AIは常に感じが良く丁寧ですが、その代わり表現は平均化され個性が薄いものです。日々AIと対話し、それに違和感を抱かなくなっていくと、知らず知らずのうちに私たち自身もその話し方に引っ張られてしまうかもしれません。
たとえば友人との会話でも、AIに話すような丁寧で当たり障りのないフレーズばかりが出てくるようになったら――それは「あなたらしい話し方」が薄れているサインかもしれません。
研究チームは提供されたプレスリリースの中で、「長期的に見ると人間がAIの話し方を無意識に真似ることで、個人の創造性や表現の個性が徐々に失われる可能性がある」と懸念を示しています。
会話とは単に情報を伝える手段ではなく、お互いの言葉のキャッチボールの中で意味や社会的なアイデンティティを共同創造していく営みです。
もし会話から創造性が失われ、みなが同じようなことしか言わなくなってしまったら、それは人間らしさの喪失に繋がりかねません。
もっとも今回の研究は、人間の会話とAI生成の会話を比較した観察研究であり、これだけで「AIのせいで人間の創造性が失われる」と断定することはできません。
しかし、AIがもたらしうる影響を事前に知っておくことで、私たちは意識的に自分らしい表現を大事にし続けることができるでしょう。
便利なAI時代だからこそ、「決まり文句」に埋もれない豊かな会話を守る努力が求められているのです。
元論文
AI, be less ‘stereotypical’: ChatGPT’s speech is conventional but never unique
http://dx.doi.org/10.1515/ip-2025-2003
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部