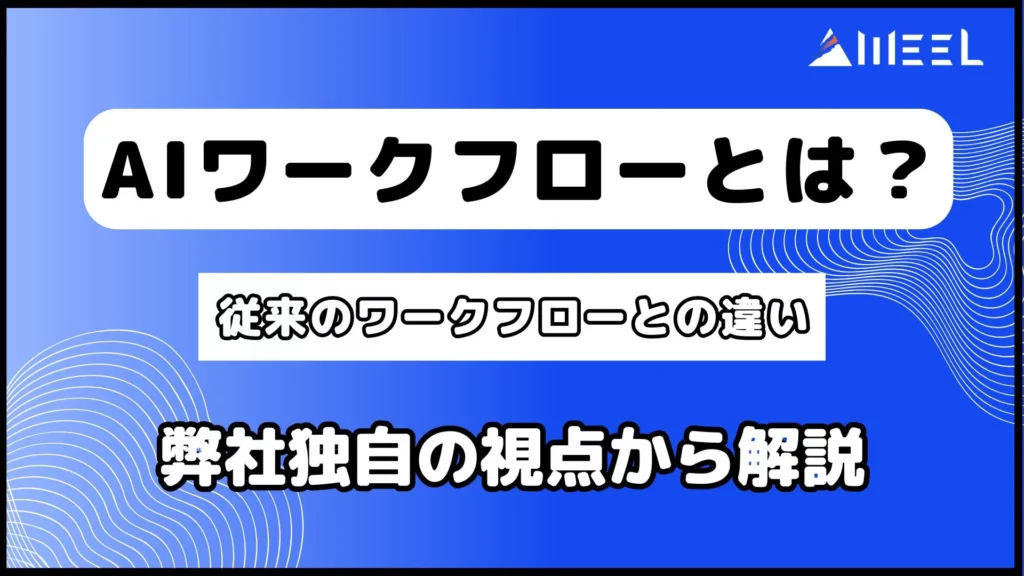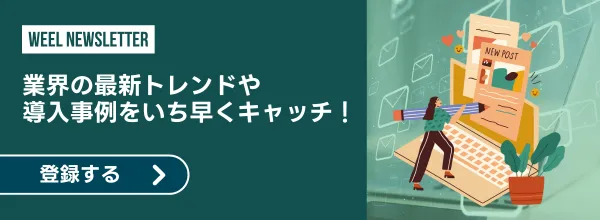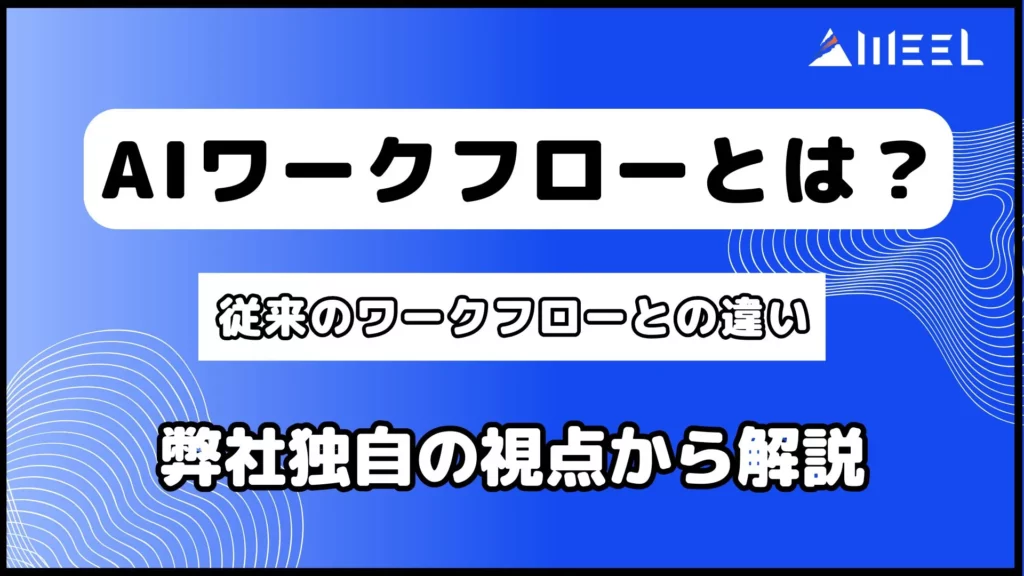
- AIワークフローとは一般的に生成AIや機械学習を用いて各業務工程を自動化・最適化する仕組みのこと
- AIワークフローの定義はまだ確立されておらず曖昧な部分も多い
- AIワークフローは導入目的を明確にしつつ、小規模から始めるのがおすすめ
生成AIが発達したことによって注目されている、「AIワークフロー」という言葉をご存知でしょうか?
AIワークフローとは、一般的に生成AIや機械学習を用いて各業務工程を自動化・最適化する仕組みのことを指しています。ただ上記はあくまで一般論で、AIワークフローの厳密な定義はまだ確立されていません。
そこで今回は、AIワークフローにおける我々WEELの見解や具体的な活用事例を紹介します。最後まで読むことで、AIワークフローを理解し、自社業務の効率化に活かせます。
ぜひ最後までご覧ください。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
AIワークフローとは

上記でも述べましたがAIワークフローとは、一般的に生成AI・従来AI(機械学習)を用いて業務工程を自動化・最適化する仕組みのことです。まずは、AIワークフローの定義や従来のワークフローとの違いを解説していきます。
AIワークフローの定義
AIワークフローは、一般的に生成AI・従来AI(機械学習)を用いて業務工程を自動化・最適化する仕組みを指します。ただし、国や特定の機関が明確に定義しているわけではないため、文脈によって解釈が異なる場合があります。
そこでWEELでは、AIワークフローを次のように定義しています。
- ワークフロー型AIエージェント
- ハイブリッド型(業務特化型)AIエージェント
- 完全自律型AIエージェント
完全自立型AIエージェントを含めた、上記全てがAIワークフロー
このように、AIエージェントにはさまざまな型がありますが、いずれも根幹に存在するのがAIワークフローです。つまり、AIエージェントを効果的に活用するためには、AIワークフローを適切に設計・構築することが不可欠だと考えています。
代表的なサービスとしてはdifyやn8nがあります。これらは業務の流れを設計しやすく、生成AIを組み込んだワークフロー構築に適しているため、AIワークフローを理解するうえで分かりやすい例と言えるでしょう。
AIエージェントとの関係
AIワークフローとAIエージェントは、切り離せない関係にあり、全くの別物ではありません。当サイトでは、AIワークフローを設計・構築できることが、AIエージェントの能力を最大限に活かすために重要だと考えています。
具体的に、AIエージェントは用途や自律性のレベルによって以下の3種類に分類できます。
| 比較項目 | ワークフロー型 | ハイブリッド型(業務特化型) | 完全自律型 |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 人間が設定した手順・ルールに従ってタスクを実行 | 一部タスクは自律判断。人間の指示やワークフローと連携 | 高度な判断・意思決定まで自律で実行 |
| 自律性 | 低 | 中 | 高 |
| 主な用途 | 単純作業の自動化・業務効率化 | 特定業務の効率化や意思決定支援 | 戦略立案・複雑業務の自動化 |
| AIワークフローとの関係 | ワークフロー設計に依存。AIは手順通りに動く | ワークフロー設計とAIの判断を組み合わせて最適化 | 根幹はワークフローに依存。適切な設計で最大限の効果を発揮 |
つまり、AIワークフローはAIエージェントの「動かし方」を設計する仕組みであり、AIエージェントそのものではありません。
しかし、AIワークフローを適切に構築できることが、ワークフロー型から完全自律型までのAIエージェントの力を最大化する鍵となります。
なお、AIエージェントに関しては下記の記事を参考にしてください。
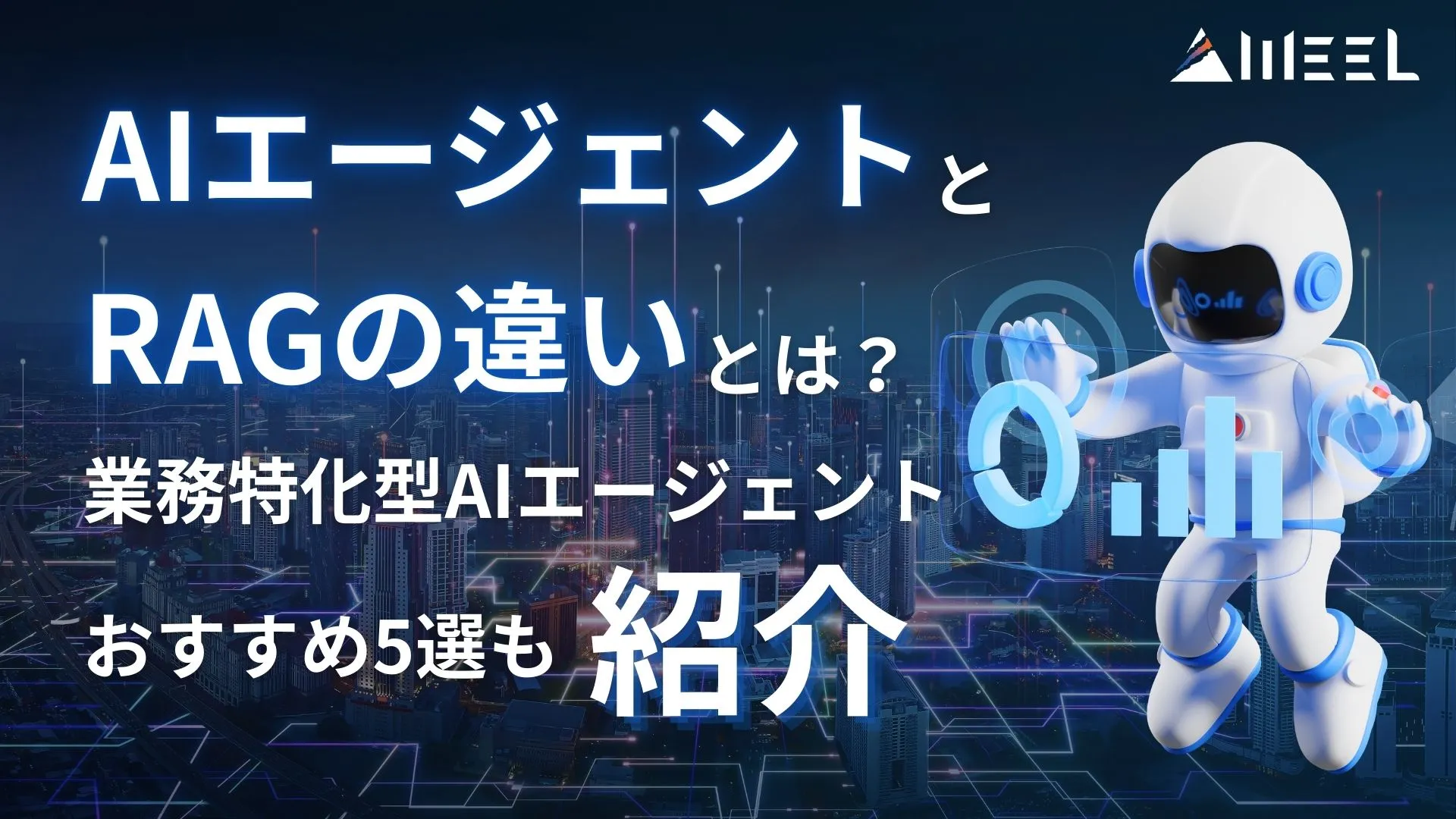
従来のワークフローとの違い
従来のワークフローは、あらかじめ決められているルールに基づいて業務を順序通りに進める仕組みです。AIワークフローは、AIを活用して判断・処理を自動化し、柔軟に業務を最適化できる点というで大きな違いがあります。
| 項目 | 従来のワークフロー | AIワークフロー |
|---|---|---|
| 処理主体 | 人や固定ルール | AI(生成AI・機械学習など) |
| 柔軟性 | 手順が固定、例外対応は手動 | データや状況に応じて自動で判断・調整可能 |
| 自動化レベル | ルールに沿った単純作業の自動化が中心 | 判断・予測・意思決定まで含む高度な自動化 |
| 学習能力 | なし | 過去データや結果から改善・最適化が可能 |
| 導入目的 | 手順の可視化・効率化 | 業務全体の最適化と意思決定支援 |
AIワークフローは単なる業務の自動化ではなく、AIが業務の判断や調整まで担うことで、従来のワークフローよりも柔軟かつ効率的に業務を進められる仕組みと言えます。
AIワークフローを実現する主要ツール
| 項目 | Dify | n8n | Copilot Studio |
|---|---|---|---|
| 概要 | 生成AI中心のワークフロー構築プラットフォーム。チャットボットやドキュメント生成などに特化 | オープンソースのワークフロー自動化ツール。ノーコードでAPIやサービスをつなぎ業務を自動化 | Microsoft提供のローコードAIエージェント開発プラットフォーム。Microsoft 365と連携可能 |
| 主な用途 | AIエージェントの作成、生成AIによる業務自動化 | 複数サービスの連携、自動化タスク作成、条件分岐や通知 | 業務特化型AIエージェント構築、複雑業務プロセスの自動化、意思決定支援 |
| 料金 | SandBox:無料 Professional:月額59ドル Team:月額159ドル | セルフホスト(ローカル):無料クラウド版は有料 (月額20ドル〜) | 従量課金制 月額プラン:月額29,985円 |
| 対応AI | GPT・Claude・Geminiなど | GPT・Claude・Geminiなど | Azure OpenAIのGPTモデル |
| 対象ユーザー | 非開発者・AI初心者でも扱いやすい | ノーコードでの自動化を求める個人・チーム | 開発者~業務担当者。複雑なAIワークフローや業務特化型エージェントを構築したい人向け |
AIワークフローを実現する主要ツールとしては、Dify・n8n・Copilot Studioなどが挙げられます。
DifyとCopilot Studioは、AIワークフローを構築するためのAIエージェントなどを開発するツールですが、n8nは既存のツールを組み合わせてAIワークフローそのものを構築するイメージです。
ノーコードの自動化ツールZapierやMakeも似たツールとして挙げられますが、これらの既存のiPaaSツールとDifyなどでは、自律性や役割などで違いがあります。
Dify・n8n・Copilot Studio
→AIが判断や生成まで行うため、ワークフロー内のタスクを自律的に処理できる
Zapier・Make
→iPaaSはあくまで「決められた手順を自動で実行する」ツールで、AIによる柔軟な判断はできない
AIワークフローの導入メリット

AIワークフローを導入すると、以下のようなメリットがあります。
- 業務効率化:繰り返し作業の自動化で時間短縮・省力化
- コスト削減:少人数で業務を回せ、人件費や外注費を抑制
- 精度向上:ヒューマンエラーを減らし、一貫した成果物を提供
- 迅速な意思決定:データ分析や予測に基づく判断が可能
- 顧客満足度向上:パーソナライズやAIチャットで体験を改善
- 新規ビジネス創出:AI活用で新しいサービスや商品を展開
- スケーラブル:業務量増加や多言語対応にも柔軟に対応可能
それぞれのメリットについて具体的に紹介するので、AIワークフローの導入を検討中の方は参考にしてみてください。
業務効率化:繰り返し作業の自動化で時間短縮・省力化
AIワークフローを導入する最大のメリットの一つが、繰り返し作業の自動化による業務効率の向上です。これまで人間が手作業で行っていたデータ入力・レポート作成・メール対応などのルーティンタスクを、生成AIが自動で処理できるようになります。
その結果、単純作業に費やしていた時間を大幅に削減でき、社員はより付加価値の高い業務や意思決定に集中することが可能です。
コスト削減:少人数で業務を回せ、人件費や外注費を抑制
AIワークフローを導入することで、少人数でも効率的に業務を回すことが可能になります。繰り返し行う作業を生成AIが担当するため、従来は複数人で行っていた作業を大幅に削減できます。
その結果、人件費の抑制や外注によるコストの削減につながります。また、業務を自動化することで、忙しい繁忙期や人手不足の状況でも安定した作業量を確保でき、外部リソースに依存せずに業務を遂行できるのも大きなメリットです。
精度向上:ヒューマンエラーを減らし、一貫した成果物を提供
AIワークフローを活用することで、ヒューマンエラーを大幅に減らし、常に一貫した品質の成果物を提供可能です。
データ入力や計算、情報整理など、従来人間が行っていた作業はどうしてもミスが発生しやすいですが、生成AIが自動化することでエラーを防ぎ、正確な処理を実現します。
また、AIワークフローは処理ルールや手順を標準化できるため、複数人で業務を行う場合でも成果物のばらつきが少なくなります。品質管理の手間が減り、社内外への信頼性向上につながるのもメリットです。
迅速な意思決定:データ分析や予測に基づく判断が可能
AIワークフローを導入することで、大量のデータを瞬時に分析し、予測に基づいた意思決定が可能になります。従来は人間が膨大な情報を整理・分析する必要があり、判断に時間がかかることも少なくありませんでした。
生成AIは、過去データやリアルタイムの情報をもとに、傾向分析やリスク予測を自動で行い、意思決定に必要な情報を即座に提供します。迅速かつ根拠のある判断が可能となり、業務や戦略のスピードを大幅に向上させられるのが魅力です。
顧客満足度向上:パーソナライズやAIチャットで体験を改善
AIワークフローを導入することで、顧客一人ひとりに最適化された体験を提供できるため、顧客満足度の向上にもつながります。
顧客一人ひとりに最適化された体験を提供できるのは、生成AIが顧客の属性や過去の行動履歴に基づいたパーソナライズされた情報提供や提案が自動で行えるためです。
さらに、AIチャットボットや自動応答システムを組み込むことで、問い合わせ対応やサポートを24時間365日体制で提供でき、迅速な対応が可能になります。
新規ビジネス創出:AI活用で新しいサービスや商品を展開
AIワークフローの導入により、従来では実現が難しかった新しいサービスや商品の開発が可能になります。生成AIやAIエージェントを活用すれば、膨大なデータから市場動向や顧客ニーズを分析し、アイデアの迅速な検証や試作が行えるためです。
また、生成AIは継続的に学習し改善するため、新規サービスや商品の精度や価値を高めながら提供可能です。これにより、企業は競合との差別化を図りつつ、迅速に市場ニーズに対応するビジネスモデルを構築できます。
スケーラブル:業務量増加や多言語対応にも柔軟に対応可能
AIワークフローを導入することで、業務量の増加や多言語対応など、変化するニーズに柔軟に対応することが可能になります。生成AIは同時に多数のタスクを処理できるため、業務が増えても人手を大幅に追加することなく、安定した処理を維持できるためです。
また、多言語対応も生成AIの得意分野です。顧客対応やドキュメント作成などで複数の言語が必要な場合でも、AIワークフローを活用すれば、自動翻訳や言語別対応の自動化が可能となり、国際的なビジネス展開にも貢献します。
AIワークフローを導入するときの課題

AIワークフローを導入するメリットは多いものの、同時にいくつか課題も存在します。それぞれの課題を詳しく紹介していくので、AIワークフローの導入前に確認しておいてください。
初期コスト:システム導入や学習データ整備に費用がかかる
AIワークフローの導入には、システム構築やAIモデルの学習データ整備などの初期投資が必要です。特に、業務特化型のAIエージェントを作る場合は、データの収集・クレンジング・ラベル付けに時間とコストがかかります。
小規模な企業や個人では、この初期コストが導入のハードルとなるため注意しましょう。
データ品質の確保:AIの精度はデータに依存、誤ったデータでは誤判定のリスク
AIワークフローの精度は、学習データの質に大きく依存します。不完全なデータや誤った情報でモデルを学習させると、判断ミスや誤った推奨が発生するリスクがあります。
そのため、正確で偏りのないデータの収集と管理が不可欠です。
業務プロセスとの適合:既存フローに合わないと運用が複雑化
既存の業務フローにAIワークフローを組み込む際、プロセスが複雑化してしまうことがあります。自動化の範囲や条件分岐を適切に設計しないと、逆に作業効率が下がったり、担当者の負荷が増えるため注意が必要です。
そのため、AIワークフローの導入前に、既存の業務プロセスとの適合有無を慎重に見極めましょう。
人材不足:AIを扱える人材や管理できる人材が限られている
AIワークフローの運用には、AIモデルや自動化プロセスを設計・管理できる人材が必要です。しかし、国内外問わずこうした専門人材は不足しており、導入・運用のボトルネックになることがあります。
業務の属人化を防ぐことを目的にAIワークフローを導入するにもかかわらず、結局一部の人材しか該当の業務に従事できない事態にもなりかねません。
そのため、AIワークフローを導入する際は、自社でAI人材を育てるなどの準備も必要です。
社内理解・浸透:現場が「使いにくい」と感じると定着しにくい
AIワークフローを導入しても、現場が操作や活用方法を理解できない場合、定着率が低くなり効果が出にくいです。最終的に、ほとんど使われなくなり、導入コストが無駄になるといったケースも少なくありません。
したがって、AIワークフローを使いやすいインターフェースに設計したり、教育・サポート体制を入念に準備することが重要です。
セキュリティ・コンプライアンス:機密情報や個人情報の取り扱いリスク
AIワークフローでは、顧客データや社内機密情報を扱う場合があります。対策が不十分だと大切なデータが漏洩してしまうリスクがあるため、注意が必要です。
したがって、AIワークフローは、アクセス制御や暗号化などを徹底し、法令・規制に遵守しながら運用しましょう。
ブラックボックス化:AIの判断根拠が不透明になり説明責任を果たしにくい
AIが自律的に判断する場合、判断プロセスや根拠が不透明になりやすく、説明責任を果たすのが難しくなります。何か問題があった際に、対処が難しくなるため注意が必要です。
特に、意思決定や法的判断に関わる業務では透明性の確保が重要です。
継続的なメンテナンス:モデルのアップデートや再学習が必要
AIワークフローは導入後も継続的なメンテナンスが必要です。業務内容の変化やデータの更新に応じてモデルを再学習させ、精度や性能を維持する必要があります。
放置すると、精度低下や誤判断のリスクが高まるため、あらかじめ継続的なコストや手間がかかることを考慮しておきましょう。
なお、生成AIを社内に導入するときのポイントに関しては下記の記事を参考にしてください。
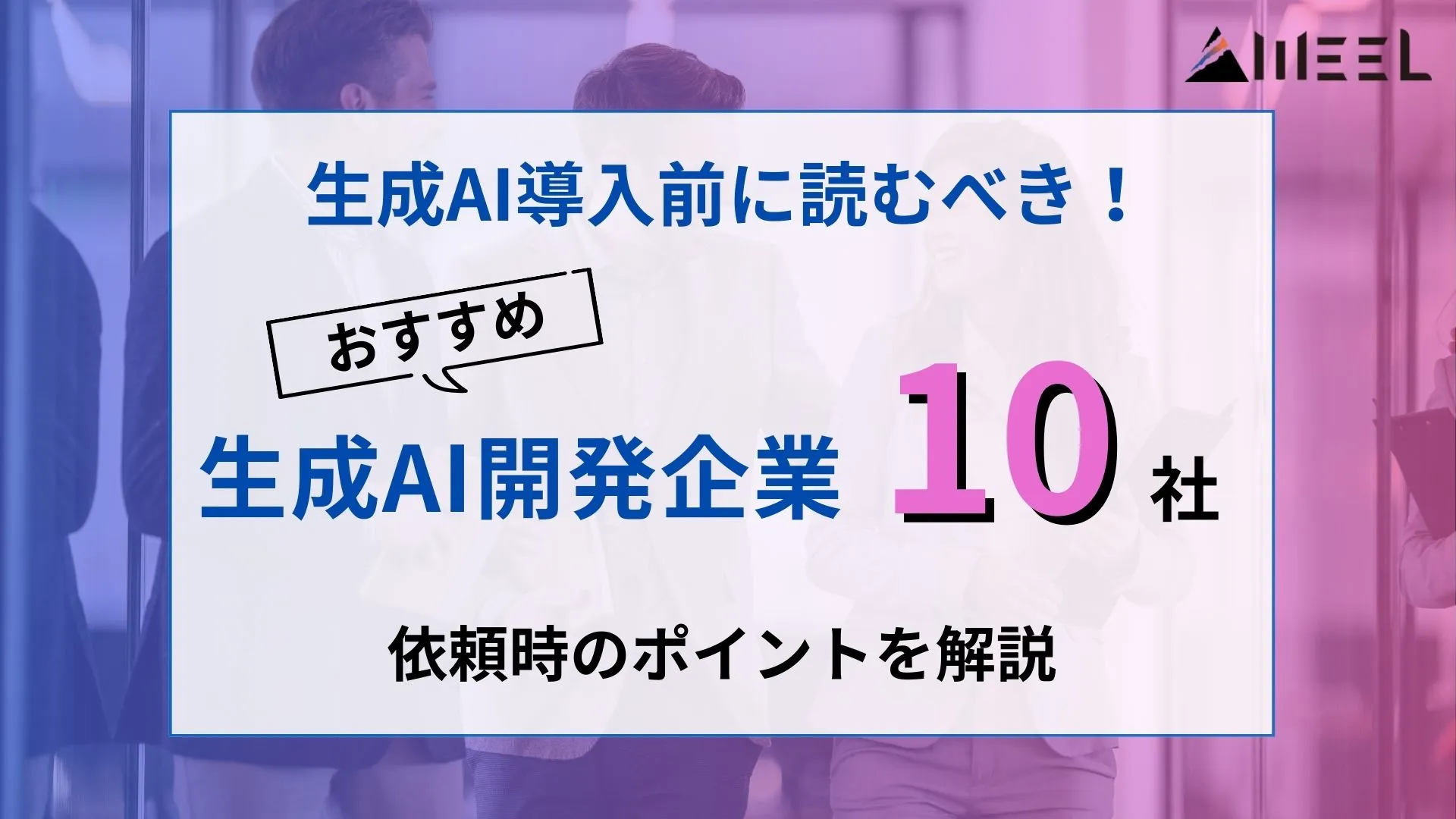
AIワークフロー導入時のポイント

AIワークフロー導入の課題を解決するためにも、以下のポイントを意識するのがおすすめです。
- 目的を明確化:効率化・コスト削減・新規価値創出など、導入のゴールを設定する
- スモールスタート:小規模プロジェクトから試して効果を確認し、段階的に拡大する
- データ整備:AIの精度を左右するため、正確で整理されたデータを準備する
- 業務フローとの適合:既存のプロセスにどう組み込むかを設計してから導入する
- 現場の使いやすさ重視:ユーザーが直感的に使える仕組みにすることで定着を促す
- 教育・人材育成:AIを理解し使いこなせる人材を育てる
- セキュリティ・ガバナンス:個人情報や機密データの管理体制を強化する
- 継続的改善:導入後も運用データを活用し、モデルやフローを見直し続ける
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説していきます。
目的を明確化:効率化・コスト削減・新規価値創出など、導入のゴールを設定する
AIワークフローを導入する際には、最初に「なぜ導入するのか」をはっきりさせることが重要です。
単に流行だから導入するのではなく、業務効率化・コスト削減・新しい価値やサービスの創出といった具体的な目的を明確にすることで、導入後の成果を正しく評価できるようになります。
また、目的が明確であれば、導入範囲や必要なデータ、人材育成の方向性も定まり、社内での合意形成もスムーズに進みます。
スモールスタート:小規模プロジェクトから試して効果を確認し、段階的に拡大する
AIワークフローの導入は、一度に大規模に進めるのではなく、小さな範囲から始めると効果的です。限られた業務プロセスや部門で試験的に導入することで、効果や課題を早期に把握できます。
その結果を踏まえて改善を重ねながら、徐々に適用範囲を拡大していくことで、失敗のリスクを抑えつつ社内全体へのスムーズな展開が可能になります。
データ整備:AIの精度を左右するため、正確で整理されたデータを準備する
AIワークフローの成果は、入力されるデータの質に大きく依存します。データに欠損や重複、誤りがあると、AIの判断精度が低下し、業務への効果が十分に発揮されません。
そのため、事前にデータをクリーニングし、分類や形式を統一することが重要です。また、継続的にデータを更新・蓄積していく仕組みを整えることで、生成AIのモデルを磨き続け、より信頼性の高いアウトプットを得られるようになります。
業務フローとの適合:既存のプロセスにどう組み込むかを設計してから導入する
AIワークフローを導入しても、既存の業務プロセスと噛み合わなければ現場で活用されず、かえって作業が複雑になるリスクがあります。導入前に「どの業務をAIに任せ、どの部分を人が担うのか」を整理し、全体の流れを最適化する設計が欠かせません。
また、現場の担当者がスムーズに利用できるよう、既存システムとの連携や操作性の調整も重要です。業務フローとの整合性を意識することで、生成AIが真に生産性向上に貢献する仕組みを構築できます。
現場の使いやすさ重視:ユーザーが直感的に使える仕組みにすることで定着を促す
AIワークフローは、現場で日常的に使われてこそ効果を発揮します。しかし操作が複雑だったり、入力や確認作業が増えてしまうと、現場は「かえって手間が増えた」と感じてしまい定着が難しくなります。
そのため、導入時にはユーザーインターフェースを直感的でシンプルに設計し、既存の業務システムやツールと自然に連携できるようにすることが重要です。
現場の声を取り入れた仕組みにすることで、抵抗感を減らし、生成AIが日常業務にスムーズに溶け込みます。
教育・人材育成:AIを理解し使いこなせる人材を育てる
AIワークフローを導入しても、それを活用できる人材が不足していると十分な効果は得られません。生成AIの仕組みや限界を理解し、適切に運用・改善できるスキルを持った人材の育成が必要不可欠です。
特に現場担当者には、専門的なプログラミング知識がなくても使いこなせるようなトレーニングが必要になります。また管理職や意思決定層は、生成AI導入の目的やリスクを把握し、戦略的に活用できる視点を身につけることが重要です。
セキュリティ・ガバナンス:個人情報や機密データの管理体制を強化する
AIワークフローの導入では、顧客データや社内の機密情報を取り扱うケースが多く、情報漏えいや不正利用のリスクを伴います。そのため、セキュリティ対策とガバナンスの強化が不可欠です。
具体的には、アクセス権限の制御・暗号化・ログ管理などの基本対策に加え、利用するAIツールやクラウド環境のセキュリティ要件を十分に確認する必要があります。
また、法規制や社内規定に準拠した運用ルールを設け、監査体制を整えることでリスクを最小化できます。
継続的改善:導入後も運用データを活用し、モデルやフローを見直し続ける
AIワークフローは、一度構築して終わりではありません。環境の変化や新しい技術の登場に合わせて常に改善していくことが大切です。
運用の中で蓄積されるデータやユーザーのフィードバックを分析することで、ボトルネックの解消や精度向上が見込めます。
AIワークフローの活用事例
ここからは、AIワークフローの活用事例を紹介していきます。これから導入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
チャット入力でAIがワークフローを自動生成
AIワークフローは、チャットでの指示入力だけで自動的に構築可能です。
上記投稿では、ユーザーが自然言語で要望を伝えるだけで、AIが必要な処理を組み合わせたワークフローを生成しています。
従来のように複雑な設定やノーコードツールでの細かい操作は不要で、対話ベースで直感的に業務プロセスを設計できるのが大きな利点です。
特に非エンジニアでもスピーディーに自動化を実現できる点は、導入ハードルを大きく下げています。
問い合わせフォーム入力で自動メールが飛んでくるワークフロー
AIワークフローを活用すれば、問い合わせフォームへの入力をきっかけに自動でメールを送信する仕組みを簡単に構築できます。
上記の事例では、顧客がフォームに入力した内容を生成AIが受け取り、そのまま自動返信メールや担当者への通知メールを生成しています。
従来なら手作業やシステム連携が必要だったプロセスが、シンプルなワークフローで完結するのが特徴です。顧客対応のスピードが向上するだけでなく、担当者の負担軽減にもつながります。
ショート動画を自動生成するワークフロー
AIワークフローを活用すると、動画制作のプロセスも自動化できます。
上記の事例では、入力したテキストや画像素材をもとに、AIが自動でショート動画を生成するワークフローが紹介されています。
従来は編集ソフトや手作業で行っていた作業が数クリックで完了するため、制作時間を大幅に短縮可能です。また、テンプレートや自動編集機能により、専門外の方でもクオリティの高い動画を効率的に作成できるのも大きなメリットです。
企業決算スライドを自動生成するワークフロー
AIワークフローを活用すると、企業決算データからスライド資料を自動で作成可能です。
上記では、決算データをAIに入力するだけで、グラフや要点を整理したスライドが自動生成されています。
従来は手作業で表やグラフを作成し、内容を確認する必要がありましたが、AIワークフローを活用することで作業時間を大幅に短縮でき、担当者は分析や戦略検討に集中できるのがメリットです。
また、統一されたフォーマットでスライドが作成されるため、資料の品質と見やすさも向上します。
暗号資産のトレンド監視システムをAIワークフローで作成
AIワークフローの機能を活用して、複数のブロックチェーン上のトレンドを自動で監視するシステムを作成した方がいたのでご紹介します。
こちらの事例では、Ethereum・Solana・Base・BNB Chain・Arbitrum・Optimism・Polygon・Avalancheの8チェーンを対象に、SNS言及・オンチェーンデータ・価格・出来高を統合分析。ロング・ショート候補や急騰銘柄を日本語でTelegramに通知するワークフローが紹介されています。
このシステムの特徴は、重複防止・リスク除外・日次サマリーといった安全運用ガードが組み込まれている点です。生成AIを使用することにより、こういった高度なワークフローを短期間で実現できています。
AIワークフローが仕事の常識を変えていく!
AIワークフローは、生成AIや機械学習を活用して業務プロセスを自動化・最適化する仕組みです。導入することで、作業の効率化やコスト削減、迅速な意思決定など、多くのメリットが得られます。
ただし、データ品質の維持やセキュリティ管理などの課題もあり、計画的な運用が欠かせません。AIワークフローを導入する際は、目的を明確にしつつ小規模から導入し、業務効率化を実現させましょう。

最後に
いかがだったでしょうか?
AIワークフロー導入は効率化だけでなく新規事業の創出にも直結します。自社に最適な活用方法を知ることで、競合に先んじた成長戦略を描けます。
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。
︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。
最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。
また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。