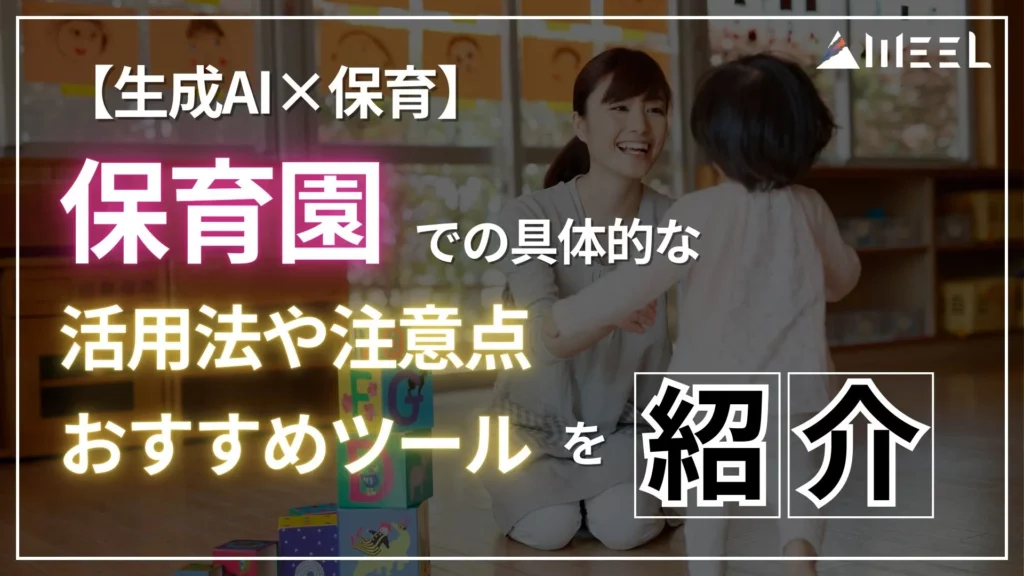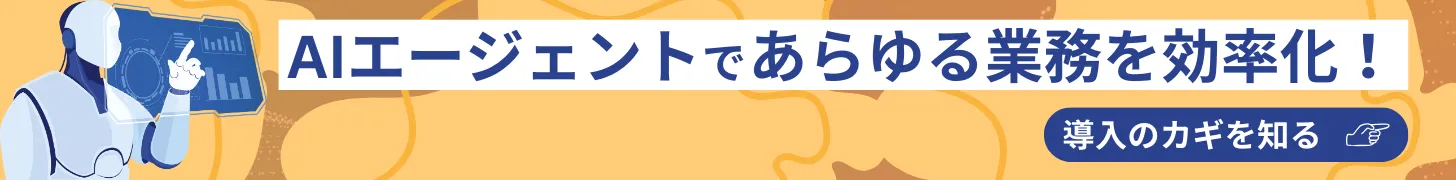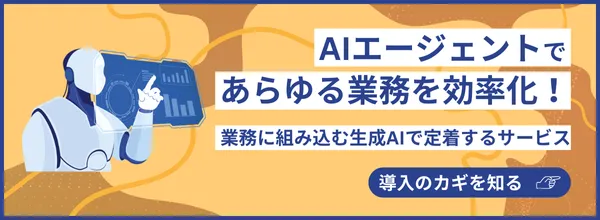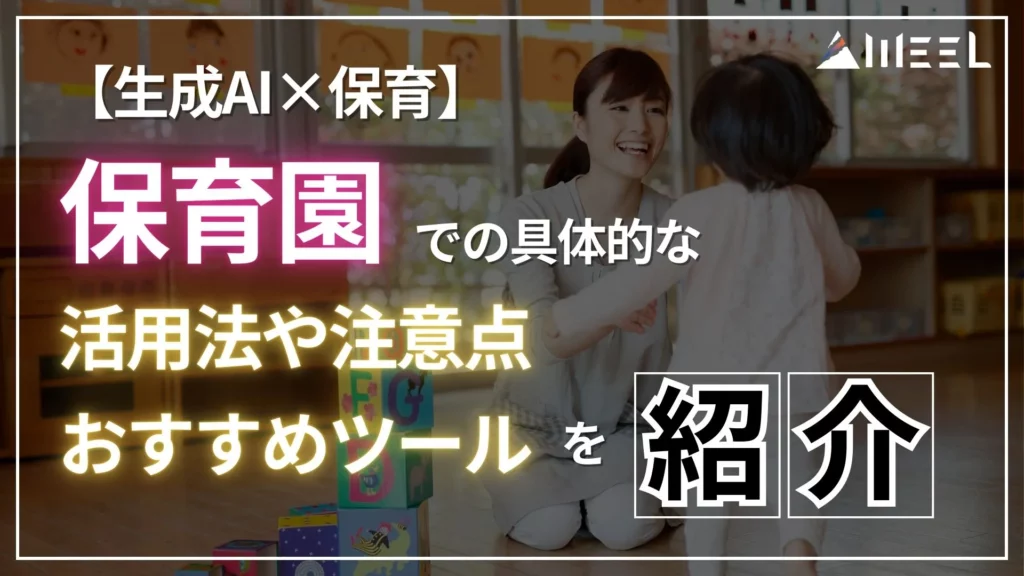
- 保育現場の書類作成やアイデア出しを生成AIがサポートし、業務負担を大幅に軽減できる。
- おたより作成・絵本制作・記録整理などに活用でき、子どもと向き合う時間をしっかり確保できる。
- 誤情報や個人情報流出リスクもあるため、ツール選定や運用ルールを明確にして活用することが重要。
近年、急速に注目を集めている「生成AI」。
文章や画像、音声などを自動で生成できるこの技術は、教育やビジネスだけでなく、保育の現場でも活用が進み始めています。「業務が忙しくて書類作成に時間をかけられない」「もっと子どもたちと向き合う時間を確保したい」…そうした保育士の悩みを解決するツールとして、生成AIは大きな可能性を秘めているのです。
本記事では、生成AIとは何か、実際の保育にどう役立つのか、導入の注意点やおすすめツールまで、保育現場の視点でわかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/
そもそも生成AIとは?保育の現場でどう関係するのか
生成AIとは、画像・文章・音声などを自動生成する人工知能技術の一種です。インターネット上のあらゆるデータを学習し、新しいコンテンツを生成する能力を持っています。
生成AIは多種多様な業界で活用されており、保育の現場でも近年注目を集めています。
AIと生成AIの違い
まずは従来のAIと生成AIの違いについて見てみましょう。
「AI(人工知能)」全般は、データの分析や予測を行うための技術ですが、生成AIは特に「生成する」ことに特化しているのが特徴です。具体的には、以下のような違いがあります。
- 従来のAI:決められた行為の自動化が主な目的であり、出力されるものは構造化されたデータ(数値やテキストなど)です。
- 生成AI:既存のデータを基に新しいコンテンツを創造することができ、例えば条件に応じた文章を生成したり、画像を作成したりすることが可能です。
このように、従来のAIは「判断・認識・処理」が得意なのに対し、生成AIは「創造的なアウトプット」が得意な領域と言えます。
生成AIが保育の現場で注目されている背景
保育現場では、慢性的な人手不足や書類作成の負担、保育士の長時間労働といった課題が存在します。
こうした中、生成AIが注目されているのは、保育士の業務を効率化する手段として期待されているためです。たとえば、保育日誌の下書き、連絡帳の文案作成、行事案内のテンプレート作成など、文章作成の負担を軽減できます。自動化・効率化できる点を生成AIに任せることで、保育士が本来の「子どもと向き合う時間」を確保できるという点も大きな利点です。
生成AIは、単なるITツールではなく、働き方改革の鍵として捉えられています。
なお、生成AIによる教育業界の業務効率化方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
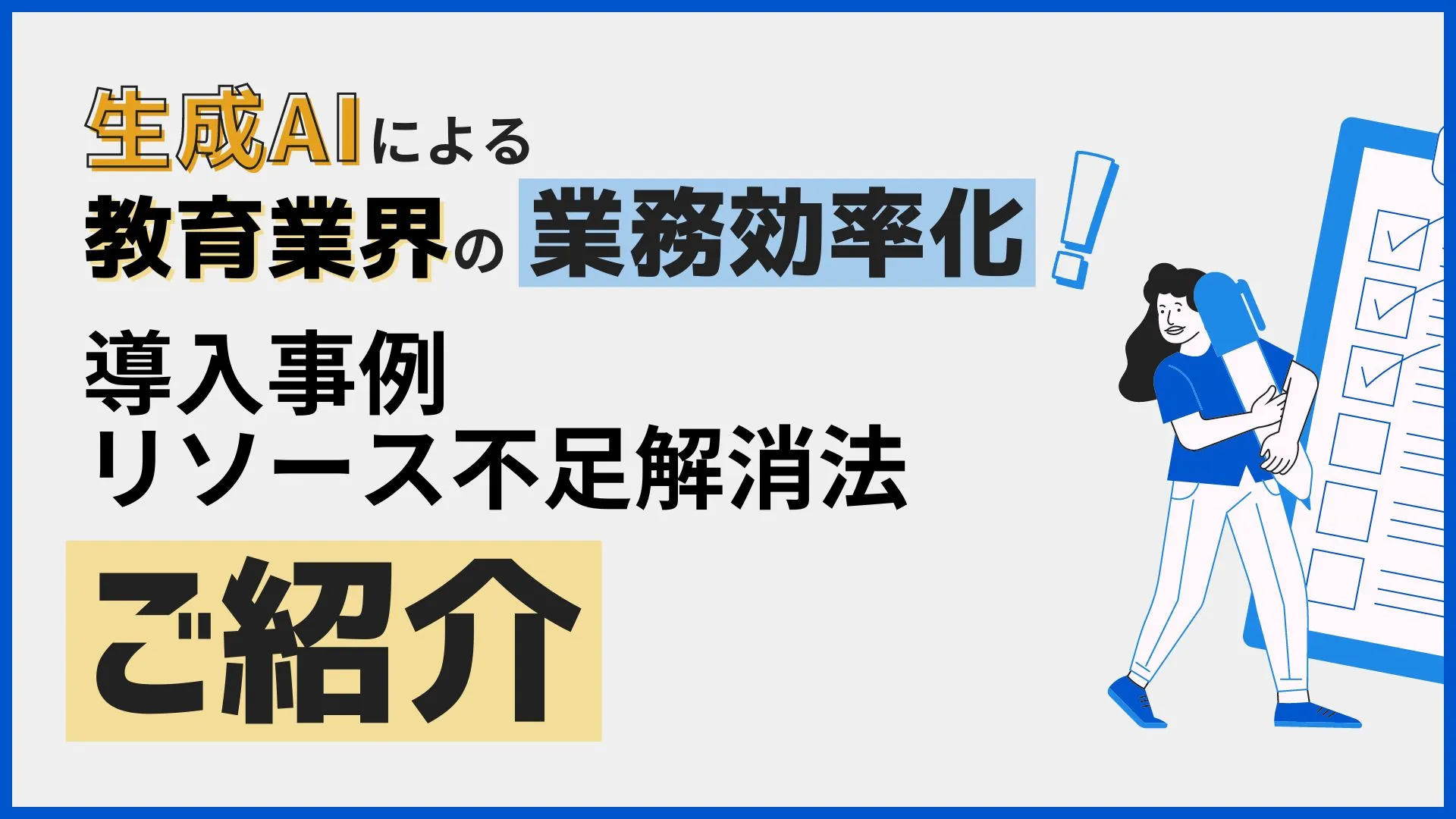
生成AIには何ができる?主要な機能と種類を解説

生成AIは、文章や画像、音声、動画などを自動で生成できる技術です。ここでは、代表的な生成AIの機能と種類についてそれぞれ解説します。
テキスト生成
テキスト生成は、生成AIが最も普及している分野の1つです。
与えられた指示に従って、自然な文章を自動で生成します。たとえば、記事の下書き、メール文面、ストーリー作成、長文要約などに活用されています。
有名なツールには、OpenAIの「ChatGPT」や、Googleの「Gemini(旧Bard)」、Anthropicの「Claude」などがあります。
生成AIがあらゆる業種に対応できることから、教育・ビジネス・福祉現場など幅広く利用が進んでいます。
画像生成
画像生成は、テキストによる指示(プロンプト)をもとに、オリジナルの画像を作成します。画像から新しい画像を生成することも可能です。
風景画からイラスト、ロゴ、商品パッケージのデザイン案まで多様な用途に対応可能です。デザイナーの作業補助や広告制作にも導入が進んでいます。
代表的なツールには「DALL-E」、「Midjourney」、「Stable Diffusion」などがあります。最新の画像生成AIは非常に高精度でリアルな描写が可能です。
音声生成
音声生成は、文字情報をもとに人間のような自然な音声を作る技術です。
ナレーション、読み聞かせ、音声アシスタント、案内音声などに使われています。多言語対応や感情表現も進化しており、教育や保育の現場でも、絵本の読み上げ支援などで注目されています。
有名なツールには「Voicebox(Meta)」、「Amazon Polly」、「Text-to-Speech(Google)」などがあります。
動画生成
動画生成は、静止画やテキストから動きのある動画コンテンツを自動生成する技術です。
プレゼン動画、教育用コンテンツ、SNS用ショート動画などに活用でき、効率的なコンテンツ制作が実現します。画像と音声を組み合わせたナレーション付き動画も自動生成可能です。
代表的なツールには「Sora」、「Runway」、「Pika Labs」などがあります。簡単なテキストプロンプト(または画像や動画)から高品質な動画を作成でき、動画制作のハードルが一気に下がる技術です。
保育現場での具体的な活用方法5選
生成AIは保育現場でもさまざまな業務を支援できます。ここでは、特に実用性が高く、現場で導入しやすい活用例を5つ紹介します。
保護者向けおたより・連絡帳の作成支援
毎日の連絡帳や月次のおたより作成は、保育士にとって大きな負担の1つです。
生成AIを活用することで、文章の自動生成や校正が可能になります。たとえば、「◯歳児の今月の活動まとめ」や「今日の様子をやさしい言葉で」などの指示で、自動的に適切な文案を提案してくれます。保育士はそれをベースに修正するだけで済むので、時間短縮につながります。また、文章のトーンや言葉遣いも柔軟に調整できるため、特定の情報を強調したり、親しみやすい表現に整えたりできます。
保護者向けおたよりや連絡帳の作成に生成AIを活用することで、保育士はより多くの時間を子どもたちとの関わりに充てることができ、保護者とのコミュニケーションも円滑になります。
絵本やストーリーの自作
生成AIは、オリジナルのストーリーや絵本の作成にも活用できます。たとえば「3歳児向けで、季節をテーマにした優しいお話を作って」といったプロンプトで、子どもたちに合わせた創作が可能です。さらに、画像生成AIを併用すれば、挿絵付きのオリジナル絵本を作ることもできます。
生成AIによって作成されたストーリーは子どもたちの興味を引く要素をより多く取り入れることができるため、言葉や感性の発達を促す教育的効果も期待できます。
遊びや活動のアイデア出し
保育士が子どもたちに提供する遊びや活動のアイデアを考えるのは、時に難しい作業です。しかし生成AIであれば、さまざまな遊びのアイデアを瞬時に作り出すことができます。
たとえば、「雨の日の室内遊び」「少人数でできる知育遊び」など、生成AIは条件に応じた保育アクティビティのアイデアを短時間で大量に提案できます。既存のアイデアにひと工夫加えたいときや、新しい刺激が欲しいときにも役立ちます。
保育士が一から考える時間を短縮しつつ、子どもたちにとって魅力的な体験を提供する支援ツールとして注目されています。日案や週案作成にも応用可能です。また、AIが提案するアイデアは多様性に富んでいるため、保育士自身の発想を広げる助けにもなります。
ヒヤリハット・事故報告の記録整理
ヒヤリハットや事故報告の記録は、保育現場において非常に重要ですが、文章化に時間がかかることも少なくありません。
しかし生成AIを使えば、「○○の場面で子どもがつまずき転倒した」などの概要を入力するだけで、形式に沿った報告文を生成可能です。また、過去のデータを参照し、類似の事例を分析することで再発防止策を提案することもできます。
生成AIの活用により、記録作成にかかる時間を大幅に短縮できるだけでなく、報告の属人化が防げ、記録の質を保つことも可能です。職員間の共有や管理者への報告もスムーズになり、業務の効率化と安全管理の向上が両立できます。
職員会議資料の自動要約やサポート
保育現場では職員会議が定期的に行われますが、その際の資料作成や議事録の作成は手間がかかります。こういった会議の議事録作成や資料作成にも生成AIは活用できます。
生成AIは会議の内容を自動で要約し、重要なポイントを抽出することができます。また、会議中の発言をリアルタイムで記録し、後で簡単に議事録を作成することが可能です。さらに、過去の会議資料を分析し、次回の会議に向けた提案を行うこともできます。
会議資料だけでなく、保育方針の共有文案や施策の比較提案、意見の分類なども可能で、効率的な会議運営が可能になります。特に多忙な年度初めや月末などにおいて、時間と労力を節約できる手段として生成AIは非常に強力なサポーターとなるはずです。
なお、学校における生成AIの使い方について詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。
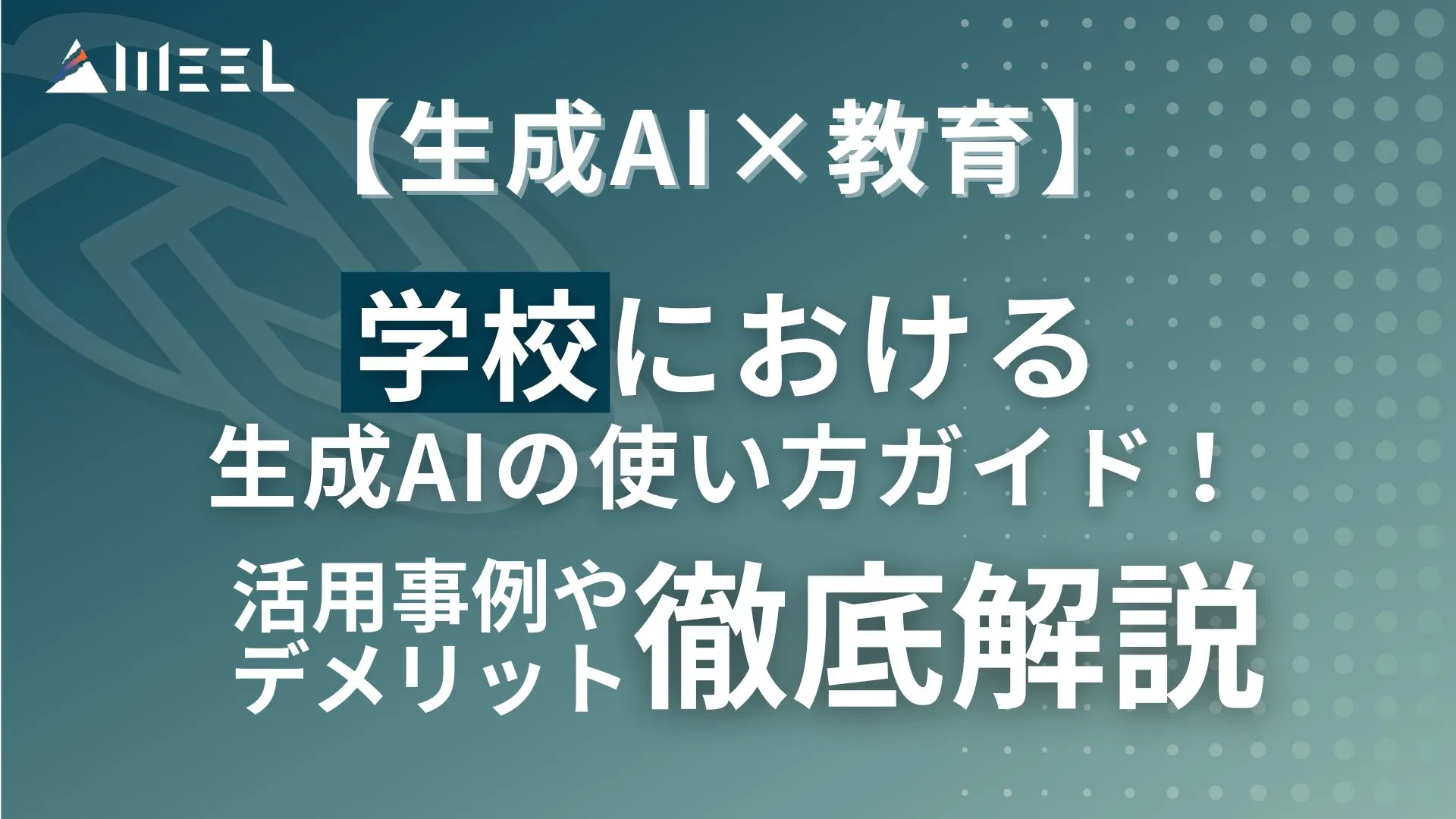
生成AIを使う上での3つの注意点
生成AIは非常に便利で保育現場において多くの利点をもたらす反面、使い方を誤ると大きなリスクを伴います。ここでは保育現場での導入時に特に注意すべき3つのポイントを解説します。
誤情報や偏りのリスク
生成AIは大量のデータをもとに出力を行いますが、その情報が必ずしも正確とは限りません。(ハルシネーション)
学習したデータが偏っていたり不正確であったりすると、出力される情報にも誤りや偏りが生じる可能性があります。特に、医療や発達、心理など専門性の高い内容では、誤った情報や偏見が含まれることもあります。
教育や保育の現場では特に正確な情報が求められるため、生成AIが出力した内容をそのまま受け入れることは危険です。例えば、生成AIが提供する情報が事実と異なる場合、子どもたちに誤った知識を与えてしまう恐れがあります。
また、AIは学習データの傾向に基づいて回答するため、文化的・倫理的なバイアスが混入する可能性も否定できません。AIが持つバイアスが反映された情報が出力されることで、特定のグループに対する偏見を助長するリスクもあります。
保育現場で生成AIを使用する際には、必ず人の目による確認と判断を行うことが必要不可欠です。必要に応じて専門家の意見を求めることも大切です。
子どもの個人情報保護
保育業務では子どもや家庭に関する繊細な情報を多く取り扱います。
生成AIを使用する際には、子どもやその家族の個人情報を保護することが非常に重要です。生成AIには、個人が特定されるような内容(名前・住所・顔写真など)を絶対に入力してはいけません。特にクラウド型のAIツールを使用する場合、データが外部サーバーに送信・保存されるケースもあるため、情報漏洩リスクを理解したうえで運用する必要があります。
子どもたちのプライバシーを守るために、保育現場で生成AIの利用に関するガイドラインを策定し、職員全員が遵守することが求められます。また、保護者に対しても、生成AIを使用する際のリスクや注意点を説明し、現場で使用することに対する同意を得ることが重要です。
使いすぎによる保育の質低下
生成AIの過度な利用は、保育の本質である「人と人との関わり」を損なう恐れもあります。
たとえば日誌や連絡帳をすべて生成AI任せにすると、子どもの個性や成長に寄り添った記録が失われがちです。また、職員間の意見交換や内省の機会が減ることで、保育の質そのものが低下する可能性もあります。
生成AIの導入は業務の効率化を図る一方で、保育士が子どもたちと直接関わる時間が減少し、感情的な交流が不足することにもなりかねません。特に幼少期の子どもにとっては、人との関わりが成長において非常に重要です。
生成AIはあくまで補助的なツールと捉え、保育士が子どもたちの成長を見守り、関わる時間を大切にすることが求められます。
保育園が生成AIを導入する際の5つのステップ

生成AIを保育園に導入するには、事前の準備と段階的な導入が重要です。ここでは、現場で無理なく活用するための5つのステップを紹介します。
導入目的の明確化
まず最初にすべきは、「なぜ生成AIを導入するのか」を明確にすることです。
保育園が生成AIを導入する理由は多岐にわたりますが、たとえば、業務の効率化、保育の質の向上、保護者とのコミュニケーションの強化などが考えられます。まず大枠を明確にし、さらに細かく「保護者連絡の効率化」や「書類作成の時間短縮」など、具体的な課題や期待効果を洗い出すことが重要です。
目的を明確にすることで導入後の評価や改善も行いやすくなります。また、目的がはっきりしていれば現場の理解や協力も得やすく、ツールの選定や運用方針にも一貫性が生まれます。
安全なツール選定(セキュリティ・利用規約)
次に、生成AIを選ぶ際はセキュリティ面や利用規約をしっかり確認することが不可欠です。
保育園では子どもたちやその家族の個人情報を扱うため、選定するツールがどのようにデータを管理し、保護しているかを確認する必要があります。特にクラウドベースのツールを利用する場合、個人情報や入力データが外部に送信されることがあります。情報漏洩を防ぐには、個人情報の取扱いに関するガイドラインが明記されたサービスを選びましょう。
また、日本国内での利用実績やサポート体制のあるツールを選ぶことで、安心して導入を進められます。信頼できるプロバイダーからのツールを選ぶことで、リスクを最小限に抑え、安全にAIを活用することができます。
試験運用とフィードバック収集
導入にあたってはいきなり本格運用せず、まず小規模な試験運用を行い、その結果を基にフィードバックを収集することが重要です。
たとえば、一部の職員に限って連絡帳作成や資料要約で試すことで、AIツールの実際の操作感や効果、課題点を明確にできます。その後、職員からのフィードバックをもとに調整や改善を行いながら、本格導入に向けて準備を整えましょう。この段階を丁寧に踏むことで、現場での混乱を防げます。
また、試験運用の結果を保護者にも共有することで透明性を保ち、信頼を築くことができます。
職員への研修とサポート体制
生成AIを効果的に活用するためには、現場職員への丁寧な研修が欠かせません。
新しいツールを導入する際には、職員がその使い方を理解し、自信を持って活用できるようにする必要があります。生成AIの基本的な使い方から、情報漏洩を防ぐ入力ルールまで、実際の保育業務に即したマニュアルや研修会を実施しましょう。また、導入後も操作方法やトラブル時の相談先など、継続的なサポート体制を整えておくことが重要です。
職員の不安を軽減し、全員が安心して使えるようになることが現場定着のカギになります。
段階的に活用範囲を広げる
最後に、生成AIの活用範囲を段階的に広げていくことが重要です。
導入初期は限定的な用途に絞り、効果や課題を見極めながら、徐々に活用範囲を広げていくのが現実的です。たとえば、まずはおたより作成からスタートし、慣れてきたら日誌や研修記録の下書き、アイデア提案などにも応用していきます。
一気に広げるのではなく、園全体で共通の理解を持ちながら段階的に展開していきましょう。このアプローチを徹底することで、職員がAIツールに慣れる時間を確保し、導入のリスクを軽減することができます。また、段階的に進めることで各ステップで得られた成果や課題を分析し、次のステップに活かすことができます。
保育向けおすすめ生成AIツール【無料・有料あり】
保育の現場でも活用しやすい生成AIツールが増えています。ここでは、文章・画像・資料作成などに役立つおすすめのツールを、無料・有料含めてご紹介します。
ChatGPT
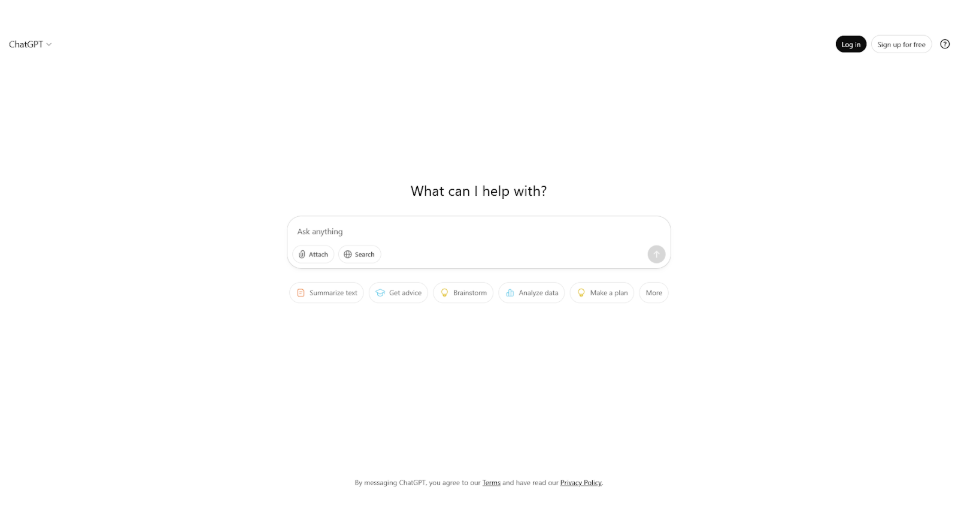
OpenAIが開発する対話型AI「ChatGPT」は、保育日誌やおたよりの文案作成、活動アイデア出しなどに幅広く活用できます。自然な日本語生成が可能で、無料でも利用できますが、有料版(ChatGPT Plus)では最新モデルGPT-4oや様々な高度モデルが使え、より高精度な出力が可能です。
保育士の業務負担を減らし、柔軟な活用ができる万能型AIツールです。
なお、ChatGPT Plusについて詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。

Notion AI

「Notion AI」は、メモやタスク管理ツール「Notion」に組み込まれた生成AIです。議事録の要約、園内会議の記録整理、文書の下書き生成などに最適です。保育業務で多く発生するテキスト整理作業をスムーズにこなせます。
視覚的に整理された操作画面で初心者にも扱いやすく、職員間の情報共有にも活用できます。
なお、Notion AIについて詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。
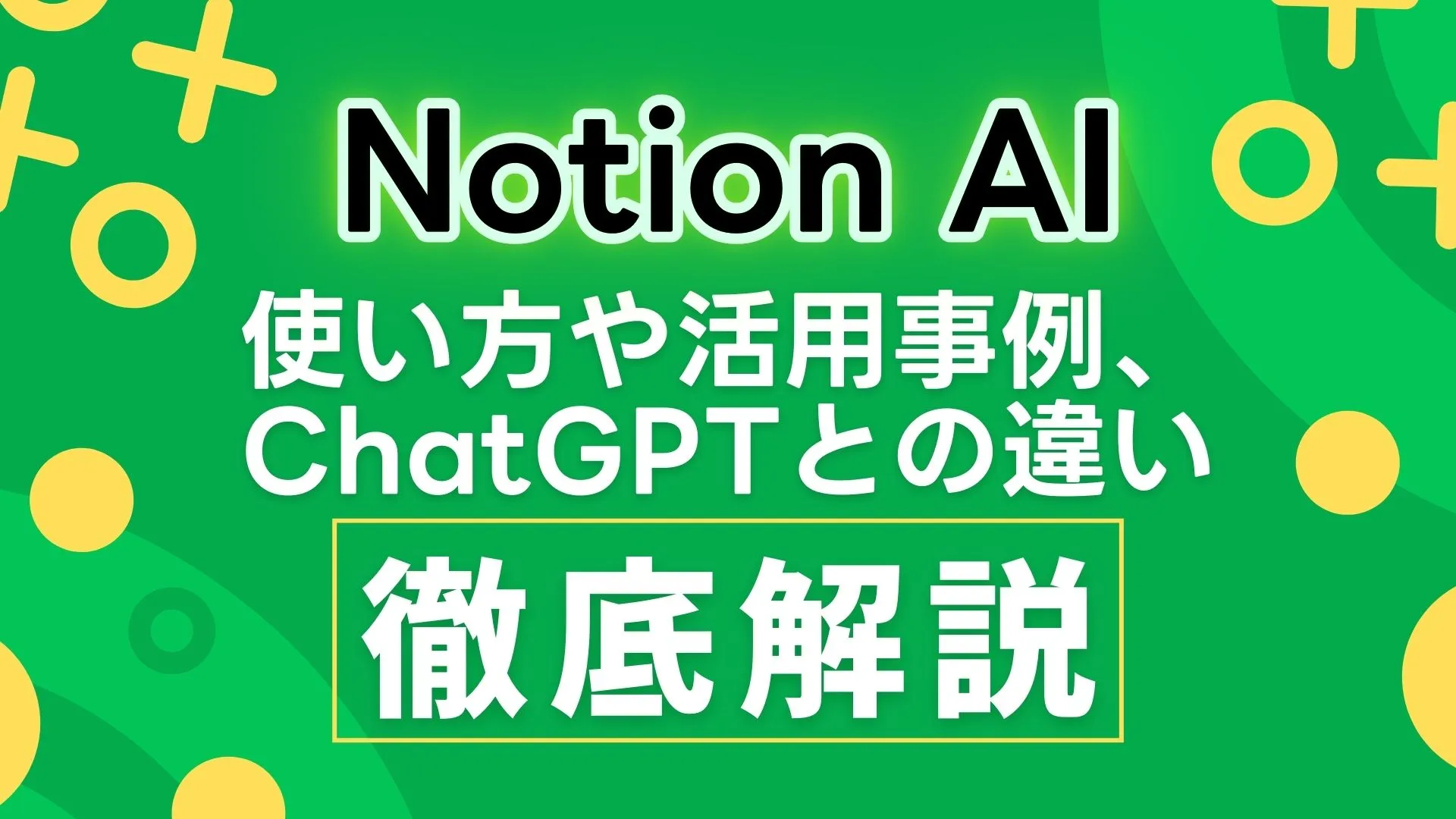
Microsoft Copilot
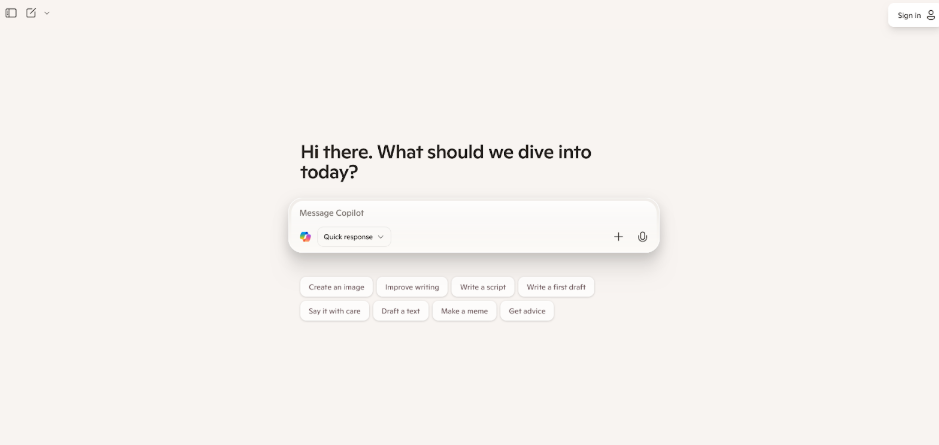
「Microsoft Copilot」は、WordやExcelなどOffice製品に統合された生成AIです。たとえばWordでのおたより作成支援、Excelでの出欠管理や事故記録の表自動作成など、実務に即した活用が可能です。
Microsoft 365環境で使用でき、セキュリティ面にも優れています。既存の業務ツールと連携できるため、導入のハードルが低いのも利点です。
なお、Microsoft Copilotについて詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。

Midjourney
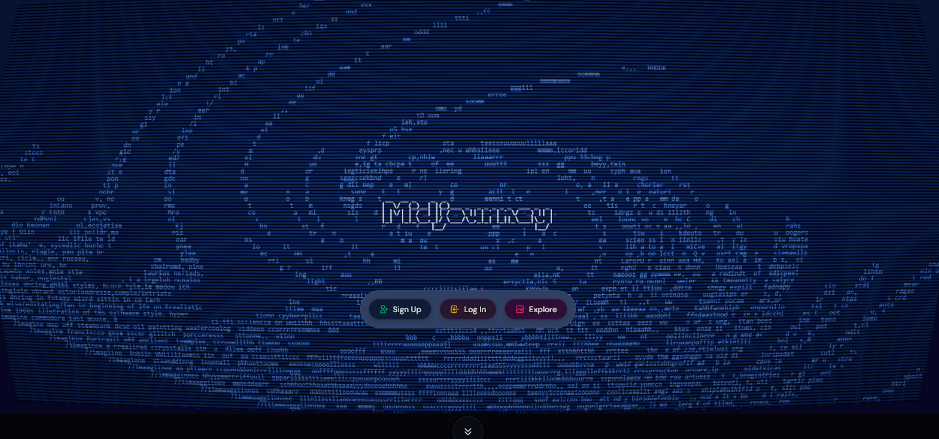
「Midjourney」は、高品質なイラストやアート風画像を生成する有料の画像生成AIツールです。園だよりの挿絵、保育教材用のオリジナルビジュアル、絵本の表紙など、創作活動に活用できます。指示(プロンプト)を入力するだけで多彩な画像を出力でき、保育現場でのビジュアル表現の幅を広げてくれます。
2025年7月現在、Web版とDiscord版から利用可能です。
なお、Midjourneyについて詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。
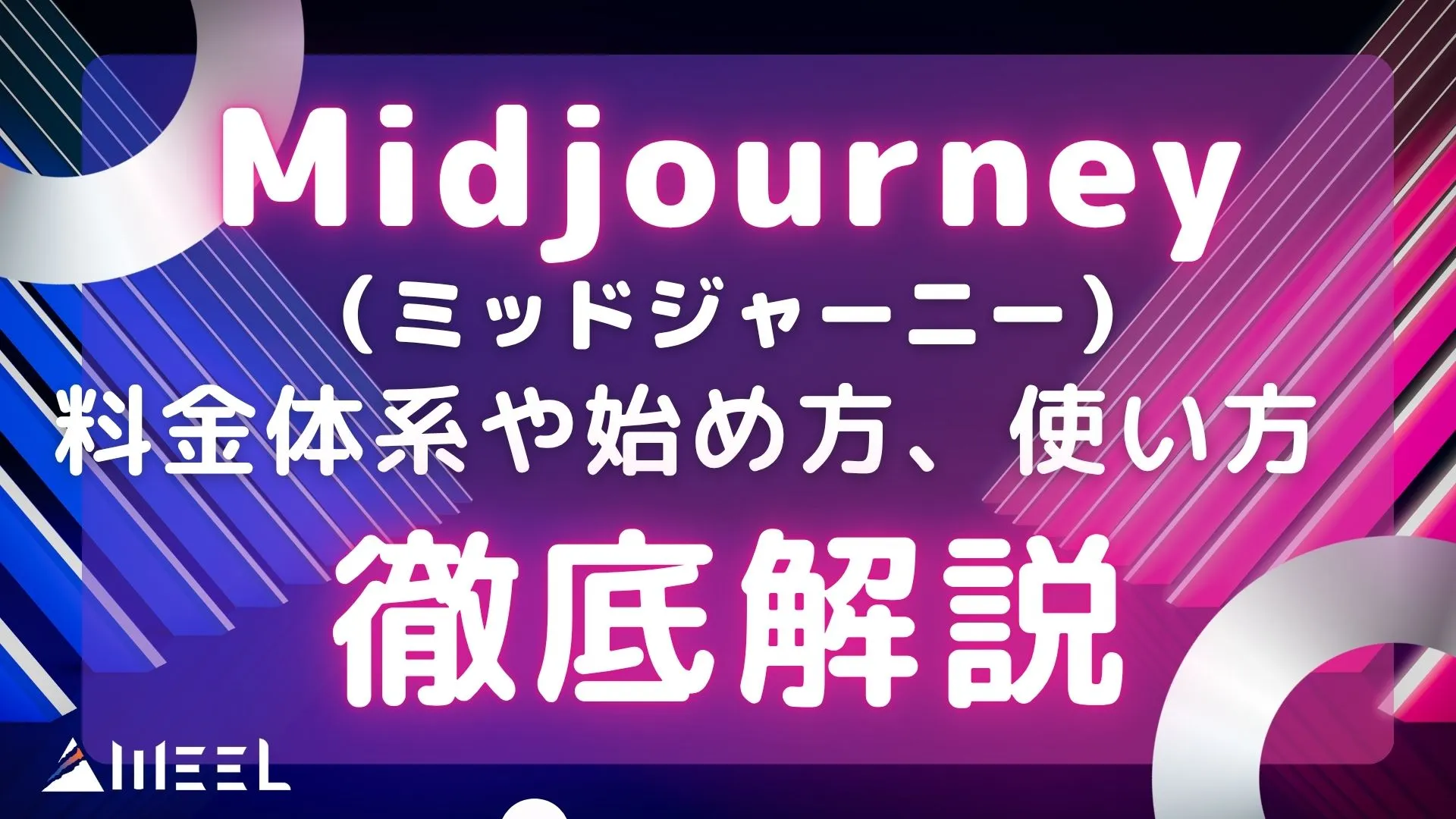
Canva AI

「Canva」のAI機能は、デザイン初心者でも簡単に使えるビジュアル作成ツールとして非常に優秀です。保護者向け資料やイベントポスター、日誌の表紙デザインなどが短時間で完成します。文章生成(Magic Write)や画像生成(Text to Image)など多機能で、保育現場のあらゆる「伝えるデザイン」をサポートします。
Canvaは、他のAIツールに比べて無料でも多くの機能や素材が使える点が魅力です。
なお、Canva AIについて詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。
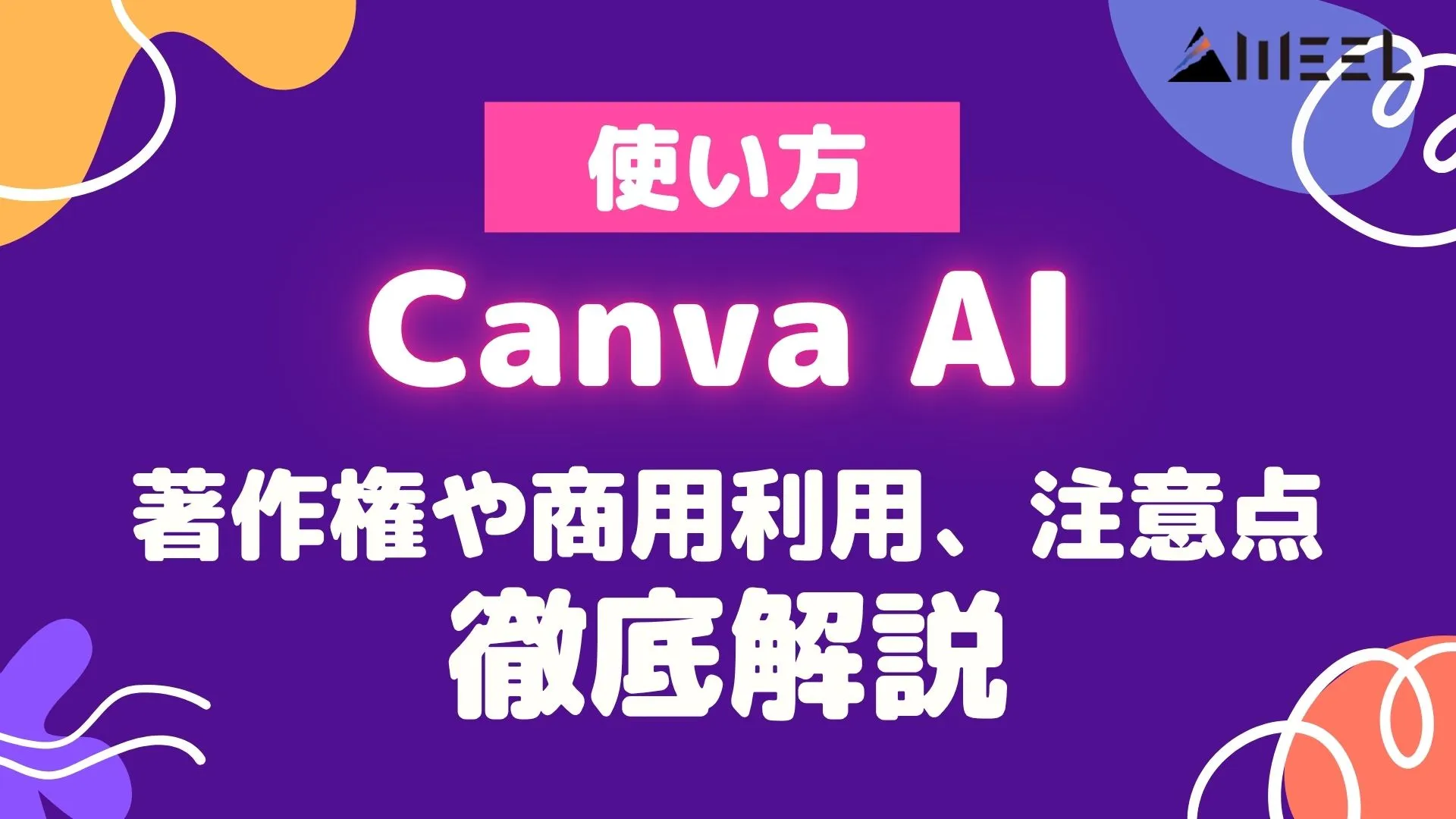
Adobe Firefly
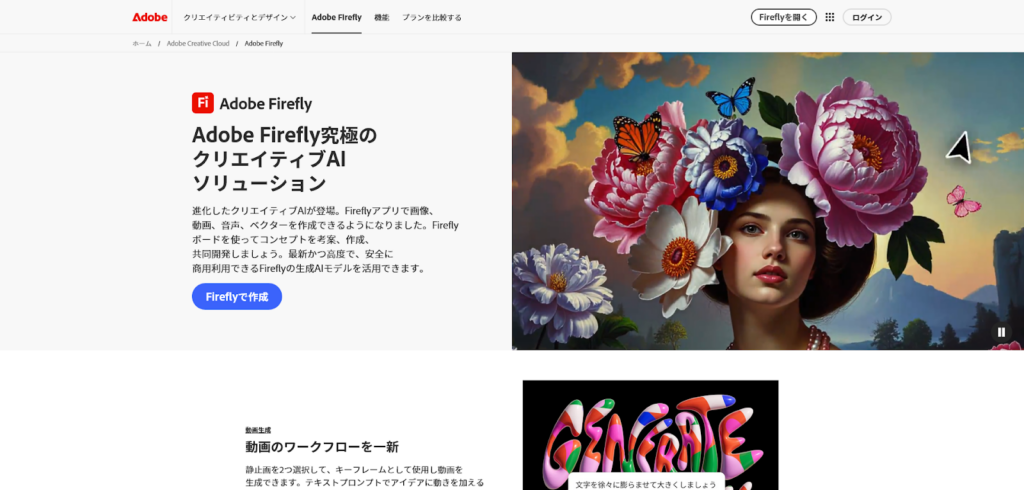
「Adobe Firefly」は、クリエイティブ用途に特化した生成AIで、テキストから高精度な画像や装飾文字を作ることができます。保育イベントのフライヤーや教材のビジュアル作成に適しており、PhotoshopやIllustratorとの連携もスムーズです。Adobe Fireflyの独自生成AIは、著作権侵害の心配がない画像のみを使用して学習されているため、生成された画像は著作権の心配なく商用利用ができます。
教育現場での表現力アップに大きく貢献できるAIツールです。
なお、Adobe Fireflyについて詳しく知りたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。

生成AIで保育をもっとクリエイティブに!
生成AIは、単なる業務効率化のツールにとどまらず、保育をより創造的に、柔軟にする大きな可能性を秘めています。
おたより作成やアイデア出し、絵本制作など、日々の業務をサポートしながら、子どもたちにとって豊かな保育環境づくりに貢献できます。もちろん、個人情報の扱いや使い方には注意が必要ですが、うまく取り入れれば「保育士の働き方改革」と「質の高い保育」の両立も目指せます。
未来の保育を支えるツールとして、ぜひ保育現場での生成AI活用を検討してみてください。
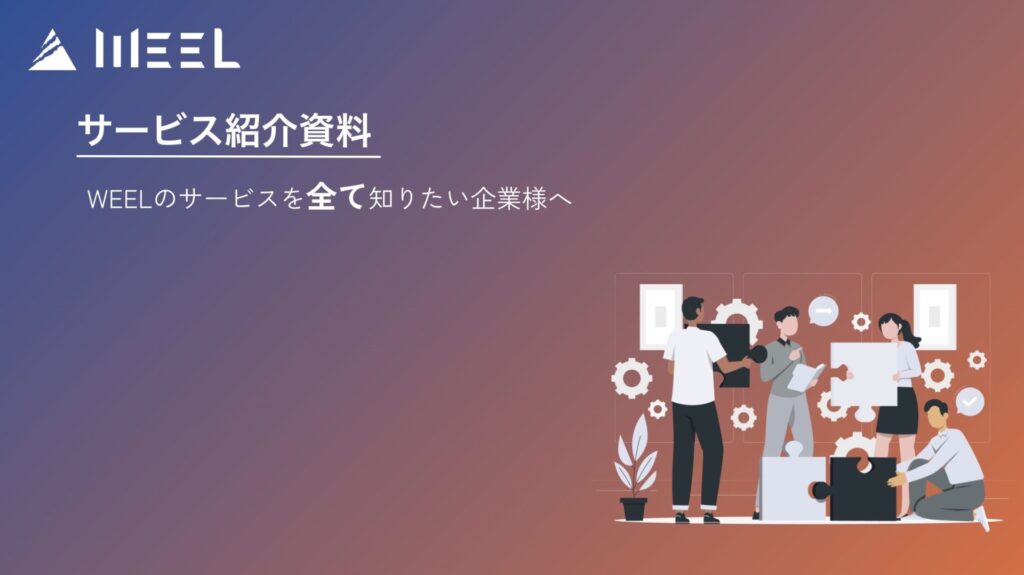
生成系AIの業務活用なら!
・生成系AIを活用したPoC開発
・生成系AIのコンサルティング
・システム間API連携
最後に
いかがだったでしょうか?
生成AIの導入で業務効率化と保育の質向上を両立させるための最適なステップを、課題に合わせてご提案します。
株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!
開発実績として、
・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント
・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット
・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト
・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール
・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用
・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント
などの開発実績がございます。
生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。
まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。
︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。
セミナー内容や料金については、ご相談ください。
また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

【監修者】田村 洋樹
株式会社WEELの執行役員として、AI導入支援や生成AIを活用した業務改革を中心に、アドバイザリー・プロジェクトマネジメント・講演活動など多面的な立場で企業を支援している。
これまでに累計25社以上のAIアドバイザリーを担当し、企業向けセミナーや大学講義を通じて、のべ10,000人を超える受講者に対して実践的な知見を提供。上場企業や国立大学などでの登壇実績も多く、日本HP主催「HP Future Ready AI Conference 2024」や、インテル主催「Intel Connection Japan 2024」など、業界を代表するカンファレンスにも登壇している。