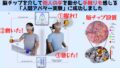日本の沖縄科学技術大学院大学(OIST)で行われた研究によって、外部電源を用いずに「宙に浮き回転し続ける円盤」が実現しました。
直径わずか1センチほどのグラファイト(高純度の黒鉛)製の円盤が、磁石の作る軸対称の磁場によって浮き、しかも回転の妨げとなる摩擦(渦電流の抵抗)を原理的にゼロにできる条件を示し、実験では極めて小さく抑えることに成功したのです。
摩擦のない世界への扉を開くようなこの発見は、精密なセンサーや量子力学の研究にも大きく役立つ可能性があります
なぜ円盤は延々と回り続けることができたのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年10月10日に『Communications Physics』にて発表されました。
目次
- グラファイトを浮かせる――科学者たちが目指した新たな挑戦
- 電源不要の『浮く回転円盤』が実現
- 超精密センサーへの道――回転摩擦抑制のインパクト
グラファイトを浮かせる――科学者たちが目指した新たな挑戦

「摩擦を極限まで小さくした宙に浮く円盤がある」と聞いたら、「またまた、ご冗談を」と思うでしょうか?
ところがこの嘘のようなことが、最新の研究で現実になったのです。
磁石の上にそっと置かれた小さな円盤が、まるで魔法のじゅうたんのようにふわっと宙に浮いて、外部からエネルギーを与えなくても長い時間回り続けます。
SFのようですが、科学の力によって、そんな夢みたいな光景が生まれたのです。
しかし、磁石で遊んだことがある人は「そんなこと本当にできるの?」と首をかしげるかもしれません。
実際、普通の磁石を使って何かを空中に浮かせようとすると、なかなか思い通りになりません。
磁石の極と極が反発しあっても、不安定でぐらぐらと揺れたり、すぐに横にすっ飛んでしまったりしますよね。
この難しさには、実はちゃんと理由があり、「アーンショウの定理」と呼ばれています。
これは簡単に言えば、「磁石だけでは物体を宙に安定して浮かせ続けることは不可能だ」という物理学のルールなのです。
ただし、このルールには例外もあります。
たとえばリニアモーターカーは、強力な超電導磁石と精密な制御システムを使い、安定して浮いて高速で走ることができます。
これは外から電気エネルギーを供給して強力な磁場を作り続けるから可能なことです。
でも実は、もっと手軽に、常温でも磁石だけで安定に浮かせることが可能な素材があります。
それが、炭素からなる「グラファイト(黒鉛)」です。
グラファイトは「反磁性」という性質を持っていて、これは磁石にくっつくのではなく、磁石の磁場から逃げようとして押し返される性質を持つことを意味します。
適切な配置をした磁石の上にグラファイトを置くと、強い磁力に押し上げられて、ふわっと安定して浮かんでしまうのです。
しかし、グラファイトを宙に浮かせて「回転させる」となると、途端に新しい難問が現れます。
それが「渦電流」という現象から生まれる摩擦なのです。
少し詳しく解説しましょう。
電気を通す金属などの素材が磁石の近くで動くと、その物体の中では磁石の磁力を打ち消そうとして、小さな電流が勝手に渦巻き状に流れ始めます。
これが渦電流です。
渦電流が起きる理由は、中学生で習った「電気・磁気・力」の関係にヒントがあります。
物体が動いて磁石が作る磁場の中を横切ると、そこにいる電子たちは動きに応じて流れ始める性質を持っています。
電子が磁場の中を動くと、動きによって電気が発生する、という仕組みです。
でもこの電気(電流)はタダで流れるわけではありません。
電流が流れると、それによって物体の中には新しい磁力が発生します。
元々の磁石の磁力と、この「新しく生まれた磁力」の間で力が発生し、その力が回転する動きを邪魔する方向に働くのです。
これは物理学では「レンツの法則」と呼ばれ、磁石のそばで起こる電流は必ず元の動きを止めようとする反対向きの力を生み出します。
この力が「摩擦」の正体であり、物体は次第にエネルギーを奪われてゆっくりと止まってしまうのです。
これを聞いて「じゃあ、摩擦ゼロの浮遊円盤なんて絶対に作れないの?」と思ってしまうかもしれません。
確かに従来の研究でも、この「渦電流摩擦」を避けようと色々な方法が試されてきました。
たとえばグラファイトを微粒子に砕いてワックスに混ぜ、渦電流が広がるのを防ぐ方法などが考え出されました。
この方法はかなり成功したものの、ワックスが重くなって浮上しにくくなるという欠点がありました。
そんな中、今回の研究チームは「摩擦を避ける」のではなく、もっと根本的な解決策を考え出しました。
そのポイントは、磁石と円盤の配置を「完璧な対称」にしてしまうことです。
では、なぜ対称性が重要なのでしょう?
たとえば、磁石を完全な円形に並べ、その真ん中にまったく同じような円形の円盤を置いたとします。
この状態では、円盤が回転しても円盤から見る磁石の並び方や磁場は常に同じ景色として見えます。
磁場に「動き」がないように見えれば、電子たちはそれを見て「磁場が変わらないのなら、自分たちは動かなくてもいいんだ」と考えることになります。
円盤を磁石の並びと完全に揃えることで磁場の変化が完全になくなり、電子はまるで騙されたように反応しなくなるのです。
例えば、普通の磁石の上で回転する円盤は、坂道を上り下りする自転車のようなものです。
磁場の変化は坂道のアップダウンのように電子を揺らし、電流を生み出します。
これがさらなる磁力を作り、回転を止めてしまいます。
しかし、磁石を完璧に対称にすると、電子にとってはまったく起伏のない平坦な道を自転車で走るのと同じです。
すると電子は揺らされることがなく、電流も生まれず、回転を妨げる摩擦も生まれないことになります。
もしこの「対称性を高める」というアイデアがうまくいけば、純粋なグラファイトの円盤を使っても、渦電流による摩擦をゼロに近づけることが可能になるはずです。
果たして「対称性」という発想一つで、渦電流という壁を打ち破ることができるのでしょうか?
科学者たちは、この大胆な仮説を検証するために実験を行いました。
電源不要の『浮く回転円盤』が実現

研究チームが実際に行った実験は、一見シンプルな装置で構成されていました。
直径1センチ、厚さ約1.12ミリという非常に小さな円盤が主役です。
素材はグラファイト(高純度の黒鉛)で、鉛筆の芯に使われる炭素からできた物質です。
この円盤を、希土類磁石という非常に強力な永久磁石を円形に並べた装置の真ん中にそっと置きます。
すると、円盤は磁石の力によってふわっと宙に浮きます。
ポイントは、この磁石が軸対称(中心を軸に完全に同じ配置)に並べられているということです。
さらに重要なことは、この浮遊に電気や電子制御を使わず、磁石の自然な力だけで成り立っているという点です。
磁石が持つ自然な磁力だけで、このグラファイト円盤を静かに宙に浮かせてしまったのです。
ただ浮かせるだけでなく、実験チームは円盤を手でそっと回転させてみました。
すると円盤は、軸対称な磁場の中で安定した姿勢のままクルクルと回り続けました。
この状態をより正確に観察するため、装置全体を真空チャンバーの中に入れて空気抵抗を極力減らし、円盤の回転速度がどのように変化するかを精密なカメラとモーショントラッキング技術で追跡しました。
実験の結果は、研究者の予想を見事に裏付けるものでした。
大気中の通常の状態では、円盤は当然ながら空気の摩擦によって徐々に減速します。
ところがチャンバー内の空気を少しずつ抜いて真空に近づけていくと、回転の減速がみるみる小さくなり、ほとんど減速しないような状態になりました。
しかし、完全な真空に近づけたときにもごくわずかながら減速は残りました。
このわずかな減速の原因を詳しく調べると、装置の僅かな傾きや円盤や磁石そのものの微細な不均一さによって、ほんの少し軸対称が崩れていることが分かりました。
この微妙な対称性の乱れが、理論上ゼロになるはずだった渦電流を発生させてしまったのです。
研究チームはここで諦めません。
傾きや加工精度をさらに高め、磁石の並びと円盤の形をもっと理想的な軸対称に近づければ、この微小な摩擦すらほぼ完全に取り除ける可能性があると考えました。
実際に研究チームが行った数値シミュレーションや理論解析でも、完璧な軸対称状態で回転する円盤の内部では、定常的な渦電流は流れないという結果が示されています。
現実の実験で測定された結果では、最小の回転減速率は約5.5×10^-5 s^-1という極めて低い値になりました。
これは、円盤を回して放置したとしても、約5時間かけてようやく回転速度が最初の約37%にまで落ちるという非常にゆっくりしたペースの減速に相当します。
言い換えれば、ほんの数時間ではほとんど止まらないほど、回転摩擦が極限まで小さくなったのです。
研究チームはさらにこの実験結果を元に、理論的な推定を行いました。
その結果、「装置の傾きをマイクロラジアン(極めて小さい角度)単位で精密に制御できれば、減速率およそ1000億分の1ヘルツという驚異的な低レベルまで抑えられる」と試算しています。
もちろんこれは現時点ではあくまで理論上の見込みですが、将来的な技術の進歩で達成可能な数字として非常に興味深い結果です。
今回の研究が示した最大のポイントは、「完璧に対称な磁場と円盤の組み合わせ」というシンプルな工夫だけで、従来は必ず付きまとった渦電流の摩擦を理論上ほぼゼロにでき、実験でも極めて小さくできたということです。
完全に「摩擦ゼロ」には至っていないものの、回転体から摩擦という最大の敵を取り除く夢に大きく近づいたことは間違いありません。
今後さらに技術が向上し、「摩擦ゼロの世界」にどこまで近づけるのか、期待が膨らむばかりです。
超精密センサーへの道――回転摩擦抑制のインパクト

今回の研究が示した一番大きなポイントは、特殊な電源や難しい装置がなくても、摩擦を極限まで小さくした回転する円盤が作れる、ということです。
言い換えれば、磁石と円盤を完全に対称的に配置するというシンプルなアイデアだけで、今まで大きな障害だった渦電流の摩擦を理論上ほぼゼロにでき、実験でも極めて小さく抑えられることが分かりました。
この発見の面白さは、「複雑な方法で摩擦を避ける」のではなく、「摩擦が発生する根本的な原因」をなくす方向から解決したことにあります。
磁石と円盤を完璧な対称形に整えることで、渦電流の元となる「磁場の変化」自体を生じさせないという新しいアプローチを取ったのです。
先に説明したように、従来は素材を微粒子にしたり、特殊な加工を施して渦電流の広がりを防ぐ方法が主流でした。
しかし今回の研究では、それとはまったく違う発想で、摩擦を原理から減らすことに成功しました。
では、この発見は私たちにどのようなメリットをもたらすのでしょうか?
簡単に言うと、私たちはこれまでにないほど高精度な「回転センサー」を手にする可能性が出てきました。
こうした摩擦がほとんどない回転装置は、「ジャイロスコープ」と呼ばれる精密な方向測定器や、非常にわずかな圧力や加速度の変化を測る超高感度センサーとして理想的です。
回転が止まる原因となる摩擦がほとんどないため、わずかな外からの変化でも円盤の回転に影響が現れるのです。
ただ、現時点ではまだ完全に摩擦をゼロにしたとは言えません。
実験でも、ごく僅かな傾きや磁石・素材の不均一さによって、微量ながら摩擦が残っていることが確かめられています。
これは実験を行う上で避けがたい現実的な限界です。
とはいえ、研究チームはこれらの限界も将来的には克服できると考えています。
より精密な加工や装置の安定化を進めれば、今よりさらに摩擦を小さくできる見込みがあるからです。
また今回の実験は常温環境で行われました。
超高精度な装置を作る場合、通常は超低温や特殊な環境が必要になりますが、この円盤は常温でも非常に低い摩擦を実現できています。
そのため、将来的にはもっと幅広い分野での応用も期待できます。
例えば、これをもとにして日常的に使える高精度な測定機器が登場するかもしれません。
そうなれば、私たちの暮らしの中で「目に見えない微小な変化」を簡単に測定できるようになる可能性もあります。
さらに研究チームは、この装置が将来、量子現象の研究にも役立つ可能性があると指摘しています。
量子現象とは、ごく小さな粒子が常識では考えられない動きを見せる世界のことです。
今回の円盤は非常に摩擦が少なく、長時間回転できるため、こうした量子のふるまいを、より大きなスケールで観察する実験にもつながるかもしれません。
言ってみれば、量子の世界と私たちの日常世界の「橋渡し」になる可能性を秘めているのです。
科学というのは時に非常にシンプルな発想で大きな壁を越えます。
今回の研究もまさにその一例でしょう。
「対称性」という単純な考え方が、摩擦という長年の難題をほぼ解決できる可能性を示したのです。
参考文献
浮上ローターが切り拓く、古典・量子物理学のための超精密センサー
https://www.oist.jp/ja/news-center/news/2025/10/10/freely-levitating-rotor-spins-out-ultraprecise-sensors-classical-and-quantum-physics
元論文
A magnetically levitated conducting rotor with ultra-low rotational damping circumventing eddy loss
https://doi.org/10.1038/s42005-025-02318-4
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部