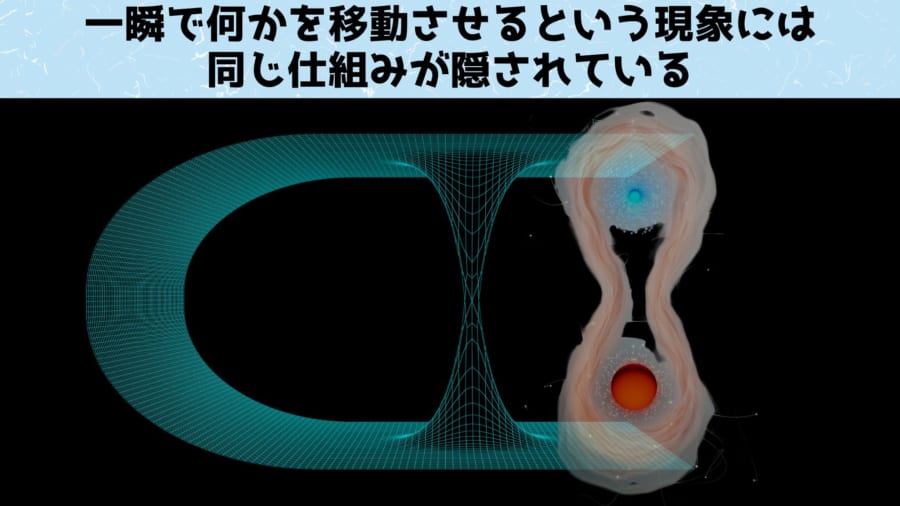同じ物体でも視点が違えば、全く異なる形にみえることがあります。
米国のハーバード大学で行われた研究によれば、これまで別物だと考えられていた「通過可能なワームホール」と「量子テレポーテーション」が、実は同じ現象に対して異なる解釈をしていたに過ぎないことが実験的に示されました。
現在物理学者たちの大きな悩みのタネの1つが、非常に小な世界を説明するための量子理論と、星が発する重力など非常に大きな世界を説明する一般相対性理論に、全く互換性がないということです。
しかし新たに行われた研究では量子プロセッサーに通過可能なワームホールの特性を疑似的に組み込むことで、量子力学と相対性理論の結び付けに成功します。
さらに「量子もつれ」の状態にある量子をワームホールの端と端に配置することで、量子の情報がワームホールの内部を一瞬で通過する「ワームホールを用いた量子テレポーテーション」つまり「ワームホールテレポーテーション」を再現することに成功しました。
にわかには信じがたい話ですが、論文が掲載された『Nature』は自然科学分野で最も権威ある学術誌であり、結論に至る過程も科学的妥当性があるものとなっています。
研究者たちは、このような現象がみられた理由として、情報を一瞬で遠くに送る量子テレポーテーションと、通過可能なワームホールが同じプロセスを背景に持っているからであると結論しています。
一瞬で何かを送るという仕組みを、私たちの宇宙はどのようにして構築しているのでしょうか?
研究内容の詳細は2022年11月30日に『Nature』にて掲載されました。
目次
- 「一瞬で何かを移動させる現象」には共通の仕組みが隠されている
- 通過可能なワームホールは量子情報を一瞬で伝達する
- 疑似的ワームホールから本物のワームホールで予測される特性が観測された
「一瞬で何かを移動させる現象」には共通の仕組みが隠されている
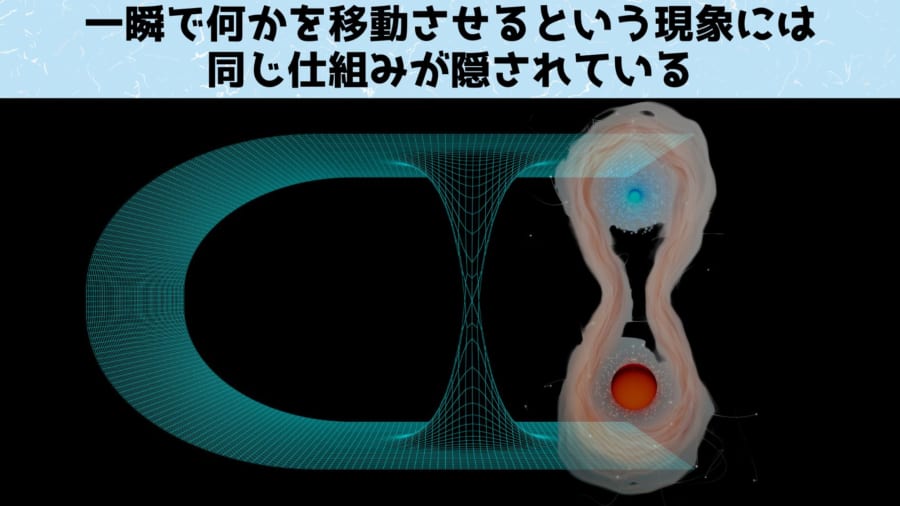
SFなどでしばしばワームホールは、遠く離れた場所に一瞬で移動するための超光速航行技術、また量子テレポーテーションは遠く離れた場所に一瞬で情報を送るための超光速通信技術として描かれています。
SF世界ではどちらもすいぶんと「応用」が進んでいるようですが、現実世界では発展速度に大きな差がありました。
一般相対性理論によれば、ワームホールは入口と出口を備えた時空のトンネルのような構造をしており、入口と出口が何億光年も離れた別の銀河にあっても、一瞬で通過できると考えられています。
しかし現在に至るまでワームホールが発見されたことはなく、通過可能なワームホールを作る技術もまだありません。
一方、量子テレポーテーションはずっと研究が進んでおり、量子テレポーテーションに必要な数学的条件がわかっているだけでなく、実験で再現することにも成功しています。
そして2022年のノーベル物理学賞は量子テレポーテーションの実証にかかわった3人の科学者たちに送られました。
研究速度に大きな差がある理由は、理論の核となる存在の違いです。
ワームホール理論の核となるのは、星など大きな物体から観測される時空のゆがみであり、これは古典物理学の相対性理論から語られるものです。
一方、量子テレポーテーション理論の核は目にみえない小さな世界を語る量子理論です。
この2つは基礎となる理論がまるで異なっていて、それぞれに互換性はありませんでした。
しかし、相対性理論が描くワームホールと量子理論が描く量子テレポーテーションには奇妙な一致点がありました。
物体のスケールは異なるものの、どちらも「何かを一瞬で別の場所に送る」という性質があったからです。
そのため一部の研究者たちは、まるで異なる理論で描かれるワームホールと量子テレポーテーションが、大いなる宇宙の仕組みを、単に別の角度から見ているに過ぎない可能性について考えるようになっていきました。
距離に関係なく、銀河の端と端にあっても一瞬で物体を移動させられるワームホール、同じく「もつれ状態」にある量子情報が距離に関係なく、一瞬で伝達される量子テレポーテーション。
言われてみれば確かに、両者の間に何らかの共通の仕組みが存在していてもおかしくはありません。
問題は、どうやってその仕組みを暴くかでした。
通過可能なワームホールは量子情報を一瞬で伝達する

どうやってワームホールと量子テレポーテーションの背後に潜む共通の仕組みを暴くのか?
キッカケとなったのは2013年に行われた野心的な研究でした。
この研究ではじめて、ワームホールと量子テレポーテーションの基礎になる「量子のもつれ」が「関連」していることを示す基礎理論が提唱されました。
2017年になるとさらに理論が発展し、通過可能なワームホールを説明するのに使われていた重力理論が、量子テレポーテーションとして知られるプロセスと本質的に「同等」であることが理論的に示されました。
しかし理論的な理解は進んでも、ワームホールと量子テレポーテーションが本質的に同じ現象であるかを実証するのは困難でした。
足を引っ張っていたのは、解明が遅れているワームホールでした。
人類は既に20世紀末の段階で、量子テレポーテーションを再現することに成功していました。
しかし現在に至るまで通過可能なワームホールは発見されておらず、ワームホールと量子テレポーテーションの関係を実験的に確かめることは困難でした。
しかし2015年に発表された研究が大きな転機になります。
この研究では、量子プロセッサーにワームホールの特徴を回路として組み込むアイディアが提案されていました。
そして2019年になるとこのアイディアがさらに改良され、量子もつれの状態にある2つの量子を、疑似的なワームホール回路を挟むように設置する方法が考案されます。
この配置で量子テレポーテーションを実行すれば、ワームホール内部を情報が通過する様子をシミュレートすることが可能になります。
そこで今回、ハーバード大学の研究者たちは実際に、9ビットの量子から構成される量子プロセッサー内部に、ワームホールの特徴を発揮する疑似的なワームホール回路を埋め込み、何が起こるかを観察することにしました。
結果、量子もつれ状態にある2つのうち一方の量子の情報が、疑似的なワームホールを介して移動し、もう一方に伝達されていることが判明します。
この結果は、量子情報がワームホールを通過可能であることを示しています。
また実験結果は、通過可能なワームホールを表現するために用いられる重力理論が、量子テレポーテーションとして知られるプロセスを別の角度から表現したに過ぎないことを実証するものとなりました。
しかしより興味深いのは、情報通過にともなう疑似的なワームホールの挙動でした。
疑似的ワームホールから本物のワームホールで予測される特性が観測された
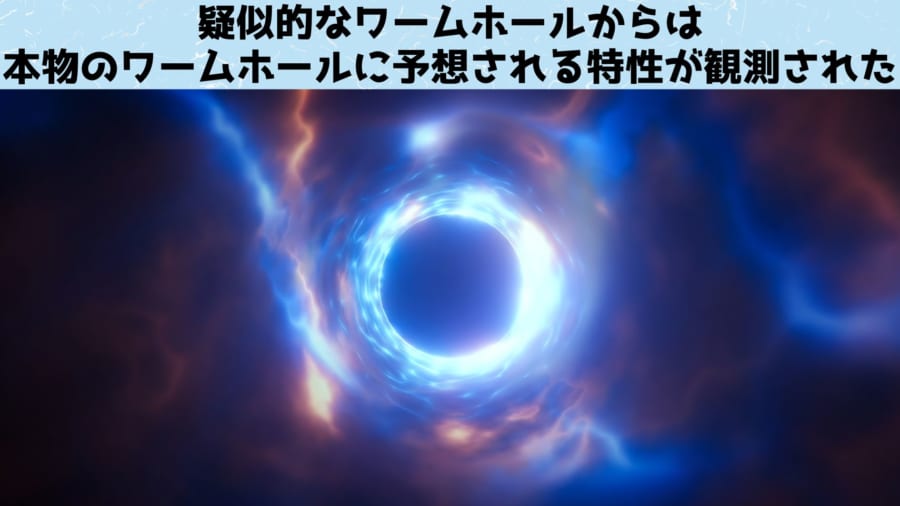
これまでの理論研究により、量子情報がワームホールを通過する場合にはワームホールが「負の反発エネルギー」によって開かれていなければならないことが示されています。
そこで研究では理論を検証するため、疑似的なワームホールに対して負の反発エネルギーと正の反発エネルギーが供給を行い、情報の行方が調べられました。
結果、負の反発エネルギーを供給した場合のみ、量子情報が疑似的ワームホール内部を通過し、正の反発エネルギーを供給した場合には、情報は「特異点」に落下して通過できないことが判明します。
また他にも本物のワームホールで起こると理論的に予想されている、重力によって情報が歪んでしまう現象(シャピロ遅延)、届けられる情報の時間的な順序、疑似的ワームホールでも予想と同じパターンで観測されました。
この結果は、疑似的ワームホールが本物のワームホールの挙動をかなり正確に反映していることを示します。
そのため研究者たちは、新たに開発された「疑似的ワームホールを搭載した量子プロセッサー」には、通過可能なワームホールの物理特性の主要なものが保持されており、実験室内でワームホールと量子の関係を調査するにあたり重要なプラットホームになると結論しています。
参考文献
Physicists observe wormhole dynamics using a quantum computer
https://www.caltech.edu/about/news/physicists-observe-wormhole-dynamics-using-a-quantum-computer
元論文
Traversable wormhole dynamics on a quantum processor
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05424-3
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部