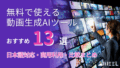地表に植物が根を下ろすよりもはるか昔、地上は菌類のものだったのかもしれません。
日本の沖縄科学技術大学院大学(OIST)やハンガリーの生物学研究センター(HUN-REN BRC)などの国際研究チームによる最新の研究で、現在の菌類(真菌とも呼ばれるキノコなどの仲間)の共通祖先は約14億〜9億年前に出現した可能性が示されました。
これは陸上植物の出現時期(約6.1〜4.3億年前)よりも最大で約10億年も古いことになります。
つまり菌類は、従来考えられていたよりもはるか前から陸上で繁栄し、岩石の風化や土壌形成を通じて地球の陸上生態系の「地ならし役」を担っていた可能性があるのです。
地上を支配した菌類たちは、どんな姿をしていたのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年10月1日に『Nature Ecology & Evolution』にて発表されました。
目次
- 従来説を揺るがす問い — 菌類はいつ陸にいたか?
- 植物より10億年早く菌類が陸を支配した
- 菌類たちは植物よりも先に上陸し地ならししていた
従来説を揺るがす問い — 菌類はいつ陸にいたか?

私たちの多くにとって、菌類はひっそり暮らす地味な存在です。
もしそんな菌類たちが、はるか昔には地球の主役だったとしたらどうでしょう?
これは、地球史を描いた教科書の内容そのものを塗り替えるほど、大胆な話です。
私たちが学校で習ってきた地球の歴史では、陸地に植物が根を張る前の世界は「荒涼とした岩の荒野」だったと教えられてきました。
植物はおろか、動物すらまだ姿を見せない、砂漠よりもずっと寂しい世界が広がっていたと考えられてきたのです。
ところが最新の研究は、この「何もない世界だった」という常識を揺さぶっています。
キノコの仲間である菌類こそが、その「植物のいない荒野」に先駆けて地上を支配し、ひそかに世界を変えていた可能性が出てきたからです。
生物の歴史を少し振り返ってみましょう。
地球の歴史をひもとくと、私たちがよく知るような複雑な多細胞生物は、主に五つのグループで別々に進化しました。
動物、植物、菌類、紅藻(こうそう:赤い藻類の仲間)、そして褐藻(かっそう:昆布などの仲間)です。
この五つのグループは、それぞれ全く異なる単細胞生物の祖先から独立して進化し、大型化や複雑化を達成しました。
こうした生物がいつ頃出現したのかを調べるため、ふつうは地層に眠る「化石」を証拠にします。
化石を掘り出すことで、「○○は△△億年前には存在した」という進化の年表が見えてきます。
たとえば紅藻については、現在の紅藻につながる祖先と思われる化石が約16億年前の地層から見つかった可能性があります(この解釈には議論も残ります)。
動物では、エディアカラ紀(約6億年前)の地層から多細胞の不思議な生き物たちの化石(エディアカラ生物群)が大量に見つかっています。
このことから、6億年前ごろには動物が地球に登場していたことがわかります。
陸上植物については、オルドビス紀中期(約4.7億年前)ごろにできたクリプトスポア(胞子の化石)が最古の証拠です。
実際に植物が地上にはっきり根付いたのは、その後の約4.7〜4.3億年前の間だと考えられています。
このように、多くの生物グループの進化年表は、地層に残った化石をもとにおおよそ整理されてきました。
ところが、この進化年表に大きな空白を残してきたグループがあります。
それが真菌類です。
真菌といえば、カビやキノコなど、柔らかくて糸のような体を持つ生き物たちです。
真菌たちは細菌や古細菌よりも人間に近い生物であり、ときにキノコのように目に見えるサイズにまで集まることもできます。
ただキノコのような菌類の化石は非常に珍しいことが知られています。
化石は硬い殻や骨格が残りやすいため、菌類のような柔らかく壊れやすい生物はなかなか化石になりません。
このため、古生物学者たちは菌類がいつから存在していたのかという謎に長い間苦労してきました。
もし過去にキノコ王国が地上を支配していたとしても、その痕跡を探すのは容易ではないでしょう。
コラム:真菌は細菌と全然違う生命
真菌(キノコやカビの仲間)は、細菌や古細菌とは根本的に異なる生命グループです。複雑な細胞構造を持ち、多細胞化することで大きな体をつくってキノコになったり、他の生き物と共生して地衣類のようなユニークな生き物にもなれるのです。一方でで細菌(バクテリア)や古細菌(アーキア)は真菌に比べてシンプルな細胞をしており、多細胞化して目に見える複雑な体を作ることはできません。迷路を解いたり巣から脱走するタマホコリカビも真菌に含まれます。なお今回の記事ではわかりやすさのために真菌の代表として「キノコ」を多く引き合いに出していますが真菌=キノコという意味ではありません。
さらに菌類の進化は、他のグループよりも特別に難しいという事情があります。
動物や植物は、それぞれ「たった一回の多細胞化」から大きく進化しましたが、菌類の場合は、単細胞から多細胞への進化が複数回、異なる道筋で起こった可能性があります。
つまり菌類は、進化のスタートラインが一本ではないため、「菌類の多細胞化はいつ起きたか?」という根本的な問いに答えるのが非常に難しかったのです。
もし仮に菌類が植物よりもずっと前に地上で活動していたとしても、その正確な時期を知る方法がありませんでした。
そこで科学者たちは「分子時計」という手法に目を向けました。
分子時計とは、生物のDNAの変化が一定の割合で進むことを利用して、「化石がなくても進化の年代を推定できる」方法です。
ところが菌類の化石が極めて少ないため、分子時計を正しい年代に合わせるための「目印(校正点)」がほとんどありませんでした。
結果として、これまで菌類の進化史はぼんやりとした輪郭しか描けなかったのです。
果たして、この困難な菌類の進化の謎に、研究チームはどのように挑んだのでしょうか?
植物より10億年早く菌類が陸を支配した

菌類の進化の歴史を探るため、研究者たちはちょっとユニークな方法を考え出しました。
その名も「時間樹(タイムツリー)」です。
普通の「系統樹」というものは、生物の進化的なつながりを示す家系図のようなものですが、時間樹はその系統樹に「時計」の要素をプラスしたものです。
つまり、生物がどの時代に、どの系統から分かれていったかを詳しく時系列で示した、進化の地図というわけです。
でも、ちょっと待ってください。
そもそも、「菌類の進化の歴史」を知るにはどうすればいいのでしょうか?
化石を使えばいいと思うかもしれませんが、実は菌類は体が柔らかくて壊れやすいため、化石になるのが非常に難しいのです。
そこで登場するのが「分子時計」というテクニックです。
分子時計というのは、生物が持っているDNAの中に蓄積される小さな変化(変異)が一定の速度で起こることを利用して、その生き物がいつ頃ほかの生物から枝分かれしたのかを推測する方法です。
ただし、この分子時計にも一つ問題があります。
時計を使って時間を測るためには、時計を合わせる(校正)必要がありますが、菌類はその校正に必要な「化石記録」が極端に少ないのです。
時計を合わせる目印となる化石が見つからなければ、正確な年代を知るのはとても難しいわけです。
そこで今回、日欧合同研究チームは新たなアイデアを投入しました。
そのアイデアとは、別の菌類の系統へと偶然遺伝子が移動する「水平遺伝子伝播(HGT)」という現象を使う方法です。
これは、簡単に言えば、菌類同士の間で「遺伝子のお引越し」が起きるという珍しい現象のことです。
遺伝子というのは普通、親から子へ縦方向に受け継がれますが、ごくまれに、まったく別の種類の生物同士の間で遺伝子が横方向に移動してしまうことがあります。
これがHGT(Horizontal Gene Transfer、水平遺伝子伝播)です。
たとえば、古い菌類の系統Aから新しい系統Bへ遺伝子が「引越し」していたら、「Aの方がBよりも昔から存在していた」ということがはっきり分かります。
こうした関係が見つかると、進化の順序(どちらが古いか新しいか)が明確になるわけです。
研究チームは、さまざまな菌類ゲノム(生物が持つ全遺伝情報)を徹底的に調べ上げ、このような遺伝子のお引越しを17件も検出しました。
そして、この17件の「どちらが古い・新しいか」という情報を、数少ない化石記録と組み合わせました。
実際に使用した化石記録は27か所(合計24の枝分かれ部分=ノード)の年代データで、これとHGTの情報を使って分子時計を精密に調整したわけです。
こうして集めた情報をもとに再構築した菌類の「時間樹」から、研究チームは驚くべき結果を導き出しました。
それは、「現生のすべての菌類が共有する共通祖先」が、約14億年から9億年前にすでに存在していたということです。
ここで注目したいのは、陸上植物が地上に姿を現したのがおよそ4億7千万年前ごろだったという事実です。
つまり、この菌類の共通祖先は、私たちが知る最古の陸上植物よりもはるか昔、少なくとも5億年以上前から地球上にいた可能性が高いのです。
言い換えれば、植物が地球に進出するよりずっと前から、菌類は地上で栄えていたことになります。
これまで考えられてきたよりも、はるかに長い「菌類先行時代」があったことになるのです。
実際にこの新しい年代推定では、カビやキノコなどの「主要な菌類グループ」が約10億年前頃にはすでに枝分かれを始めていた可能性が示されています。
このことから研究者たちは、地球の各地に複数の「キノコ王国」が存在していた可能性も指摘しています。
では、菌類たちは具体的にどのような形で当時の地球環境に関わっていたのでしょうか?
研究チームは、菌類が地球環境にどのように関わったのかについても、興味深い解釈を示しています。
約10億年前の地球の地表には、まだ私たちがよく知るような植物はまったく存在していませんでした。
いわば、陸地という陸地は岩石ばかりで、どこまでも続く荒れ果てた岩の世界です。
しかし、この岩だけの世界に、実は菌類たちはすでに進出していたかもしれないと研究者たちは考えています。
さらにその菌類は一人ぼっちではなく、藻類(そうるい)と呼ばれる原始的な植物の仲間と共に地上に暮らしていた可能性もあるのです。
こうした菌類と藻類の共同生活がどんな姿だったかというと、現在の地球上でよく見られる「地衣類(ちいるい)」のような薄い微生物マットに近い状態だったと想像されています。
地衣類というのは、実は藻類と菌類がタッグを組んだ共生生物で、厳しい環境でも岩石の表面にへばりついて生きることができる不思議な生き物です。
この「地衣類」のような生物コミュニティが岩石の表面に広がることで、岩が少しずつ風化して栄養が循環し、初歩的な土壌(植物が育つ土)ができていった可能性があるわけです。
こうした菌類と藻類の関係を裏付けるヒントも見つかっています。
研究チームは約11億年前に登場したとされる菌類の共通祖先(接合菌類+子嚢菌類+担子菌類という、現在の主要な菌類のグループが分かれる前の祖先)が、藻類と何らかの相互作用(互いに関わり合うこと)を持っていた可能性を指摘しています。
これはどういうことかというと、その菌類は「PSE(ペクチン分解酵素)」という特殊な酵素を持っていたことが、遺伝子情報から年代推定されているためです。
ペクチンというのは、植物や藻類の細胞壁に多く含まれる成分です。
つまり、このペクチンを分解する能力を持つ菌類は、藻類の細胞壁を利用して生きる準備が整っていたということです。
もちろん、これだけで菌類と藻類が実際に共生していたと断定はできませんが、こうした能力を菌類が持っていたことは、両者が互いに何らかの関わりを持つ環境が整っていたことを強く示唆しています。
こうした菌類と藻類による長い下積みの時代を経て、地球の環境は少しずつ変化し、徐々に陸上植物が育つ準備が整っていったのかもしれません。
そして約4億数千万年前(4.7億〜4.3億年前)のオルドビス紀からシルル紀にかけて、いよいよ最初の陸上植物(コケやシダの祖先)が根を下ろすようになったのです。
つまり植物たちは、何もない荒地に突然現れたのではなく、すでに菌類たちが丹念に整えてきた舞台に、満を持して登場した可能性が高いというわけです。
さらに研究チームは、地球史において「退屈な10億年」と呼ばれる時代についても新たな視点を提供しています。
これまでこの10億年間は、地球環境に目立った変化がなかったため、地質学や生物学の分野では「退屈な期間」として知られてきました。
ところが、今回の研究結果をふまえると、この「退屈な10億年」こそが、実は菌類が地上に繁栄した輝かしい時代だったのかもしれないのです。
菌類は化石としてほとんど残らないため、その輝かしい時代は地層からは見えにくいのですが、実際には菌類たちがこの長い時間をかけて地球環境をじっくりと作り変えていた可能性が高いのです。
言い換えれば、地質学の教科書では「空白」とされてきたこの時代は、菌類が地上で密かに活躍し、繁栄を遂げていた華やかな時代だったとも考えられるわけです。
もしかしたら私たちが知らないうちに、この地上に菌類が築いた巨大な大帝国が存在し、それが化石にはならずにひっそりと消えていったのかもしれません。
まるで、歴史から忘れ去られた古代文明のようにですね。
菌類たちは植物よりも先に上陸し地ならししていた

今回の研究が何を示したか、一言で表現すると「生命が陸に上陸する物語の陰の主役は菌類だった」ということになります。
地球の歴史において、植物がまだ現れていない陸上はずっと「荒涼とした岩だけの大地」だと考えられてきました。
しかし、この研究によって、それがちょっと違った視点で見えてきました。
植物が地上に現れるよりはるか昔から、菌類はすでに地表を覆い、岩を砕いて土壌を作り出し、目立たないながらも重要な役割を果たしていた可能性が浮かび上がったのです。
まるで映画や舞台の裏方のように、菌類は目立たない場所で地球環境を少しずつ整えていたわけです。
これは、現在の生態系を考える上でもとても重要な気づきを与えてくれます。
私たちが普段気にすることはほとんどありませんが、実は私たちの足元の土壌には無数の菌類が存在しています。
こうした菌類は植物の根とタッグを組んで養分の循環を手助けし、生態系を維持する「縁の下の力持ち」のような存在です。
つまり、菌類がいなければ森は育たないということです。
今回の研究で明らかになった過去の菌類の役割を知れば、私たちが暮らす現在の世界もまた、菌類がいなければ成り立たないことが改めて見えてくるでしょう。
さらに、この発見が科学に与えるインパクトは相当なものです。
なぜなら、これまでの教科書的な説明では、「植物が陸に現れたことで初めて陸上生態系が成立した」とされてきました。
ところが今回の研究で示されたのは、その植物が現れるずっと前から、菌類たちがひっそりと環境を整える「地ならし」をしていたということです。
これは、地球の歴史を解釈する上での重要な視点の転換であり、これからの教科書が見直される可能性があるということにもつながります。
また、現代的な視点で考えても、「菌類が環境を整える仕組み」を深く理解することは、現在進行中の気候変動に対して土壌や炭素循環を管理するヒントになる可能性を秘めています。
例えば、岩石を分解する菌類の働きを研究することで、長期的な炭素循環の仕組みや土壌を豊かにする方法についての新たな知識が得られるかもしれません。
もちろん、この研究には慎重に考えるべき限界もあります。
今回の年代推定は、あくまで「分子時計」というDNAの変化速度を利用したモデル計算によるものです。
つまり、今回示された年代は「DNAを分析した結果、このくらいの年代だった」という計算結果であり、その時代の菌類の化石が実際に見つかって証明されたわけではありません。
当然、このような計算には不確実性(計算結果が実際とズレる可能性)が含まれているので、将来的には新たな化石の発見や分析方法の進化によって、推定された年代が修正される可能性があります。
特に、この研究で新たに使われたのは「水平遺伝子伝播(HGT)」という、異なる系統の菌類同士で遺伝子が移動した証拠を利用して年代を校正するという珍しい方法です。
研究チームは合計17件のHGTイベントを検出して、菌類進化のタイムラインを精密に調整しましたが、こうした方法が他の生物グループに対しても同じように使えるかは、これからの検証が必要となるでしょう。
それでも、この研究が示したのは、化石という限られた情報に頼らずとも、生き物のDNAに残る「時の痕跡」を読み取ることで生命の歴史の空白部分を埋められる可能性です。
科学者たちにとっては、今回描き出された新しい「菌類のタイムライン」が、今後の化石探索やさらなる研究の大切な道しるべとなるでしょう。
この道しるべを頼りに、研究者たちは地層に眠る未知の菌類や藻類の化石を発掘できるかもしれません。
参考文献
菌類は、これまで考えられていたよりも数億年も早く、陸上生命の舞台を整えていた
https://www.eurekalert.org/news-releases/1100095?language=japanese
元論文
A timetree of Fungi dated with fossils and horizontal gene transfers
https://doi.org/10.1038/s41559-025-02851-z
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部